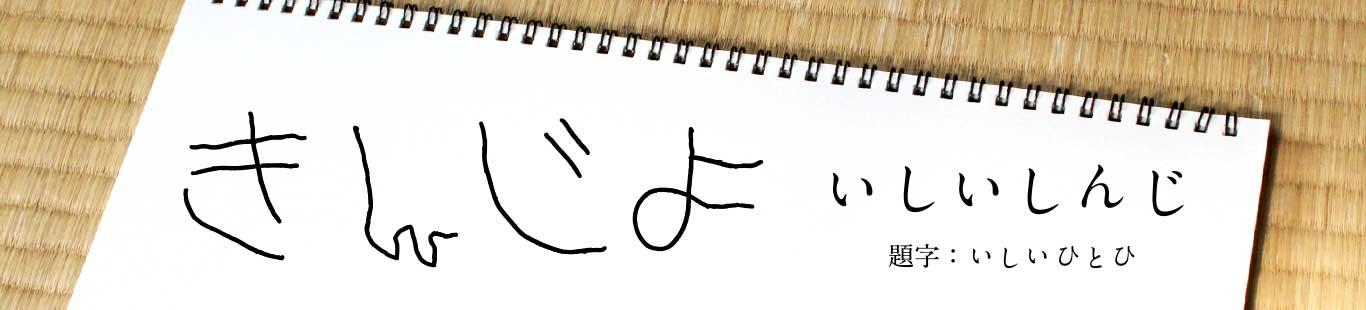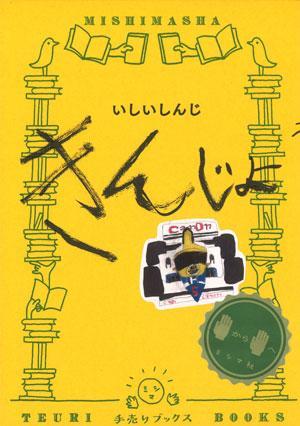第44回
夏のじぞうぼん
2018.11.05更新
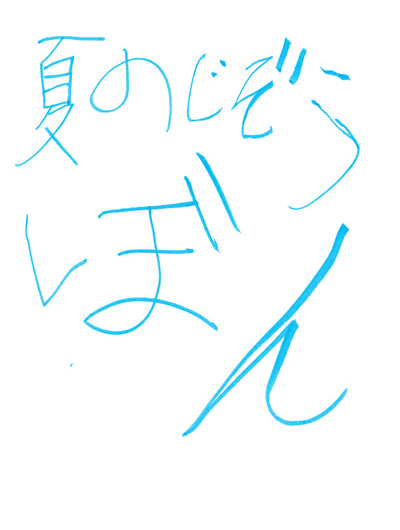
京都にはお地蔵さんの祠が、だいたい五〇〇〇くらいある。だいたい、というのは、誰も正確に数えたことないし、お地蔵さんだから、たぶん日常の上で、自分で増えたり減ったり、加減しているだろうな、ということがある。
お地蔵さんはふだん、役目として、こどもたちの安全を守っている。ことに、親より先にこの世を離れてしまった、こどもたちの面倒をみる。三途の川原で立ちつくし、えんえん、えんえん、こどもたちは泣いている。親のことを思い、いくら賽の河原で石を積もうが、鬼たちがやってきては、片っ端から壊してしまう。えんえん、えんえん。お地蔵さんは子らに寄る。衣のなかに子らを招き入れ、一時も休まずに、からだじゅうをやさしく撫でさする。
毎日、毎夜、子どもたちは、世界じゅうから河原へ来る。お地蔵さんは、表情はおだやかに笑ったままだが、仕事がら、相当疲労がたまっている。
そんなお地蔵さんを慰労するのが、八月末の地蔵盆だ。
朝にまず、祠から出されたお地蔵さんの固く冷え切ったからだを、やわらかな布でマッサージ。果物や花で飾り立てられた、ふだんとは違う祠で、お坊さんがありがたいお経を読んでくれる。ちょうどその頃「きんじよ」の子どもたちが集まってきて、自然に地蔵盆がスタートする。
ゲーム大会、かき氷。忘れちゃいけない数珠まわし。ヨーヨー釣りにスイカ割り。日暮れ頃には花火大会。おとなたちはこの日、子どもたちが最大限遊びつづけられるよう、全力でバックアップする。その遊びの輪のなかに、必ず、お地蔵さんがいる。うちの町会はこどもが30人以上集まるが、東山のあたりでは、おじいさんとおばあさんが公民館でカラオケ大会を開いているそうだ。まあそれもお地蔵さんにしたらリラックスできそうだけれど。
夏の「きんじよ」祭でも、ぜひ地蔵盆をひらきたかった。家を社屋にしているミシマ社は、親子であがりやすく、地蔵盆会場にぴったりだ。知り合いの家族、「きんじよ」関係者に声をかけた。八月二十四日は、暦の上でもドンピシャ地蔵盆にはまっていた。
社屋が引っ越しすることは決まっていた。廊下にずらりとならんだ紙のお地蔵さんは、きっとこの家で、生まれては出てゆく本たちを見まもってきたのだろう。ミシマ社のみんなは本に対しては信心深いから、きっと、積まれた新刊の山に面とむかったら、手をあわさずにいられない。お地蔵さんはずっとそれを見てきたのだ。
庭から、子どもたちが入ってくる。おとなたちは先導され、おずおずと部屋にあがる。
まずはミシマさんの「うんち」コール&レスポンス。場が和んだのか混ざったのか、ともかくこどもたちが笑っている。それならお地蔵さんも笑っているはずだ。
五百円玉争奪ジャンケン大会。からだも気持ちもあったまり盛りあがる。地蔵盆といえばこれ、という駄菓子の詰め合わせが子どもたちに配られる。最初、片手で足りるくらいだった子らの数が、いつのまにか倍々ゲームで増え、足の踏み場もなくなっている。親御さんたちには廊下のほうへさがっておいてもらう。それでも子どもたちは増える。ちょうど京都市内のお地蔵さんの数が、人智を越えて、勝手に増減をくりかえしているように。
ここで今日一話目の「かいだん」。コワイはなし。
僕が前に出て、照明を消す。
「きょうとに、むかし、ふるいふるーいお寺があってな。そこに、おしょうさんと、たいそう悪知恵のはたらく、こぞうさんがすんでおった。おしょうさんは、みずあめをなめるのが、好きじゃった・・・」
いっきゅうさん。いっきゅうさんや。子らのあいだをヒソヒソ声が走る。
「しょうぐんさまによばれた、悪知恵のはたらくこぞうさんの前に、おほりが現れた。橋が一本、かかっている。たてふだには『このはし、わたるべからず』と書いてある」
ぜったい、いっきゅうさんやん! いっきゅうさんやって! 興奮気味に叫ぶ子どもたち。僕は淡々とつづける。
「こぞうさんは、どぼんとおほりへ飛びこむと、スイスイおよいでしょうぐんさまのいるお城にはいっていった。ろうかはもう、ずぶずぶだあ。だれか、ぞうきん、ぞうきんをもて!」
「虎をつかまえてやりますから、さ、しょうぐんさま、虎をびょうぶの外へ追い出してくださいよ。へっへっへ」
「悪知恵のはたらくこぞうさん」は「しょうぐんさま」や「けらい」など大人たちを悪知恵と屁理屈で手玉にとりあざ笑って帰っていく。翌朝、こぞうさんはふとんのなかで血まみれになって死体で発見される。まわりには黄色と黒の毛が散乱し、獣くさい匂いが充満している。寺はそれきりつぶれてしまって、いまはもう、あとかたもない。
「おしまい」
はじめ舐めてかかって「いっきゅうさん、いっきゅうさん」と騒ぎまくっていた子どもたちが、しんと黙りこくっている。へっへっへ。
つづいて、盛りあがること必定の「スイカ割り」。ごく小さい子には後ろから、お地蔵さんが見えない手を添えてくれる。そばで見るたびいつも、こんな非道いことを考えついた遠いご先祖も、そのころはまだ子どもだったのだ、と考えをめぐらす。僕がうまれかわって絶対になりたくないものナンバーワンはスイカ割りで殴られるスイカだ。
岡崎蔦屋でひとひのイベントを盛り上げてくださった書店員の鵜飼さんはじつはお坊さんだ。お坊さんの格好でやってきて、そうして、長い長い、どこまでも無限につづく数珠をとりだした。数珠とは環状だからたとえでなくほんとうに無限だ。輪になった子どもたちとともに「なんみょうほうれんげきょう」を唱えながら数珠をまわす。大珠がまわってきたら頭に押しあてて拝む、というのを、知らないはずの子どもたちが、いつのまにかごく自然に拝んでいる。お地蔵さんはどこに混じっているだろう。「数珠まわし」をしてはじめて、ミシマ社の地蔵盆はほんものの地蔵盆になった。ありがとう、お地蔵さんみたいな鵜飼さん。
つづいてのマルバツクイズは、たとえば、ミシマ社の亀は逃げ出したことがあるでしょうか、とか。うちのメダカの数は十四匹でしょうか、とか。ちょっと「きんじよ」すぎるクイズ。商品は、うちから持って行ったブリオの汽車セットとか、ミシマ社から出ている絵本とか。ほぼすべての子どもに商品が行き渡りました。おめでとうございます。
最後に「かいだん」そのに。
照明を消すと、夕暮れの淡い光だけが部屋を照らす。
「さーて、つぎは、青色に塗られたどうぶつ型ロボットと、メガネをかけたひきょうな男の子のはなし」
えーっ、と声があがる。ドラえもんやん。それ、ぜったい、ドラえもんや!
「ちゃう。どうぶつ型ロボット〜、なんとかしてよー、とまた今日も、メガネをかけたひきょうな男の子が、部屋へとびこんできました」
即興だったので細かなところはよくおぼえていないが、たしか男の子は、同級生のからだのでかいいじめっ子から、おまえ、怪談なんてきいたらおしっこちびるだろ、ヤーイ、ヤーイ、弱虫、とからかわれる。その日の夕方、子どもたちを集めて怪談の会がひらかれるのだ。
ロボットは男の子に、「こわい・こわくないキャンディ」みたいなものをあげる。こわいキャンディを食べると、どんな話をきいてもめっちゃこわい。こわくないキャンディを食べると、どんな話をきいてもこわくない。
男の子はしかえしに、いじめっ子にこわいキャンディをあげる。いじめっ子は友だちが「やきゅうしようよー」と誘いにきた声をきいて泡を吹いて卒倒してしまう。
メガネの男の子は、こわくないキャンディを阿呆みたいに飲みまくり、怪談の会にのぞむ。みなもとしずかちゃんやできすぎくんが怪談のあまりの恐ろしさに震えている。が、のびた、ちゃうわ、メガネのひきょうな男の子はぜんぜんこわくない。怪談師がどれだけ本気だしてもへーきの平座。
「へーん、おかしな話だったなあ。けらけらけら」
そういって夜道をひとり、メガネのひきょうな男の子は帰っていく。そのとき、どこかでブザーが鳴る。すぐさま同時に、いろんなところでブザーが鳴り出す。携帯電話の非常災害速報。ブーッ、ブーッ、ブーッ! 男の子はケラケラ笑いながら道をゆく。ブーッ、ブーッ、ブーッ! けらけらけら、きょうの晩ごはんのおかず、なにかなー。ブーッ、ブーッ、ブーッ!
ブーッ、ブーッ、ブーッ!
ブーッ、ブーッ、ブ!
ブザーを鉈で切り捨てたみたいな沈黙のあと、しばらく間をとってから「おしまい」というと、きょとんとした顔の子、真っ青な子、困った顔の子、いろいろといて、こっちから見渡している風景がおもしろかった。こういう微妙な話のほうがたぶん、あとでじわじわ効いてくるのだ。
すべてのプログラムが終わったあと、割り箸でカメ釣りをし、ささやかな打ち上げをもよおした。おとなはビールで乾杯し、子どもは、減ることなくひたすら増えていくおかしを口に頬張った。夜は更けることなく、時間はずっと、夕方のままだった。ミシマ社の社屋が、子だくさんの家族が住む家みたいに見えた。
来年も、あたらしいミシマ社の社屋で、地蔵盆開催予定。ぜひお楽しみに、お地蔵さんもおおぜい待ってますよ。