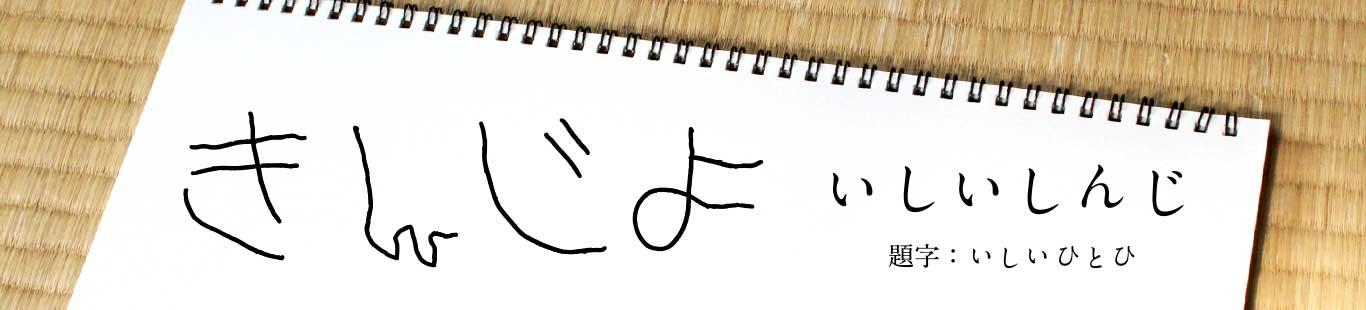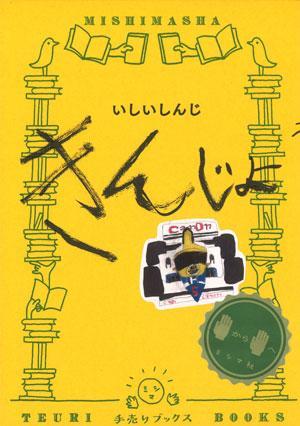第45回
にゅういん&もんじゃ
2018.12.02更新

バカみたいに暑かった夏のあと。九月。急に冷え込みが来た朝。
けほん、けほん。ひとひは咳をしていた。いってきまーす、と、笑いながら駆けだしていった。それでオッケーなんや、と思いこんでしまった。
スイミングは自分から休むといった。「いきつぎできへんかったらしんどいから」。うちに帰って熱を測ったら38度近くあった。その夜は外でひとと会う約束があった。夜中に戻ると、ひとひは、ふとんの上でうつ伏せで丸まっていた。背中に耳をあててみると、ぜん鳴が出ている。
ぜん鳴、とは、ぜん息のとき、胸もとがヒューごろごろ、ヒューごろごろ、と鳴る「あれ」のこと。経験者には「あー、あれね」とわかるけれど、未経験者にはさっぱり通じない。息を吐くことはできても、肺にぜんぜん吸気がこないので、正直、ことばの正確な意味で死ぬほど苦しい。
また、眠いのに眠れない。眠気を促進するホルモンは気管支を収縮させる作用もある。つまり、眠くなればなるほど喘息はきつくなる。窒息し、気絶する。それでようやく半睡できる。
翌朝、かかりつけの小児科、坂田医院にいった。
「これは、あかんよ」
と、めずらしく青い顔になった坂田先生から、第二日赤病院への紹介状を渡された。この時点で僕も園子さんもどういう展開になるか正味わかっていなかった。
府庁前の路上にレンタカーを停め、小児科へあがる。血圧、血中酸素量を計られ、
「あ、これは、泊まっていってもらわないとねー」
と看護師さんにいわれた。
「え、入院?」
「そうですねー」と看護師さん。
「明日には帰れますか」
「いえいえ」と看護師さん。「最低、五泊ですねー」
小児科のフロアでひとひは地団駄を踏み、僕の膝に取りすがって、喘息患者とは思えない声量で訴えた。
「いやや、いやや、い、や、やー!」
ひとひの頭のなかが透けてみえる。だだっ広い部屋、無数のベッド。知らない子どもたちばかりがスースー寝息を立てているまんなかで、眠れず、目をあけたまんま、いつ終わるとも知れない真っ黒い夜の底に、たったひとり取り残されたかわいそうな子ども、それはいしいひとひ、つまり自分。
僕と園子さんが交代で、ベッドの横で真夜中じゅういてるから、だいじょうぶ、と何度も話すうち、ごねるのにも疲れたのか、ひとひは入院を受けいれた。点滴の針を射しこむ瞬間、僕のからだに顔面を押しつけて目をつむった。
目をあけると、透明な管が自分の腕から長々とのび、点滴スタンドの袋につながっている。看護師さんが、スタンドの把手をつかんで押して、どうやって歩いたらいいか教えてくれる。五秒前とうって変わった表情で、
「おもしろいなあ」
ひとひは笑い、スタンドといっしょに病棟の廊下をぐるぐるまわりだした。
「おとーさん、ぴっぴ、ロボットみたいやんなあ」
おさないころ僕は、けっこう重度のぜん息持ちだった。埃がたったり、急に寒くなった夜には必ず発作がでた。
当時の治療はシンプルだった。看護師さんがベッドを指さし、
「寝とき」
という。それだけ。枕をいくつも積んでソファ状にし、仰向けに横たわる。3時間、4時間、5時間。自然と気管支がひろがって、息がととのい、ふたたび歩きだせるまで、ひたすら待つ。
そんな発作がいまは、霧みたいな気管支拡張剤の吸引と点滴で、たった1分で治る。見ているとおり、ひとひはもうケラケラ笑いながら、スタンドを押し押し、病棟の探検をはじめている。
とはいえ、いまだ血液中の酸素濃度は高くない。うちに帰り、はしゃいで走りまわったりすれば、肺にまたもや発作がとりついてしまう。みずからの呼吸だけで、ふだんどおりの分量の酸素を体内にとりこめるようになるのが、およそ三、四日。大事をとって五泊、というのが入院の理由。結局のところ「待つ」わけだ。
ということで現在、ぜん息治療最大の難題は、呼吸困難でも睡眠不足でもなく、タイクツである。薬は、動物系の図鑑、モータースポーツの雑誌、ドラえもん、飛行機の本。さらに、「チキチキマシン猛レース」「インクレディブル・ファミリー」「トイ・ストーリー」などのDVD。ベッドの手すりを舞台に、右手くんと左手くんの指人形劇場。即興でつくるオリジナルの「ドラえもん侍」や「大きくなったちびまる子」などの小話。大部屋の隅で、まわりの迷惑にならないよう、声をひそめて話す。けれどもカーテンの向こうでは誰かが聞き耳をたてている気配がする(くすくす笑ったり)。
看護師さんと仲良くなり、ずっと共に歩む点滴スタンドにも「テルモくん」と名前をつけて親友になった。
第二日赤病院のある府庁前は、うちから市バスの204、202、93番のどれに乗ってもほぼ5分とわりと「きんじよ」にあり、一日券を買って、園子さんとふたり、着替えや食べもの、本やDVDをリュックに詰め、日に何度も何度も往復する。二日目の朝、ひとひのベッドの向かいのカーテンがあいていた。利発そうな男の子がベッドの上で、ちらっ、ちらっとこちらを見る。ひとひが手を振ると手を振りかえしてくれる。ひとひより少し年上の感じ。
友だちか、あるいはきょうだいだろうか。同じ年頃の子どもがおかあさんといっしょにやってくる。ひとひは遊びたそうだが、入院中、ということは自覚しているようで、自分のベッドからは出ていかない。それでも子どもと子どものあいだには、大人の目にみえない糸電話が張られている。三日目、ひとひは少し誇らしげに、
「ともだち、なってん」
テルモくんに加え、人間の友だちが増えたわけだ。
翌朝から僕は山形ビエンナーレのクロージングに行かなければならなかった。行ってくんなー、と手を振ると、ひとひは、うん、うん、と頷いて、小旗のように手を振った。入院という経験は、ひとを内省させるかもしれない。なにもせず、ただ考える、自分をさぐる、といった時間を、小学生は学校や家で、意外と持ちにくいのではないか。入院前とくらべ、ひとひの顔がずいぶん引き締まったように見える。
山形で三日過ごし、京都に戻ってきた。タクシーで細い道にはいり、家に近づいていくと、戸口の前にひとひが立ち、じいっとこっちを見つめていた。スポンジボブのTシャツと半ズボン。僕がタクシーから出ると同時に駆けてきて飛びついた。小学二年の25キロをもちあげ、さっき飛んできたばかりの空高く掲げて、くるくるとまわした。
「おとーさん、にゅういん、ぴっぴたのしかったわー」
「あ、そうなん」
「もっかい、にゅういんしたいくらいや」
「ほな、いまから、まっさかさに地面へ落としとこか」
入院中に「ともだち」になった男の子からひとひに手紙が来た。一日遅れで退院し、いまは元気で家にいるという。「おとうさんがもんじゃ焼きの店をしています」と、正真くんは、その表情通り、こころのこもった字で書いていた。「食べにきてください」
叡電の、一乗寺の駅のすぐ近く。自転車で前を通りかかったことはがあり、あたらしいお店、とは思っていたが、もんじゃの店だとは知らなかった。日曜日、ひとひのピアノの発表会で大阪のおじいちゃんおばあちゃんが来る、そのタイミングで行ってみよう、ということになった。
ひとひが弾いたのは自作曲「空こう」だ。空港でアナウンスの前に流れる、ピンポンパンポーン、のメロディをモチーフに、飛行機が離陸し、着陸する様子を曲にしている。ふだんふざけっぱなしのひとひが、こんな穏やかな、落ちついた曲を、と、まわりの先生たちは少し驚いている。ひとひのなかには、生後10ヶ月からえんえん聴きためたレコードのメロディが、何百何千何万とたまっているのだ。
出町柳から三つ目が一乗寺。足の痛いおじいちゃんを気遣い、きょろきょろ振りむきながらひとひは歩く。と、もうお店の前についていた。 「もんじ屋」。
清潔そうなガラス張りの店内に鉄板が並んでいる。予約しておいた僕たちの席以外すべて埋まっている大盛況。お客さんもお店のかたもみんな全身が笑いで波打っている。鉄板がジュージューうたい、その上をみんなの声が飛び交う。まちがいない、ここはすばらしいお店だ。
「しょうまくんは?」
ひとひがきく。
「いるよ、しょーまー!」
おかあさんが呼ぶ。と、物陰から、待ち構えていたチーターみたいに正真くんが飛びだした。ふたりの糸電話が一気に弾ける。ひとひと正真くんはともに奥へ。そうしてしばらく帰ってこない。入院の時間は入院したものにしかわからない。そこで結ばれた縁はたぶん他では得られないものだ。ふたりの子どもたちはそれをことばでなく理屈でなくきっと本能でわかっている。
ようやっと出てきたときひとひはニヤニヤ笑いがとまらなかった。そして、生まれてはじめて食べるもんじゃにすっかり魅せられてしまった。食べたらまた正真くんと奥へ。糸電話は自在に、伸びたり縮んだりをくりかえす。
まさか入院するなんて、思ってもみなかった。一乗寺でもんじゃを食べるとも、想像さえしていなかった。ふたりは奥へいったまままだ戻ってこない。僕はビールを飲みながら「空こう」のメロディを口笛で吹く。正真くんのおとうさんが鉄板のうたに合わせて腕を振っている。僕たちの「きんじよ」はこんな風に、いろんなものを詰め合わせて、もんじゃみたいにひろがっていく。

編集部からのお知らせ
京都の老舗パン屋さん「 進々堂」でいしいしんじさんの書き下ろし小説が手に入ります!
進々堂さん企画・発行、いしいしんじさん著の無料配布パン小説が完成しました。今回で第3弾となるこの企画、ミシマ社が編集とデザインを担当しております。パン探偵ブレッドが、一匹の猫を探して街をかけめぐる、楽しいお話です。全店すべてのレジ横、テーブルに設置されています。この冊子、なんと進々堂をご利用のお客様はどなたでもご自由にお持ち帰りいただけます。ぜひお手にとってみてください!

『ブレッドはパン探偵』いしいしんじ(表)