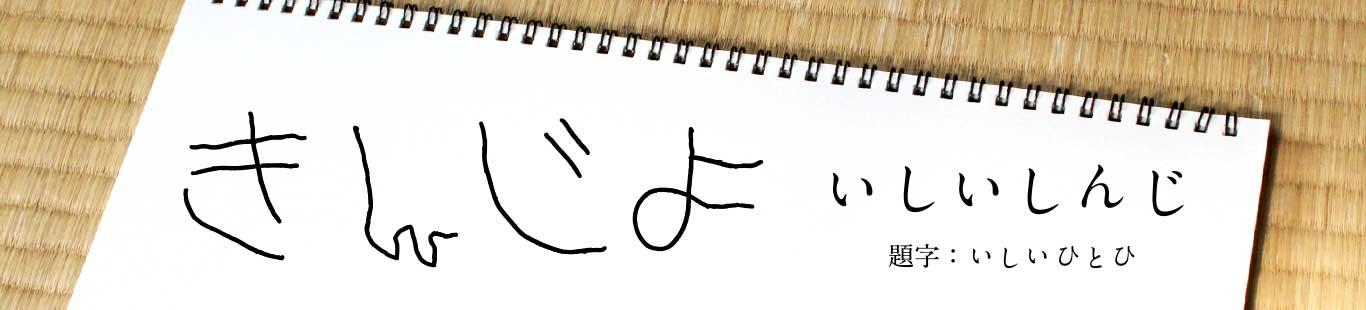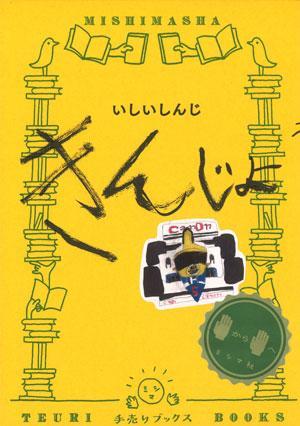第47回
芝は、ディープインパクト ダートは、クロフネ ていうかどっちも武さんやけど
2019.02.09更新

きょうの図工は、クラスのみんな、それぞれ好きなすごろくを作ったそうだ。
「で、ぴっぴはどんなん作ったん」
そうきいてみると、2年生のひとひは、なにをいまさら、といった風に、
「え、ダービー」
とこたえた。
「日本ダービーすごろく。ディープインパクトとかオルフェーブルとか、オグリキャップとかキタサンブラックとか、ウォッカとかグラスワンダーが、コマやねん」
ここまではまりますか、というくらいはまっている。競馬に。
きっかけは乗馬だ。1年生の2月から乗馬にかよいだしたことはこの連載にも書いた。場所は京阪の樟葉駅から、バスに揺られて15分ほどのところにあるクレイン京都。ほぼ毎週土曜。ベーシックBCという級からはじめて、あのキツすぎた夏の三ヶ月は休み、ほぼ1年をかけてベーシックA、そしてベーシック馬場まで二段階進級を果たした。
ある秋の日、クレイン京都の売店で「20世紀の名馬列伝」なる本を見つけた。ぱらぱらめくってみると、ひとひの愛読するマンガ「元競走馬のオレッち」の著者おがわじゅりさんが、大好きな競走馬たち20頭を短編マンガで紹介している。オルフェーブル、ウォッカ、アグネスタキオンと、僕でも知っている名前がずらりとならぶ。
帰りの電車のなかで、ひとひはもう、のめりこんでいた。漢字の読めないところは僕に尋ね、何回も何回も何回も何回も、くりかえし読んだ。
もともとマンガでも雑誌でも図鑑でも、好きなものならいつまでもページをめくっている。自分の連載する「オートスポーツ」や「F1速報」、さらにF1ネタの4コママンガ「グランプリ天国」など、どこへ行くにも何冊かリュックに詰めて持ちはこぶ。
「名馬列伝」を、そのうち、毎日学校にも持って行くようになった。
「中川くんに、見してあげたら、中川くんロードカナロアが好きやって」
と、自分が褒められたかのように喜んでいる。
十一月中旬の日曜、クレイン京都での乗馬を終え、午後すぐの京阪で帰ろうとしたら、ひとひが真剣な顔で、「きょう、淀のきょうとけいばじょうで、マイルチャンピオンシップあんねん。G1やねん」といった。「わかった」と僕はこたえた。「しゅくだいは?」「きのう、やった」「あしたの、がっこうのじゅんびは?」「きのう、やった」
僕はうなずき、「ほんなら、淀、いきますか」
京阪電車のイベントで、なんの気なしに一家で競馬場へ行ったことはあった。ただしそのときは、最後の2レースを見て帰っただけだったし、当時、たしかひとひは3歳、いつか自分が馬に乗ることになるなんて想像もしていなかったはずだ。
それがこの日、みずからG1の日程をしらべ、翌日からの用意をすべて整えて、気合いをこめて淀に、京都競馬場に降りたつ。入り口で配られる出走票を、このレースに会社の明日がかかっているタコ社長みたいな燃える目つきで、立ったまま見つめる。すごい集中力だ。
「ぴっぴ、パドックいこか」
「パドック!」と、2年生が叫ぶ。おがわじゅりさんの描く馬たちは、パドックで跳ねたり寝転んだり、おもろい癖持ちばかり。人生初パドックのひとひは、するすると最前列まで出ていき、鉄柵を握りしめ、
「うわー、かっこええなあ。これからみんな走るんやもんなあ。がんばってほしいなあ。ああ、あしげやー。かわいいなあ。でも、かげもやっぱり、かっこええやんなあ」
えんえんひとり、お経かラップみたいに呟いている。
僕が小学生のときも、クラスにひとりかふたり、競馬好きの子がいた。僕はその髙橋くんに馬のことをいろいろ教えてもらった。よくお父さんと阪神競馬場に行くそうだ。「こないだ、二万の馬券とってん。帰りに串カツいったわ」と髙橋くんはいった。うらやましかった。
髙橋くんたちと違うのは、ひとひは乗馬から入っている、ということだ。つまり、どんな馬も一頭ずつ、気性も能力も違う、ともともと知っている。つまり、馬ならなんでも、分け隔てなく好きなのだ。
馬は一頭ずつ、いのちをもっている。うまれたてのサラブレッドには、みな、名前がつけられる。おとうさん、おかあさんの馬にも名前がついている。一頭ずつが、何百という名でつながれる、壮大な物語の末端を生きている。
ダービー、菊花賞、有馬記念にジャパンカップ。どのレースでも、勝者はただ一頭。けれども、残りの馬たちにも名前があり、いのちがある。
重賞を何度も制し、名馬として語りつがれマンガにもなる馬がいる。そのいっぽうで、乗馬クラブにはいり、長くしずかな生活を過ごす馬もいる。毎週のように樟葉に通い、鞍にまたがり、馬と触れ合っているひとひにはそれがよくわかっている、勝ったのも負けたのも、どの馬たちも愛おしい。だからこそ、G1に勝つ馬と調教師さん、馬主さん、騎手たちが、どれだけの努力を重ね、この日を迎えたかもわかる。勝利の重みも、8歳にしてたぶん感じている。
「来たっ」
スタンドで短く叫ぶ。第4コーナーの出口を、いのちのかたまりが芝を蹴り上げて突っ走る。地鳴りが響き、スタンドじゅうから歓声が巻き起こる。
「いけっ、いけっ、いけっ」
舌先で蹴りつけるように、ひとひが叫ぶ。すべての馬たちに全身で祈りをこめて。そうして一頭がゴールに飛びこみ、残りのみんなも次々と、緑のラインに走りこむ。
レース後もひとひは、スタンドからなかなか立ち去ろうとしなかった。この3時間でもう終わりなん、と、何度も何度もターフのほうを振り向いていた。「ステルヴィオもペルシアンナイトも、アルアインも、みんなもう帰ったかなあ」
「そやな。おいしいごはんもろて。ひと息ついて、帰るころかな」
「おとーさん、けいば、よかったなあ」
「そやなあ。はじめて近くで見たしなあ、一生忘れへんかもな」
「うーん。ぜったい、わすれへんわ」
翌週末、11月25日、東京競馬場でジャパンカップが行われた。このレースで3歳牝馬アーモンドアイが、芝2400メートルの世界記録をたたき出して優勝した。オスメスこえて、史上最強かもしれない3歳馬の姿にひとひは一発でやられた。次の日のスポーツ報知の競馬欄は、年が明けたいまも大切にピアノの上に置いてある。
年末の「いしいしんじ祭」では電車を乗り継いでいっしょに三崎にいった。祭の当日は中山競馬場で一年の締めくくり、有馬記念グランプリがあった。僕が三崎館本店の大広間で、お客さんに見まもられながら小説を書いているとき、ひとひは中華料理店「牡丹」のカウンターに、三崎の若い衆と陣取り、競馬中継の画面に見入っていた。ひとひのイチオシは障害レースから転戦してきた7歳馬のオジュウチョウサンだったが、
「かつんは、うーん、たぶん、ブラストワンピースかな」
と、雑誌サラブレを参考に予想していた。予想は見事的中し、ブラストワンピースは久々に3歳での有馬記念優勝馬となった。
もうじき春競馬がはじまる。ひとひは毎日カレンダーをめくり、淀での日程をたしかめている。けれどそれまでにも毎週、樟葉での乗馬がある。
クレイン京都には、本気で走ればけして負けなかったタイキシャトルの子が、最後のレースでG1を制したステイゴールドの子が、ふざけすぎのダービー馬ジャングルポケットの子が、史上最強馬ディープインパクトの子がいて、そしてひとひは、いつかまちがいなくその馬たちに乗れる。大きな物語を読みながら、そのなかにじっさいに潜れ、物語そのものを生きることができる。ひとひが馬から離れる日が来るとは、僕にはどうしても想像も妄想もつかないのだ。