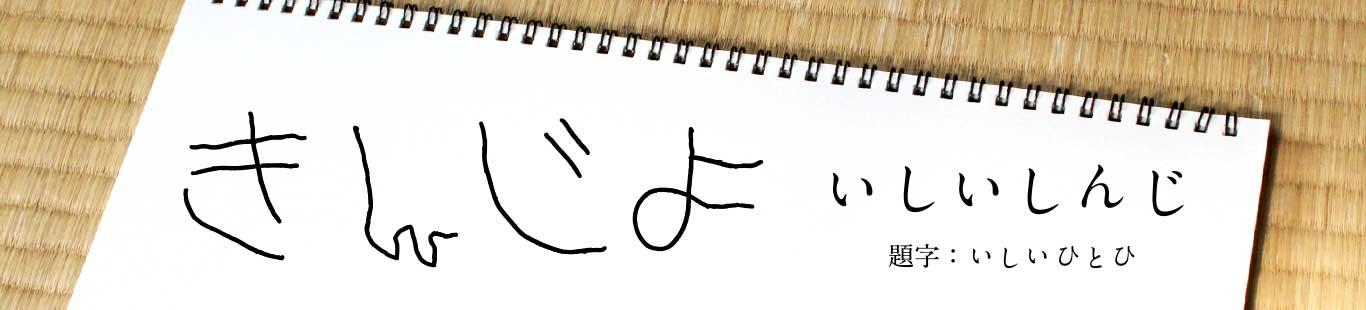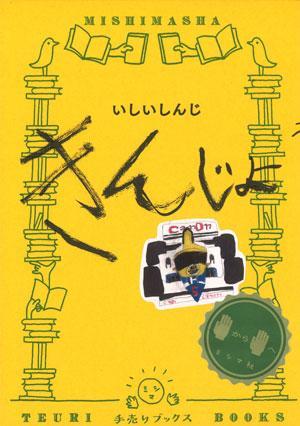第48回
めざせ日本シリーズ1位 がんばれ阪神タイガース
2019.05.26更新

どういうわけか、サッカーより、はじめから野球だった。
モータースポーツ熱と馬好きの陰にかくれて、なかなか表面にはあらわれなかったが、振り返ってみれば、うちのひとひは、野球の話にずっと興味を示していた。
阪神タイガース優勝のときのバカ騒ぎ。
京阪電車のテレビカーで見た、近鉄対広島の日本シリーズ。
野茂英雄のトルネード、ノーヒットノーラン。
通っている小学校には、「錦林ジュニア」なる一年生から入れる少年野球のチームがあり、その体験会には、入学してすぐの時点でなんとはなしに参加して、まったくの未経験にしては、わりとうまかった。
ところで、自分が小学生をやっているときはもちろんわからなかったことだけれど、一年生にとっての学校は、二年生以降と、まったく意味がちがう。それは、初恋の相手がたったひとりであるのとほぼ同じことだ。
これから長くつづく、学校、という社会の入り口を、一年生たちは同時に、よくわからないままにくぐる。親、先生たちは、手を引き、後押しし、なだめ、手を離す。
一年生たちはみんな、全員が全員、同じ方向を向いている。初めて目の前にそびえたつ学校のほうへ。一年生最大の仕事は、足し算でもひらがなでもなくて、新しく入った学校という場所、時間に慣れること。つまり、小学生、というより、一年生とはまず「新入生」なのだ。
学校、というあたらしさを、毎日、毎日くりかえし、からだごと、こころごと、徐々に適応していくことで、一年生はだんだんと小学生になっていく。そうして、次の新入生を迎えるころ、一年生たちの「新入」は終わっている。二年生からが、正真正銘、小学生のはじまりだ。
二年の、あたらしい教室。もう、みんながみんな同じ方向を向いてはいない。クラスを見わたしてみれば、同い年の子らが、自分と同じように、ふしぎそうにまわりを見つめている。
目が合う。意識する。声をかけ合う。
ことばを交わすうち、からだの奥で、なにかが響き合う。
何度かの響き合いのはて、その日の学校が終わったら、いっしょに遊ぶ約束をかわしている。
ひとりでは、サッカーも野球もはじまらない。おにごっこも、かけっこさえも。でも、友だちがひとりだけいれば、何時間ボールを蹴っていても飽きない。かくれんぼは、見慣れた「きんじよ」の町並みを最高の遊園地に変える。小学二年生になってから、ひとひは割と自然に、そのようになっていた。習いごとのない日は、誰かがうちに来るか、誰かのうちに遊びにいくようになった。
こどもの日、東京のおばあちゃんに、左利き用のグローブを買ってもらった。ゴムのボールはふにゃふにゃしてかえって受けにくいから、はじめは素手で、受けては投げる。一年生の頃はタコ踊りのようだったフォームが、鴨川の河原で遠投をくりかえすうち、だんだんとそれらしく固まってきた。
野球のうまい友だちができた。錦林ジュニアにはいっている。
「ぴっぴもはいったら」
と水をむけると、ちょっと考えてから、照れくさそうに
「ええわ」
と首を振る。
「乗馬もやりたいし、連休とか、どこもいかれへんようになるやん」
少年野球をやっている子は、やっていない子にくらべ、もう段違いにプレイがうまい。球の速さも、キャッチングも、なにもかもかなわない。それでも、グローブを持っている子はそう多くないから、しょっちゅうひとひは仲間に入れてもらえる。そして、小学二年生は、野球がうまくてもへたでも、いっしょにいさえすれば、みんな同じ、遊びたい盛りの小学生なのだ。
「ぴっぴー、こっちー!」
「つぎ、ピッチャー、こうたいな」
「うわー、まじかー、10対0?」
岡崎公園の隅、三人きりの野球で、二時間でも三時間でも、球を投げ、打ち、追いかける。
三年生にあがったひとひは、玄関にランドセルを投げ捨てるや、グローブを手に外へ飛び出す。友だちと時間が合わないときは、 「おとーさん、野球!」 と、僕がなにをしていようが、ストレートど真ん中に声を投げてくる。
使うのは軟球。練習プログラムは「ピッチング」と「しゅびれんしゅう」のふたつ。
ピッチング、で僕は、うちの隣の駐車場のコンクリート塀を背に中腰になり、十メートルほど離れた路地の入り口から投げこんでくる、ひとひの球を受ける。ボールはときに、駐車場の果てへと転がっていったり、うちの玄関にワンバウンドで当たったりする。
「腕はからだの上にまっすぐ立てんねんで」
「足の踏み込みを、まっすぐ、おとーさんのほうに出すようにし。右に踏みだしたらボール右いくし、左に踏みだしたら左いくで」
わかっていても、うまくいかない。けれどもたまに、低めのど真ん中にストレートが決まれば、昼の花火みたいにひとひは笑う。
「しゅびれんしゅう」では、軽いゴロ。ゆるやかなフライなら、初めからうまくとれた。
タバコを吸いに外に出てきた、お向かいの奧村さんが、
「腰が高いで」
と声をかけてくる。
「ひとひちゃん、ちょっと、こないして構えてみ」
「うん」
そこへゴロを転がすと、ひとひは流れるように横移動し、グローブにぴたり、球を収めた。花火みたいな笑み。奧村さんは昔、長く野球をしていた。そうして最近まで、少年野球のコーチをつとめていた。
フライがあがったときの、グローブの構えかた。腰を落とし、ボールをキャッチしてからのスローイング。ひとひがどんどんうまくなっていく。僕が、電線より高く投げ上げるフライも、ボールから目を離さずゆうゆうと捕る。
十連休中のある日。はす向かいの辻さんの若いご主人が犬の散歩に出てきた。僕は二階で洗濯物をとりこみ、ひとひはひとり、駐車場のコンクリート塀相手に、黙々とピッチング練習をしていた。
「ひとひくん、ちょっと、ピッチングみたろか」
と、辻さんの声がきこえた。「きんじよ」のスポーツ万能兄弟、あこがれの、勇力くん大賀くんのおとうさん。そして「錦林ジュニア」のバリバリの指導者。ひとひの胸できっと、喜びの鳩が一万羽はばたいたはず。
ゼロ、いち、に。
ゼロ、いち、に。
足をあげ、腕をあげ、踏みこんで投げる。
足をあげ、腕をあげ、踏みこんで投げる。
ただ漫然とあげるのではない。足をふりあげたとき、バッターに背中がむいているくらい、からだをひねっている。それで、踏みだす瞬間、自然と体重が移動する。
足をあげ終わったとき、ボールを持った手はもうグローブから離れ、うしろにまっすぐ伸びている。「踏みこんで投げる」は、うしろから前に移動した体重を、ボールに乗せて前へ投げこむこと。
三十分後、ひとひの投げかたは、マウンドに立つピッチャーさながらになっていた。僕がいっているのと同じことを、辻さんは、野球好きのこどもが一瞬で納得するいいかたで伝える。少年野球のコーチはみんな、昔、野球少年だったのだ。
「あっとーざいましたーっ!」
帽子をとって、ひとひがお辞儀する。ヤンキースでもタイガースでもなく、世界耐久選手権で優勝したトヨタのキャップであるところがひとひらしい。この日から、辻さん、奧村さんは、ことあるごとにひとひの守備、ピッチングに指導を入れてくれる。お向かいとはす向かいにコーチが住んでいるとは、まるで野球マンガの設定みたいだ。
ゴールデンウィークには、京セラドームにオリックス対ロッテの試合を見に行った。関西圏の小学生はタダ、という日が年に何日かある。
限りなく外野に近い一塁側内野席。むかし東京ドームで試合途中、当日券ではいったことはあるが、最初から最後まで、ボールの動きを生で見まもるのは、ひとひにとってこれがうまれてはじめてだ。
ダブルプレイ。大飛球。ファウルボール。ロッテの応援はあいかわらず、いつ練習するんだ、と思うくらい息が合っている。エラーや四球の少ない、引きしまったいいゲームになった。まわりの家族は、父母子どもたちみんなオリックスのユニフォームで盛りあがっていた。
七回にあがったジェット風船の景色を、きっとひとひは一生おぼえているだろう。一度京都競馬場できいたファンファーレを二度と忘れないのと、鈴鹿サーキットの駐車場からコースまで目をつむっても歩き通せるのと、まったく同じように。
ぜろ、いち、に。
ぜろ、いち、に。
外ではひとひが黙々とピッチング練習に励んでいる。
六月には、ドームにオリックス対阪神の交流戦を見に行く(これも格安)。京都の子だけあって、やっぱりタイガースを応援している。 「さいきん、阪神、強なってきたやんなあ」と、バックスクリーン三連発を目撃したおっさんみたいに三年生がいう。「ぴっぴ、近本が好き。あ、木浪もええな」というのは、このふたりが新人にしてレギュラーに定着し、しかも大活躍しているからかもしれない。三十代まではよく見ていたが、もう一度、タイガースの試合を毎晩テレビで見ることになろうとは思ってもみなかった。
二年生までは「ぴっぴ、府中の競馬場、いってみたいなあ」が口癖だった。この願いはまだかなっていない。いま人気のアーモンドアイやサートゥルナーリアの出る秋競馬になら行ってもいいかも、と思っている、だが、おそらくその前に、もうひとつ、三年になってからの夢が早めにかなう。すなわち、 「おとーさん、ぴっぴ、甲子園でジェット風船飛ばしてみたい!」
行くときは、小学校の、野球友だちもいっしょに。