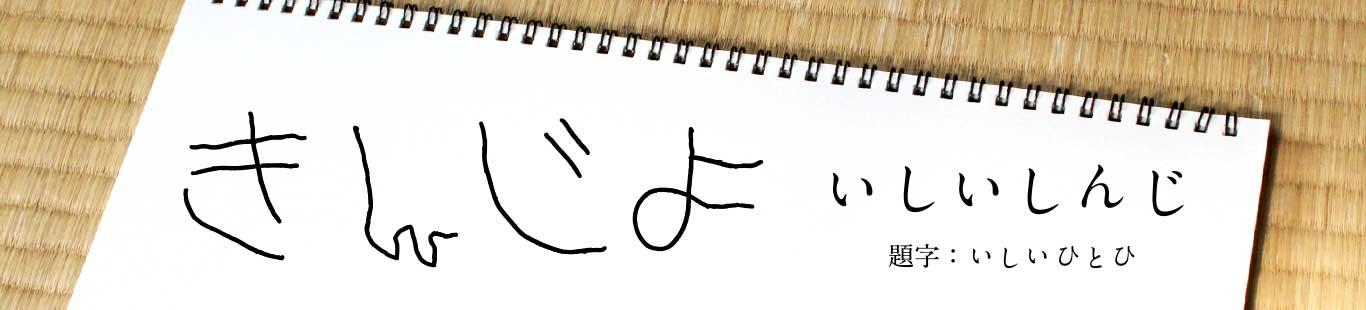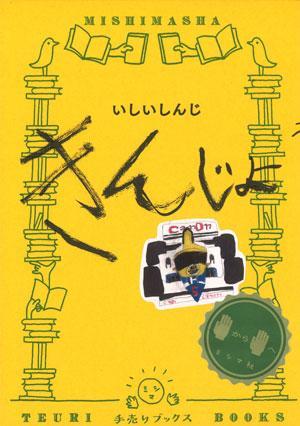第49回
トゥバのまるやき
2019.09.22更新

トゥバに行ってきた、というと誰もが、
「東洋の美、それは真珠」
といったような顔をする。それは鳥羽。
トゥバ共和国。いちおうロシア連邦の一国で、シベリア中央部の最南端、チベットの北西。というような地理的情報より、頭蓋骨を楽器みたいにして倍音を響かせる喉歌「ホーメイ」の本場、といったほうが、通りがよいかもしれない。
トゥバの作家たちが、アジア各国に呼びかけて「トゥバ文学者会議」なるものをひらくことになった。ホーメイ、口琴を日本に紹介した音楽家、ヒカシューの巻上公一さんは、現地の大統領と顔なじみなくらい、トゥバではよく知られている日本人だ。その巻上さんに、トゥバ作家協会が、日本から誰か作家を呼んでくれないか、と依頼があった。巻上さんは旧知の作家ふたり、茅野裕起子さん、石原燃さんに声をかけた。そして茅野さんから僕に、
「トゥバなんて、これ逃したら一生いけないかもよ」
と連絡があった、とまあ、そんな流れである。
僕が学生のころ、バックパックひとり旅行記の類いが大いに流行っていた。そのはしりが、岩波文庫で出た『トゥバ紀行』だ。みんな読んでいるものと思いこんでいたから、トゥバ、といって誰も知らなかったのに、かえってこちらがびっくらこいた。
成田で集合。リーダーは巻上さん。茅野さんと石原さんは中央アジアをともに旅したことがある。園子さん、ひとひと離れて外国に行くのは、およそ二十年ぶりな僕は、ひょこひょこ後ろからついていく。アエロフロート機で二時間。ハバロフスクで国内線に乗り換え、四時間かけて、シベリアの中心都市クラスノヤルスクに着く。ここで一泊。
翌朝7時、運転手ヴィクトールさんの4WDに四人で乗りこむ。ここからトゥバの首都クズルまで12時間かけドライブしていく。クラスノヤルスクから飛行機も飛んでいるのだが、巻上さんの考えで、行きはクルマで地べたを通っていくことにした。
深い森。濃厚な雨。
夏のシベリアはここぞとばかり緑が濃い。旧ソ連時代からの伝統らしく、森のなかだろうが峠だろうが、路面の舗装状態はすこぶるよい。土地がとにかくばかっ広く、道路を敷く際の制約が少ないためだろう、アールのつけかたも直線の伸びも、ひとの手をこえているくらいナチュラルで、後部席にいるだけでその走りやすさが風ごしに伝わってくる。
巻上さんが最近トゥバで話題になったニュースを紹介してくれた。人食い熊に襲われた男の話だ。熊は男のからだを喰い散らかし、残りはあとで平らげようと、こっそり穴に埋めた。
仲間が森を捜索し、熊の埋めた穴を見つけた。穴を掘り返してみると、半分食われた男のからだがあらわれた。仲間たちが嘆いていると男の口からか細い声がもれた。男は生きていた。陽の届かない穴の底で、自分の小便をすすって息をつないで。
そんな、うっそうとした森林を抜けて草原に出る。一気に視界がひろがる。あちらこちら、点在する湖のほとりには、土産物や民宿の看板はもちろん、ボート小屋、桟橋、柵のたぐいさえ見当たらない。風景が巨大すぎ、誰もそんなことしようなどと思わない。何百年、何千年ものあいだ変わらない景色のなかを、完璧な弧をえがき、地平線の果てまでハイウェイの線がのびてゆく。
とある峠のてっぺんで、ロシアとトゥバの国境をむかえる。チベット仏教の祭壇が石と木と色とりどりの旗で高々と立ててある。訪れるものはそこらの石を三つ拾い、祭壇のまわりに石を一個ずつ置きながら三周する。これで、悪いものがとれるらしい。途中まで出迎えにきてくれたホーメイ歌手、オトクンさんが、桃色に染まった夕空の下、空っ風のような声で何度もつぶやく。
「シャーマニズムだ、シャーマニズムだ」
首都クズルの広さはおよそ大阪市の半分くらい。人口は10万と少し。通りを行く男女の顔は、大阪、京都の住宅地を歩くひととまったく変わらない。ロシア連邦のなかでも八景ロシア人の比率が少なく、トゥバ語という独特の言語をもっている。
ロシアの最近の国家施策として、地方の国々に、それぞれの伝統文化を守らせる、という方針がある。「共産主義」という巨大な宗教のかわりに、伝統や歴史、地方ごとの文化に、各国のアイデンティティを担わせようという狙いだそうだ。おかげで僕たちは昔ながらのスタイルで、ほんもののホーメイを味わえる。
オトクンさんが日本人四人を実家に招いてくれた。広い前庭を抜け、レンガ作りの玄関にはいると、もうそこで、横倒しになった羊が解体されていた。オトクンさんの親戚の男性がふたり、手際よく専用の包丁をふるっている。トゥバでは、昔からこれが、遠来の客に対する最大のもてなしだ。
じつは数年来、オトクンさんは、脳梗塞のせいで半身が不自由で、歌をうたうのもホーメイもむずかしい状態がつづいている。そのオトクンさんを、巻上さんらは日本に招き、リハビリ用の治療院に通わせた。滞在先は石原さんの自邸である。オトクンさんにとってふたりは一生の恩人。このふたりを中心とした日本人作家四名に、できうる限りのもてなしで返礼したい、そんな気持ちが、僕にはわからないトゥバ語のむこうから、磁力のようにじわじわ伝わってくる。
解体した羊は毛をむしり、残った産毛はバーナーで焦がす。肉の塊を寸同鍋に移し、塩ゆでにするのが昔ながらのやりかた。とりだした小腸に粗挽き肉を詰めてソーセージをつくる。
肉が茹であがるのを待つあいだ、居間で車座になってホーメイをきく。トゥバのひとたちは百年、千年も前からそのようにしてお客をもてなした。オトクンさんは豊かなトゥバ人脈を駆使し、いま聴ける最高の演者をふたり、その場に招いてくれた。
演奏がはじまる。ふたり椅子に腰かけ、それぞれちがった形の弦楽器を弓で弾く。地鳴りのようなだみ声のハーモニー。一コーラス目の歌唱が終わり、ホーメイがはじまる。
ふたりの頭のすぐ上で、目に見えない竜巻がうずまき、空気と空気がこすれ、居間に風が吹きこむ。トゥバのホーメイは、歌詞のある歌と歌のあいまに、間奏のようにはさみこまれる。人間が人間をこえ、音を奏でる楽器となって全身の輪郭をふるわせている。人間の息がこんな自由に跳ねまわる様を、僕はうまれてはじめて目の当たりにした。居間で車座になった僕たちは、ふたりの呼吸のなかに完全に取りこまれ、この世の目にみえる表面を自在に出たり入ったりしつづけた。「うたう」とは「息をする」「生きる」ことだと、当たり前のことが深々と腑に落ちた。
「ホーメイが、なにに似ているか」と、演奏の合間に、角刈りの、やさしげな目をした演者がいった。「風。山。せせらぎ。つまり自然です。犬の吠え声、羊の鳴き声、馬が走ってくる蹄の音、すべてホーメイになる。わたしたちは、自然そのものをうたっているんです」
家のなかに吹き巻く自然。山、川、みずうみ。馬が駆け、おおかみの遠吠えがひびく。声を浴びながら僕たちは、千年前のエニセイ川をさかのぼり、千年後の草原を高みから見おろす。ホーメイとはただの音楽じゃない、トゥバを自在に行き来するためのタイムマシンであり、どこでもドアでもあるのだ。
前庭のテーブルをかこむ。茹であがった羊肉が運ばれてくる。骨を握り、かじりつく。肉汁をのみこみながら思う。これも、食べられるかたちをしたホーメイにちがいないと。
酒屋にいくと、トゥバ作家協会の会長さんが、ウォッカの瓶を大量に抱えているのが見えた。
その日のミーティングが終わったあと、
「きみたち四人は、カーヘム地方にいきたくないか」
と会長がいった。何百年も同じ暮らしを貫く「ロシア生協古儀式派」のひとたちが住む村、エルジェイがある。ほとんど手ぶらで、なんの用意もなく会議に出ていたため、心配性の茅野さんが、
「そこ、日帰りでいけますか」
ときいた。
「たぶん」
と、会長さんはこたえた。
会長さんの自家用車に加え、二台の4WD車がやってきた。旧ソ連時代から活躍してきた、装甲車のようなヴァン「UAZ」。
町を出発してまもなく、道路は舗装をうしない、大小の石ころが転がる荒れた路面となった。UAZは速度を落としたものの、車内はぎっこんばったん、シーソー遊びのように揺れた。
やがて森へはいる。ほとんど小川のような水流を踏み越え、木の根をよじのぼってUAZは走る。会長さんも自家用車を置き、重たげな段ボール箱といっしょに、UAZの助手席へ乗りこんでくる。
古儀式派のひとたちは数百年前、ロシア中央の追っ手を逃れてトゥバまでやってきた。さらに奥、その奥へ、追っ手の足がけっして届かないほどの僻地まで。だからこそ、数百年前のままの暮らしを、二十一世紀までつづけられた。
道などない原野を野豚のように邁進する。UAZは跳ね、僕たちの手足、頭や胴は車内でバラバラにちぎれ、シェーカーのなかのカクテルみたいにごっちゃに入り混じる。四時間、五時間、えんえん揺れている。あと何時間これがつづくのかわからない、というのは正直きつい。きつすぎて、へそのあたりから変な笑いがこみあげてくる。ここまではしかし、平らだったからまだよかった。
川べりに出た。目の前の風景が信じられない。赤い岩石が、土砂崩れのあとのように、左側の山から右側の谷へ、斜面をなして積もっている。UAZはその斜面へゆっくりと乗り上げ、岩を踏んで前進する。一歩まちがえば谷底へ落下。川ではカワカマスたちが歯をカチカチ打ち合わせて待ち構えている。遊園地のアトラクションで、こんなマシンを作ったら、冗談でもやめろ、と苦情が殺到するだろう。斜めにかしぎながら岩の上で跳ねるUAZ車内は、悲鳴と頭突きと怒号の嵐。悪路の走破というより、もはやこれは一種の格闘技だ。
なあにが、日帰りでいけますか、たぶん、だ。