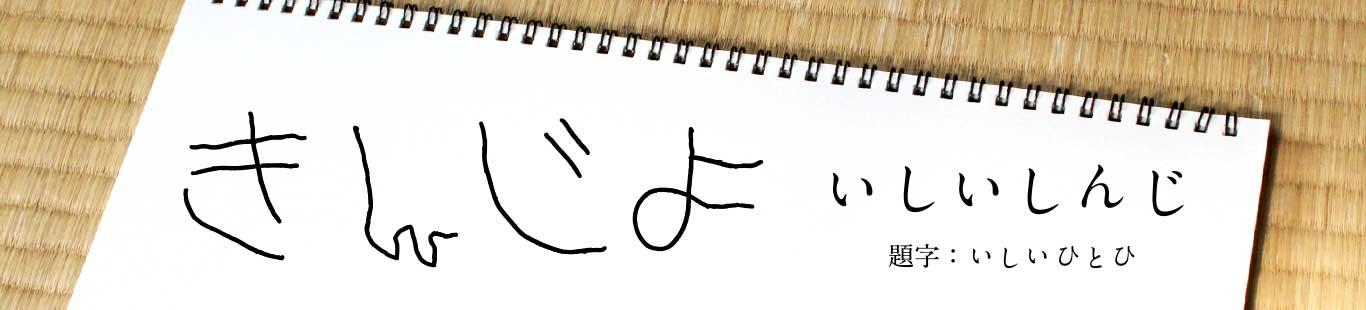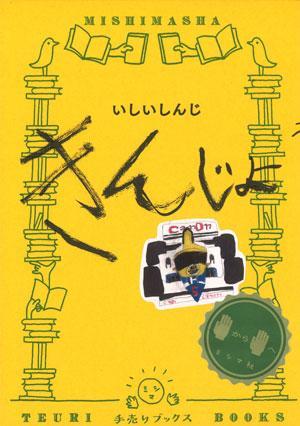第53回
きんじよマスク
2020.07.29更新

目にみえない透明なものに暮らしを理不尽に圧迫される、というのは、2011年春以降のときとそっくりだ。
ただ今回は、その同じ風景が、東京や東北や太平洋岸にとどまらず、ニューヨーク、パリ、北京、カイロ、リオデジャネイロ等々、この星の津々浦々にまでひろがっている。
ニューヨークの知り合いがこんなことを書いてきた。
「古いアパートから、ここひと月、一歩も外に出ていません。子どもたちは、階段を使ってする遊びを日ごとに発明し、さらに磨きをかけて洗練させていっています。アパートのなかだけで三組、小中学生の音楽ユニットがうまれました」
パリでも似たり寄ったりの状況がつづく。
「アパルトマンの全家族がローテーションを組み、週に一度、男性が三人、日用品の買い出しにでかけます。一階の入り口で全身に消毒スプレーをかけ、各家庭に配ります。品物はそれぞれの自宅でさらに洗浄します。缶ビールやペットボトルは石鹸で泡立て、紙のパッケージは玄関で中身をあけたあと、スプレーをかけ外に出します」
二十一世紀にはいってこのかた、僕たちは、グローバリゼーションの世界に生きている、と、そう信じ込まされていた。けれどもそれは、カネとモノだけのグローバリゼーションにすぎなかったのではないか。インターネットでイスラエルのレコード屋さんから蓄音器用のSP盤を買えるようになっても、イェルサレムのこどもがいまいちばん夢中なものはなにか、どんなおとなになりたいか、僕はまるっきり想像することさえできなかった。
コロナ禍は、そんな状況を少し変えた。
全世界じゅうの家庭が、同じように暮らしを圧迫され、同じような悩みをかかえ、同じく手をとりあって前へ進もうとしている。僕は、ニューヨークの知り合いのアパートで、子どもたちが階段をのぼりおりしながら、ときおりあげる笑い声を想像することができるし、パリ在住の、とある女性の冷蔵庫に、いまなにがはいっているか、なんとなく想像がつく。ウィルスのせいで、ウィルスのおかげで、僕たちはいま、地球のかたち、そのサイズを否応なしに実感している。世界中の子どもがあっという間にグローバライズされつつある。京都の左京区とパリの六区が隣り合わせのようにつながれる。
途方もなく広いようで、気持ちをとばせば一瞬で触れあえる「きんじよ」に、いつのまにか僕たちは住んでしまっている。
作家の石原燃さんから、Eメールがとどいた。文面をみて、僕は愕然となった。
この連載の「トゥバ」の回に何度も登場した、ウォッカ好き、いたずら好きの、トゥバ作家教会の会長さんが、コロナウィルスに感染し、亡くなった。
首都クズルの酒屋でばったり会ったとき、段ボール箱いっぱいのウォッカを抱えていた会長さん。
カーヘム地方へ、日帰りで行けますか、と作家の茅野裕城子さんにきかれ、たぶん、と鼻をかきながら受けながした会長さん。
ロシア正教・古儀式派のバンガローでの酒宴で、ワインを口にはこんでいた日本人作家たちに、「そんなのはやめてトゥバの酒をのめ」といって、コップにとぷとぷウォッカを注いでくれた会長さん。
僕は石原さんを通じてトゥバ作家協会にお悔やみのメールを送った。書き終えた三秒後、その文面は成層圏の上をまわる星々をかすめ、トゥバのクズルに降った。
訃報を伺い、ほんとうに驚きました。
ご遺族のみなさま、おご心痛、お察し申し上げます。
日本の雑誌に何編か、トゥバのことを書きました。
そのページには必ず、チュルグチュさんの影がにじんでいました。
歓迎の食事会での握手、
まちなかでばったり会ったときの笑顔、
連れていってくださったバンガロー村の星空。
クズル郊外の、あの雄大な空、山、大平原を思いだすと、
そこにチュルグチュさんの顔が重なります。
チュルグチュさんはきっとトゥバの風になって、
永遠に、あの景色のなかを旅しているように思います。
いつかきっと、またトゥバを訪れ、
チュルグチュさんの風にむかって手を合わせようと思います。
いまは、極東の島国から、
クズルのほうを向いて手を合わせています。
大平原と緑と風にかこまれたトゥバのような土地に、ウィルスがはびこる。そんなことは想像の外だった。
会長さんの死によって、クズルの町は、神戸や大阪、いや、右京区や北区よりもいっそう身近な「きんじよ」として、僕の前にありありと立ちあらわれた。ひとが亡くなるというのは、知っている誰かがこの世から消えてしまうという事件は、文字どおり、地球を揺るがすほど強烈なできごとだと、あらためて知らされた。
存在より、不在のほうが強い。
そのことは小説を書きながら、じゅうじゅう承知しているはずのことだった。二十一世紀初め、長編小説を書きだしてすぐのころ、東京で、三崎で、インタビューを受けるたび相手からしょっちゅうきかれた。
「いしいさんの小説には、目がみえないひとや、ことばが不自由なひとがよくでてきますが、どういう意図があるのですか」
意図もなにも、あらすじさえ考えず、行き当たりばったりで書いていくので、ほんとうのところはわからない。ただ、と僕はこたえた。耳や手、視力、肉親。小説のなかでなにかが欠損していれば、そこには、必ず物語が埋まっています。片腕を失ったひとが夜中にその腕を掻いてしまう幻肢のように。
あらゆる欠損、不在は、物語のはじまりです。逆にいえば、失われたなにかにまぼろしの手で触れるため、人間は、人間として生きはじめて以来ずっと、物語をかたりつづけてきたのかもしれません。
今月号の文芸誌「群像」に短編を寄せた。ふだん、時事問題やニュースとはまったくかけはなれた、ねぼすけのホラみたいな小説ばかり書いている僕にしてはめずらしく、目にみえない透明なものに圧迫される、京都の日常を描いている(といって、やはり、いきあたりばったりに書いていったのですが)。
主人公は、陸上部に属する高校生・夏実。鴨川の河原を走っていたとき、飛んできた金属バットが頭に当たって、それ以来、ひとの吐きだす息の色、かたちが、目にみえるようになる。
青い風船のような息。ハーモニカのように輝く棒状の息。花火みたいに弾ける息。噴水みたいに空へ噴き上がっていく青い息。とりどりの息に夏実はうれしくなって町じゅうを駆けまわる。学校の教師は鼻から二本、はたきみたいなかたちの息を、スピー、スピー、と吐いている。
ある日、学校が休みになる。父親の営む工務店も、お菓子屋さんも、商店街も、すべてシャッターがおろされる。
自主練で河原にいくと、ランナーたちはすべてマスクをしている。マスクのすきまからつぶれた息の欠片、残骸が、ぼろぼろと草間にこぼれ落ちる。夏実は、空中に残る飛沫や息の粒を避けながら走る。そのうち、まったく吐息のみえない(息をしていない?)謎の人物「袋田」との出会いをきっかけに、夏実の「息」の見え方は少しずつ、少しずつ、確実に変化していく。
いまふりかえれば、この短編「息のかたち」を書きだして少し経った頃、会長さんの訃報に触れることになった。だからなのだろう、小説の後半、夏実の視線は街中、学校、河原を飛びこえ、風のように地上高く舞いあがって地球をみわたす。
「また息を吐く。喉を逸らし、真上をむき。のびてゆく息の先端に意識をのせてみる。
はるか頭上、夜の雲を突きぬける。鳥の目、GPSの目で夏実は、綾なしてひろがるこの星の山稜や渓谷、海原を見おろす」
「零下四十度を下まわる氷原。吹きまくブリザード。氷を削ってしつらえた窪みに、アザラシの皮で身をくるんだ袋田が身をめり込ませ、唇のまわりを凍らせながら、雪雲の通過をひたすらに待っている」
夏実の視線で僕はトゥバを、シベリアを、パリを、ニューヨークを、ひとつの息につながれた世界としてみわたしたかったのかもしれない。その底に、会長さんがほほえみながら、ウォッカの瓶を片手に横たわっている。
いろんなことが、書いてみないとわからない。「息のかたち」を僕は、トゥバ作家協会会長・チュルグチュさんにまっさきに読んでほしくて、朝の光のなかで書きつづっていった気がする。
(了)
編集部からのお知らせ
ミシマ社主催「こどもとおとなのサマースクール2020」
講師にいしいしんじさんをお招きします!
希代のストーリーテラーであり、作家のいしいしんじさんが、文章を書くことのおもしろさを教えてくださいます!
第1部では、手を動かしながら、字を書く、文章を書くことに慣れるべために、さまざまな運動をします。そして第2部までにまとまった文章を書いてもらい、第2部ではそれをふまえ、ことばを書くことがこころにどんな作用をもたらすかをさぐります。ただ、作文を書くだけでなく、ことばによって、思ってもみない自分の内側を再発見できるはず!この夏、文を書く喜び、そして奥深さを感じながら親子で作家デビューしましょう!
「作文を書こう」いしいしんじ
◼︎開催日時
第1部:8/2(日)10:00~11:30
第2部:8/23(日)10:00~11:30 ※時間が変更になりました。
◼︎開催方法
オンライン配信(オンラインイベントの参加方法の詳細はこちら。)
※ご参加者には、イベント開催の翌日ごろ、録画動画をお送りいたします。
当日、ご都合がつかない場合も、ご安心ください。
◼︎チケット情報
全講座参加チケット(全10回):¥25,000+税 ¥15,000+税(先着50名限定)
講師ごとの単独チケット(全2回):各¥6,000+税 ¥4,000+税