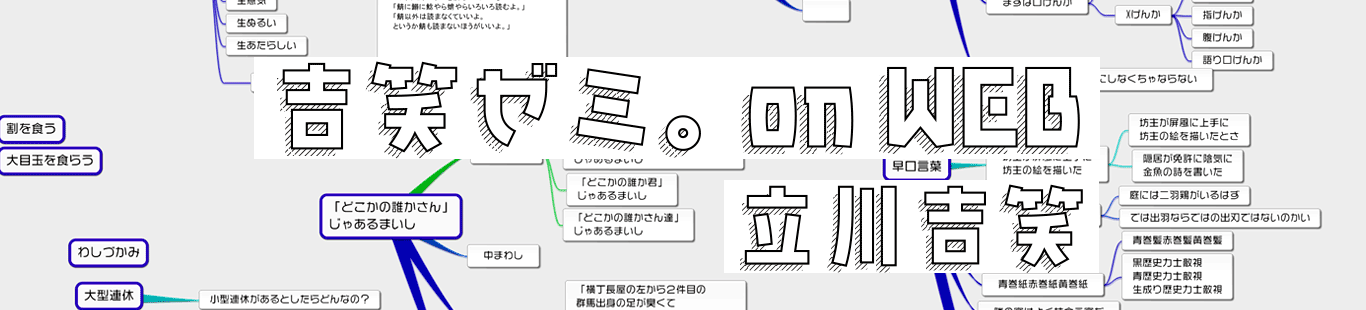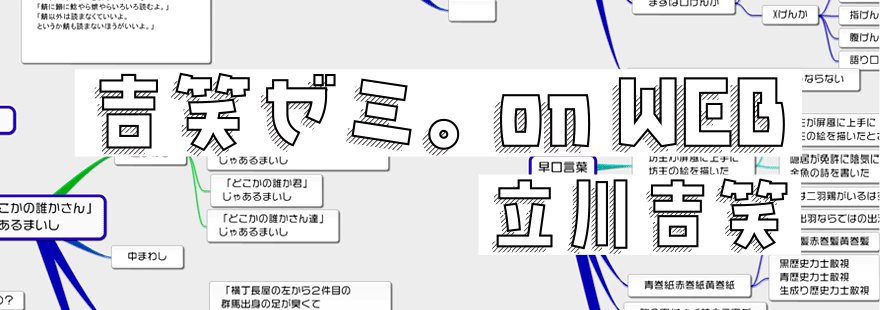第1回
1限目:オリエンテーション
2018.04.11更新
初めまして。
今回から『みんなのミシマガジン』で連載をさせて頂くことになりました、落語家の立川吉笑(たてかわ きっしょう)です。2010年に師匠である立川談笑に弟子入りして、今は8年目。34歳の若手落語家です。
いきなりですが、まずは僕のことを知ってもらうべく、こちらの高座音源を聴いて頂ければと思います。
『一人相撲』という20分ほどの一席です。自分の資料用にiPhoneのボイスメモで録音した音源なので音質は良くないですが、普段の高座の雰囲気は掴めると思います(と言いつつ、見栄を張って、結構ウケている音源をチョイスしてあります)。
通勤時間とか、お昼休みとか、散歩しながらとか、何とか20分を確保してお耳を貸して頂ければと思います。そしてお聴き頂いた後で、またこちらでお会いしましょう。
お聴きいただいたのは立川吉笑で『一人相撲』。いかがでしたか? こんな感じで東京を中心に1ヶ月で20日ほど高座を勤めています。
少し落語に明るい方だったら、『落語立川流』という江戸落語の流派に所属しているのに、関西弁の噺をやっていることを不思議に思われたかもしれません。もちろん江戸落語をやることが多いのですが、僕は京都出身ということもありネタによっては関西弁を使うこともあるのです。
そして、江戸弁と関西弁を使い分けること以外に僕の落語の特徴を挙げると、『擬古典(ぎこてん)』というスタイルを採用していることです。擬古典とは、古典落語的な世界観で作られた新作落語のことで、先ほど聴いて頂いた『一人相撲』も実は僕が作った新作落語です。もし古典落語だと思ってくださったなら作り手としてこんなに嬉しいことはありません。
もちろん古典落語も、そして現代が舞台の新作落語もやるのですが、自分が一番重きを置いているのは擬古典形式の落語です。その理由は『現在落語論』という初めて出した単行本に詳しく書いてあるので、ここでは割愛します。
『一人相撲』は2016年に作ったネタで、現時点での僕の代表作の1つだと言えます。自分らしい切り口が込められていて、なおかつ演芸としてきちんとお客様に楽しんで頂ける可能性が高いモノを僕は良しとしています。現に今年もすでに12回高座にかけていて、他のネタに比べてダントツ多いです。
少し自慢になりますが、これだけ頼りになるネタを僕は『吉笑ゼミ。』というイベント中に、即興で作り上げました。
『吉笑ゼミ。』とは、毎回様々なジャンルのゲスト講師をお招きして、それぞれの専門分野について50分間ほどレクチャーをしてもらうイベントです。このミシマガでも連載をされている「数学」の森田真生さんや「哲学」の下西風澄さん。「拡張現実」のAR三兄弟・川田十夢さんや「建築」の光嶋裕介さんなど、これまで8名の素敵な先生方に登壇して頂きました。
このイベントの肝は、ゲストの講義を僕自身も客席の後ろで聴いて、しかもその講義から着想を得てその場で落語を作り、15分の休憩を挟んだあとで生披露するということです。まるで大学生が授業のレポートを提出するように、僕は落語を提出するのです。
そんなことが可能なのか? と自分でも思いますが、追い詰められたら普段以上の力が出るのか、今のところ何とかその場で落語を作って披露できています(毎回胃がキリキリしますが)。
『一人相撲』が出来たのは、フリーアナウンサーの清野茂樹さんがゲスト講師に来られた第6回公演のことでした。
AR三兄弟・川田十夢さんの講義を受けて、当時の僕は拡張現実にとても感心を持っていました。「風を可視化する風鈴も、拡張現実の1つと言えるのではないか」というようなお話を聞いて、それこそ僕の拡張現実の概念が拡張されました。日常に潜んでいる広義での拡張現実世界に注目するようになったのです。
そんな中で、そう言えば実況中継も拡張現実と言えるんじゃないかと閃きました。たまに野球場でイヤホンを耳に突っ込んでラジオ中継を聴きながら観戦されている方がいます。目の前で実際の試合が繰り広げられているからラジオを聴く必要など無い気もしますが実はそうじゃなくて、ラジオから聴こえてくるのは解説だったり、選手の詳しい成績だったり、スタンドからは見えないベンチ裏の状況だったり。これってまさに拡張現実なのではないかと。
そこで、プロレス実況を中心に様々なイベントで実況を担当されている清野さんをお招きし講義をして頂きました。
この講義がめちゃくちゃ面白くて、例えば清野さんがプロレスの名試合「アントニオ猪木VSハルク・ホーガン」の実況を実演されたら、少しずつ目の前に猪木とハルク・ホーガンの姿が浮かび上がってくる。息づかいまで聞こえてくる。
さらには僕と猪木が戦っているように実況してくださいとお願いしたら、猪木にコブラツイストをかけている立川吉笑が浮かび上がってくる。
聴き手の脳内でイメージを補完させることで、ありとあらゆるモノが表現できてしまう実況の特徴は、まんま落語にも当てはまることでした。
ゾクゾクしながら講義を受けていると、清野さんの口から決定的なワードが飛び出しました。それは『実感放送』という言葉。
1932年に開催されたロサンゼルスオリンピックでのこと。トラブルで競技場内に中継ブースを用意できなかった日本の放送局がとった策が痛快で、アナウンサーがメモを取りながら競技を観戦し、試合が終わると近くに借りたスタジオに急いで移動して、あたかも競技場で実況しているように放送したらしいのです。アナウンサーの実感に基づく実況だから『実感放送』。
このエピソードを聞いてすぐに浮かんだのは、100メートル走で、「よ~い、ドン!」からトップの選手がゴールするまでの10秒弱を、例えば15秒かけて実況しても、臨場感ある実況であればリスナーにバレないんじゃないかということ。もっと言えば、1時間かけてわずか10秒を実況することもできるんじゃないかということ。
これが着想の種になり、この後やるネタの方向性が固まりました。
「江戸時代的な世界観」で「実況中継を登場させる」。そして「現実世界と、実況で描く架空世界とに差をつける」。
そういった条件から、江戸時代からあるもので、なおかつ現代のお客様にも想像しやすい「相撲を実況する」という設定にたどり着き、舞台は相撲が開催される両国・回向院から遠い場所の方が面白いだろう考え、大阪にすることを決めました。
そして出来上がったのが、冒頭で聴いて頂いた『一人相撲』です。
「ことごとく実況中継が下手すぎて、全然景色が想像できない」というネタになりましたが、即興でやった時はさらにひと展開ありました。
あの後、何度も奉公人を江戸に送り込み相撲中継をさせた結果、どんどん中継技術が向上し、ついには架空相撲の方が実際に相撲を見るよりも面白くなってしまった世界を描きました。架空相撲の方は聴き手が脳内で補完できたら何でもありだから、それこそ「張り手を受けた力士が空高く吹っ飛ばされるけど、入道雲を掴んでギリギリ助かる」みたいに夢見たいな取り組みを表現することもできるから、それを楽しみにするファンがどんどん増えてきた。
架空相撲に大勢の見物衆が集まるようになり、ついには会場に入れなくなった旦那さんが、最終的には奉公人に架空相撲の様子を見てきてもらい、それを実況してもらおうとするという、振り出しに戻るオチです。
即興でネタを披露するときは、当然ですが細かいセリフや構成が決まっていない状態で高座に上がることになります。「こういう感じにしたい」というコンセプトだけを用意して高座に上がるから、逆にそういう時の方がテーマ的には根っこまで迫れることが多いです。
『一人相撲』もバーチャルがリアルを超えていく部分を描いた初演の方が、聴いてもらったバージョンよりも鋭く実況中継というモノに迫れている気がします。
しかし一方で、落語家はお客様に楽しんで頂くことが一番大事だったりします。いくら良いコンセプトのネタを作っても、笑ってもらえなかったら本末転倒です。
何度も実際に高座でやってみて、お客様の反応からブラッシュアップした結果、後半の展開はすっぱりカットして、今の形に落ち着きました(聴いて頂いたバージョンも少し前のものだから、今はまた少し修正を加えてありますが)。
さて、話はこの連載についてに戻ります。
僕が『吉笑ゼミ。』を始めたきっかけは、勉強する楽しさを多くの人に伝えたいと思ったからです。落語家ごときが何を偉そうに、と自分でも思いますが、本当にそう思ったのです。
少なくとも僕の周りでは、「勉強」というだけで退屈なものだったり、難しいものだったり、面倒なものだったりとネガティブな印象を持たれてしまうことが多いです。でも本来、知らないことを知る瞬間、人は鋭い喜びを感じるものだと思うのです。
知らないことを知る瞬間。例えば「風鈴も拡張現実の1つだ」という新しい考えに触れた瞬間、少し大げさかもしれませんが、さっきまでの自分じゃなくなる感覚を伴うことすらあります。これまでとは世界が少し違って見えるのです。
『吉笑ゼミ。』では、ゲスト講師をお招きすることで、知らないことを知るきっかけを用意します。そして、僕も一人の生徒としてお客様と同じ講義を受けるだけでなく、講義を聞いて考えたこと、思いついたことを落語という形で発表します。
お客様にはその落語を楽しんでもらいたいのは当然として、それ以上に同じ講義を聞いて「自分はこんなことを考えた」「こんなことを閃いた」と、自分自身に起こった変化を楽しんで頂きたいと思っています。同じ講義を受けたのに、お互い全然違うことを考えられたことって不思議だし、楽しいと思うのです。
思えば知らないことを知る瞬間、学びのきっかけは、日常のあらゆるところに潜んでいると思うのです。この連載ではゲスト講師をお招きする代わりに、身の回りにあるあらゆるモノ、日々のちょっとしたほつれを題材に、僕が感じ、考え、学んでいく様子をお伝えしたいと思っています。
そして願わくばこの連載が読者の皆さんにとって新たな学びの糸口になればこんなに嬉しいことはありません。