第1回
2023.06.16更新
僕はいま、京都の東山の麓の小さな古民家を日々の仕事場にしている。山との距離が近く、いつもいろいろな生き物たちが、季節のささやかな変化を知らせてくれる。
裏庭には小さな菜園があって、野菜や山野草、果樹やハーブなどが、ほとんど無秩序に植えられている。そのなかに、小さなレモンや山椒の木もあって、春になるとここに、アゲハチョウが卵を産みにくる。レモンは、いま七歳の長男が三歳で、いま三歳の次男がまだ生まれてまもない頃に、周防大島の友人にもらったレモンの種を、ここに長男が植えたものである。背丈はまだ低く、実がなったこともない。それでもこの数年は、アゲハが必ずここにきてくれるようになった。
今年も五月の初旬に、目の前でアゲハが産卵する様子を、子どもたちと見ることができた。周囲を念入りに確かめるようにあたりを飛びまわったあと、チョウはさっとレモンの葉に降り立ち、くっと尻をまるめて葉の裏に卵を産みつけていく。生まれたての卵は、まるで宝石のように、春の光に照らされて眩しく輝いていた。
日本では、春に新しい学期が始まる。無事に冬を越えた植物たちが、ひとつまたひとつと芽や蕾を開き、虫たちの動きがにわかに活発になり始める頃、人間もまた、新鮮な気持ちで、新しい生活を始める。入学や進学を迎える子、その子を送り出す親・・・・・・みなそれぞれに期待や不安で、心が騒がしくなる季節でもある。
子が育つ環境を思いやる親の心は、人間だけのものではないだろう。数ある植物のなかから、アゲハの母は、やがて産まれてくる子のために食べられる葉を選び、慎重にそこに卵を産みつけていく。新しくやってくる子たちのためにと、親が子の育つ環境を選び、場所を整えていくのだ。
子は親のそんな思いを知ってか知らずか、卵の殻を破ると、母が選んだ場所で、その植物の葉を食べながら、すくすくと育っていく。もちろん、子は親が選んだ環境に守られるだけではない。アリやクモ、ハチや鳥など、身近に脅威はあふれている。生まれてきたイモムシのなかで、サナギにまで育つことができるのは、全体のなかのごく一部でしかない。
子は自分で一から環境を選ぶことができない。親がどれほど慎重に選んだ場所でも、それが子にとって最善とは限らない。だから生まれてきた子どもは、自分がたまたま生まれ落ちた場所から、とにかく生きることを始めてみるしかない。
「新しい」とは、どういうことだろうか。それは、ただゼロから始めることではない。母から子が生まれ、古木から若い枝葉が芽吹いていくように、遠く、古くから続くものに支えられていてこそ、いのちは「新しく」あり続けることができる。
地下から湧き出す新鮮で清冽な水は、かつて地上に降った雨が、大地を通って浸み出したものだ。地上に降り注いだ雨が、地下に浸透して地下水となってから、湧き水などの形で流れ出していくまでの時間は、世界の地下水の平均で六百年超にもなるという(『見えない巨大水脈 地下水の科学』)。何年もかけて地中を経めぐり、ようやく地上に現れてきた水を、僕たちは「新しい」と感じる。新しさと古さは本来、矛盾し合うのではなく、支え合うものなのである。
子どもたちのいのちは新しい。
清冽な湧き水のように、力漲る芽吹きのように、若く、瑞々しく、そしてその来歴は、古く、懐かしい場所へと通じている。
河合隼雄は著書『子どもの宇宙』のなかで「老人と子どもとは不思議な親近性をもっている」と指摘している。
子どもはあちらの世界から来たばかりだし老人はもうすぐあちらに行くことになっている。両者ともあちらの世界に近い点が共通なのである。
新しいことは無から始めることではない。滅びることは、無へと消えていくことでもない。生成と消滅は連続している。その連続性を、哲学者で詩人の下西風澄は「精神史」という文脈で次のように美しく描写している。
消滅とは、無への抹消ではない。人間における心の消滅とは、別の再生のための潜水、巨大な来歴のうねりのなかへの回帰だ。生成とは無からの創造ではない。人間における心の生成とは、夥しい数の失われたものたちからの再生である。
下西風澄「生まれ消える心――傷・データ・過去」
(『新潮』5月号)
「夥しい数の失われたものたち」から、すべてのいのちは生まれ出てくる。誰もがやがてふたたび回帰していく「巨大な来歴のうねり」への近さという点で、子どもと老人のあいだには、「不思議な親近性」がある。
子どもとともに生きることは、この「巨大な来歴のうねり」を近くに感じ続けることである。彼らの言葉や声を通して、いのちの「新しさ」を支える「夥しい数の失われたものたち」を身近に思い続けることである。
哲学者のティモシー・モートンは、著書『Humankind』[1]のなかで、「humankind」という言葉に意外な意味を吹き込んでいく。
僕たちはただ、「人間でないもの(nonhuman)」から切り離された「人間(human)」なのではない。「humankind」とは、自分を取り巻く無数の者たち
「a kind of ・・・・・・」「a sort of ・・・・・・」といえば、「・・・・・・のような」「・・・・・・みたいな」という意味の表現である。新鮮な野菜のために骨身を削って働く農家は、雨や太陽、季節の虫たちの訪問を、まるで野菜そのものであるかのように感じられるかもしれない。子を思う親は、ときに自分がその子自身であるかのように、悲しみ、笑い、傷つくかもしれない。「自分らしく」あれるからではなく、自分でないもの「のように」なれるからこそ、僕たちはみな本来「human - kind」なのである。
自分がウイルスでもなく細菌でもなく、太陽でもなくキノコでもないということが「人間である」ということなのだすれば、人間であるという感覚を維持し続けることは、ますます難しくなってきている。何しろウイルスや細菌の一切の侵入をなくしてしまえば、僕たちは自分自身であり続けることすらできない。僕たちはただ「人間である」だけでなく、ウイルスのように、細菌のように、太陽のように、キノコのように、様々な自分でないもの
カエルの近くでカエルのようになり、松の手入れをしながら松のようになる。子どもの近くにいれば大なり小なり、子どものように感じ、子どものように考えるようになる。それはhumankindの性なのである。
子どもは単に「若い」のではない。古く、懐かしい生命の「来歴のうねり」からやってきたばかりだからこそ、その感性は瑞々しく、その魂は新しい。子どものように感じ、子どものように考えること。そうすることでしか見えない風景がある。
それはただ、子どもに戻ることではない。子どものそばにいて、もう子どもではない自分が、それでもまるで子どものように感じ、子どものように考えてみる。そうして生まれてくる思考や感覚を、試みとしてここに記録してみたい。
二〇二〇年の春から今年の三月までおよそ三年にわたり、ミシマ社に主催してもらい、瀬戸昌宣さんと協働するかたちで、「学びの未来」をめぐる対話や思考を重ねてきた。この連載は、ここで重ねられてきた対話や思考の「続き」でもあり、また、二〇一九年の冬から三回にわたって連載をしてきた「聴し合う神々」の新たな文脈での再出発でもある。
「人間らしさ」や「自分らしさ」を支えるこの世界の地盤は揺らいでいる。しかしだからこそ、あらかじめ決められた「らしさ(identity)」にしがみつくだけでなく、「やさしさ(kindness)」が伝播していくような学びの場所を作りたい。そんな思いで、「みんなのミシマガジン」のこの場を借りて、新しい連載を始めてみたい。
イモムシは母が選んだ葉を食べながら育つが、そのときに母はもういない。夥しい数の「らしさ」が生成消滅していく世界で、それでも伝わり続けていく「やさしさ」がある。
まずは身近なところから始めてみたい。子どものように、子どもみたいに感じ、考えてみる練習――「human」から「humankind」への生まれ変りの
[1] 邦訳は、『ヒューマンカインド 人間ならざるものとの連帯』(篠原雅武訳、岩波書店、2022年)。
編集部からのお知らせ
本連載と連動した、森田さんのトークライブを開催!
 【6/30(金) @SPBS本店】
【6/30(金) @SPBS本店】
森田真生「子どものように考える 2023初夏」
2020年の春から、森田真生さんと瀬戸昌宣さんを中心に、ミシマ社では「学びの未来」を考える場を主催してきました。そこでは主に、「学びの未来」や「学びの場をつくる学校」のコミュニティメンバーに向けて発信されていた森田さんの「子ども」と「学び」をめぐる思考ですが、今月から、より多くの方に開かれた形で、その「続き」を展開していただくことになりました。
また、ミシマガジンで連載「子どものように考える」もスタート。本連載と連動していく形で、森田さんのトークライブも各地で開催していきます。
そのトークライブの第1弾を、6月30日に渋谷のSPBSさんで開催します。
独立研究者・森田真生がいま、見ている風景とはいかなるものか?
当日は、オンライン配信はせず、会場のみの開催となります。
ライブでしか体感できない森田さんの肉声とその振動をたっぷり味わっていただければ幸いです。
日時 6月30日(金)18:30〜20:00 (18:15開場)
会場 SPBS本店
住所 東京都渋谷区神山町17−3 テラス神山 1F
出演者 森田真生
参加費 4400円(税込)




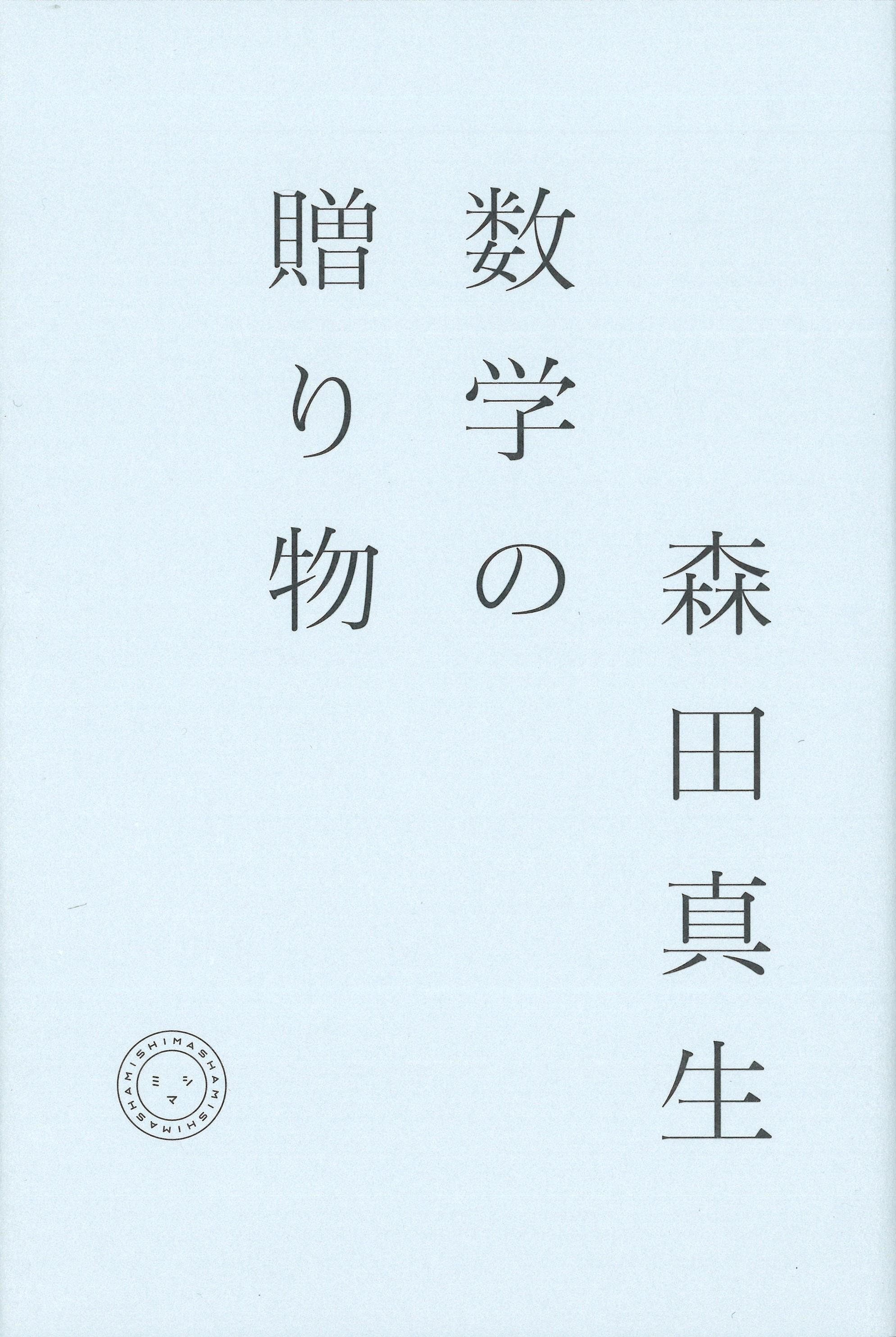
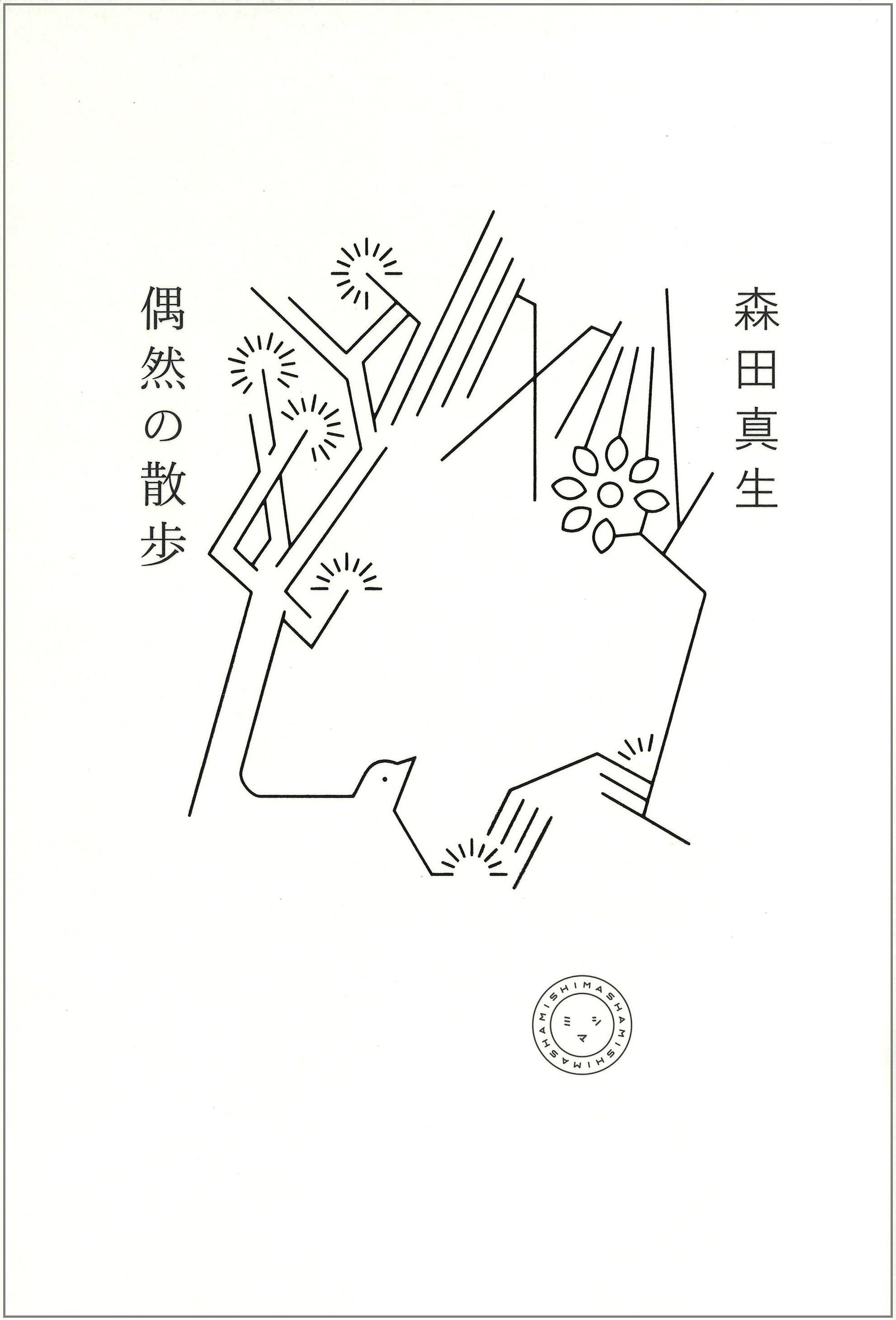

-thumb-800xauto-15055.png)



