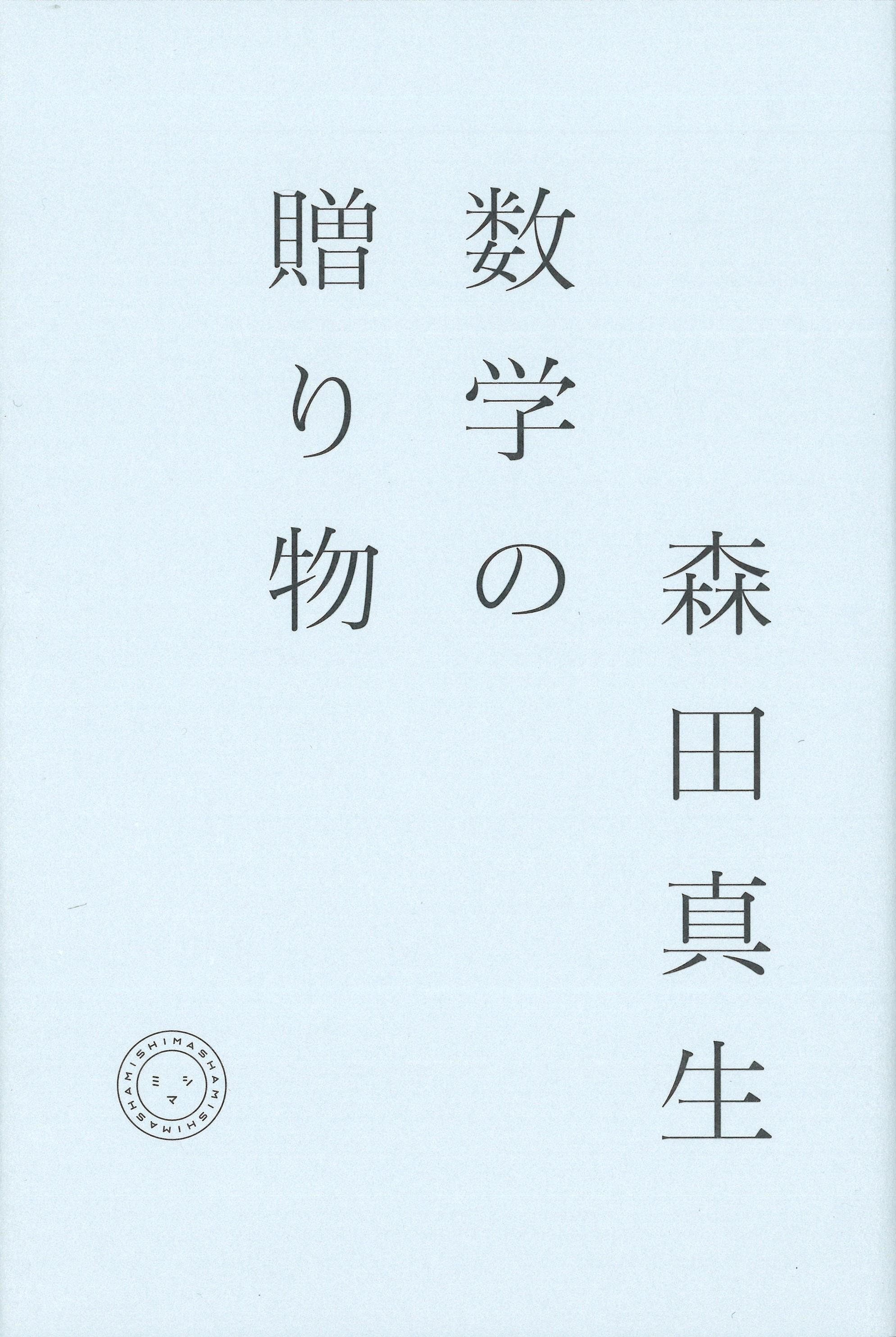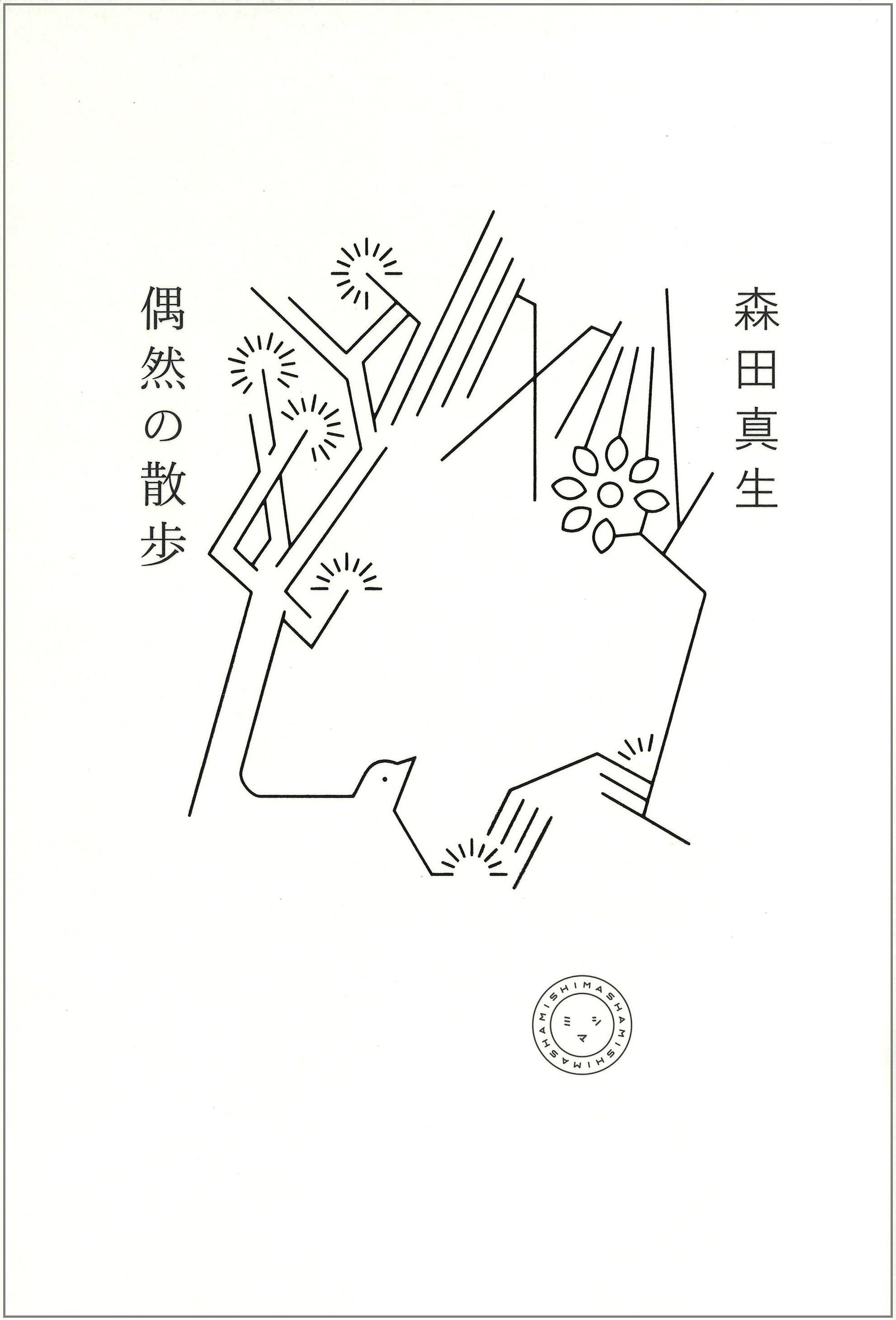第2回
2023.08.18更新
六月のある日のこと、「家の前に大きなカタツムリがいたよ」と言いながら僕が帰宅すると、長男が「見てくる!」とすぐに玄関を飛び出していく。
「おっくんも!」と次男が後を追う。
家の前にカタツムリがいたと聞いて、すぐに玄関を飛び出していく大人はあまりいないかもしれない。だが、子どもは何事も自分の手と目でたしかめたい。誰かから聞いた「情報」だけではけっして満足しない。
大きなクワガタの角を指でなでる。セミの筋肉の震えを手で感じる。逃げようとするカエルを自分の力でとらえる。図鑑で何度も見た虫や動物であっても、自分の手で捕まえ、自分の目で見てみたいのだ。川があったら足を入れてみたいし、雪が降れば全身が雪まみれになるまで遊びたい。
彼らはいつも、経験に飢えている。その情熱に僕はいつも圧倒されるばかりだ。
水に濡れ、石を投げ、たんぽぽの綿毛を風に乗せて飛ばす。それだけで、彼らは目を丸くして驚く。何かを見たり、触ったりするだけで、いまは面白くて仕方ないのだ。
自分の身体を動かし、この世界にじかに触れられるということ。それがどれほど驚くべきことかを、僕たちは次第に忘れていく。生きている限り、自分の身体はいつもここにある。いつもあるものにいつまでも驚き続けるのは、簡単なことではない。
何かが「ある」ことの驚きを思い出すためには、何かが「ない」と想像してみることが役に立つ。身体があることが当たり前ではない状況を、想像してみることはできるだろうか。
先日、テッド・チャンの「ソフトウェア・オブジェクトのライフサイクル」(大森望訳『息吹』早川書房、所収)という中編SF小説を読む機会があった。ここに登場する「ディジエント」と呼ばれる、デジタル仮想環境で生きる人工生物たちは、まるで子どものようにいつも経験に飢えている。何しろ彼らは、ソフトウェアなのである。コンピュータでシミュレートされた世界の外にあるものに、じかに触れることができる「身体」を持たない。
そんな彼らは、人間がつくったロボットの筐体のなかに入っているときだけ、外界と触れ合うことができる。借りものの身体に接続されているときだけ、物理世界を動き回ることができるのである。
想像してみてほしい。
もし身体を使って世界に触れられる時間が、あらかじめ限定されているのだとしたら。やがて、身体を通してこの世界とじかに触れ合うための、あらゆる手段が失われてしまうのだとしたら。いましか使えないこの身体を使って、何に触れ、何を見、何を聴こうとするだろうか。
この小説のディジエントたちは、この世界の「手ざわり(texture)」に魅了された。彼らが暮らしている仮想空間では、オブジェクトの表面の細かな手ざわりまでは実装されていない。デジタルな仮想空間は、表面的な視覚のディテールこそつくり込まれているものの、そこに摩擦以上の触覚を生み出す要素はない。
だから彼らは、ロボット筐体につけられたセンサー・パッドを介して、初めて世界の表面に物理的にアクセスできるようになったとき、まずその手ざわりに夢中になった。あるディジエントなどは、持ち時間の最初から最後まで、「ビルの階段に敷かれている滑り止めのざらざらした踏み板」をひたすらさわって過ごしたほどである。
蝉の筋肉の震えを指で感じる。クワガタの大きな角をなでる。蝶を追う。穴を掘る。採れたてのトマトを頬張る。子どもたちもまた、身体を与えられたばかりのディジエントのように、目の前にある世界に全身で触れることに夢中だ。
身体を自分で動かせることは、当たり前ではない。身体を通して世界と触れ合える「持ち時間」は限られている。身体的な経験の可能性の条件そのものが、いつまでも続くわけではないという点では、人間もまたディジエントたちと同じ状況にある。
夏休みは毎朝のように、早朝から子どもたちに「虫とりに行こう!」と誘われる。虫を探しに行くのは、いつもほとんど決まった場所ばかりである。どこか遠くへ冒険に行くよりも、いつもと同じ場所を「また探す(re-search)」ことが、彼らにとっては何より楽しいらしい。
同じ場所でも、探しに行くたびに、違う何かが見つかる。もちろん、何も見つからないときもある。とろうとしてとれない、つかまえようとしてつかまえられない――そのくり返しこそが、虫との交流である。
追いかけた蝶が虫網をかわす。狙っていた蝉が、空高く逃げる。そのたびに僕たちは学んでいく。何かを「つかむ(take)」瞬間の喜びは、何度も「つかみ損ねる(mis-take)」経験のくり返しの先にある。
わかることはいつも手探りである。未知の何かをわかろうとするとき、あっちか、こっちかと、細かな推測を重ねる。あっちではない、こっちでもない、あれでもない、これでもないと、小さな推測の誤り(mistake)を重ねながら、少しずつ何かをわかっていく。
Gradually arrive at what this is through at least ten guesses.
少なくとも十回の推測を重ねながら、これが何であるか、少しずつ近づいてみなさい。
壁に張りついた謎のオブジェクトの下に、このような指示が書き込まれている。荒川修作とマドリン・ギンズの「The Mechanism of Meaning(意味のメカニズム)No.2」第四章「Degrees of Meaning(意味の諸段階)」の作品の一つである[1]。
壁に張りついているのは、赤い四角の謎のオブジェクトである。子どもたちは「レンガ!」「化石?」「机の足」「赤い宝石!」などと、いくつもの推測を重ねながら、未知のオブジェクトに近づいていく。
よく考えて一発で正解しようとするのではなく、いくつもの推測を、間違いとして重ねながら、少しずつオブジェクトのそれまで見えなかった側面を見つけ出していく。まっすぐ正解に向かおうとするのではなく、手ざわりをたしかめるように、なでるように、小さな試行錯誤をくり返していく。
手ざわりをわかるためには手を動かしてみる必要がある。肌の手ざわり、生地の手ざわり、土の手ざわり・・・・・・何を触るにしても、ただまっすぐ手を伸ばしてぴたっと指を当てるだけでなく、あっちへ、こっちへと、時間をかけてゆっくりとなでるように、肌や生地の質感をたしかめていく必要がある。動きながら感じ、感じながら動く――そうして「少しずつ(gradually)」そこにあるものが何であるかをわかっていけばいい。
身体があるということ。それを自分で動かせるということ。だからこそ、時間をかけてじかにものに触れ、推測と間違いを重ねながら、未知の何かに
目の前にあるものに触れ、舐め、握り、転がし、叩き、咥え、放り投げてみながら、意味は、少しずつ見つけていけばいい。ときにはこぼし、壊し、転び、落とし、破れ、傷み、何度もつかもうとしたものを「
MIS-TAKE & RE-SEARCH.
自分だけの間違いをいくつも重ねながら、何度でも同じ場所を、また探し続けていくのだ。
[1] 引用箇所は筆者訳。現在、軽井沢のセゾン現代美術館で《意味のメカニズム》全作品127点を公開する展示会を開催中(会期は10月9日まで)。機会があればぜひ足を運んでみてほしい。
編集部からのお知らせ
本連載と連動した、森田さんのトークライブ第2回を開催!
本連載は、エッセイの更新と連動して、森田さんのトークライブを行っていきます。
第2回ライブは、オンラインでの開催が決定しました!
森田さんは2020年の春から、瀬戸昌宣さんとともに「学びの未来」を考えるプロジェクトを主催してきました。「子どものように考える」は、その延長線上で、森田さんの「子ども」と「学び」をめぐる思考をより多くの方に開かれた形でお届けしていきます。
今回のキーワードは、「MIS-TAKE & RE-SEARCH」(つかみ損ね、また探すこと)。
森田さんが、今まさに見ている風景は、どんなものなのか。
アーカイブ配信のない、一度かぎりの臨場感あふれるライブです。その場だけに立ち上がる豊かな時間を、ぜひお楽しみください。
日時:9月19日(火) 19時〜20時半
出演:森田真生
形式:オンライン配信
参加費:3,850円(税込)