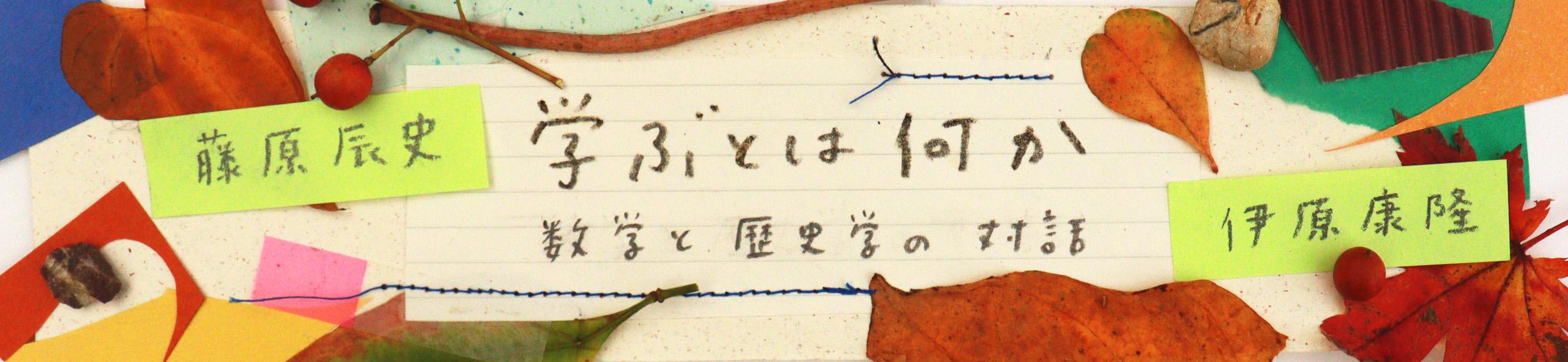第4回
「本物」と「わからない」という試金石(伊原康隆)
2021.12.20更新
歴史学者の藤原辰史さんと数学者の伊原康隆さんによる、往復書簡の連載です。藤原さんから伊原さんへの前回の便りはこちらから。
伊原康隆>>>藤原辰史
大変興味深く拝読いたしました。文系、理系の相違を超えて共感するところ大でした。様々な連想が日替わりで湧いてきましたが、その一部を含め、自分が慣れている言葉で書かせていただきます。
まず「高校などで大人が用意する探」と私の意味の「探」の関係について。窓を開けてもらったり背中を押してもらったりする前者は、生徒にとっては「教育環境の状態」。他方、私のイメージの「探」は、何かに(知的な)火がついた「個人の心の状態」に関する言葉です。同一方向に向かうとも限りません。環境が与える「正の方向」に向かうのと、生徒が反発して逆方向に向かうのと、両方あり得るわけです。若者ですから背中を押されるより自分の足で蹴って進みたいという本能的な欲求もあることでしょう。とにかく両方向ありですから、まずこれらを別々なものとして区別し、概念としてはむしろ対立させて論じたいのです。蹴る足と蹴られる地面、あるいはプラス電荷ともう一つの「マイナスまたはプラス電荷」のように。藤原さんが提唱された「縁学」は、極めて含蓄豊かだと感じますが、これは論としては第二以降の段階で導入するほうが自然な複合概念(両者の結合体のような)ではないでしょうか。ご意見をお伺いします。
さて、自分を発見するためには「本物」と「わからない」の二つを大切にしましょう。これが私の本音です。「本物」が「外なる試金石」なら「わからないという気持ちを大切にすること」は「内なる試金石」であろう。さまざまな本物に接する中で、何に興味が持てるかを知る 。何に対してなら「自分には、まだわからない、もっと知りたい」と心から思えるのか、そして思えたらその気持ちを何よりも大切にする、これが個性発見に繋がるのでしょう。本物、知りたい、わからない、アッそうか! の順で。藤原さんの場合、本物ドストエフスキーに出会い、最初わかりづらいと感じつつもそれを大切にされ、乗り越えてこられたのでしょう。
関連して次のエピソードを紹介しましょう。やや進んだ深入り段階の話ではありますが。
パリの美術館にフランスのある著名な画家の絵が展示されており、その一つを眺めていたある日本人が、あれ、もしかして上下逆ではないか? という思いにとらわれた。そのうち誰かが気づいて直されるだろう、とも思ったが翌年もそのままだったのでそれを伝え、結局展示の上下は正され、当地の新聞にもそのことが載った、という話です。かなり有名な話で、ご存知かもしれません。
画家はクロード・モネ、絵は彼が晩年よく描いた池の睡蓮作品群の一つ、場所はパリのマルモッタン美術館、時は1970年代初頭、逆展示に気付いて指摘したのは光通信の大家(故)西澤潤一氏でした。いわば光の両大家ーー芸術方面と科学方面ーーの、時代と国境を超えての「ご対面の図」。そこから生まれた話です。
これを単に、たまたまの出来事だとか誰かの過ちに気付いて恥をかかせた話だとかみる人もいるかもしれませんが、私はこれこそ文化を学び支える重要な要素が読み取れる含蓄豊かな話ではないかと思っています。西澤氏はモネの大ファンだったそうですから、まず作者への半端でない敬と愛があります。当然、自身の眼でこの作品も直視したいーーとしばし佇んだことでしょう。そして睡蓮の絵では、水面が鏡の如く上部の様々な景色を映しています。どの光が直射でどれが反射か。うーん、おや? まさか? と首を傾げたあと、上下逆にした場合の絵も頭でイメージしてご覧になったことでしょう(青年時代の彼なら「天橋立の股覗き」風もあり得たかもしれませんが)。そして、お、上下逆ならピッタリだ、とわかった、それで権威ある美術館が如何なる判断をしていたとしても自分の判断が正しいと確信できた、ということでしょうか。
本物への愛、
探の心による自分の眼での直視、自分の頭での分析
見えないものもイメージしてみようとする習性(これが大切)
自分の判断の明確化とそれへの自信
どれもが普遍的な重要性を含んでおり、ともすれば薄っぺらくなりがちな現代、それらは大切なことだぞ、と西澤氏が暗に教えて下さったのだ、この教訓は大勢で共有してしかるべきだと思った次第です。
私が前回書いた「授業がつまらなかったらクラスメートのことを考えたら?」について、藤原さんは新鮮味を感じたと言って下さいました。いつから私がこう思うようになったか記憶が定かでありません。でもその後の関連した記憶についてならお話しできます。その一つは、秋月りすさんの4コマ漫画集「OL進化論」(40数冊、長い間の寝る前の友達です。ちなみに共同研究の仲間だった名大の松本耕二君も彼女の漫画の大ファンと知りびっくりしました)の中のどこかで、カチョウ夫人が「数学は苦手、こんなことを勉強して何になる」と拗ねた息子に向かって「でも数学が得意な子もいるでしょう、どう思う?」「それはすごいと思う」「そう、そういうことがわかるだけでも大切なことと思わない?」のようなやり取りがありました。
もう一つは村上春樹さんの自伝的な小説の中に「僕は微積分計算にはこれっぽっちも興味が持てなかった、バルザック全集を読破する方がずっと愉しかった」(短編集『一人称単数』中の「クリーム」)、「学校の授業はおおむね退屈だった」(『猫を棄てる』)といったくだりがあり「ふーむ」と考えさせられました。ここでは、まずは微積分の弁護を、次いでどう教えられたかの推測、そして書かれていない部分から読み取ったことを書いてみます。
「変化と結果との関係に思いをはせ、変化の規則を知って結果を予測する」
これが生物が生きてゆく上で根本的に重要、とは誰しもが認めるでしょう。野球で外野飛球が打たれた瞬間だけを見て、上手い外野手は一目散に後ろ向きに走りピッタリな場所とタイミング(と高さ)でジャンプ、キャッチできる。これは体が経験の蓄積によって無意識に「積分」しているからですね。甲子園の浜風など風向きも頭に入れてあって。初期条件と変化の規則が分かっていれば結果がわかる。この理論的な基礎づけが積分法、逆に結果の推移から変化の規則を知るのが微分法。これらは互いに逆演算になっていて微分の方が計算しやい、という事情を積分を計算するのに組織的に利用する知恵。「僕」には興味が持てなくても、自分の住む社会がそれを活用できることの大切さにも思いを馳せてほしい。
でも多分、授業ではこう言う風には教わらない。私もこう教わったわけではない。授業で本質的なことを言ってくださる先生は稀でしょう。先生が普段の授業で教えるのはその使い方の手順です。そして手順など、たしかに村上春樹さんに興味が持てなかったことでしょう。村上さんは「僕は」と自分の主観であることを明示した上で微積分やそういう授業をばっさり切り捨てておられます。そこを補っての私の感想は、この拒否(と『バルザック』の選択)は村上さんにとっての根源的な「探」であったのだろう、他方、微積分を役に立て得る生徒がいて然るべきなのだから、彼の「かっこ良い切り捨て」はそれ以上の影響力を持ってほしくはないな、でした。
なお、世の中で起こる変化は大抵は「規則的」どころではなく、そこには偶然としか言い表せないほど複雑な要素が入ってきますね。早い話、ヒットラーの両親がたまたま出会っていなかったら歴史は同じではなかったでしょう。この世の変化は「外野飛球のようにすら」規則的ではない。微積分が万能だとは数学者自体が決して思っておりません(念のため)。
今回のが年越しバトンになりましたが、来年(正月早々!)もよろしくお願いいたします。皆様どうぞ良い年をお迎えください。