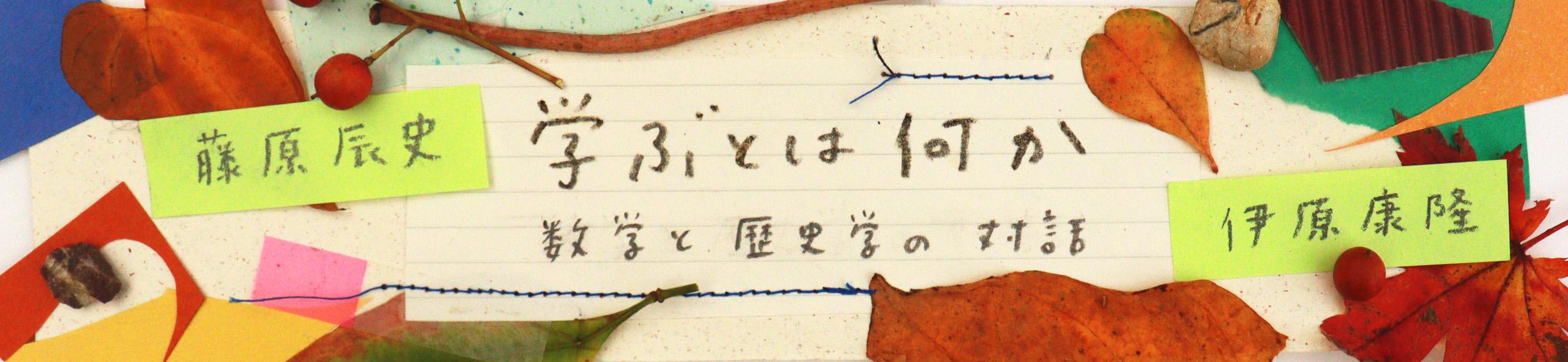第7回
歴史学習における「したい」と「しなければならない」(藤原辰史)
2022.02.11更新
歴史学者の藤原辰史さんと数学者の伊原康隆さんによる、往復書簡の連載です。伊原さんから藤原さんへの前回の便りはこちらから。
藤原辰史>>>伊原康隆
「本物とは何か」という直球の質問に対して、直球でお答えいただきありがとうございます。伊原さんの言葉を読んでいると、これまで私が身につけてきたさまざまな「見方」の重装備ぶりを指摘され、それをいったん取り外していいんだよ、と言ってくださっているようです。これも不思議なのですが、伊原さんとお話をしていると、小さい頃は自分の心に直撃していた「鼓舞する気持ち」や「打ちのめされて、しばらくぼんやりする気持ち」がよみがえってきます。なので、今日からもっと羽を伸ばしてお便りが書けそうです。
重装備を解除する前に弁解を少し。人文社会科学の訓練を受けていく中で、私は、「すべてを疑え」というマルクスのモットー(彼は娘の質問に対してそう答えていたことを、ドイツのトリアーの彼の清生家にあるマルクス博物館で知りました)に忠実に、真偽、正否、美醜など、その価値体系の背後にある社会的構造や権力構造を読み取る癖を身につけてきました。上記のことはもちろんとっても大事なのですが、それを内面化しすぎた人文社会学者の一部は、「素直に心が動かされない」という病にかかっているのかもしれないと思うことがあります。
さらに、このような見方には、あきらかに限界がきています。とりわけ日本では、優れた例外を除いて、先輩研究者たちの研究との差異にこだわりすぎるせいか、自分のモチーフの弱い、スケールの小さな作品が増えているような気がします。人文社会科学の作品に接したり、発表を聞いたりする中で、「屈折すること」や「素朴でないこと」が目的になってしまい、「これはたまらん」という体験が減っているように思えます。私は、ある種の「ポーズ」であり、鎧である過剰な屈折が人びとの心に届かない理由だと思い、もちろん事実にまつわる権力性を十分に理解し分析した上で、諸先輩よりももっと素直に対象と交流できないか、と考えてきました。伊原さんがずっとおっしゃっている素直に作品や対象と出会って、無条件に「敬」が沸き起こるような気持ちですね。ですので、人文社会科学も、もっと言えば人文学そのものも、数学と同様に、芸術の世界に極めて近いところに存在すると私は感じています。久しぶりに童心に帰って無邪気にじっくりと「梅の花」を眺めることを教えてくれた伊原さんに感謝です。焦ってはならない、つまり結論を急いではならない、という戒めは、歴史学にもあてはまります。
とにかく、伊原さんの「大学は客観的評価ばかり気にせず、より深い実地体験をしてそれを生かせる人物を大切にせよ」というご意見には諸手を挙げて賛成で、客観的評価を文科省から得るために膨大な書類を研究者に押し付けることを続けていけば、近いうちに、日本から優れた研究が出なくなることは目に見えていると思います。
さて、次回はいよいよ伊原さんから数学のお話が聞けるとのことで、楽しみでなりません。私は、専門の歴史学の「したい」と「しなければならない」の連鎖について、少しだけ思うところを述べるにとどめておきます。
私は高校の世界史や日本史で覚えてきたはずの膨大な知識は、学生になって、専門の現代史をのぞいて、もったいないことにほとんど忘れてしまいました。あれだけ一生懸命勉強したのに。やはり、「したい」が少ないにもかかわらず「しなければならない」ことを大量にしてしまったツケだと思います。では、高校でどんな歴史教育が理想的でしょうか。来年度から「歴史総合」が始まり、それがある意味の出発点になるのだと思いますが、私はこんなことを考えます。
(1)歴史家たちの論争に加わる
イギリス近代史を専門とされ、チャリティの研究をしてこられた金澤周作さんを中心に中堅の歴史学者が、高校生や大学生など初学者向けに面白い本を編集されました。『論点・西洋史学』(ミネルヴァ書房)というものです。私も参加させていただいていたのですが、どの項目も読んでいて飽きません。第一次世界大戦の原因は何だったのか(ナショナリズム、ドイツの責任、ドイツの金融的脆弱性化など)、冷戦の原因はソ連の拡張政策かアメリカの行動か、あるいは別の説明がありうるのか、産業革命によってイギリスの生活水準は上昇したか、それとも下降したのかなど、ワクワクするような問いにあふれています。数学ではおそらく研究すべき課題はある程度共有されているのではと思いますが、歴史学ではそれほど共通の問いを有していることへの意識が強くなく、散漫になりがちです。ただ、このように、一つの現象にも多方面の見方があり、それぞれがお互いに敬意を持ちながらも徹底的に批判し合ってきたことを高校生たちにも知ってもらったうえで、自分の感覚に基づいて議論に加わってみることは、「したい」という意識が自然に世界史の基本知識の習得につながっていく近道だと思うのです。本物の格闘を実地で体験する、ということでしょうか。
(2)歴史書の書評を書いてみる
新聞での書評のお仕事をするようになって数年たちましたが、その数百倍もある内容の本を400字や800字にまとめて紹介し、自分なりの考えを記すのは結構たいへんです。一文を削るために数時間かかることもあります。いうまでもないですが、800字だからといって「はじめに」と「あとがき」だけ読んで書いてもつまらない書評に終わってしまいます。たとえば、高校生に短い歴史の新書を読んで書評を書かせて、それを一年かけて何冊かやってみるというのもよいと思います。なぜなら、日常生活でもそうですが、人に説明しようとしてようやく自分が何を言おうとしていたのかを発見することが多いと思うからです。しかも、歴史書に対する鑑識眼も肥えてくると思います。元来、書評はとてもクリエイティブな作業で、これを生業にされている方がおられるほど、奥の深い仕事です。
(3)自分で歴史の本を書く(つもりになる)
私は京都大学の一般教養科目で「現代史概論」を担当しています。そこで学生たちに講義の初めにこんな質問をします。『〇〇の20世紀』という新書を書くとして、あなたならば〇〇に何を当てはめますか、副題も考えてください。もちろん学生みんなの前で私が読み上げます。『戦争と平和の20世紀』というものもあれば『物理学の20世紀』『原子力の20世紀』と書く理学部生もいます。面白いのは、『ロックの20世紀』や『アクアリウムの20世紀』や『タロット占いの20世紀』など趣味から入る学生もいて、それを展開したレポートを提出してもらうと、それぞれ自分の趣味と時代背景を連動させて描こうとしていて、そこに「学び」が入ってきます。説得するためには調査が必要ですから。アクアリウムの歴史を知るためには、それを享受した社会層の変化はもちろん、技術史や魚類研究の歴史、さらに、この学生から学んだのは、経済先進国の需要の応じて、南米などで魚の乱獲が見られていることです。こういう学びは、趣味から入っているからこそ、かなり深くなると思います。できることならホッチキス綴じでよいので簡易版の冊子を作ってもらうとなおいいかもしれません。そこで、逆に本を書くことの難しさや困難さを体験してもらえるならば、一石二鳥ですね。
以上、三つほど挙げてみましたが、数学の「学ぶ」とはまた異なる点もあると思います。このあたりでバトンをおわたししますね。