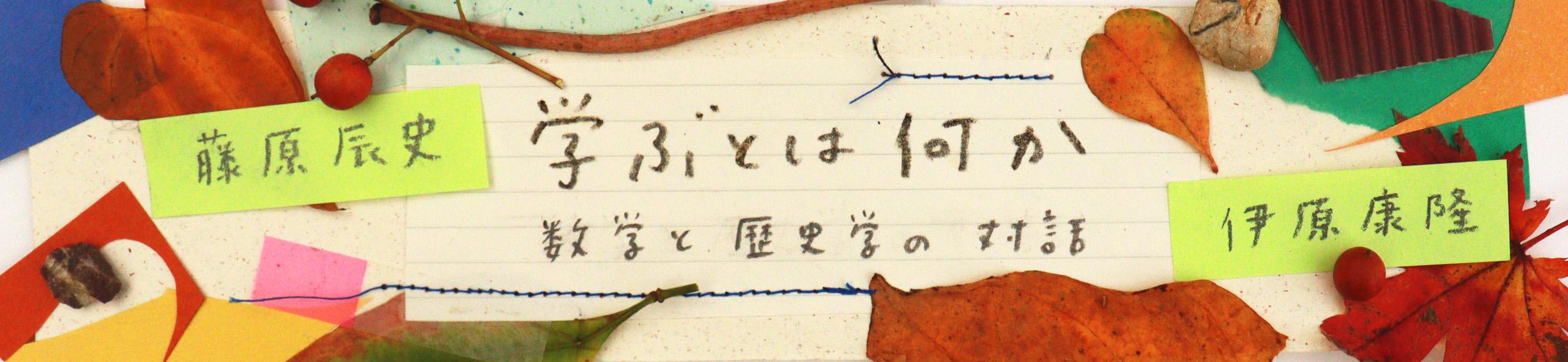第10回
言葉はわける 話はつなぐ(伊原康隆)
2022.03.20更新
歴史学者の藤原辰史さんと数学者の伊原康隆さんによる、往復書簡の連載です。藤原さんから伊原さんへの前回の便りはこちらから。
伊原康隆>>>藤原辰史
タイムリー に貴重な現状分析とご見識を大変有難うございました。まだ拝読して間もない今回、感想は以下の段落(終盤のポイント)に関してのみ述べさせていただきます。
悲観はまだ非観ではない。観たくない現実を観る力がまだ私たちに残っている以上、せめて学びを共有することはやめないでいたい(中略) そして、芸術も学術も現実の悲惨さだけではなく、その背景を「学ぶ」ことで、普遍性を獲得していったのだと思います
我が意を得たり! 仰るように「観る」の内容は、決して「悲惨な映像を繰り返し見よう」ではない。映像で感情的になるのは「我が国民がこんな酷い目にあったのだから」と逆用もされかねない。むしろ「言葉を心の眼で観よ、彼らの言葉に騙されるな」でしょう。ヒットラーに顕著(『我が闘争』にも)で、あの人この人にその後も利用されているいわば悪魔の呟き、「大衆は小さな嘘には(慣れていて)騙されないが大きな嘘には簡単に騙される――だから為政者がこれを利用しない手はない」 。これは「簡単なことしか大衆の耳には入らない、短い刺激的な言葉だけを使おう」とセットになっていましたね。従って「観る」の第一歩は
「発せられた言葉をうのみにせず、十分分析し、区別して理解し、区別して使うこと」
と私は解釈しました。言葉の複合性は大きなテーマですから後半にまた戻ってきますが、これが広いそして正しい意味で「学ぶ」の基本中の基本。また芸術も普通の言語では表しきれない「心」を表現できる分野ですから、その道の方々はたとえ軽い言葉で何か言われても「何か変だ」とまず感じとることが出来やすく騙されにくいことでしょう。仮に歴史学を深く学べる状況になくても、何かを系統的に学べば言葉の複合性にも敏感になって騙されにくくなると思うのです。ただし、嘘らしいとは見抜けてもそれを率先して嘘と指摘し世論に働きかけることができるかは別問題。このためにはそれらの背景を含む歴史学の深い知識、見識と実績が必要で、今回の藤原さんのご指摘は大変ありがたい指針でした。
***
さて対談の連載も10回目(5回ずつ)になりました。その間、友人たちからも感想や質問をいくつかいただきました。その中の根源的な二つの問いは、まず
「誰に対して語りかけているの?」
これに対する答えは、まず藤原さん、編集部の野崎さん、そして見えない読者の方々で、そこからの広がりをいささか期待しているのですが、理系の話題に関しては(以下の理由で)大学生以前、特に高校生の方々にも目を向けているつもりです。
藤原さんの前々回 (第7回)の大学での試みのお話も大変参考になりました。これによって、まず共通に大切なのは「具体的な問題意識」を持って勉強すること、そうすると自分なりに「系統立てた勉強」ができ、かりにそのテーマを続けなくても「特定の軸にそって知識を蓄える」という楽しみが勉強を能率化、加速化すること。加えて「書く」ことが極めて大切、も共通していると感じました。他方、相違点といえば、興味に目覚める時期が理系では普通かなり早いので、それ以前からの心理的な励ましを、と思うのです。
次の問いは
「どこに行くつもり?」
ひとことで答えれば、それは対談の基本テーマ「学ぶとは何か?」に関する、それぞれの体験に基づく私見、そしてすり合わせです。
この対談で辿った道を、私の分についてざっと振り返り、次いで目指す方向を描いてみましょう。
最初のポイントは学習における「習」と「探」を意識的に区別しよう、でした(第2回=私の1回目)。そして「探」を見つける試金石は「本物」に直に接すること(西澤潤一氏とモネの絵など(第4回前半))に加えて、真に知りたいことについての「わからない」を大切に、でした。この後者については、まだ話が進んでおりません。本物とは何か(第5回)についての論議が 6回目の後半でした。
数学がらみも、入口のご案内だけでしたが、微積分は「変化と結果の関係を知る」という普遍的な問題への数学的アプローチだよ(第4回後半)、虚数は「90°回転という 幾何の対象」と「2乗して -1 になる数という 代数の対象」を結びつけて線から面への思考の広がりを啓発してくれる数学だよ(第8回後半)。藤原さんが前回(第9回)早速引用して下さって嬉しかった。
「習と探」とくればそれらの選択が、従って能力(の偏り)を自分で知ることも、大切でしょう。自分の「短所と長所の表裏」に気づいて徐々に「探」の分野を絞ってゆくこと。たとえば、一口に「記憶力」といっても、どういう学習内容なら無意識にでも鮮明に記憶に残るのか(第6回前半、調和美への感性「梅の花」の話)、これは知における適性を表しているであろう。
さて、「習」「探」に加えて「能力」、この三つの心理の根っこである
「しなくてはならない」「したい」「できるできない」
の区別がくっきりと意識されやすい言葉、これこそ大切であろう。でも日本の言語文化ではどうやらそこが曖昧で弱い、こう感じた私なりの模索の結果、イタリア語の3つの基本的な動詞(dovere, volere, potere; 頭文字 D, V, P ) を借用しました(第8回前半)。友人の一人は日本語でこれらを区別する「標語的な名詞」(義務など)を提案して下さいましたが、名詞は固い、たとえば標語的な名詞は個人に対する「縛り」になりそうです。大切なのは「自由に感じること」であり、自分の感情や指向性を表す基本は「動詞」に求めたい、と思いました。
その後、実は日本語でも、この種の動詞を先行させる表現法が(個人の試みとしては)過去使われており、ただ誰にも採用されないままに廃れてしまっていたのだということを偶然知りました。鴨長明『方丈記』の冒頭近くの「知らず、〇〇」といった表現法でした。『海道記』にも類似の表現がありました(ドナルド・キーン「百代の過客、日記にみる日本人」より)。これだけでは足りないので、どなたか現代の鴨長明になって下さい!
***
ここからの後半は、冒頭の二つの主題「学びの共有」と「言葉の複合性に気をつけよう」についての以下の三話から始めたいと思います。
第一話は、両方に共通する話です。言葉としての「学びの共有」。これにも複合性がありました。それをまず十分認識した上で、次に、異なる意味合いの二つを結べる「橋わたし」を探る。これが順序でしょう。言葉「学びの共有」の受け取り方には
「広い人間社会で起きる不幸を防ぐため、各自が知恵と鍛えられた批判精神を持ち寄って輪を作ろう」もあれば
「学問や芸術分野の広い世界に自らを没入しつつある個人個人が、それぞれの段階で得たものを共有したり企画を立てて連帯したり」というのもあります。
広い「何」に包まれた中で考えるのかの相違。藤原さんの力点は(両方あるのでしょうが主には)前者でしょうか、私の体験は大部分が後者と感じます。実は、この幅広さに早めに気づけたのは編集部の野崎さんが二人の連続書簡(私のはこれの草稿)を比較して問うて下さった鋭い質問のおかげでした!
第二話は「学びの共有」の諸段階について。私はかねがね「第一歩だけでは足りない、第二歩も踏み出さなくては意味がない、重心も乗らない」と考えています。知の世界での「歩」は一つずつが段階です。その「二歩め」は(〇〇したいの動詞 volere に加えて)「習得した一歩め」に重心を乗せて踏み出すものでしょう。専門分野では 一、二歩どころではありませんが、ここでは分野をまたぐ場合がポイントですからそう深入りはできない、だから一歩か二歩かの相違も重要だと思います。ところがこれを友人たちとの共有の場で進めようとすると、あれあれ、いつの間にか孤立して浮き上がってしまっている自分を発見することが多く、共有の難しさを感じます。仲間との議論で、一歩めは踏み出せ共有できたと考え、さて重心を乗せようとすると仲間から浮き上がる、これどういうこと? 一つは自分の二歩め(と私のせっかちさ)に問題がある場合ですが、より根本的には「二歩進める」は「系統立てる」の始まりであり、他者による系統立てについてゆくのは、先生と生徒でない限り、伝統的に日本に根付いていない習慣なので、一種の精神的支配を受ける(dovere的な)気分になってしまうからではないか、と感じています。
話し手の動機が「共有したい」であっても、系統立ては聞き手にとっては「話し手に支配されそうな」気分になりやすいのでしょう。政治の話をしにくいのも同列の問題ですから、私の欠点だけでもなさそう。対等な間での質疑応答の習慣(ギリシャ時代のような)から始めなくては、ということでしょうか。藤原さんのご感想をお聞きしたいな。
筋は(かなり)違うが参考になる話を一つ追加しましょう。実はヒットラーも建築現場で働きつつ仲間と政治論議を闘わせていた頃、彼のいう「第二歩」に踏み出そうとする度に先日やっと共有できたと思った「第一歩」が全く理解されていなかったと絶望し、それらによって「大衆は簡単なことしか理解しない」との強い印象を受けたようです。
系統立てを嫌うと系統立てを(内密の)武器をする側に対抗できなくなること、そしてヒットラーやその周辺と現在のわれわれは本質的にはどう異なるのか、これらもよく考えてみないといけませんね。藤原さんが「ナチスを理解するにはもっと近寄ってみないといけない」といわれたのに私がすぐ共感できたのは、祖父の実家の物置で(大昔)ひもといてみた『我が闘争』の印象からでした。
第三話。言葉の複合性の分析は、仲間からの刺激がもとになった場合でも、結局は個人が一人になってから考えることでしょう。ここで一つ(非政治的な)具体例をあげてみます。比較的最近の話ですし、イメージがやや汚くて恐縮ですし、他所でも書いたことですが好評でしたので繰り返します。
ものの本には
「尿」は、血液を腎臓のフィルターで繰り返し濾してできる
と書かれています。ここで言葉「フィルター」をイメージしてみると、普通は汚染された液体の汚い部分を網に引っ掛けて除き、綺麗になった方を残すための「網」でしょう。でも、「綺麗であるべきなのは血液であり、尿は汚い部分を捨てているに違いない」というのは誰でも抱く先入観で、それと相容れない。それでも「分かったような分からないような」うちに自分を「納得」させてしまいます。それは「ごまかし」です。その説明文を分かったとして早く通過したいからでしょう。現に、腎臓病に関する先日のある新聞記事でも、案の定、そこが勘違いされて書かれていました。実はフィルターに引っかかるのは血液中の大きな分子であって、その代表が血球、フィブリノーゲン、グロブリン、アルブミンなど血液に残さなくてはいけない方の成分、逆に、尿素や塩分などは小さい分子だからフィルターを通過して尿の方に行くのでした。通過する方が尿ですから、通常のフィルターとイメージが逆です。でも、ものの本には「逆ですよ」とは書かれていないようです。読者が読んで「ちょっと変だ」とうすうす感じたとき、その「変だ」を大切にして自分でイメージし直してみることで初めてわかります。
なお話の続き(二歩め)として一言付け加えます。尿管に入った塩分と尿素はまず濃縮され、尿管側の高まった浸透圧によって(腎臓内のサーキットの別箇所で)一旦できた尿が再び血管に戻る。この循環の仕組みによって濾過が何度も繰り返されることで健康が保たれるのだそうです。
***
最後に対談書簡への反応の話に戻りましょう。私の対談記事を読んでくれた旧友の一人は「君の話には「努力」という言葉が出てこない、これは才能に恵まれているので努力を必要としなかったのではないか、凡人には努力こそ、ではないか」とのご意見を寄せられました。いや、とんでもない。私は飛ぶ鳥ではありません。地中のミミズです。それが証拠に中学三年の頃のあだ名が「ミミズ」いや「メメズ」でした。鳥は用がなくなったと感じれば直ちに飛び去っていきます。ミミズは一箇所に長く滞在し、視界が効かないので掘りつつ徘徊しないと用が足せない、でも鳥には気づかれない栄養源を見つけられる、ということかもしれません。あんな所でも引っかかる、要所で何かを感じ、考えたり調べたりするのは通常の意味の努力とはちょっと違いますね。私が人文科学を応援したくなったきっかけの一つは、藤原さんが「社会科学と人文科学の相違」を端的な喩え話で説明して下さったことに由来します。
一人の人間が滅しても「全く変わらない」というのが社会科学、「人は人々の記憶の中で生きているのだから大いに変わる」が人文科学。また「鳥の目線」が社会科学で「虫の目線」が人文科学である、と。おお、わが土壌!
一部の鳥が「インターネット」という霞網に引っかかっても、地下にいる「本の虫」は生き残るかもしれませんね。
とりあえず、私は「現代のガンジーとナイチンゲール」がウクライナと人類を救ってほしいと切に願っています。かのクリミア戦争のとき、イギリスのヴィクトリア女王が「ナイチンゲールからの情報は直接自分に伝えろ」と命じるほど彼女を尊重し、国を挙げての支援を惜しまなかったのは(その帝国主義はともかく)やはり偉かった、と思います。その情報には、野戦病院の惨状の様々な角度からの分析を明瞭に可視化(して女王を説得)するために彼女が発明した、先駆的な「蜘蛛の巣チャート」――放射線状に延びた数値軸の上の値を結んだ多角形――も入っていたとのこと。これも白衣の天使の中の優れた知性だったのでしょう。
散漫になりましたが、いささかの関連性――私自身見失いそうになるもの――を読み取っていただけたでしょか。厳しいご指摘をお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。