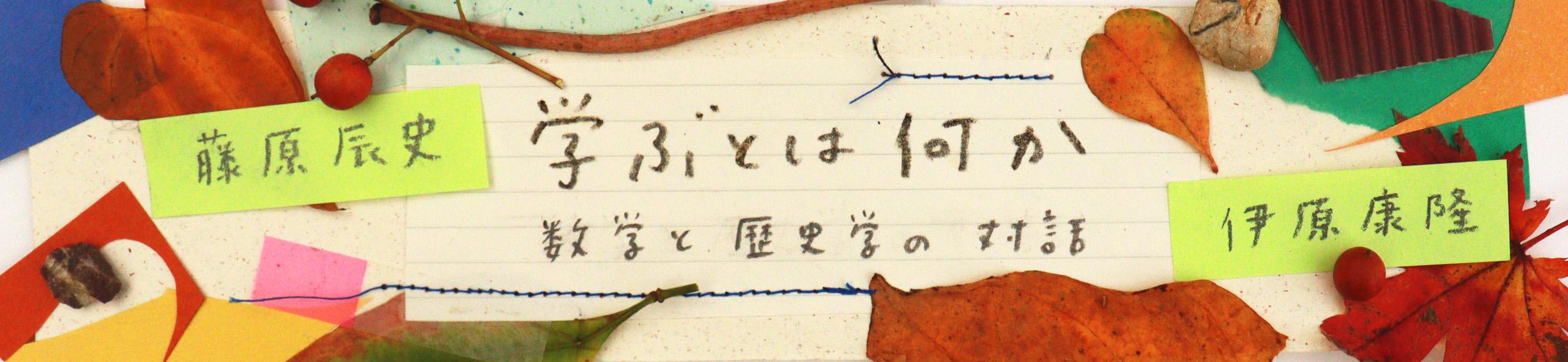第11回
「第二歩目」について(藤原辰史)
2022.04.10更新
歴史学者の藤原辰史さんと数学者の伊原康隆さんによる、往復書簡の連載です。伊原さんから藤原さんへの前回の便りはこちらから。
藤原辰史>>>伊原康隆
こうやってお手紙を交わしているうちに、だんだんと伊原さんの考え方の輪郭が見えてきているように思えます。実数から虚数の扉を開けることで世界が平面的に広がっていくありさま。1と2という2つの自然数のあいだに広がる距離。以上のことだけではありません。伊原さんのお手紙を読むということは、人文系の考え方にどっぷり浸かってきた私にとって、自分の考え方の脆さに気づく恐ろしい機会でもあります。どれだけ歴史学の訓練をしても、結構だまされやすく、大きな物語に回収されやすい性質が私に残っていることに気づくからです。
今回のお手紙を読んで改めて思ったのは、伊原さんの中には、第一に、簡単にはわかった気になるな、大きな物語や権威筋の理論に同調しない、納得するまで問い続ける、という態度と、第二に、定義があいまいなまま大手を振って流通する言葉に注意せよ、という警告、そして第三に、異分野をさわるだけではなくせめて第二歩目まで足を動かし、両足を未知の世界に置き、自分の中に体系ができるまで恐れず学ぶという態度がある、ということでした。
これら三つの知の態度は、伊原さんのミミズ(という比喩には驚きました)がのたうち回るような数学研究の厳しさの基本であるとともに、ウクライナ侵攻がもたらしているロシアと欧米の報道合戦の只中にあって、どちらかの陣営の思考のパッケージを脳みそにインストールして安心するのではなく、できるかぎり、冷静につぎはぎだらけの事態を「観る」態度であると思います。
ここでは、この三つの態度について、私の失敗を思い出しながら、述べてみたいと思います。世の中には、自分のこれまでの努力は無駄だったのかと落胆させるような天才的歴史家もいるのですが、私のような凡人歴史家の学習過程を示しておくことは、後世の歴史家のためにも有意義だと感じるからです。
第一に、簡単にわかった気にならないこと(うのみにしないこと)についてですが、これは私たちが「大きな嘘に騙されやすい」ということとつながっていますね。「大和民族は世界で最も優秀な民族である」とか「満洲国では五族協和が実現される」という戦前から日本で喧伝されたスローガンの虚偽性は言うまでもないでしょう。ただ、虚偽の中で、あるいは、時代的制約の中で人生を生きた人びと、それ自体は虚偽ではなく、真実でありますので、歴史学はこのあたりの「歴史的条件」は厳しくみていく学問です。現在の高みに立って昔の人を見下ろすことは避けたい、というのが歴史学の基本ですよね。数学の中で私が面白いと思うのは、条件付け、たとえば、「ただし、-5 < x < 0とする」ということを明確に示すことです。
私が大学に入って、騙されていた嘘に気づくプロセスについて白状いたしましょう。私は、大学一年生で、ある講義を受けるまで、「日本は単一民族の国」だと信じていました。いまでも赤面します。この国には「日本人」しかいないと思っていました。不思議なのですが、私の母方は北海道出身で祖先は東北地方からの入植者です。アイヌ民族の文化や歴史については少し知っていたのですが、それでもそういうメディアで流される「嘘」を疑わなかった。日本には、アイヌ民族も琉球民族も在日コリアンも暮らしていますから、単一民族の国なんかではない。そのことによって、日本列島が起伏に富んだ世界に見えてきました。そういえば最近、上間陽子さんの『海をあげる』(筑摩書房、2020年)を読んで、一文で固定観念を打ち砕く上間さんの文の力に驚くとともに、何度も自分の固まった思考に気付かされ、ため息をつきました。沖縄で子どもにご飯を食べさせること、子どもに学校に通わせること、こんな日常的な一コマをとっても、「ヤマト」とは大きな文脈の違いが生まれてくる。それほど強烈な、「ヤマト」の沖縄に対する暴力的な支配が存在していることが本書で示されています。
第二に、定義があいまい、あるいは二義的な言葉に注意せよ、という点ですが、これは現在の新型コロナウイルスやウクライナ侵攻の問題とも関わってきます。たとえば、新型コロナウイルスによって、各都市が「ロックダウン」をしました。それ自体は間違いないのですが、私は「朝日新聞」でアダム・トゥーズ『世界はコロナとどう闘ったのか?――パンデミック経済危機』(江口泰子訳、東洋経済新報社、2022年)の書評を執筆するまで、「都市封鎖=活動停止」だと思っていました。しかし、トゥーズは、今回の各都市が選んだ政策は、「ロックダウン」というより「シャットダウン」(活動停止)と言った方が良いと主張していました。今回の事態は、「封鎖」による影響よりも「活動停止」、つまり、動くな、飲み屋で飲むな、家族に会いにいくな、死者に触るな、病院で面会するな、マスクをはずすな、大人数で会議をするな、旅行するな、観光するな、ハグをするな、という禁止の影響の方が大きいわけです。日本国民と日本住民の意味が全く異なるように、ぼんやりと結びついていた概念を「分ける」ことは本当に重要ですね。
ウクライナの問題を知るときにも私たちは注意すべき言葉がいくつかあります。ロシア史のご専門の橋本伸也さんが執筆した論文「『ジェノサイド』の想起と忘却をめぐる覚書」(山室信一・岡田暁生・小関隆・藤原辰史編『われわれはどんな「世界」を生きているのか――来るべき人文学のために』ナカニシヤ出版、2019年)には、日本語で「大量虐殺」と訳されるジェノサイド(genos=種族、cide=殺害)という第二次世界大戦中に生まれた造語が、条約で定義づけられたにもかかわらず、いかに国が他国を批判するときに都合よく使用されたり、あえて使用されなかったりしたかについて詳しく書いてあります。1948年12月9日に第三回国連総会で締結されたジェノサイド条約によると「国民的、人種的、民族的又は宗教的集団を、全体又は一部破壊する意図」をもってその集団構成員を殺したり、出生の防止の意図をもって措置をほどこしたり、肉体の破壊をもたらすために意図された生活条件を押し付けたり、集団の児童を他の集団に強制的に移したりすることを意味します。しかし、ジェノサイドという概念は、ソ連下ウクライナおよびその周辺地域の大飢饉がナチスのユダヤ人虐殺行為と変わらないことを主張するために、ウクライナ政府によって用いられたり、ウクライナ内でウクライナ政府によるロシア住民のジェノサイドが進行中だとロシア政府によって宣伝されたり、かなり乱用されているのですが、他方で、ジェノサイド研究の中にアメリカのヴェトナム戦争による枯葉剤の暴力はなかなか入ってこない。橋本さんは、ヴェトナム戦争にジェノサイドを用いることに疑問を持っていますが、だからと言ってジェノサイド研究からアメリカの暴力が特権的に排除されてきたのはおかしいし、そもそもこれほどまでに乱用されたジェノサイド概念を分析概念として用いることに批判的です。
これもお恥ずかしい話ですが、橋本さんの研究会に出席するまで、ジェノサイドという言葉を恣意的に用いる昨今の政治現象をきちんと把握していませんでした。歴史の解釈そのものが、学問的な手続きを軽視したかたちで国家間の争いの場になっています。日本の歴史修正主義も例外ではありません。幸いに私は、ジェノサイドという言葉を拙著で乱用してこなかったはずですが、果たしてどれほどこの言葉の持つ政治性について考えてきたかと問われれば、甚だ自信がありません。
先日、ウクライナの首都近郊にある小都市のブチャでのロシア人による痛ましい民間人虐殺が、死者たちの写真とともに、世界各地で報道されました。あまりにも残虐で息が浅くなります。戦争はすぐに制御が効かなくなります。だから、安易に戦争に転げ落ちるようなずさんな立法を、実際の戦争状態になったときのことを考えずにしてはならないと、私は2015年から述べてきたのですが、日本の為政者は戦争の本当の恐怖をまだ理解していないように思えます。ウクライナのゼレンスキー大統領は「ジェノサイド」という言葉を用い、日本を含む各国のメディアもこの言葉やその訳語を使いましたが、ジェノサイドという言葉を使いたくなる気持ちを十二分に理解した上で、ここでも立ち止まった方が良いと思います。ジェノサイド条約の定義は果たしてこの悲劇にも当てはまるでしょうか。ここで疑問を抱くことこそ、伊原さんがずっと私に示してきた態度でしょう。
私は、ウクライナ民間人に対するロシア軍の身の毛のよだつような残虐の悲惨さを軽視したいのではない。その逆です。為政者たちが自国の犠牲の酷さを示すために乱用してきたジェノサイドという言葉は、民間人の殺害の真実から遠くなりこそすれ近づくことはできないでしょう。それによって、体を縛られて、頭の後ろから銃で撃たれた人、ロシア兵の暴行を受けた女性、拷問され殺されて路上に放置されたウクライナの人々のこの世で生きた尊厳を蹂躙したくないのです。ロシアは、様々な歴史的事件を「ジェノサイド」と呼んで、この話のインフレをもたらしています。なかったことにされる死、忘れ去られる死ほど悲しいことはありません。かといって、無惨な死のありさまを、わかった気になりやすい言葉で表現して安心することも、死者を蹂躙していることと変わりはないと思うのです。
第三の、第一歩よりも第二歩が大切、という伊原さんのご指摘には瞠目せざるをえませんでした。そういえば、世の中の応援歌や合唱曲には「一歩踏み出そう」という言葉が多いですね。私も公的な場所で何度も「一歩踏み出す勇気」の重要性を話してきました。が、「二歩目の重要性」について、正直なところ、あまり私は考えてこなかったです。
数学者の伊原さんが、生物学や進化論を、その初学者として「かじる」というよりは、二歩も三歩も進めて、ご自宅で私に語っていただいたことを思い出しています。伊原さんの学習には及びませんが、私は博士課程のとき、日本史の論文とドイツ史の論文、全く異なるジャンルのものを書きました。ドイツ近現代史の研究者がちょっと日本近現代史をかじった程度と批判されないように(「そんなことはもっと本業をしっかり学んでからね」と言われないように)、というよりは、ドイツ近現代史を広い視野から理解するためにがむしゃらに(土の中のミミズのように)日本現代史の本を読みあさり、方位感覚を身につけようと努力しました(「しなければならない」ですね)。もちろん、それができたかは心もとない限りですが、私自身、できる限り二歩目を恐れない気持ちは持ち続けたいと思います。とともに、農業や食の歴史を執筆する過程で、どうしても農学の自然科学的な説明を加えることが多いのですが、これについてはまだ1.5歩というところなので、現在、大学院生から1カ月に一回、物質や生物やエネルギーの基本的な考え方を学んでいます。学生の頃のようにノートを取って、未踏の地に両足で立ってみる。生涯一書生として、学びの覚悟をもちつづけることが、混迷を深める今こそ、必要だと感じます。
(伊原さんから藤原さんへのお返事は、毎月20日に公開予定です。)