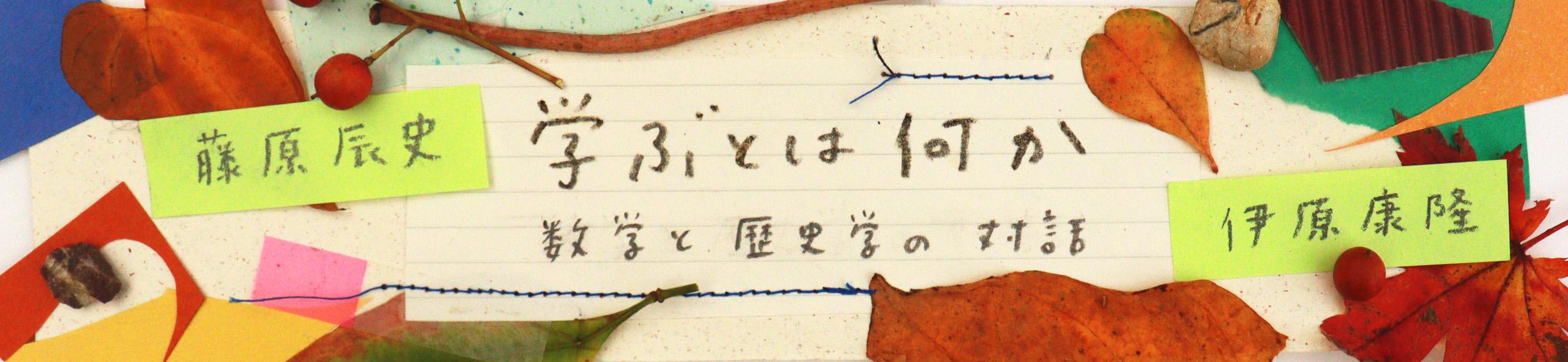第15回
異端を育てるために(藤原辰史)
2022.06.09更新
歴史学者の藤原辰史さんと数学者の伊原康隆さんによる、往復書簡の連載です。伊原さんから藤原さんへの前回の便りはこちらから。
藤原辰史>>>伊原康隆
伊原さんの渾身のご批判が公表されたあとにもかかわらず、国際卓越研究大学法案は残念ながら国会を通ってしまいました。世界中の数学者たちと深く、互いに敬意を持って関係を築いてきた伊原さんのような人の言葉は、もっと政治家たちが耳を傾けるべきだと強く思います。にもかかわらず、もう既定路線であったかのようにあっさりと通ってしまいました。
この法案は、私の同僚の卓越した比喩によると「毒と書いてある毒まんじゅう」にほかなりません。
国際卓越研究大学に手を挙げれば、数百億円という研究費と引き換えに、経済原理に学問の魂を売り渡すことになります。市場価値のない研究にはお金がつかない傾向はますます強まるでしょう。こんな「毒まんじゅう」を、早速「うまそうだ」と舌なめずりをしている大学がいて、しかもそこに京都大学も入っているわけで、暗澹たる思いになります。毒がまわってからでは遅い、とここではっきり申し上げたいと思います。とくに、あえて、誰からも評価されにくいジャンルに挑戦しようと思っている若手の思いを挫くことにつながります。
今日は、伊原さんのご指摘に勇気づけられ、とくに人文社会科学系から見た「異端」のお話をしたいと思います。
独創的研究のすべては異端から始まる、最初は理解されないが、徐々に理解されるようになる、だから時間がかかるのだ、という伊原さんの言葉に何度も頷きました。人文系の学問も同じなんです、と声に出したくなりました。現在のような短期決戦型、社会への還元が求められる研究ばかりがはやれば、日本という国からはもう新しいことがほとんど生まれなくなり、生き生きとした空気が日本の文化から失われていくでしょう。
私が馴染んでいる歴史学という領域では、この百年で新しい「歴史の見方」があらわれたタイミングが何度かありました。いうまでもなく、どれもが最初は「異端」であったのですが、次第に多くの人がその方法論を認める見方として定着してきました。王侯貴族や政治家など著名人たちの華やかな活動よりも、名もなき一般人たちの活動こそ重要な歴史の中心である、という観点を掲げて世界を席巻したのが「社会史」(あるいは「日常史」)。男性たちばかりが登場する歴史の中で男性以外の性のあり方に着目しつつ、男性と女性という二つの型に与えられた役割がどのように社会に影響を与えてきたのかを明らかにする「ジェンダー史」。歴史に登場するのはいつも人間たちだが、人間たちの暮らしの条件である自然環境にもっと着目せよと世に出てきたのが「環境史」。虚構に描かれた文学表現を分析し、現実で起こっていることとの緊張関係を明らかにする「文学史」。そして、科学の営みを歴史の営みの重要な局面としてとらえる「科学史」。私が大きな影響を受けた歴史の変革は、主として以上の五つです。それぞれ厳しい批判を受けつつも、単なる「異端」的な扱われ方を脱却し、現在では、重要なジャンルであると認識されつつあります。
ただ、日本の歴史学はどちらかというと、内発的な「変革」を世界に向けて発信してきたというよりは、このような海外の「変革」を紹介しながら、変容を遂げてきました。そんな中で、単なる紹介に終わることなく、主体的な変革を求めてきた歴史学者も少なからずおられて、私も多くを学んできましたが、伊原さんが論文を発表し、世界の数学者を瞠目させた、というような迫力にはどうしても欠けます。おそらく、その理由は日本の歴史学者が独創的でないから、ではほとんどなく、多くが日本語で発表してきたからだと思います。それも悪いことではありません。日本語は、漢字とひらがなとカタカナの組み合わせでかなり表情豊かで多言語併存的叙述が可能です。主語が省略されるので、多少論理展開に難がありますが、曖昧翻訳も他言語にもまして蓄積されているため、少なくとも人文社会科学の分野では深い議論がしやすい、と私は感じています。
それにしても、やはり日本の歴史学の担い手が、どこか「紹介者」の域を脱せられないのは、ちょっと残念な気がしますし、反省しています。しかも、国際卓越研究大学の制度は、そんな残念な状況をより深刻にするだけだと思うのです。
ではそんな状況下で、異端の学問をのびのびと育てるために、学問の商業化・産業化に抗する人文社会学者は、どうすればよいのでしょうか。
スカッとするような答えはもちろんありませんが、ヒントとなるのは、民俗学者の赤坂憲雄さんの言葉だと思います。一時期、海外で執筆された文献を一度も読まない時間を作ったことがあると、あるとき私に言っていて、ずっと心に残っていました。赤坂さんは、のちの私との往復書簡でもこのことに言及しています。
1992年に山形に拠点を移したとき、わたしははっきりと、洋モノを封印しました。これからは、東北というフィールドで自分なりの歩行と思索のスタイルを探しながら、言葉そのものを編み直してゆこうと、ある覚悟だけは固めていたのです(赤坂憲雄+藤原辰史『言葉をもみほぐす』岩波書店、2021年、28頁)。
私は洋モノを捨てる勇気はなかったのですが、文化の果てる田舎から学問の世界に入ったこともあって、農家のおっちゃんやおばちゃんたちが見向きもしないようなカタカナ語や難易語は使わないことを自分と約束し、今もそれを可能な範囲ですが、履行しています。私たちの世代ではまだ、英仏独の哲学者や思想家の翻訳概念を振り回せば(そこにアジアや中東の言語はほとんどなかったのが問題ですが)、それで箔がつくと考える院生や教員が少なからずいました。あろうことか、そういう人に限って「異端」を気取ることさえありました。
そうではなく、一から、自分の言語であらゆる事象を考え直すことで、どんなことでも、深く理解した権威を取り外して、透明な心で先達たちの業績を学べると信じていますし、そこからしか学界の権威に対する本質的な違和感を感じ取ることができず、正面からの批判もできない。とくに、概念先行を許さない歴史学の構えは、そういう方法に馴染みやすいと思います。私の貧しい海外での研究発表の経験からしても、自分で発掘した資料をもとに自分の頭でひねり出した英語の方が、誰かネイティヴ・スピーカーに翻訳してもらった英語を読み上げるよりも、あとの反応が良いことが多いです。私のように哲学から農学までなんでも手を伸ばしてしまう人間は、正統的な歴史学からすれば異端ですし、そう思われたり、それゆえに疎んじられたりしたことも多々ありますが、それは例外で、基本的には居心地の悪い思いをしたことはあまりありません。私が学問の訓練をした大学院人間・環境学研究科でも、最初の職場である人文科学研究所でも、自分が正統から外れた存在であることを意識することは少なかったし、私の同僚や友人たちがそれぞれの「異端ライフ」を自然体で楽しんでいたので、突然変なことを口走っても排除されない、という安心感がありました。
私たち中堅以上の研究者に課されているのは、基本的な学問の練習を踏まえた上で、借りものではない概念で考える時間を若手に存分に与えることであり、既成の学説への違和感を感じ取りつつも、それをどう昇華させるかに悩んでいる若手と勉強会をすることであり、奇抜なアイディアが浮かんだのに誰も相手にしてくれない若手が、少なくともその思いを書くことのできる媒体と、誰かが話を聞いてくれる椅子とテーブルを準備することです。私も、微力ながら、友人たちと、若手が勉強しやすい「京都歴史学工房」という名前の研究会を運営していますが、まだまだ十分ではないという自覚があります。
とにかく、政府が押し進める厳しい研究者競争の中で、レースに勝ち残ることに精一杯である学生に、そのような時間と余裕を持ってね、と安易には言えない状況が続いています。とにかく、この国の学問には困ったことばかり起こりますね。
(伊原さんから藤原さんへのお返事は、毎月20日に公開予定です。)
編集部からのお知らせ
新刊のお知らせ
ミシマ社より、2022年6月11日に藤原辰史さんと小山晢さんによる共著書『中学生から知りたいウクライナのこと』を刊行いたします。二人の歴史学者が意を決しておこなった講義・対談を完全再現。緊急発刊します。本連載の第9回「ウクライナ侵攻について」を収録しています。