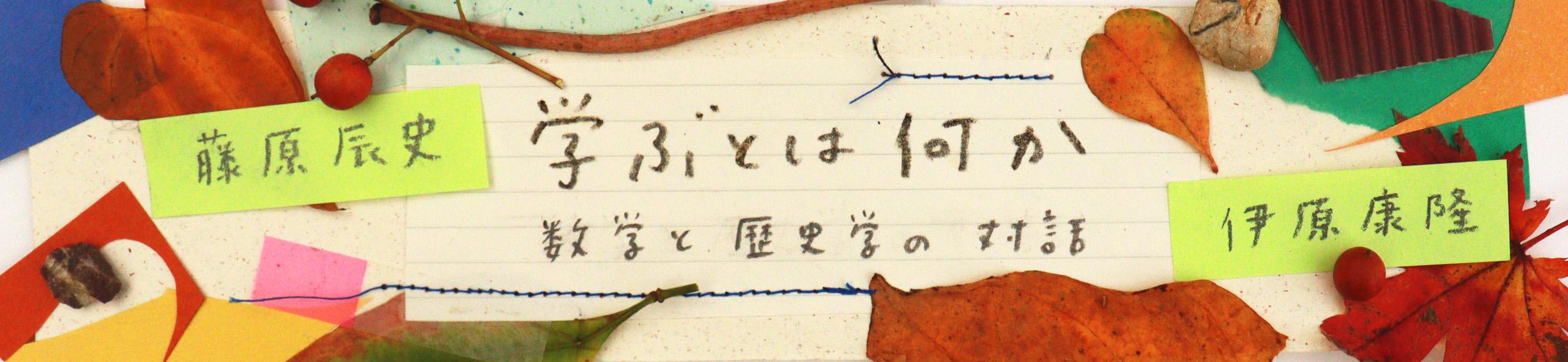第19回
歴史の中の「射」と「群」(藤原辰史)
2022.08.11更新
歴史学者の藤原辰史さんと数学者の伊原康隆さんによる、往復書簡の連載です。伊原さんから藤原さんへの前回の便りはこちらから。
藤原辰史>>>伊原康隆
数学の用語と歴史学の用語
人文系の学者がほとんど違和感なく用いる数学の用語は、せいぜい「足し算」「引き算」「イコール」や「ベクトル」「指数関数的」「変数」「相関関係」など、初歩の初歩ばかりですが、伊原さんのお手紙を読んでいると、本当に私たちはもったいないことをしていると感じてしまいます。歴史学がユークリッド幾何学段階を超えるのはいつなのだろうか、と考えさえしました。
「数学分野で開発されてきた言語」だけれども、「一般性が期待されるから普通の言語と差別して欲しくない言語」ということで「射」と「群」という概念を紹介いただき、とても触発されました。もちろん、とりわけ今回いただいた「補足」は、先頭をぶっちぎりで走る伊原さんの背中を望遠鏡で覗くような気持ちではありましたが、それでも伊原さんが説明されている数学用語は、哲学や歴史学や文学の研究でもどんどん使えそうな気がします。私たちはあまりにも数学を学んでこなかったせいで、思考の節約を怠ってきた、すなわち思考の浪費をしてきたような反省もしました。いつの間にか、思考を節約よりは、思考の増殖(と思考の個別化)に加担してきた人文学の最近の営みは、数学に見習うことがやはり多いと直感しました。
ここでは、ちょっと無理をして、教えていただいた数学の概念を用いて、歴史学を考えてみたいと思います。
ブローデルの三つの波動
伊原さんのお手紙を読んで真っ先に思い出したのは、フランスの歴史学者で『地中海』という名著を書いたフェルナン・ブローデルという人物でした。ブローデルは、歴史の時間を三層に分けています。短期波動、中期波動、長期波動の三つです。短期波動は、端的にいえば、カエサルの暗殺やアレクサンドロス大王の死、本能寺の変、世界恐慌、広島の原爆投下などの一回性の事件のこと。中期波動は、たとえば、人口動態や穀物生産量の変遷、あるいは、長期に続く体制など、短期波動よりは比較的長い緩やかな変遷のことです。では、長期波動とは何か。それは、地球の諸要素、たとえば、太陽、土、海、川、山、天候、気温など、持続的に私たちの生活を形作っている環境になります。この三層の複雑な絡まり合いの中で、歴史はこれまで進んできた、という考え方です。私も含め、今を生きる歴史家の少なからぬ人が、ブローデルの歴史観に多大なる影響を受けてきました。
1970年代頃に、環境破壊を背景にしてアメリカで環境史というジャンルが登場して以来、歴史学の中でも長期持続にスポットライトが当たるようになり、それこそ、気候変動と漁獲高の相関関係、気候変動とフランス革命勃発の関係などのテーマがどんどん発表され、統計を駆使した研究も現れるようになりました。
中長期の波動の時間では、比較的、数学的叙述が可能のように見えますし、現に大量のデータを用いた論文も世界でたくさん執筆されているのですが、しかし伊原さんがおっしゃっているのはそこだけではないと感じます。
ドイツの歴史を「射」と「群」で考えてみる
比較的私が馴染んでいるドイツ近現代史の流れをあえて、「射」と「群」を援用して(誤用だったらすみません)、考えてみたいと思います。
1871年に登場するドイツ帝国(この時代を帝政期と呼びます)、第一次世界大戦を挟んでドイツ革命が起こり、1919年に産声を上げるヴァイマル共和国(この時代をヴァイマル期と呼びます)、そして、1933年に登場するヒトラーの第三帝国(この時代をナチ期と呼びます)です。
帝政期の特徴は、軍人とその供給源である地主貴族(かつてはユンカーと呼ばれましたが最近ではこの言葉はあまり用いません)、重化学産業と電気産業の勃興(その背景として科学の発展)、鉄血宰相と呼ばれたビスマルクによる外交と社会主義とキリスト教の弾圧、アフリカや東アジアや太平洋の植民地、家父長制の強化、税金の納める量によって選挙の重みが変わる差別選挙(女性の参政権はなし)、第一次世界大戦での崩壊などです。(1)カリスマと(2)対外膨張と(3)敵対勢力という三つの指標が、時代が変化するにつれてどのように変化していくのかをみていきます。
(1)帝政期のカリスマはビスマルクです。ドイツではビスマルクを讃える記念碑がたくさんあります。私が一年ほど住んでいたシュトゥットガルトには「ビスマルクの塔」というイカツイ塔が丘の上に立っていて、見晴らしが良いので、よく周辺を散歩していました。彼は、1890年に失脚しますが、その後の首相にはそんなカリスマがありません。また、立憲君主制なのですが、ヴィルヘルム一世はあまり目立ちませんでした。その後を継いだヴィルヘルム二世は世界政策を打ち出し、植民地拡大を目指し第一次世界大戦時のシンボルなので歴史上の重要人物ではあるのですが、やはりビスマルクほどのカリスマ性はありません。ビスマルクはバランス・オブ・パワーを重視した外交でヨーロッパ内の安定を図りましたが、他方でヨーロッパ列強によるアフリカ分割を調整した人物でもあります。第一次世界大戦でホーエンツォレルン家が打倒され、ヴァイマル時代になるとカリスマ的指導者はほとんどいなくなります。あえて言えば、社会民主党員で初代大統領の馬具職人の息子フリードリヒ・エーベルトか、1925年から大統領に選出されるヒンデンブルクでしょうが、エーベルトはビスマルクほどのインパクトはなく、ヒンデンブルク、すなわち、大戦時に参謀総長を務めた老人はむしろドイツ帝政期のシンボルであります。その弱くなったカリスマの地位を埋めるのが1933年1月にこのヒンデンブルクによって首相に任命されるヒトラーです。ヒトラーの人気は独ソ戦で敗北が続く辺りまであまり影響がなかったと言われます。ビスマルクのカリスマ→カリスマの不在または弱体化→ヒトラーのカリスマという流れになります。
(2)対外膨張。帝政期は、英仏に遅れを取りますが、アフリカの植民地を拡大しました。しかし、第一次世界大戦の後に締結されたヴェルサイユ条約で植民地を全て失い、国内植民が活発化したり、労働者住宅の建造のラッシュになったりします。とともに、相対的に狭い領土に対する不満がくすぶります。重要なのはここからです。ヒトラーは、その不満を吸収して選挙で勝つのですが、アフリカや太平洋の植民地の再度獲得を目指しませんでした。むしろ、石油や食料といった基本的な資源を開発する目的で、ポーランドやルーマニア、ウクライナなどの中東欧の地域を占領していきます。膨張先は、アフリカ&太平洋→国内→中東欧という流れになります。
(3)これまでの歴史が明らかにしている通り、国民国家(一民族一国家を原則とする国のあり方)を形成するために政治家は「敵」を名指し、憎悪を「創出」してきました。保守主義者のビスマルクにとって国内の敵はカトリックと社会主義でした。ドイツ民族のプロテスタントを中心とする国家を形成するにあたって、オーストリアやイタリアの国家の根源であるカトリックの教義は邪魔者でした。これを「文化闘争Kulturkampf」と言います。しかし、その後、ビスマルクは、主要な敵を、国内の階級対立を煽る社会主義者に定め、文化闘争を終わらせます。ヴァイマル共和国時代は、政府にとっての敵は極右(ナチ党など)と極左(ローザ・ルクセンブルクなど)でした。社会民主主義の中で資本主義を温存しながら改革していく流れが中心となりました。が、世界恐慌の中で、極右と極左に票が流れ、結局ナチ党が政権を獲得します。ナチ時代の敵は、「ユダヤ人」と「マルクス主義者」と「資本主義」でした。ビルマスクからヴァイマル共和国まで一貫して民衆の心を巣食っていた反ユダヤ主義を利用したわけです。ナチは、「国民社会主義者Nationalsozilalisten」と自らを名乗っており、社会主義的政策には一定の理解を示していましたが、国際的なマルクス主義の同盟を結ぶ共産主義と、金融資本家(ユダヤ人が相対的に多い)には批判的でした。よって、「共産主義」や「マルクス主義」や「資本主義」を一つの統合する敵として、「ユダヤ人」への憎悪を「人種学」という似非学問を利用して強引に創出していきます。
繰り返される歴史、繰り返されない歴史
(1)〜(3)は、それぞれの「群」の中で、超時代的な関係性を保っています。帝政期からヴァイマル期への「射」は劇的な変換というべきものですが、なぜか、第一次世界大戦の衝撃の只中から生まれたヴァイマル共和国からナチスへと二度目の「射」のあと、要素間の関係性が帝政期の関係に似てきます。ヴァイマル期にようやく手に入れた民主主義も、男女平等も手放して、人びとが父権的なもの、独裁的なものにすがり始めるのです。第三帝国とナチスが自らの国家を名乗るとき、その背景にあったのは、第一帝国である古代ローマ帝国と(神聖ローマ帝国という人もいます)、第二帝国であるビスマルクの帝国です。ヒトラーもビスマルクを比較的高く評価していました。ヴァイマル共和国の時代、ハイパーインフレや世界恐慌で社会がボロボロになったこともこの「回帰」の原因と考えられます。
ただ、ビスマルク時代からヒトラー時代への「射」は、単なるコピー&ペーストではもちろんありません。繰り返しますが、膨張の先は海の向こうか、陸地の続きという違いがあります。ビスマルクは、ヨーロッパ内の関係性はできるだけ安定を目指した。ヒトラーはそのヨーロッパに侵攻します。膨張という志向において、変換の刺激を与えたのは、第一次世界大戦期の食料危機による飢餓の経験と(よって、中東欧やフランスの穀倉地帯を目指す)、同じく第一次世界大戦期のイギリス海軍による封鎖の衝撃(よって海を使った膨張は諦めざるを得ない)、地政学、そして人種主義です。ドイツの人口が増えているにも関わらず、英仏のような植民地を第一次世界大戦後に失ったし、いまもなお相応しい土地が与えられていない、という考えに基づき、土地の「膨張」を他国に要求するという自己中心主義的な考え方です。これを正当化するために、中東欧の入り組んだ民族構成を刺激するリスクを冒して、優生学はもちろん、「人種主義」の教義を全面的に押し出しました。ドイツ人の優秀性は、人種学という「科学」によって既に証明されている、という考え方です。これは、膨張主義のベクトルがアフリカからヨーロッパ内へと変わったことと深く関係していると思います。つまり、すでにある程度まで立派な国民国家ができている中東欧で自民族の発展を訴えるには、旧来の植民地主義(文明国が野蛮な国を開発してあげる)ではインパクトに欠けることに気付いたからです。先天的な優秀さ。人種的なエネルギー。ここに、ヒトラーは、植民地を手放したはずのドイツ人の発展の根拠を求めます。
もちろん、そんなことは似非科学によってしか証明されませんので、無理があります。第三帝国がわずか13年で滅んだのは、人種主義の教義を推し進めるために、優秀でない人種を殲滅する悪行に手をつけるという「無理」をしたからでもある、と言えるでしょう。
歴史の法則の「すきま」
このような見方は、ドイツ近現代史を整理するのに役立ちます(もちろん、ドイツ近現代史から戦後のイスラエル国家の歴史への「射」をどう考えるかという別の難問がありますが、それはまた別の機会に)。たとえば、「ドイツ人のプライド」という事象を考えれば、時代の変遷によって、どのようにそれが「創出」されたのか、カリスマ、膨張主義、敵という三点からはっきりと見えてきます。ただ、ビスマルクのカリスマも安定していたわけではなく、ヴァイマル期のカリスマ不在の時期にはむしろ「テクノロジー」が人を魅惑していた、という言い方をする歴史家もいます。ヒトラーも、カリスマだったとはいえ、現にオープンカーに乗っているヒトラーを是非とも見たいとずっと道路で待っていた人が、実際に見てみるとあまりにも普通だったので「黄色い人形だった」と振り返る人もいます。
それから、政権を獲ってから一年後は旱魃に襲われます。長期波動がナチスに揺さぶりをかけるわけですが、これを一つとする複合的な危機を、1934年6月から7月にかけての突撃隊の粛清(長いナイフの夜)で突破するわけです。
その「あれ、普通の人じゃん」「口だけじゃん」という失望を覆うための「演出」が必要だったことも、これを関係しています。伊原さんが、松村圭一郎さんの議論から掬い上げていただいた「スキマ」は、どんな強権的な体制でも必ずあります。
あと、ナチスは古代ローマ帝国へのコンプレックスが強いですね。ニュルンベルク党大会の跡地に研究仲間と一緒に訪れたことがありますが、コロッセオに似たような建物をヒトラーは建築家のシュペーアに造らせています。カエサル→ヒトラー、パンとサーカス→パンとオーケストラ・集会・軍事演習、属国からの奴隷の獲得→異人種や捕虜の奴隷化、古代ローマの建築→ニュルンベルク党大会の施設など、いささかの強引さに目を瞑れば、いくつか「変換」できるトピックもありますね。
この夏は、ドイツとポーランドを中心にナチスの痕跡を辿り、久しぶりに史料を集めてきます。伊原さんも京都の暑い夏を乗り切ってくださいね。ご著書『ーー数学者の目線で見直すーー生物進化と遺伝子のなぞ』も落手しました。ありがとうございます。ダーウィンなどの原典を読み込んだ伊原さんの「うるさい素人」という言葉、とても印象的です。