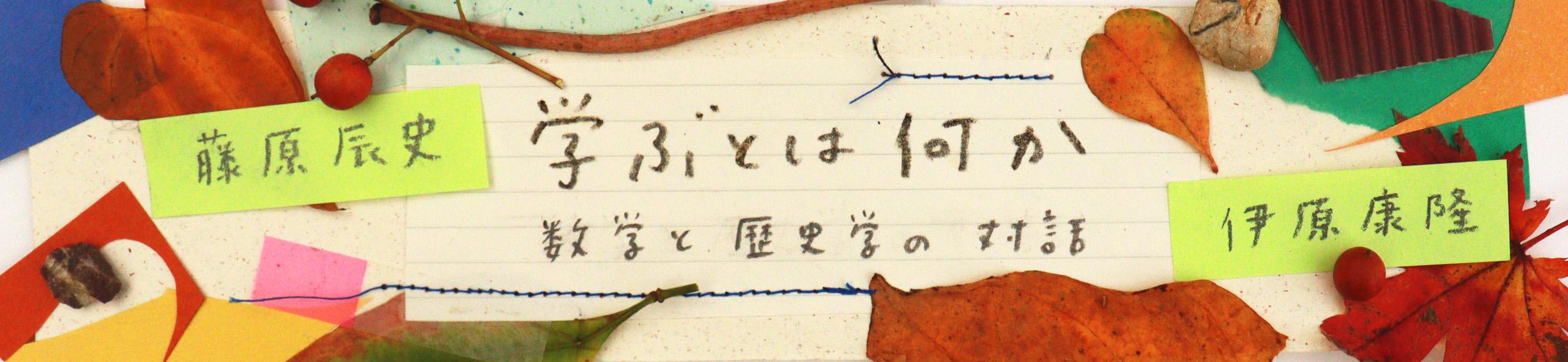第22回
ことばの関節を使いこなす(伊原康隆)
2022.09.20更新
歴史学者の藤原辰史さんと数学者の伊原康隆さんによる、往復書簡の連載です。藤原さんから伊原さんへの前回の便りはこちらから。
伊原康隆>>>藤原辰史
お帰りなさい。そしてヨーロッパでの歴史と地理の交差点からのお土産話もありがとうございました。その間に季節はめぐって秋になり、対談も終盤に近づいてしまいましたね。私は京都の自宅で、エアコン様々と古い簾に守られつつ、言語をめぐるホットな話題について収束への私側からのアプローチを模索しておりました。その話の糸口から入りましょう。
1 ジェイン・オースティン の『高慢と偏見』より学ぶ
原題は Jane Austen "Pride and Prejudice"
周知のように英国の代表的恋愛小説です。それが 200 年を超えて世界の名作とされているのは、ヒロインの精緻な会話を通して「合理性と女性的優雅さは両立する、そして新たな深い魅力を醸し出す」ということが如実に示され読者の希望を膨らませてくれるからでしょう(補足のミニ書評)。ここではその一面である「合理的思考の適切な表現」をとりあげます。
彼女は権力者に追い詰められたとき、ことばを
「くっきり区切り、精緻な用語をしっかり繋げる」
スタイルで反論しています。これは、個人、特に控えめが美徳とされていた当時の英国の女性にとって、自己の精神的自立の宣言として、また象徴として、徐々に浸透し当時(18~19世紀)の女性解放運動とも結びついたそうです。なお、家庭で女性が期待される役割についての当時の英国の保守側の意見は 200 年後の日本の某内閣の主張と驚くほど重なります。
では対応する表現が日本語ではどうなるのか? 多くの和訳のうち目を通すことのできた4冊の範囲では、残念ながら上記の点が十分には伝わっていないようです。その原因を分析すると、
「個人の心の志向を伝える動詞が、日本語では(たとえあっても)使いにくい」
ことに加えて
「和訳はなめらかな日本語であるべし」
とみなされている。だから個人の目覚めを象徴する会話の和訳で、対応する肝心な区切りの一つが抜け落ちてしまう、このためではないかと思います。
以下、まずそのごく一端を具体的にお伝えし、次いで現代の日本人として何が学べるか考えてみましょう。
新しい女性像の体現として登場したヒロインのエリザベスですが、恋愛相手の叔母ーーうわさを聞いて駆けつけてきた貴婦人ーーから、身を引くよう長々と高圧的な説得を受けます(第56章)。彼女のそこでの一連の返事が啓発的です。ちなみに、これらは叔母をさらに怒らせた一方で、二人を一気に結びつける方向に働きました。その一つについて、2つの和訳を対比検討してみましょう。なおこの対比は、特定の訳文の問題点をあげつらうためではなく、原作の意図と「受け入れられやすい日本語表現」との本質的なズレを参考にするためですのでご了承下さい。他の和訳例も補足に追加しますが、いずれも翻訳本の特定はいたしません。
(原文)
I do not pretend to possess equal frankness with your ladyship.
You may ask questions, which I shall not choose to answer
(和訳1:直訳に近い)
私は、奥様と同等な率直さを自分も持っているといったフリはいたしません。
奥様が質問を自由にされても、(質問次第では)お答えすることを私は選びません。
(和訳2:標準和訳の一つ)
私は奥さまのような率直な女ではありません。
ご質問に全部はお答えできません。
同じではないのか? いやいや、肝心な点が違います!
会話の際の基本要素は、まず「相手と自分」、そして自分に関しては「基本スタンス、聞く(耳)、話す(口)」の三要素でしょう。エリザベスはまずこれらを分け、それぞれで自由意志に従う、つまり、基本スタンスは(この状況では解放的は損だし自分は正直でいたいから)率直というフリはしない、耳は塞がない、口はときに応じて開閉する、と宣言しています。きちんと分けた上で、それぞれで自由選択をしますよと繋いでいます。ヒロインの精神的自立、心意気、そしてそれを支える言語の精緻な使用が、原文では(これに限らず様々な例で)よく表現されています。私の和訳1はそれに忠実に添ったつもりです。この場合「日本語としてこなれたもの」にしないところに意味があると考えます。
他方、言葉が十分に分化してない和訳2では、それらがすっぽり抜け落ち、単純な頑迷さのような誤った印象を与えています。そもそも、大人の率直性は「A さんは B さんに対して率直だ」というような「相対的」なもの。子供は「不合理なことをいう大人がいる!」と悟ったときから相手によってとっさに率直性を使い分け、そして大人になっていくのだから、「私は率直な女ではない」はめちゃくちゃ。エリザベスは普通の相手に対しては率直なのです。「貴方に対しては率直になれない」、「貴方の期待に沿った率直性はもてない」もありますが、以下の点も考慮すると、和訳1が原文の意図を最も伝えているかと思います。
主に注目していただきたいのは、前後2つの文章に於ける not pretend (フリをしない)と not choose(選ばない) が「当人の意志の方向性をまず示す重要な動詞である」ということです。筆者が調べた他の和訳(補足)でも、(それ以外では文句のつけようがなくても)この2つの動詞が無視され、硬直した「状況を表す用語」にすり替えられていたことに変わりありませんでした。言葉としては日本語にもあるのにそれらが「なめらかな日本語訳」が尊ばれるという風潮のなかで消されているのでしょう。「言語体系は文化に影響する」というサピア・ウオーフ仮説(4月号と補足)は怖ろしいほど正しい、と私は感じます。
「たったこれだけをとり上げて...」と批判的感想を抱かれたでしょうか。その場合は2月号の前半でとりあげた話もちょっぴり思い出していただきたいな。学びにおける方向性「習」「探」「能」を一般化した心の3つの指向性「〇〇しなくてはならない」「〇〇したい」「〇〇できる」は、(たとえば)イタリア語では、そのためにこそあるのかと思われる3つの「従属動詞」(後続動詞を従属させるという意味)によって明確に区別されていて、それが冒頭にくる。他方、日本語ではそこを後ろのムニャムニャで済ませる。だから普段の人間関係とは異なる「肝心なときに自己主張し難いという心配がつきまとう」という話でした。
ちなみに動詞「望む」は、もともと貴人に仕える際の姿勢、月の出を待つときの気分などを表す漢語が由来だそうですね。民は受動的であるべし、とされた時代の名残りですから、勢いがないのでしょう。せめて「選ぶ」「選ばない」の積極的な表現は大切にしたいものです。
さて、これらを踏まえ、藤原さんが6月号で引用された「言葉そのものを編み直す‥‥」への意見も述べさせていただきます。「自分の言葉であらゆる事象を考え直す」は大いに賛成です。数学でも、かの「高木類体論」は、第一次大戦でヨーロッパから文献が来なくなったことを契機に、以前ドイツのヒルベルトの元に留学していた高木貞治氏が、孤立の中で理論の根底を最初から考え直したことによってこそ生まれました。
ただし「自分の言葉」は「まず広げてから」がその大前提であろう、と思います。藤原さんが引用された赤坂憲雄氏の「洋モノ封印」も、それはかなり高い段階での自戒の言葉であろう、それを大前提として明記しておかないと、それでなくても内向き思考といわれる若い方々が、狭い言語体系の枠の中で「表現を日本語として受け入れられやすくすれば良いのだ」と誤解されかねないと思うからです(ああ怖い)。
それは、いわば関節を使いきれないようなもの(次節)ではないでしょうか。
2 アーティキュレーション;ことばの関節
『高慢と偏見』でヒロインの「自立」を支えた表現上のポイントはどうやら、十分に豊富な語彙ーーとくに精緻な言葉ーーに基づいた
ことばの「アーティキュレーション」
のようです。これは解剖学的には「関節」(またはその繋がり方)、会話では「クッキリ区切った喋り方」、音楽では音の流れの「フレーズより細かい単位への区分け」(註)、そして形容詞「アーティキュレット」は「思想を表現できる」「ちゃんとはっきりものが言える、発言できる」と訳されています。いずれにせよ「くっきり区切る」と「適切な用語をしっかり繋げる」の同時可視化です。
(註)タイ、スラー、スタッカートなど個々の派生記号も「アーティキュレーション」と呼ばれていますが、これは本来は概念を表す一つの言葉が、様々な繋げ方や区切り方の名称を区別するための「用語集」にすり換えられて使われているということです。
与えられた苦しい状況の中で立ち上がるには、股関節、膝、足首と足指などの関節をそれぞれ自由に働かせる必要があるでしょう。特定の価値観に囚われた支配者の認識では「この関節は動かしてはならない」が当然とみなされていますから、それを打破するには「自分はそれぞれの関節をこう動かしますよ」と表明するしかないでしょう。言葉が分化していないというのは、小さな関節が使えず、たとえば腕を上げれば指先まで上がってしまう、というのと同類。そこで私はこう表現したいと思います。
精神の自立は「言葉の関節」を使いこなすことによって表現できる
感情的に自立を表現するには、ときには乱暴な表現にたよるほうが有効? は誰でも体験すること、ここで「心の、ではなく精神の」としたのは、その場合の方がより精緻さを要するとのオースティン等の認識に添うためでした。
私のかつての若き恩師、久賀道郎先生は大声で「わたしも三流あなたも三流、と肩を叩くような人たちがいるぞ、アハハ、でもそういう仲間には絶対入るな」と言っておられました。当時その意味はよくわかりませんでしたが、他に敬意をもつことと自分に密かな自負を感じること「こそ」親近関係にあるのであり、自分を卑下する人は実は相手も大したことないと思うことで心の安らぎを得ているのだ、と徐々に感じて来ました。なおここで述べる「卑下」はかなり広い意味で「自分もあなたもどうせ社会の N 分の1 に過ぎないのだから時間を無駄にしあおう」的な気分も含めています。
文化の発展は卑下からの目覚め
卑下(と尊大)は関節を硬くする
尊大から誇りを守るためには小さな関節まで必須
目覚めはその表現を伴う必要がある
オースティンは小関節を多用してそれを表現した
ところが日本語らしい日本語に訳したら消えてしまった
3 不変な基本用語であってほしい形容詞の一つ「理性的」
重心はむしろ「不変な基本用語」の方にあり、「理性的」はその例として、という心づもりです。理系と文系の相互理解のために欠かせない例ではありますね。
辞書にたよる
私が調べた結果を総合すると(哲学用語を別にすれば)、「理性」とは「道理の連鎖を重視した考え方ができ、それをもとに物事の判断ができる傾向や能力」、というのが共通のところのようです。そして「道理」とは、一つ一つそれだけを取り出せば人々が納得できる基本的な要素で、自然の法則にもとづく「因果関係」に加えて「人の道」のようなものも含まれる、ただしその度合いは言語や社会によって一様ではない、ということでしょうか。
ちなみに理性のほぼ唯一の英訳は、理由に相当する reason でした。「因」は「果」の reason だから、この方が因果関係の連鎖という意味合いがはっきりしています。他方、reasonable には、理にかなった(agreeable to reason) に加えて、極端や過剰でない、中庸、公正(そして、価値に対して十分安価な)も含まれていますから、英語でも「人の道に沿った」も入っています。
(追記)十年後の辞書には「暴走しない」も入るでしょう(笑? いやホント)
背骨による喩え
人間の精神を肉体に(再度)喩えて「理性的」を「背骨の正常な状態」と対応させてみてはどうでしょうか。 左右対称、前後は正常なS字状、ちょっと歪んでも若いうちなら元に戻れるーー多くの椎(基本的道理に対応)が椎間(繋ぎ)によって結ばれているので、これもアーティキュレーションの傑作の一つーー。そういう「古今不変な」形容詞であってほしい。そして、これは是非とも守っていかなくてはならないと考えます。くり返しますが、「背骨の正常な状態」を表す形容詞としての「理性的」は基準用語として不変に保ち、圧力によって歪んだ「現状の背骨」はそこからの離脱と捉えることにしてほしい。不変なものをしっかり踏まえて共有しないと歪みも計測 (早めに認識)できない。基本用語はとにかく安定していて、皆がプラスのものとして受け入れられ、共有されるものでなくてはならないでしょう。
音楽による不変性の喩え
西洋古典音楽での和音ドミソド(この最後は1つ上のド)は安定した響きをもつ相対的な和音としてさらに長く古今不変です。それは振動数比が
4: 5: 6: 8
の4つの音からなる和音で、これは何万年たっても変わらず、音楽がかなり激しく展開しても、いつでもそこに安心して戻っていける基本和音ーー正確には長調のーーです。ドミソに頻繁にもどるからこそ、それが帰るべき場所という安心感の共有につながるのでしょう。他の和音も、さまざまな感情の表現のために使われ、特に大作曲家の場合はその音楽性に導かれた音楽自体の力が新たな「昇華された感情」を呼び起こしてくれます。
和音を外れた「不協和音」も、時おり効果的に使われます。「引き裂かれた心」を強烈に、あるいは「ゆらぎ移ろう不安感」を微妙に表現するものなども。しかし「不協和音による様々な負の感情の表現」を解消できるのは何かと言うと、それは基本和音への自然な移行であって、別の不協和音を新たに提示することではない」というのが音楽の、言いかえると耳と心のつながりの、基本でしょう。
バッハの音楽が包んでくれる調和のとれた安定感、こういった芸術の浸透こそが戦争を防ぐ「地盤」になるという、ウクライナなどからのメッセージも次回とりあげたいと思います。
ちょっと面白いのは小鳥の場合で、左右2つの声帯が発する音の振動数は簡単な整数比ではない(つまり和音ではない)、でも彼ら同士のコミュニケーション(警告など)には差し支えない、とのことでした。人間社会での複雑精緻なコミュニケーションには共有できる安定した基準が必要だと思うので、そうはいかないでしょう。小鳥が飛べるのは羨ましいですが、食物が主に虫、そして和音を楽しめないというのはあまり羨ましくないな。
4 ことばを広げる
通常の言語、たとえば日本語の周辺にあって「鏡」とすべきは、他国語だけではなく、音楽も、数学など科学の言葉もありました。
数学は知的、音楽は情感的といわれますが、この両者は相性が良く、双方とも「安定さの不変的な基準」をもっています。数学は、段階をしっかり踏まえながら進めるという利点の反面、一本の線の上で展開され、「包み込むよりは支配する」感じ。音楽は響き合って流れていくから流れの自然な方向も複数あって(だからこそ不安感の揺らぎまでも表現できる)もっと立体的そして包み込む力があります。強いて言えば、数学はやや父性的、音楽は「母性的にも父性的にも」なれる。繰り返しますが、両者に共通なのは普遍性のある用語をもとにしており、正しい(数学)とか安定した和音進行である(音楽)とかの基準が共有されていることでしょう。なお、音楽の場合は、同じ楽譜でも演奏者によってピアノのタッチ一つで感じが全く変わるように、表現の幅が大きいですがそれでもまあ「範囲内」、ということでしょう。音楽については次回に補足したいと思います。
通常の言語でも、言葉のつながり感覚の「共有の広がりとその保持」のお陰で、さまざまな議論が展開され、共有されるのでしょう。例えば藤原さんの『ナチスのキッチン』『トラクターの世界史』『給食の歴史』では、それぞれの土壌で、ぐいぐい掘り起こされ明るみに出されていく歴史的事実の連鎖の、筋が通ったご説明によって理解が広がり感服したものです。それぞれの理科的内容も面白いし、『カブラの冬』では飢餓の悲惨な歴史であるにも関わらずいい音楽を聴いた後のようなペーソスも感じました。使い方次第での言語の力の強さを例示していると思います。
その根っこにある言語構造の感じ方の共有は、和音を美しいと感じる共有感覚と比肩すべきものでしょう。では「不協和音が和音感覚を危うくすること」に対応するのは何か? 不協和音は音の変則的組み合わせ。学びにとって法則と変則、まず慣れるべきはどちらか?といえば、当然法則の方でしょう。私も例外や変則が大好きな人間ではありますが、「学びとは何か」を考える際には別問題でしょう。
われわれは安定感とワクワク感の双方を必要とし、意外感のある組み合わせこそ人を惹きつけるから、安定した組み合わせを元にした静かな議論よりも、意外な組み合わせが目立つ所で求められやすい。しかしここに落とし穴をお感じにならないでしょうか。言語を主要な表現手段とする方々にとって、たとえ警句の連発のためとはいえ、本来はつながりが悪い二つの言葉を(不十分な説明のもとで)度々つなげて見せるということは、和音(の美しさと安定感の共有)を不協和音の連打で危うくするのに対応し、自ら編み出している言葉の組み合わせに対する健全な共有感覚を危うくする、いわば自殺行為ではないだろうか?
今回のご書簡からも感じたこの心配を、私の今回の締めとして問いかけたいと思います。どうぞあしからず!
(追記)フォレンジックは「現在の暴力とその地域の歴史を並列して見せる技術」の進歩としては私にも評価できますが、当てるべき焦点はあくまでも「現在の」暴力の不条理さであって、過去への攻撃でもあるという見方(というより、その強調)はむしろ焦点をぼかすのでは? 用語「過去への攻撃」「理性の芸術」とか唐突な組み合わせに説得されてよいのだろうか。私などにも理解できるためには、もっと厚みがほしいです。
どんな類推も限界があるという意味で、音楽との対比がここでも適当であったかには自信はありません。クラシック音楽愛好者からのご批判もいただきたいです。