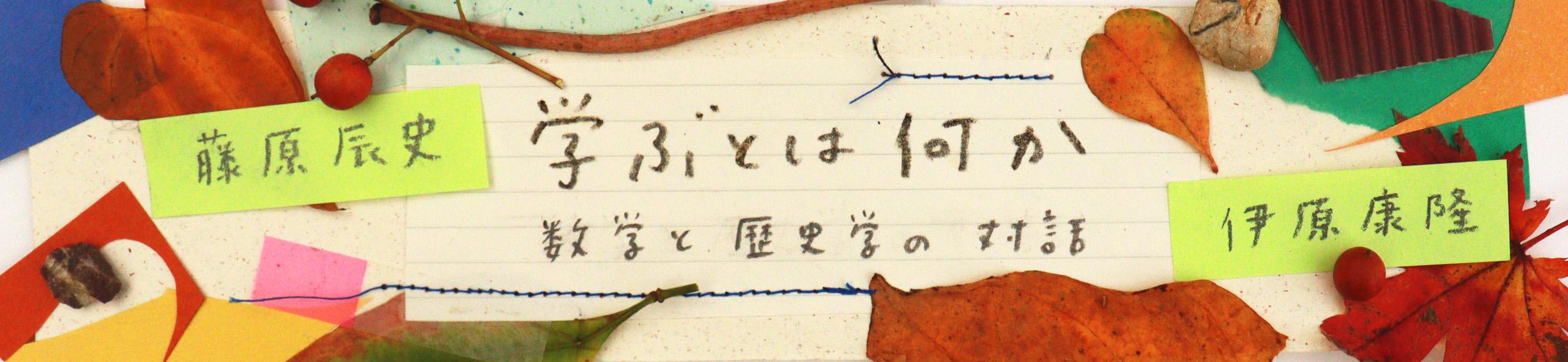第23回
不協和時代の学び(藤原辰史)
2022.10.16更新
歴史学者の藤原辰史さんと数学者の伊原康隆さんによる、往復書簡の連載です。伊原さんから藤原さんへの前回の便りはこちらから。
藤原辰史>>>伊原康隆
議論の着地に向けて、伊原さんとの往復書簡で、私があらたに気づいたり、自分が変わったと思ったりしたことをまとめたいと思います。私のように考え方において頑固なところの多い人間でも変わりうるのだ、ということをお示しするためです。
第一に、「思考の節約」という視点。
歴史を学ぶ学生にはまず、山のように史料を集めて読め、箱の単位で本を読め、と私は言ってきました。それは要するに「量」の思考です。たとえば、「1日600ページ読まないと学生とは言えない」という哲学者の廣松渉の言葉に呪縛されている人は多いと思いますが、そういう「ノリ」です。私は、自分の「見方」「考え方」「理論」をその大量の史料の読破と読書の中で鍛えていくことを勧めることに躊躇はしません。その中には「無駄だった」と思えるものも多数含まれています。私も集めた資料のうち、使える史料は実際一割に満たなかったと思います。読書についても、乱読の中で頭に残っていることも少ないし、最近は忘却する確率の方が頭に残る確率よりも高くなっています。ただ、どこかで血肉化しているとも思っていますし、今でも「量」はやはり重要だと考えています。「節約」という言葉はあまり使ったことがありませんでした。
その一方で、伊原さんのお手紙を読みながら、私のような若手へのアドバイスの中でまだ足りないと思ったのは、初学者の場合はとくに、言葉の定義をブレないようにし、思考を節約して、論理展開の筋を明確にしていくという理性の鍛え方でした。それだけではありません。伊原さんは、そうすれば、論理をもっと突き詰めることができ、見えなかった世界を見ることができると言っておられました。歴史学のジャンルでは、どうしてもそのような行為がなおざりになりがちですね。歴史を叙述する人だって、森羅万象を全て記述するようなことはできず、歴史叙述という行為自体に「思考の節約」が必要なはずなのですが、どこか物量戦だと思い過ぎているところがありました。
第二に、「正確で透明な理解と叙述」という視点。
やや弁解めいて聞こえるかもしれませんが、私の文章の中に不協和なものを感じられたとしたならば、それは私が現代史の研究者だからではないでしょうか。音楽のことはよくわかりませんが、絵画の世界では、西欧的な遠近法が崩され、新しい見方を見せようとする芸術運動が全盛を迎えます。それだけではありません。「国民国家」の考え方(一つの領土、一つの民族、一つの言語)が広まるにつれて、一つの地域に共存していた複数の民族の生活が切り裂かれていくなかで、「ハーモニー」という言葉が虚しく響くような時代を分析対象としています。この時代に登場する前衛芸術の多くは「ハーモニー」の世界に挑戦するものでした。私もそんな現代の芸術に魅せられてきました。他方で、キュビズムの絵画を「人種的に劣った」あるいは「障害者の描くような」という修飾句を用いて「退廃芸術」だと名指しして排除し、徹底的にドイツ国内の「ハーモニー」を訴えたナチスの嫌悪感はよく知られている通りです。実際、ナチスの文献を読んでいると「調和」は「健康」という言葉をセットで用いることが多いですね。健康は優生学の根幹的精神です。実は、伊原さんの今回の文章の中で背骨の比喩を聞いたとき、「正常」「調和」という言葉遣いの響きにかなり悩みました。時間が空くと、歯を磨いたり、顔を洗ったりしながら、毎日のように伊原さんの文章を頭の中で反芻しておりました。
しかしながら、伊原さんの主張しているのは、理性の厳格な定めをおろそかにするようでは、ナチズムの用いた優生学という現象でさえ見誤ってしまう、というものではないかと思うようになりました。不協和音に溢れた歴史的現実であったとしても(それに魅せられたとしても)、歴史学は「理性」を用い、それを手放さないことを論文の最後の一語まで自分に課さなければならない。そうでなければ、この世で「不安定」だと名付けられている人たちにとっての学問、「不健康」だと名付けられている人たちにとっての学問までも閉ざされてしまう。
理性的であることを定められている歴史論文は、問いと結びのあいだで辻褄が合わないといけません。それは数学者と変わりません。途中で、「ただしX>0とする」という前提条件を「やっぱりX>1に変えます」と変更することは文系といえども(しばしば見受けられますが)できません。前便で伊原さんは、ジェイン・オースティンの『高慢と偏見』の複数の翻訳の検討を通じて、読者に届きやすい言葉を探しているうちに、内容をきちんと伝えるものではなくなってしまうことに警鐘を鳴らしています。本来は調和することのない言葉を並べたり、読者をハッとさせようと考えたりするあまり、気の衒った表現を使うことに対しても伊原さんは痛烈に批判されていますね。
翻訳は、文系研究者の生命に関わることです(お恥ずかしい話、私は痛い失敗をしてきました)。ほとんどの文系研究者が最初に取り組む特訓が、外国語や古い時代の文章を一語一句読んでいくことだというのも、読むことと書くことの「透明性」と「客観性」こそ、まずは身につけるべきものだ、という暗黙の了解に基づいていると考えます。私もそうあるべきだと思います。読むという基本的な行為、外国の文化を、言語を通じて、無色透明な心で取り組む時間はいくらあってもありすぎることはありません。
つまり、私は、伊原さんとの往復書簡の中で、論理的にスキのない、どこまでも透明で淡々とした理性の世界に、日本語的流暢さを求めすぎて(日本語文化圏内だけで)分かりやすくなりすぎた世界よりも開けた思考空間が広がっていることを学んだおかげで、ちょっと初心に帰った感じがあります。もちろん、文系にとって問いは、この世の不条理であることが多い。なぜ、こうであるべきなのにああなのか。なぜ、こうであることが自然なのに、ああなってしまったのか。それをつかむには不協和音を響かせる言葉にもしっかりと耳を傾けなければなりません。ただ、それと自分が「理性」を手放さない、ということは両立するということです。
この往復書簡のタイトルの問いは、比較的学んできた年数の少ない人、これから学ぼうとする人に向けられています。そういう人たちに向けて私が言えることは、自分のまとめたことを多くの人に読んでもらおうという気概を最初から出すのではなく、当時の時代状況から考えても論理構造から考えても、妥当と思えるようなところまで史料の内容を読み込み、読みやすさを優先するあまり事実に目をつぶらず、地道に調べ、書く作業をまずはやっていくことがやはり重要ということ。18代中村勘三郎の「型がある人間が型を破ると『型やぶり』、型がない人間が型を破ったら『形なし』」という有名な言葉は、私も歴史学の先輩から聞かされ、座右の銘にしてきました。まずは「型」を身につけること。その「型」には文理ともに理解し合える場所があることを確認しておきたいと思います。
(伊原さんから藤原さんへのお返事は、毎月20日に公開予定です。)