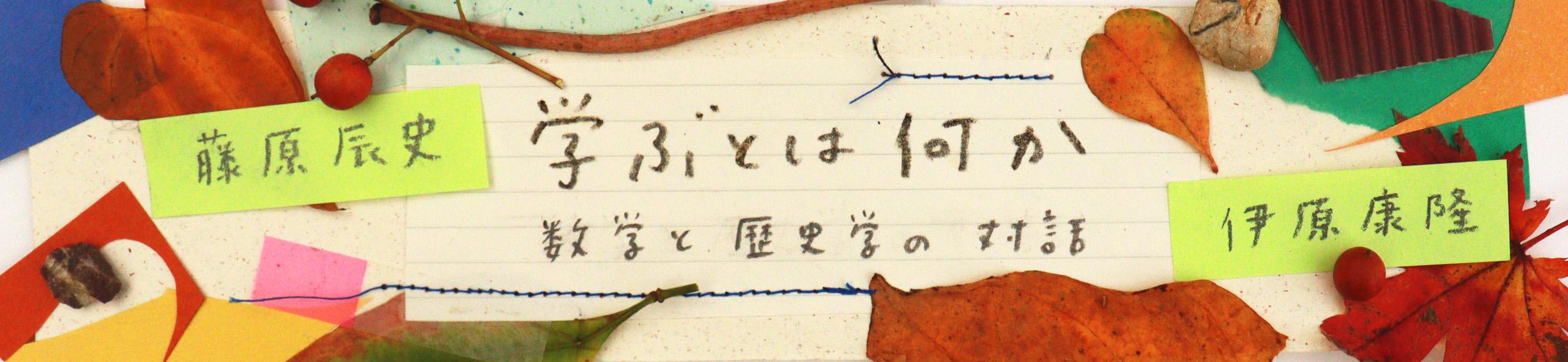第26回
好考爺のアドバイス(伊原康隆)
2022.11.20更新
歴史学者の藤原辰史さんと数学者の伊原康隆さんによる、往復書簡の連載です。藤原さんから伊原さんへの前回の便りはこちらから。
伊原康隆>>>藤原辰史
なるほど、結びつきの発見の喜びも共有していたのですね。また、その喜びは客観的記述が求められる著書や論文では直接表現できないから読者には気づかれにくい、ということも共通のようです。ですからこの企画ーー熱気を期待された異分野対談ーーの熱がそれを表面に浮かび上がらせてくれ読者諸氏とも共有できそうでよかったと思います。では数学での私の発見の具体的説明は? いや、それは空気の薄いところでの長いハイキングになり皆さん冷えてしまいかねない、控えておきましょう。
また発見にいたる経路として(たとえば人文科学では)資料検索が肝要であることもあらためて強く感じました。藤原さんは10月のご書簡で歴史を学ぶ学生さんに「大量の資料を読みこなす訓練」を勧められました。これは「目的意識を軸にした資料検索」という(どの専門課程でもある段階では)不可欠な話だろうと私も思います。
ただし、その段落で引用された「思考の節約」は、私としては7月号で「群」の概念の導入の際に限定的な意味で用いたのを、ずっと広汎な意味にお取りになったらしいということも指摘させていただきます。私のポイントは「広げて回して切り口を」(7月号タイトル)であり、その中で「群」は、回すところに出てくる動的な対象、他方、「思考の節約」と実質的に関わる個々の「単純化」は「広げて回した後の最後に」個々の切り口として出てくるものでした。ですから「思考の節約のために最初から資料を限定する」意味合いはなかったのです。
著者による「結びつきの連鎖」の説明を読者として比較的楽に堪能できた印象的な例として、藤原さんの『トラクターの世界史』をあげさせていただきます。「大衆車とトラクター」(フォード社;大量生産の二本柱)→「トラクターの、米国からソ連(当時併合され飢餓に苦しんでいたウクライナ)への安価な輸出」(ユダヤ人コミュニテイ相互援助)→「トラクターから戦車へ」(技術的つながり)→「独ソ戦と戦車隊」(地域的つながり)。
理系でも「目的意識を持ち、それを軸に諸論文を調べ、考え直して真の目的を探ること」はやはり重要ですが、それに先立つ「若い頃の基礎的思考力の訓練」が更に欠かせないのです。すると「精読」がキーワードになります。
精読
優れた書物は読者の世界を広げてくれます。長編小説など文学の名作なら一旦引き込まれればどんどん読み進められるから、何の指南も必要ないでしょう。ここでの対象は読者の考える力に依存する書物の精読です。その恩恵は、知らなかった「考え方」を知り、自分で考える力も鍛えてくれること。そして「考える」は大抵は「言葉を使って考える」のだから、しっかりした言語体系を個人の中で作っていくことにも寄与するでしょう。著者による体験の表現の妙から自分の体験の表現方法へのヒントも(文章単位の熟読でなら)得られるかもしれません。
精読は「眼光紙背に徹す」と通じますから、勧められる読み方は多読とは別方向、「先へ先へ」ではなく「奥へ奥へ」でしょう。系統立った書物を精読するのは、精緻に配置され分岐点も多い「線路」の上を「注意深く脱線せずに」進むようなもの。
一見読みやすそうな啓蒙書の類でも、読者の側に(時間に見合ったページ数を読みたいといった類の)焦りがあると目線が先へ先へと移って加速され、それだけでも脱線の可能性が高まります。他方、基礎理論の教科書は段階を踏みつつ一歩一歩進みますから、各段階の内容に十分慣れないうちは次に進めないもの、その際は焦らず読み返す必要もあるでしょう。
いずれにせよ、先頭車両は、軽快な快速電車から重量級機関車によるゆっくり牽引に替えないとだめ。重量級とは「一歩一歩に意識の重心をしっかりかける、線路に喰い込むように」ということです。たとえば資料検索では効率的な「ページをめくってはキーワード拾い読み」では分岐点すら見えません。同僚にそういう読み方をして1日何ページ読んだという人がいても、それに影響されては損をします。
もう一つの重要な注意点ーー特に哲学系、翻訳物、他分野の啓蒙書などーーは、一般的な基本用語に対して著者と読者が有している「イメージの相違」でしょう。文中に現れる基本用語に対して、読者のイメージはしばしば(著者のイメージの軸からみると)ぼやけ気味、または中心が偏ったところにあって通過時にそちらに意識が引きつけられがちです。以下は自戒の言葉ですが、特に加齢と共に、脳内には「言いたい事として出番を待ちつつある塊!」がいくつも形成されてーーつまり脳が分極化してーーおり、用語によって最初に刺激された塊がその文章すべてを引きつけてしまう、そういうことも起こりうるのです(他人事と思わず若い方々もお気をつけ下さい)。
すると著者の線路上を走る読者の車両は、基本用語に出会う度に、横向きに揺れることになるでしょう。それでは度々脱線しないほうが不思議。それを防ぐには、基本用語のイメージを再確認しながら丁寧にゆっくり進むしかないのです。他国語の翻訳の場合は、言語の相違自体が横揺れの根本原因になり、「横揺れを減らすか原意を生かすか」の課題が随所に生じるでしょうから、訳者の苦労は並大抵ではないですね。自分にとって重要な本は原書も紐解き、原文ならではの快適さを十分味わう体験をしてみて下さい。
山登りに喩えれば、新用語の相続ぐ登場は「上方勾配のキツさ」、既知用語のイメージのズレは「ある形の岩の上では体幹がぐらつく癖」、克服の方法がやや異なることを意識するとよいかもしれません。
なお、ある山に登るとそれ迄見えていなかった「遠方の高い山脈」が望見される、これは理系でもよく知られたことです。一つの問題の解決は新たな問題群の発見につながる。だから「知」には頂点や包括はない、全知全能という言葉は自己矛盾を含んでいるのではないか、これは現在の私の個人的意見ですが。
選書
辛抱強さと継続性を支えてくれるのは、まずは高度な内容への憧れの念とあくなき向上心ですが、それに加えて著者への敬意も肝要です。ですからそれが持てる著書を選ぶのが大前提ということになるでしょう。良書の条件はさまざまでしょうが、不適な条件なら数例挙げられるかもしれません。
* 「一箇のキーワードの説明が十分でないうちに次々それにオンブした新手のキーワードが現れる」もの。(自分のも、説明の過凝縮がその種の印象を与えてしまっているきらいがありそう。)
* 音楽、美術など、他の表現様式の作品の価値は本来、言葉によってはとても表現しきれないものです。逆に、雑になら「何とでも」いえてしまう、それが怖いのだと思います。私も、いくつかの名曲について自分が感じた美の表現を書き連ねたことがあります。対象が真に好きな曲であり(必要な長さの分ずっと)実際の音が心に鳴り響き続ける場合に限れば、それも許されるのではないかと思っています。異なる表現様式の壁を越えるには、まず下から目線の「敬」が必要でしょう。
* 哲学的な要素が強い場合、自説を支持してくれそうな引用が多い書物の論は、「なるほど」と感心はしますが、さらに尊敬してしまうのは、ダーウィンの『種の起源』のように、異説も積極的に取り上げ、それらに対する個別の反論をも併記してある著書です。それらは概してすっきりとは読みにくいのですが、これはイギリス流の(ややこしさを厭わぬ)丁寧さでもあるでしょう。コロナ時代の乱暴な指南本の一つの見分け方は、都合のよい材料だけを集めている風かどうか。
これらの判別感覚は、数ページでも丁寧に食らいついて読む癖がついていれば図書館での部分精読からでも感じ取れるのではないかと思います。選ぶ前に、「何が」書いてあるかだけではなく、知っていることが「どう」書かれているか、この観点からもチェックしてみましょう。
理系の教科書
理系(と多分、哲学系も)に特有なのは、思考に仮想的(抽象的)対象も含まれることであり、それは「人知によって世界は自然に広がるもの」だからでした(複素数を端緒とする抽象的な代数系や空間の導入など)。そういう思考力を身につけるためには「(自分が)選んだ良書の精読」を軸にすることこそ、といわれており私もそう思います。
たとえば7月にご紹介したガロア理論なら、ファン・デア・ヴェールデンの「アルゲブラ」(代数学のこと;ちなみこのアルは、アルコール、アルゴリズム等でも使われラテン系のイルに相当するアラビア系の定冠詞です)。まず使われる基本用語をなるべく正確に理解し、自分の中に「軸や階段」を作っていくことが基盤になります。建築と同様、これは日時のかかる仕事です。読み方としては、何より丁寧に読んで不慣れな用語に馴染む、(所有の本なら)随所に補充事項などを書き込む、停滞したり混乱に陥ったりしたら何度も読み返す、そういった辛抱強さと丁寧さが肝要です。わが家の奥まった本棚にある「アルゲブラ」(当時は「モデルネ・アルゲブラ」)を横から見ると、鉛筆のススの黒さが難渋した節目の目印になっています。
建築でもコンクリートを乾かす時間などが必要なように、合間の時間も重要です。たとえば一つの章を読んだら一旦本を閉じ、紙と鉛筆で内容の再現を試み、その確認のため読み返す。さらに大きな合間での、回遊的散歩と夜の睡眠、これらこそが、内容を無意識領域にまで浸透させてくれることを信じましょう。モヤモヤしていたのがあるときパッとわかるのは、無意識領域では継続的に仕事がなされておりその結実時の感動が意識領域に躍り出た、ということです。外からはさぼっているようにみられる時間が実はこの無意識活動にとって重要なのです(詳細は拙著『志学数学』『文化の土壌と自立の根』)
「考える」は攻撃的?
「考えるということ自体、攻撃的ですよ」とやんわり言われたのは、関節の合理的な使い方の指南を受けた(敬愛する)先生からでした。「身体の動きも物理の法則に従っているはずだから」と異論を挟んだときだったか、その後の何気ない会話のときだったか。びっくりもしましたが改めてこう思いました。「なるほど、でもその攻撃性は、まずは自分自身に向けられて自分の従来の考え方を破壊し、次いで誰かの説得に向けらたときに相手に攻撃的と感じられやすいものなのだろう」と。そして、たとえば藤原さんも私も、元来は攻撃的人間ではないのにそれぞれいろいろ考えた必然的結果として、ときにその意味の攻撃性を共有しているのかもしれない、とも。私は自称(「好々爺」ではなく)「好考爺」ですから怖がられることが「なきにしも非ず」です。
数学など、内容は客観的で感情と無関係だし、出来る限り「支配」ではなく「共有」を旨として淡々と説明しているつもりでも、残念ながら相手に攻撃的と受け取られ感情的になられることがあります。多分その原因の一つは、純然たる理詰めの連鎖こそ(逃げ場がないから余計に)相手にとって鋭い刃物なのでしょう。ただ、その矛先が実際はどこに向けられているかーー当面の対象に限定か? 相手全体なのか?ーーを見極めて冷静になれるかどうか、これは話し手の配慮にもよるでしょうが、社会の文化度にも依存するのではないかと思います。慣れていないと自分が全否定されたと感じてしまう。受ける側として、冷静に限定的に受け取れるようになることも「学びの基本」でしょう。帰する所は内面的な自信でしょうか、以下の例をご覧下さい。
G君(アメリカ)と Z君(スイスからドイツ)の素晴らしい共著論文がありました。それぞれ非常に鋭い頭脳をもち得意分野は相補的という二人がそれぞれの特技を生かせたもの。その研究途上の頃 G君の自宅に泊めてもらっていたとき、彼と Z君が電話で議論していましたが「何てバカな(stupid)ことを!」 など平気で言い合っていました。これは「個別な内容に対して相手にそう言われても自分の能力が批判されたことにはならない」という確信がお互いにあるからできることなのでしょう。
余談ですが、のちにZ君が京都に来て講演する際、そのアブストラクトを東京で見た私が、この共著論文の主張の半分(定性的部分)は既に終戦直後の論文(これこれしかじか)に載っていますよと指摘し、びっくりした彼は以後「ヨーロッパでは何を話しても安全、でも日本は怖い、これこれの雑誌に既に出ているのにお前はなぜ話すのかと言われる」といいふらしていました。私としては、自分の研究との関わりで熟知していた論文であり、またナチス時代に書かれたドイツ人の論文が戦後一様に忌避され広く膾炙していなかったこともうすうす気付いていました。でもZ君としては、その出版社がスイスで著者がドイツ人なのに日本に来て初めて存在を知ったというのがことさら印象的だったのでしょう。民族や出自よりも学問的好奇心が国境を超える力、といっては大げさですが、面白いものです。
習慣化への道
好考爺の好考について書きましたので、最後に「爺」として一言追加いたします。親が子に残してやれる最も大切なものは何か。それは「よい生活習慣をつけてやることだろう」といわれます(ベンジャミン・フランクリンの自伝など)。そこで私も、この際の老爺心として学習におけるよい習慣「の付け方」へのヒントを一つ書かせてください。何が身に付けたい習慣か、それは各自が考えることですが「こういう習慣を付けたい」と思っても、それを定着させるには一定期間の継続が必要で、その継続の力になってくれるものの一つとしてお勧めしたいのが「まず日記をつける習慣から始めること」。日記帳は広くて分厚い大学ノート(1年間分位は入るもの)がよいと思います。日記というと過去向きとお考えかもしれませんが、ここでは近未来のためなのです。
その決意を日記に書き留め、いつから始めるかの「X デー」を定め、その習慣が破られそうないくつかの要因(たとえば面倒臭くなる、飲酒、友達からの誘い、等)を想起して列挙し、それぞれに対策を考えて書きとめ、決して誘惑に負けないぞ、自分の価値がかかっているぞ、と決意表明しておくのです。日記を書くのは夜だとすると、夜の誘いはその間は要注意ですね。「X デー」とは物騒な言葉ですが、自分との戦闘開始という意味です。だから直ちには始めないことにも意味があるでしょう。開始日を初日とする星取表を作り、その習慣が守れたら○をつけるのを楽しみの一つとする、私の場合は、3週間続けるのが一つのメドでした。刺激が多い環境で自分の一貫性を保つための一つの合理的な方法としてご参考までに。
吟味と補足
『トラクター』に戻ると、これは土を掘り返すという作業を機械化したもので、手で掘るときはシャベルの類を「テコの原理」で用いる。つまり、取っ手の先端を下向きに押すことで突っ込まれたシャベルの先端が土を上に掘り起こすわけです。力点でも作用点でもない「支点の存在」を仮想したテコの一般原理も、人類の発見史の一里塚であろうと思います。でも道具が高度化することで未来の人間がテコの原理すら(頭でも体感としても)知らないようになったら、それも進歩でしょうか。この話題は「AIに全ての知を支配されたくない」人間の一人として、次回に少しでも、と期待しています。
最後に音楽関係の追加として、ここ2回述べた「不協和音」の源になる「音響的ニアミスの可視化」のグラフを補足ファイルでご覧ください。