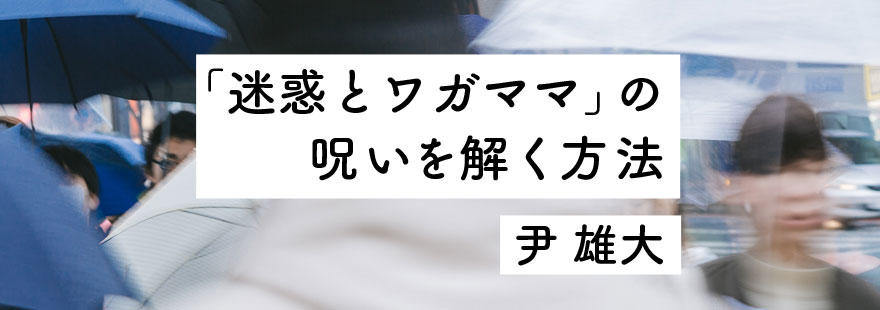第5回
恐れから私たちがついとってしまう態度
2018.09.17更新
夏休みをいただき連載に少し間が空いたので、これまでの話をさらえつつ、ぼちぼちと話を進めていきたいと思います。
さて、前回は迷惑やワガママとされる振る舞いを非難する際、しばしば用いられる「周囲への配慮がない」という言葉を取り上げ、この言い回しを使う人が隠している意図について書きました。
改めて言えば、「周囲への配慮がない」を持ち出して、他人をひどく罰したがるとき、その本意は「あなたの行いは私の気持ちをひどく損ねている。だから私に対して一言あってもいいのではないか」にあるのだと述べました。周囲ではなく、私への気遣いのなさが問題だったのです。
真意を悟られることなく、安全圏にいながら相手を批判できる。それだけこの文句は使い勝手がいいし、非常に効き目のある魔法のような力を持っています。実際、「周囲への配慮がない」を持ち出せば、相手の置かれている状況や事情だとかのいきさつを考慮せずに、とりあえず「あなたに落ち度があったのだ」と立証できたような空気をつくれます。
言われた側も「そう言われると、たしかに配慮が行き届いていなかったかもしれないな・・・」とうっかり反省したり、負い目を感じてしまいがちです。というのも、ちゃんと周りを気遣っていたか? と問われたら、本当にそうしていたか怪しくなるし、どうにも心もとないからです。
なんだか自分が悪い気がする。けれども「そう言われるとー」という前置きを必要とするくらいだから、いまいち言われた本人はピンと来ていないわけです。
この言われていることが腑に落ちていない、不明瞭な感じは、実は非難する側の意図を隠した態度がもたらしているのだと思います。なぜなら「周囲への配慮がない」とは、細かな事実に基づいての批判に要点があるのではなく、ぼんやりとした空気を作ることに目的があるからです。
配慮のなさを指摘する側は「落ち度があったとすれば、それは何か? どこまで責任を負うべきか?」といった具合に、相手と自分の認識の違いを鮮明にすることを期待してはいないでしょう。あくまで「あなたに問題がある」という漠とした空気を読ませて、「私を気遣え」と身を縮こませることが眼目なのです。
空気を醸し出す上で周囲、つまり「みんな」は欠かせません。「みんな」と言ったところで、それが友達を指すのか。近隣の人たちなのか。しかも、どちらも親しさの度合い、距離感は様々ですから、「みんな」という一括りでは、どこまでの範囲を指しているのかわかりません。けれども、わからないからこそ「みんなへの配慮がない」「みんなが迷惑している」といった表現がパワーを持ちます。
「みんな」を持ち出されることに、私たちはひどく弱いのです。幼い頃から「みんなはできているのに、どうしてできないの?」とか「みんなと仲良くしましょう」といったように、あらゆる機会を通じて「みんな」を主役に考えるよう促され、自分に価値を置くのは後回しなのだと思うようになりました。いつしか息をするようにその発想を自然と身につけ、その結果「みんな」という言葉がひとり歩きし、独自の力を持つようになったのです。
誰かができているからといって、なぜ私がやらないといけないのか。なぜ好きでもない人と仲良くしなければいけないのか。「なぜ?」と素朴に問いかけた途端、親や教師の怒りを招き、「聞き分けがない」やそれこそ「ワガママを言うな」と言われたことが誰しも少なからずあるでしょう。そうした経験を重ねれば、感じて思ったことを口にするのはいけないことなのだと学んでいきます。
周りがどうであれ、本当は意の赴くままに行動したいし、そういう自分を肯定したいにもかかわらず、体の奥深くに浸透した「みんな」への恐れが私の言動を抑制するようになってしまいました。
「みんな」に自らの振る舞いを揃えるようになると、私たちは自分の感覚や思いを否定的に扱うことに巧みになります。どこにいるかわからない「みんな」がどういう基準で評価するかわかったものではないとしたら? 爪弾きにされて傷つかないためには、私が私自身に価値を置かない。これが非難を避ける賢明なやり方になります。
聞き分けが良くなり、自分の意ではなく周りの考えに従う。こうした方法に習熟したことで私たちはふたつの身なりの整え方を手に入れました。
ひとつ目は自分の興味に従って物事を試してみて、その体験の中で培った「正しい」と感じることを述べたり、それに基づいて行動することを放棄しました。
ふたつ目は怒りを表現することを恐れ、それでいて怒りを募らせ、捻くれた形で表現するようになりました。それぞれの選択がもたらした事柄について見ていきます。
ひとつ目の「放棄」についてです。何か事件が起きて意見が対立するような局面になると、決まって「どっちもどっちだ」と述べる人が現れます。このような論調をとることが冷静なのだと捉える人は増えており、一定の層を形成しているように私は感じています。「どっちもどっち」は自分で考え行動することの「放棄」を考える上で、格好の題材だと思います。
「どっちもどっち」の主張はおおむねこういうものです。
「絶対的な正義はないのだから、どちらの言い分にもそれぞれの正しさがある。争っている両者がどちらも『自分が正しい』と信じているのであれば、なおのこと冷静に物事を解決する上で両論併記は欠かせない」
「どっちもどっち」だと俗っぽいですが、「両論併記」と言えばなんだかスマートに聞こえます。中立だからこそどちらの言い分も理解でき、物事がよく見える。だから公正な立場に立てるはずだ、というわけです。
けれども、はたしてそれは本当に中立で公正なのでしょうか。というのは、「どっちもどっち」と言えてしまう立ち位置はどこなのか? と問うと、次の疑問が湧いてくるからです。
「なぜあなたはジャッジできる立場にいるのですか?」
「どうして、『どっちもどっち』と言えるような高みに自分はいられると思えるのですか?」
「どっちもどっち」は公正でも中立でもなく、紛れもなく良し悪しの判定の結果です。しかも、起きている出来事を観察すると言うよりは、みんなの常識の平均値に配慮しています。そうして十分ジャッジしているにもかかわらず、それを明らかにしないのは、「みんな」からの非難を避ける賢明な手段だと、どこかで知っているからでしょう。
確かに批判はかわすことができます。同時に「どっちもどっち」は物事を限りなく他人事にしていくので、現実にコミットできない場所に留まり続けることになります。
何かを選ぶとき、私の感覚が指差す正しさに基づく他ありません。私にとっての現実はあなたのそれとは違うからです。私の人生は他人事ではないのだから、自らが正しいと思うことを試し、実際に生きてみて何が正しいかを検証するしかない。「どっちもどっち」ではいられないのです。
しかし、「みんな」に合わせてきた結果、自分の感覚に基づいて話し、行動するという独自の歩みは独善的でワガママなのだとジャッジするようになってしまいました。私の感覚と考えに従う。生きていく上での第一歩を「みんな」に委ねたことで、容易に「放棄」できるようになったのです。
いまどきの「どっちもどっち」は、一筋縄ではいかない現実に対する慎重さがもたらしたのではなく、独自に考えることを止めた。その結果の冷笑が生み出した態度ではないでしょうか。どちらとも言えない複雑な世界が目の前に広がっているのは確かにそうかもしれません。しかし、どちらとも言えないからこそ試してみるほかないわけです。
編集部からのお知らせ
尹さんの新刊『脇道にそれる 〈正しさ〉を手放すということ』発売中です!

『脇道にそれる 〈正しさ〉を手放すということ』
尹 雄大(著)、春秋社、2018年5月発売
1,800円+税
仕事、家族、生活・・・。私たちは様々な場面で固定観念に縛られている。社会に属しながら常識という名のレールをそっと踏み外すことができたら、何が見えてくるだろう? 「べてるの家」の人々から伝統工芸の職人まで、「先人」たちが教えてくれた唯一無二のあり方とは。