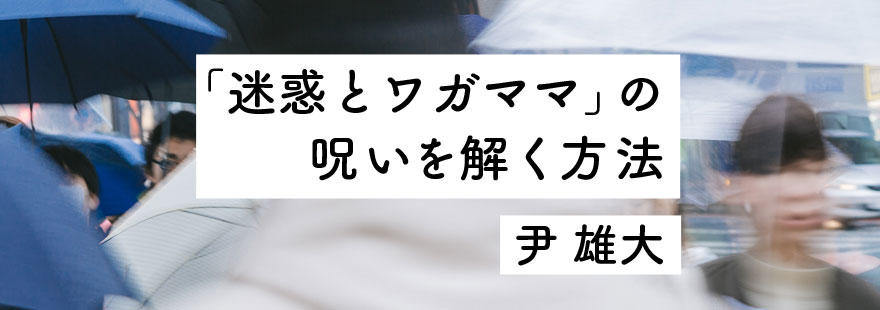第13回
私たちが自信を失うとき
2019.05.24更新
子供の頃は大人は自分の頭で考えて物事を判断できると思っていました。でも、大人になってみると自分も含め、少なからずの人が案外「嫌われたくない」とか「間違えたことを言ったら笑われる」といった恐れから自身の行動を決めていることに気づきました。
これまでの連載では、私たちの普段の言動は能動的で主体的なアクションというよりも、世間や常識の顔色を伺った結果として身につけてしまった反応、リアクションがほとんどではないか。そんな話をしてきました。
「迷惑をかけてはいけない」
「そんなワガママなことが許されると思うのか」
それらに「なぜ?」「どうして誰かの許可が必要なの?」と素朴に問いかけるのをいつしか止めてしまったのは、怒られたり罰されたりと心と身体にしこりが残るような傷を受けたからだと思います。恐怖が私たちの行動の原則になったのです。そうして辺りをキョロキョロと見渡しては「間違ったことをしていないだろうか」とビクビクし、他人と同じ行動を心がけるようになりました。やがてみんなと違った振る舞いを目ざとく見つけては、同じ恐怖を与えようと「迷惑をかけてはいけない」「そんなワガママなことが許されると思うのか」とかつて自分に言われた言葉を唱えて罰するようになりました。
他罰的な言葉遣いを学んだ結果、私たちはどんどん自信を持てなくなっています。主体的でハツラツとして積極的な行動をとれば、揃えた足並みを乱すと言われるのですからそうなって当然でしょう。その上でこう言われます。
「これをやれば自信が持てるよ」
「これができないと満足した人生は送れないぞ」
健康からビジネス、食に美容とあらゆる領域でこうしたメッセージがささやかれています。自分を信じるのではなく、誰かの提供する価値を信じろと、それらは訴えているわけです。
自分の人生は誰かが代行してくれるわけではありません。それでも虚構の設定を信じさせようとする力に私たちは絶えずさらされています。
このような状況を「身体性の消去」と表現できると思います。私が私として存在することを許さないと言い換えることもできるでしょう。
私たちは誰とも取り替えられない身体をもって生きています。この身体丸ごとの生命活動には「こうしなければならない」ということは全くないはずです。誰しもただ息をしているだけで毎回「息をしなければならない」と考えて実行しているわけではありません。ただ存在し、ただ生きています。
でも、その事実よりも「こうでなければいけない」といった概念を重んじることが常識であり普通となっていくと、どんどん自信を失っていきます。仮に言われた通りのことができるようになったとしても、「もし想定と違うことが起きたらどうしよう」と不安になっていくからです。
迷惑やワガママといった言葉で誰かを非難したがるのは、その行為が問題なのではなく、それが自らの不安や自信の欠如を突いてくるからではないでしょうか。もしかしたら、私たちは自信のある生き方をしていれば、そうそう他人の言動をチェックして迷惑だのワガママだのと言い募ることはしなくなるのかもしれません。
自信が差し迫って大事なことではないでしょうか。鍵となるのは、やはり「身体性を取り返すこと」だと思います。これについて述べていくにあたって、まず私が紹介したいのは相撲の話です。どういうことだ? と思うかもしれませんが、しばらくお付き合いください。
圧倒的なパワーを背景に長らく相撲界で人気を博したのは、小錦や曙といったハワイ出身の大柄の力士でした。ところが2000年代の初頭から角界を席巻し始めたのが、主にモンゴル出身の力士たちです。年々、大兵肥満に拍車のかかる力士に比べると、彼らはそれほど抜きん出て大きいわけではありませんでした。見た目に明らかな体格の差がないため、とりわけモンゴル人の力士の強さに対しては「ハングリー精神」を持ち出して報じる論調も多く見られました。
精神論の使い勝手のよさは、なんであれ結論に持ってくるとそれらしく聞こえるところにあります。けれども実際は何の説明にもなっていないことが多いです。
そんな折、スポーツ誌から「外国人力士台頭の背景を探ってほしい」と依頼され、モンゴルや東欧出身の力士たちとその親方にインタビューを行いました。そこでわかったのは、強さの背景にあったのは精神ではなく身体。それに伴う彼らの自信でした。
モンゴル人力士を抱えるそれぞれの部屋の稽古を見学した際、まず注目したのは彼らの足指でした。多くの日本人力士はアスファルトで敷き詰められた平面を靴で過ごす現代的な生活に慣れ、足の小指が潰れたり変形していました。けれども朝青龍や朝赤龍、それに時天空をはじめとしたモンゴル人力士たちは靴を履く文化ではあっても、指はきちんと五指に分かれていました。そのため四股を踏んだり、すり足を行うと砂が小指の股にも絡まり付いていたのです。つぶさに見ましたが、日本人力士には見当たらない現象でした。指がそれだけ分かれていれば、地面をぎゅっと掴む力にも優れていると言えます。また一様に血色が良く、骨盤も柔軟で倒れるにしても前のめりで崩折れてしまうということはなかったのです。
佐渡ヶ嶽部屋の先代親方は重量級力士の図体は大きくても、はたき込まれるとバッタリ倒れて土俵に手を付く。そうした自分の体を持て余す日本人力士のありさまを「ブタが相撲とっているようなもんだ」と苦々しげに言いました。追手風部屋の親方はジョージア出身の黒海について「話をよく聞いて理解するし、基本をおろそかにせず熱心に稽古する」と話してくれました。黒海は来日した当初は日本語を話せませんでした。つまり親方の説明は、言語的な理解だけを指していたわけではなかったのです。
そうであれば、黒海は日本語をわからずして、どういう基本を理解していたというのでしょう。ある部屋の親方の嘆きがこれについての説明で最もふさわしいと言えます。
「最近は入門してきた日本人の弟子に教えなくてはいけないのは相撲でも礼儀でもないんですよ。まず朝起きたら歯を磨き、顔を洗うことだったりします。家庭でそういう習慣が身についていないんです」
この話から推測されるのは、外国人力士は自分の身体の快適な状態を保つためのケアを普通に行い、またどうすればうまく力が発揮できるのか。そうした身体の状態を感じるといった、自分に向ける眼差しが日本人力士よりも身についている、ということです。
自分の身体の輪郭をしっかり捉えられる。ここが日本人力士との違いになっているのだと思いました。「ブタが相撲とっているようなもんだ」と重鎮の親方が吐き出すように言ったのは、「大きくなりさえすればいい」と身の丈を超えて太ってしまった結果、いったい自分が適切に快活に動けるかどうかすらもわからなくなっている様を指してのことでしょう。
さて、自信を取り返すためには身体性が必要だと先述しました。自分の身体の輪郭を把握できているかどうか。要は「自分は自分だ」と認識といった言葉での理解以前の感覚的な把握です。これが他者の声や顔色を伺うことなく自分で方途を定めて生きていく上での自信の源になるのだと思います。そこで次に触れたいのが朝青龍です。抜群の強さを誇りながら、戦績よりも「素行の悪さ」が取り上げられがちだった力士です。
マスメディアを通じて形作られた彼のイメージは「礼儀や常識を知らない」「暴言を吐く」「喧嘩っ早い」といったものだと思います。私が彼に取材して思ったのは、現代において荒ぶる神の神性を帯びることのできる稀有な人物だということです。言うなれば彼はスサノオです。
怒ったと思えば哄笑する。乱暴な振る舞いで付き人が泣いた途端、「どうした? 何が悲しいんだ?」と驚いた表情を見せて、まったく自分のしでかしたことに葛藤がない。山の天気のように移り気で、それもスサノオらしいと言えます。
その時にそう感じたからそうする。しかも、その感情の変化に対応する言葉の数が少ないから迷いがない。反省しない。それが彼の強さにもつながっていたように思います。稽古において朝青龍の取り組みはやはり異彩を放っており、しかも人を惹きつける華がありました。
朝青龍は「悪」を体現できる人でした。これは悪人ではなく、「悪源太義平」とか「悪党」で用いられる意味合いです。人として強度があるということです。
強度は何によってもたらされるのでしょう。私たちは何かを知るとか信念を持つとか、自分の外の概念に身を委ねることで強くなろうとします。けれども彼はどうやら自分を何かの基準に照らし、比較して行動することにあまり関心を払っていないようでした。
しかし、その言動からバッシングされ、一時は抑うつ状態になったと報じられるに従い、彼の動きから精彩が失われていきました。これは非常に象徴的な出来事です。自分がただ自分でいることを禁じられ、「それはおかしい」と言われ、教え込まれると病んだり弱くなって、本人も気づかないうちに自信を失ってしまう。
付き人の涙を見て驚いたことからわかる通り、朝青龍には共感をベースにしたコミュニケーションに馴染みがないように見えました。バッシングは、いわば彼に日本の常識への共感と理解を求めるものでしたが、朝青龍にはそれが窮屈に感じたのではないでしょうか。
「品格にもとる」といった非難の声に対し、ひところ彼はジブリの作品を見て品位を学ぼうとしたそうです。批判する側は「これを身につければ品格があるとみなす」と明確な基準を示したわけではありません。ですが正解かどうかを判断する立場にいます。精神性というよくわからないものを取り沙汰され、しかもその学習にアニメを選ぶあたりが滑稽でいて物悲しくも感じるのは、ここに同調圧力で才能を潰しにかかる最たるものを見るからです。
空気を読む作法からわかる通り、この社会は「わかり合う」ことへの期待が異様に高いと言えます。根底には「わかって欲しい」という渇望があるのですが、それは自信のなさに由来していることに気づけないでいるようです。私の抱く不安への共感を示して欲しい。そのためのやり取りをコミュニケーション能力と呼んでいる場合が多いのではないでしょうか。
今の暮らしの中では、自分の存在を精神や概念、意識して行えるコミュニケーションといった、ぼんやりとしたものによって「私らしさ」を代弁させようとします。それらはすでに世の中に流通しているコンセプトに合わせたものであって、自分由来のものではありません。「身体性がない」とはこうしたことです。それでは私が私であることの自信を持ちようもありません。