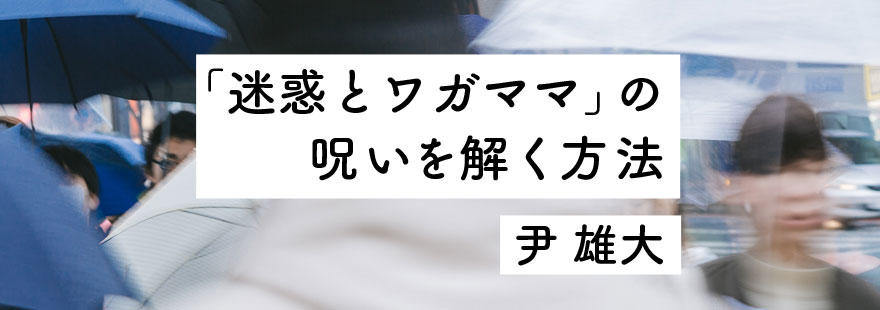第15回
個性と協調性
2019.07.17更新
閑静な住宅街の一角にあるマンションに住んでいた頃、すぐ隣に保育園がありました。登園の時間となると子供らの歓声が聞こえ、普段は落ち着いた空気の流れる一帯がにわかに活気づきます。彼や彼女らの声は小鳥のさえずりのようであり、挨拶と笑いと喜びとが分かちがたく、その調べはとても耳に心地良いものでした。
かつて自分もそうだったにもかかわらず、大人になると不思議に感じるのは、なぜ子供は身体の大きさに不釣り合いに思えるような、あんなにも大きな声でしゃべるのだろう?ということです。電車やレストランでそばにいる親が周囲を気にして口に指を当ててシーッと静かにするよう注意する光景を見たことはあるでしょう。家の内と外とを問わず声の大きさが変わらない。幼さゆえに時と所とを弁える常識がまだ身についていないという説明にどうも落ち着かないのは、そう言ってしまうと何か大事なことを見落としている気がするからです。
たとえば家路の途中で親が「もう行くよ!」と子供を促す姿を目にしたことがあるでしょう。何度目かの声かけにもかかわらず、子供は聞く耳を持っていません。何を見ているのかと思えば、こちらからすれば変哲もない路傍の花です。じっと見て離れず、あるいは行列をなす蟻を屈みこんで見て、その場から動こうとしない。あれほどまでの近さで気になるものやことに向かえたのは、集中力があるという説明は賢しらに過ぎて、ぴったりと来るのは「気持ちと行いとがずれていない」になるのではと思います。子供らの声の大きさもまたそうではないでしょうか。保育園から私の住む部屋まで流れ込んでくる声。子供らが遊戯に勤しみ笑い、泣き、叫ぶことはしゃべるのとほとんど分かれていません。彼や彼女は身のうちに声をくぐもらせることをまだ知らないのです。思いの丈にふさわしい厚みで話そうとするから、その子の身体にとっていまぜひとも必要な声の大きさになってしまう。だからいくら注意されても、声量は変わらない。
幸せとは何かをはっきりとは言えないけれど、毎朝子供らの声を聞くと、私は幸福のさしかける光彩を感じていました。と同時に幸せは形に求めることはできず、ある状態の中にしかない。決して永続しない儚いものだと理解させられたのは、歓喜の声に満ち溢れる中に別の声音が響き渡るようになったからです。
ある時期を境に男性の保育士の声が聞こえるようになり、しばらくすると園庭でただ走り回っていたはずの体操のカリキュラムが整列や行進といった内容に変わっていきました。保育士はホイッスルを吹いて「指をきちんと揃えて!」と前へならえをさせたかと思えば、「ほら、ちゃんと周りを見て!」「手を繋いで仲良くだよ!」「回れ右!」と号令をかけます。その声が聞こえるたびに不穏な気持ちになりました。
この時世に保育士になるくらいですから、彼はきっと真面目に保育に取り組もうとしているのでしょう。でも、その真面目さは何に向けて発揮しているのかを考えていないのかもしれません。なぜなら私にはホイッスルを吹いて子供を従わせることと、動物の家畜化との違いがわからなかったからです。
子供の声がうるさいと園にねじ込む住民がいるとニュースで報じられています。私にはその人たちの気持ちはさっぱりわかりませんが、「子供に対する指導がおかしい」と談判に及ぼうと何度か思ったことがありました。しかしながら彼のような指導によって「社会性が身につく」と評価する親もいるかもしれないと思うと躊躇われました。
それにしても彼の言動はこの時世の風潮を示唆しています。なにせ「きちんと・ちゃんと・仲良く」。おまけに「回れ右」なのです。ここには「自分の身体を他律的に扱い、他者に揃えることが正しい」という無言のメッセージが潜んでいます。身体を通じて行われているところにきな臭さを感じます。
たとえば「みんなとちゃんと仲良くしましょう」と協調性が大事なのだと言われ、その言葉に感化されたにしてもやがてより強く惹きつけられる概念によって影響は薄れていくでしょう。ところが行進だの回れ右だの身体を通じた教育だと、本人の自覚なしに特定の考えが身の内に深く潜り込んでしまいます。その証拠にみなさんが急に「気をつけ」と言われたらピッと背筋を伸ばして姿勢を正すのではないでしょうか。それが正しいと刷り込まれたから気をつけの姿勢を取るのでしょう。でもよく考えてみれば、とっさに動けないような緊張した不自然な格好になることがなぜ正しいのでしょうか。私たちは知らぬ間に自分が感じていることはさて置き、上位の者への従属を正しいこととして学んでしまったのです。
保育園に始まりおおよそ教育と名の付く場で「自分の身体を他律的に扱い、しかも他者に揃えることが正しい」をベースに協調性を教えられる一方、「個性的であれ」や「みんな違ってみんないい」と多様性の素晴らしさも訴えられています。
協調性は、その時々において目的を同じくする者同士の間で発生するものです。それが達成されるべきゴールとして扱われてしまっては、個性とは両立しません。目的がどうであれ「同じであること」に重きが置かれるからです。他人と行動を揃える振る舞いが個性的であるはずはありません。にもかかわらず「個性的であれ」「みんな違ってみんないい」と言われれば、混乱を来します。
仮に奇跡的に協調性と個性が並び立ったとしても、その先には「個性とワガママは違う」「みんなの和を乱すあり方は自分勝手に過ぎない」といった逸脱を禁止する言葉が待ち構えています。これら一連の言葉を口にする人がいると、つい抗いがたい説得力を感じてしまうので、相手の言っていることが正しいように聞こえます。
相手の言い分を生真面目に理解するばかりでは芸がないので、この際「説得力」を「どういうわけか汎用性を持っているように感じてしまう」と変換してみます。物事の理解に努めてばかりで判断することをしなければ、他人からお利口さんだと褒められはするでしょう。それでは私たちは個としての人生を生きることはできません。
すると浮かび上がって来るのは、「みんなのあり方を重視する人がいるとして、では、その人がそう言うだけの個人的な事情はどこに宿るのか?」です。「与えられた枠組みの中で個性は発揮されるべきだ」という言葉に説得力を持たせようとする人がいたとしたら、そこに隠れている意図は「みんな違ってみんないい。ただし私の思う"いい"に限る」になりはしないでしょうか。
そういった許可を下すことのできる「私」とは何者でしょう。特別な力を持った人でしょうか。汎用性の使い勝手の良さは「誰が言ってもそれなりに使えるところ」にあるとすれば、「その人でなければならない必然性」も「この場面では有効な主張になる」といった条件などないかもしれません。ひょっとしたら「個性とワガママは違う」「みんなの和を乱すあり方は自分勝手に過ぎない」は、深い考えなしに言えるところが最大の利点かもしれません。
背景には習慣から逸脱することや新たな変化に対する怯えがありそうです。でも、それも表面的な理由でもっと根本的には偏ること。つまりは自分が自分であること。自分が本来持っている力を発揮してしまうことへの恐れがあるのではないかと思うのです。
私たちは偏在することでしか生きられません。なぜなら私はあなたとは違うからです。顔かたちも性格も何から何まで同じ人はいません。人間としての平均値があるわけではないので誰しもが偏っています。そうなると全てが偏っているとしたらそもそも偏りはあるのか? という疑問が湧いて来ますし、偏りを正そうと均質な動きや考えを教える必要はどこにあるのだろう? と不思議に思えてきます。
偏りとは「みんなと同じ」という普遍性を帯びない私の根拠となる身体を特徴付けています。このことを説明する上であるエピソードを紹介したいと思います。
私は以前、東大病院の医師で著作も数多く執筆されている稲葉俊郎さんと対談しました。稲葉さんは医療におけるこれからの可能性に絡めて、ある研究者の新しい大学についての構想を紹介されました。それによると、これからは国家の単位で区切られることなく「地球社会の大学」といった、地球規模の歴史や哲学を問うべきだと言います。稲葉さんはそこに人種や宗教を超える可能性を見出していました。私は話を聞きながら、インターネットがもたらす有用さを念頭に置いた知の編纂の仕方なのだと理解しました。その上で稲葉さんは、普遍的な知のあり方の共通の根拠となるのが「身体ではないか」と話されました。確かに人種や宗教の違いはあっても二足歩行をして目がふたつに口はひとつと「身体」には普遍性があります。知と身体の普遍性が互いの違いを乗り越えて共生していける道を照らし出すことを期待した構想なのでしょう。それはそれで素晴らしいと思います。
私が注目したいのは、文化には普遍性がないことです。たとえば日本とナイジェリアでは座り方もお茶の飲み方、挨拶の仕方も異なります。所作が違います。身体には普遍性があっても、現にこうして生きている私の身体は常に偏りがあります。一人一人が特有の文化を持っています。私はあなたと同じ人間ではあるが、私はあなたと違う。その違い、偏りに暮らしがあり人生があり、「私が私として生きる」という源があります。仮に身体の普遍性を拠り所に地球規模の普遍的な知を目指す生き方をするならば、私たちは身体を持つ必要を感じなくなるでしょう。
普遍性や汎用性が偏りのない平易さに私たちを追いやる道を整えているとしたら?唱えられている素晴らしい理想に対しても留保をつけるくらいの警戒心は必要なのではないでしょうか。私たちが共感しやすい、普遍的に見える教育コンセプトは「教えられた内容を学んで能力が高まり、その果てに個性が花開く」というものです。
しかし、それは錯覚であり、現にこうして存在していること。この偏りの個的な存在が個性ではないでしょうか。自他の隔たりがあるがゆえに迂闊に他人に共感できない。だからこそ誰の手を握り、誰の手をはねつけるのかという主体的な選択が生じます。そこに私が私を生きるという偏りを真っ当に生きる試みが始まるのではないでしょうか。