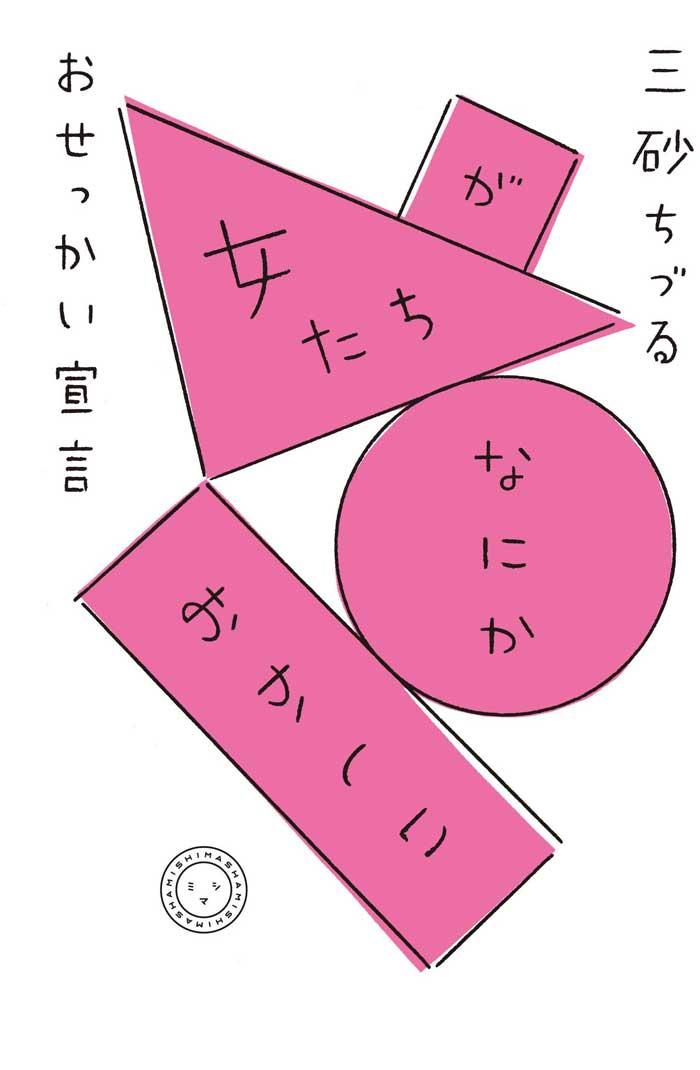第46回
「手紙」という資料
2018.05.17更新
1980年代の終わり頃、私はイギリスの大学院で勉強していた。友人の美奈子さんは南部アフリカの国、ザンビアで長期ボランティアとして働いていた。当時、メールもインターネットもない時代から、私たちはせっせと手紙を書いた。学生だからお金がない。薄くて質の良いエアメールの便箋は高い。なるべく安い、薄い罫の入った横書きの紙を買ってきて、びっしりと文字でうめ、4枚も5枚も書いて、封筒に入れ、切手を貼って、送っていた。イギリスでの学びのこと、ザンビアで出会った人のこと、開発や国際協力って一体何なのか。ああでもない、こうでもない、と、まだ20代であった私たちは真剣に悩み、思いを分かち合った。彼女のザンビアからの手紙は、五十通くらいあった気がする。それこそ束になって、手元にあった。ザンビアでのボランティア活動を終えた頃、連絡がきて、本を書きたいので、彼女が私に送った手紙がとってあれば、見せてほしい、という。私は手紙の束を彼女に送った。そうやって彼女が書いた本が『女たちの大地』[i]という本である。交換し合った手紙を資料に、本が書けるのだ。その時の私の新鮮な驚きと喜びを、今もはっきり覚えている。私との手紙を元に本が書けた友人が自慢だった。「手紙」は「資料」なのである。
私は20代から30代にかけて15年くらい海外で暮らしていたから、とにかくたくさん手紙を書いたし、手紙を受け取った。家族からの手紙、お世話になった先生からの手紙、愛を交わした手紙、ブラジルから、アフリカの国から、イギリスから、ネパールから、日本から、世界中から、いろいろな人の手を経て、1通のエアメールは私の元に届いてきたのだ。たくさんの手紙は今も、それぞれ差出人ごとに束になって手元にある。ずいぶん何度も引っ越してきたけれども、あの頃、私宛に書かれた手紙はいつも持ち歩いていたのだ。常に、読み返すわけではない。しかし、捨てられない。おそらく死ぬまで捨てられないものの一つだろう。そして、私が死んだら、おそらくは私の荷物を整理する人が、苦笑しながら、捨てるのであろう。
今は、終活とか、エンディングノートとか流行りであり、自分の荷物は整理して、様々なこともできる限りきちんとして、死ぬ準備をしておくべきだ、残った人に迷惑をかけないように、というのが主流である。結構なことである。身の周りの明らかにゴミでしかないものや要らないものは処分し、生活を身軽にし、金銭関係はクリアにしておき、家族親戚関係での問題があれば、解決しておくほうがいいに決まっているから。なんでもすぐにわかるように書いてあるのも、良き事だと思う。
よくわかっているのだけれど、私はあえて、エンディングノートとか、書いたり、死ぬ準備をしたり、そういうことはしないことにした。死ぬ時は死ぬのであって、その時は十分に誰かに迷惑をかけるのである。誰の手も煩わさないで死ぬなんてあり得ない。自分の死は自分には属しておらず(そういったのは吉本隆明さんだったが)、誰かの手に委ねられるものだ。いくらきちんと準備していても、誰かの手は必ずわずらわせる。それならできることは、自分が手をわずらわせそうな人との関係をできるだけよくしておくことだけが、大切だと思っている。どちらにせよ、一人では死ねないし、死んだ後は誰かにゆだねるしかないのだから。
部屋の整理、物の整理、金銭の整理、気になることの整理、は、死ぬ時のためにやったほうがいいのじゃなくて、今、よく生きるためにやっておいたほうがいいことだから、黙々と進めるべきであろう。これを見たら、預貯金やら保険やら関係性やらすべてわかる、みたいなものがあれば便利なのは、死ぬ時じゃなくて、生きている今なのでしょうから、作れば良いのである。私たちは死ぬために生きてるんじゃなくて、今、生きるために生きている。結果としては、同じなのですけどね。よく生きるための身の回りの整理と、終活は・・・。
と、思っているのだが、身の回りの整理をしながら、最後まで捨てられないだろうと思うものの一つが、この、「外国にいるときに受け取った手紙類」だと思っている。こういったものを死ぬ前に処分できるほどの成熟を、私はおそらく持てはしないから、これらは誰か私の周囲によって見つけられるものである。申し訳ないことだ。でも私はおそらくそれらを整理できないので、最初から謝っておくのである。
しかし同時に、「手紙の束」など残す世代は、私たちが最後である。今や、誰も手紙など書かない。すべてメール、あるいはSNSである。これって、これから一体どうなってしまうんだろう。命をかけるようにして必死で書いたメールはパソコンのどこかにしまわれ、あるいはクラウドのどこかに漂って、でもどこか目に触れるところにあるわけではない。プリントアウトでもしない限り、誰と誰がどのように頻繁に連絡を取っていて、それがどういう内容だったのか、なんてわからない。各自のパソコンに残っているものは、多くの場合その人の死亡によって、すべてなくなってしまう、と考えていいんだと思う。メールでは、「資料」になりえない。
名のある人の「手紙」による作品、資料は、数知れない。2018年4月現在、没後35年の劇作家、寺山修司のラブレターが前橋市の文学館で公開されていることが話題になっている。自分の書いたラブレターが当人以外の人に読まれることを望む人はあまりいないと思うのだが、結果として後世に名を残すような人、しかも、劇作家はいったいどういう愛の手紙を書いていたのか、は実に興味深いものであり、そういうものに私たちがふれられるのは良きことだ。今、1978年出版の『日本の村』[ii]という本を読んでいるが、そこにも資料としてマルクスとヴェラ・ザスーリチの間の手紙が出てくる。最近、ボリス・パステルナークと美しいいとこオリガとの往復書簡も読んだ。「手紙」は「資料」になるのである。マルクスやパステルナークでなくても、「手紙」が「資料」になるのは冒頭に書いた通りだが、しかし、今、様々な作家同士、有名な方たち同士のやりとりは手紙ではなく、メールやSNSなのだ、と考えると、これから文学とか歴史とかの研究ってどうなってしまうのだろうと思う。電子媒体のメールなど今後、「資料」として他の人の目にふれることはなさそうだ。
いや、百歩譲って、パソコンのパスワードを解除して、いろいろな人のメールを探し出すことも不可能ではない、とか言えるかもしれないけれど、そもそも、この電子の海に投げられた多くの文章は、やはり紙にして残さないと後世には残るまい、と思う。だいたい、いつも私たちが電気を使える状況に生きていると、どうやって言えるのか。私たちは生き延びなければならず、最後に生き延びた人類が、電気とともにあるだろう、と、なぜそのように楽観的にあれるか。最後に生き延びた人類にとって、「資料」としての「手紙」にどういう意味があるか、と言われても、それはもちろん答えられないのだけれど。
註)
[i]荒木美奈子『女たちの大地ーー「開発援助」フィールドノート』築地書館 1992年
[ii]守田志郎『日本の村』朝日選書 1978年