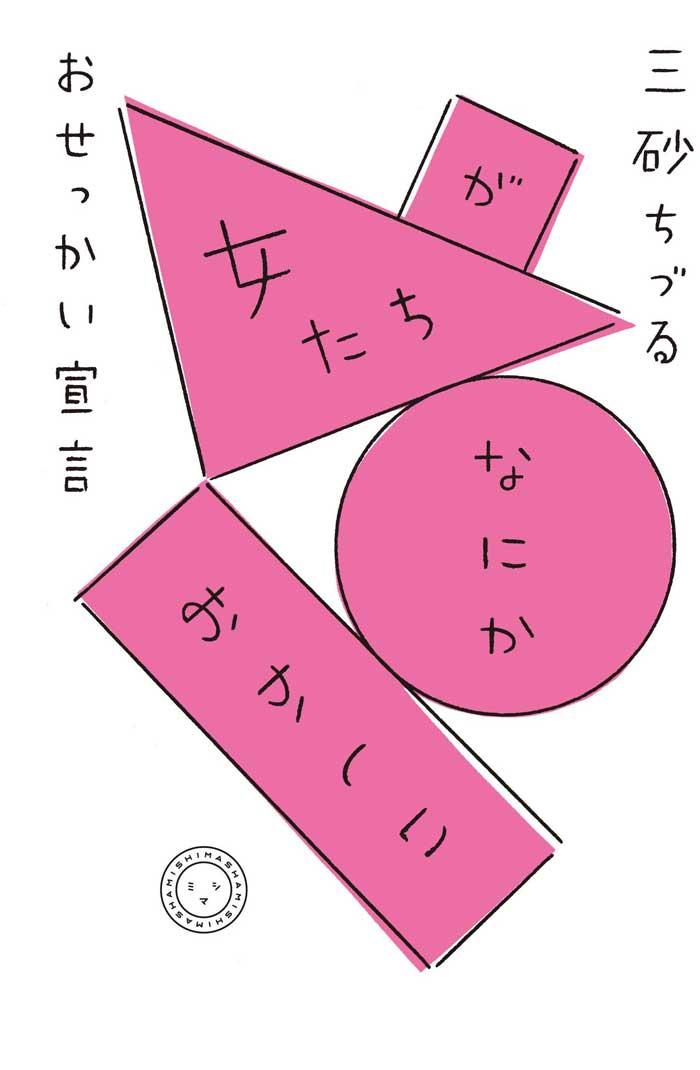第58回
男女の心中
2019.05.08更新
男と女が色ごと、というか、激しい恋愛の果てに、心中する、という話を聞かなくなった。自殺自体は、辛いことに、この国ではまだまだ深刻なレベルだし、介護を苦にしての心中、などは、ある。しかし、男女の心中、は、聞かなくなって久しい。つきあっていた相手に何らかの問題があって、殺されるというようなことはニュースになったりするが、男女間の心中は、耳にしなくなってしまったのではないだろうか。
男女が心中するのは、もちろん、思いを遂げることができない何らかの理由があったり、いま、この燃え上がっている状態のままで生を終わりたいと考えたり、とかそんな感じだったのだと思うのだが、いまとなっては、よもやそんなことをする人がいたとしても、ばかじゃないの? なんで二人で死ぬの? と思われるような感じになってきているような気がする。気がするだけかもしれないけれど。でも実際に、聞かないし。なんで死ななきゃいけないの? 恋愛くらいで・・・。
ああ、「恋愛くらいで」。恋愛はその程度のものになってしまった。思いを遂げられないような状況で恋愛をしている人はもちろん、いないはずはないのだが、そんなに切羽詰まっていないのかもしれない。楽観的にいつか結婚できると思っているのかもしれない。だいたい、結婚なんかしなくても、今が良ければいい、と思っているだけかもしれない。しかし、いったい、いつから、男女の心中がなくなったんだろう。死んでくれ、という男もいないし、私と死んで、という女もいないのだ。恋愛は命をかけるものではなくなった。
ほんの少し前まではそんなことはなかったんじゃないだろうか。故 渡辺淳一氏の書いた「失楽園」は300万部を超えるベストセラーとなり、映画になったりドラマになったりした。あれは1997年のことで、具体的には今から約20年ほど前である。今さら、ネタバレと非難されることもないだろうから、書いてしまうけれど、「失楽園」に登場する主人公たるカップルは、心中する。この小説は、心中で終わるのだ。大手企業のビジネスマンで、もちろん妻帯者である男と、医師の妻であるヒロインの「不倫」物語。どうにも出口がなく、また、どうしてもお互いを求め合う激しさの中で、気持ちが最高に盛り上がっているままで命を絶ちたい、と、愛し合った姿のままで心中するのである。若い人から見れば20年前って大昔かもしれないけれど、昭和生まれにとっては20年前はほんのついこの間である。だから感覚がずれるのはいたしかたないことだ。昭和生まれの私たちが若かった頃、昭和の元号を遡ること二つ、明治生まれの人がどんなにか「昔の人」にみえたことだろう。令和の時代になって、いまはわたしたちは前の元号のその前の元号の頃に生まれた人。とんでもない昔の人、であることをまず自覚しなければならない。
それはともかく。とにかく1997年は20年前とはいえ、ついこの間で、そのころには、心中することはちっとも陳腐なことじゃなく、みんなが共感していて、「失楽園」は、繰り返すが300万部売れたのだ。いかなる意味でも命を自ら断つことは厳しいことであり、残されたものに考えられないような深い悲しみを残す。それはわかっていながら、あのころは、俗物と言われようが、自分勝手と言われようが、「愛に殉じる」ことは、自分がやらなくても、共感をもって感情移入して読むことができたのである。今、そんなことができるのだろうか。今は、もっと、恋愛関係は「さっぱり」しているようにみえる。
それでいて、前の連載に書いたのだけれど、「60代、70代で後悔していること」を聞けば、多くの人は、「死ぬほどの恋をしなかったこと」だというのだそうだ。だから、20代のうちに死ぬほどの恋をしましょう、ということを書いてある本があるらしいのだが・・・。あなた、死ぬほどの恋をしましたか、と聞かれて、はい、しました、と言える60代、70代がどのくらいいるのだろうか。死ぬほどの恋をしても、死ぬほどの恋が成就したら、つまりは、死ぬほど愛し合っていた相手と具体的に結婚するなり、長期的に愛し合うなりして、長く親密に付き合うと、それはイコール日々の生の営みをなんらかの意味で共有することになり、そういうことを共有していると「死ぬほど」の恋であった幻想は、良き形で日々の日常で具現化されてゆき、死ななくてもよくなるので、その始まりが「死ぬほどの恋」であったことは、しばしば忘れられるのである。
逆に、死ぬほどの恋をしていた相手との関係がなんらかの意味で成就しなかったとしたら、そして、その恋と相手を冷静に思い出せるほどに時間が過ぎているとしたら、それはまた別の意味で、「死ぬほどの恋」であったことは忘れないと、自分の日常が立ちゆかなくなるから、時間がたてば、なんであれが死ぬほどの恋であったのかわからなくなってしまったりするのだ。およそ、「死ぬほどの恋」たるものは「そこで死なないで生き延びる」と、けっこう日常の中でマンネリ化するか、忘れられるのである。だから切羽詰まって「死ぬほどの恋」を「死ぬほどに突き詰めていって生きていった結果」が、いかようなものであっても、「死ぬほどの恋」は忘れられる。つまりは、「死ぬほどの恋」は、死なないと、死ぬほどの恋にはならないのだ、きっと。だから、憧れて心中したのだろうか。いや、ちがうような・・・。
恋愛で死んでしまうほどに思い詰めるには、二人の時間も必要だが、おそらく一人の時間も必要なのだろう。一人でずっと相手を思い詰め、関係性について思い悩む時間。いまや、SNSが発達して、いま、このときの自分の気持ち、を、自分だけで一人で思い詰める前に、相手にさらっと、LINEを送ったりしてしまえる。思い悩む前に相手に投げてしまえる。投げてみて、返事が来なかったら、それこそ、それまでなのである。SNSが発達して世界中どこにいてもワイファイさえあれば(それがあるのだ、いまどき。世界のどんな片隅に行っても)瞬時に相手とつながることができる。だから、やっと手紙を書いて、その手紙が届くまで待たなければならなかった頃と比べると、感情のタメ、と、時の重りがなくなった、とは、こちらも以前の連載に書いた覚えがある。心中するためには、すぐに連絡の取れない相手を思い、一人で思い詰める時間が必要なのかもしれない。いや、誤解してもらっては困るが、心中することがよかった、とか、心中するほうが純粋な愛だとか、そんなことを言っているのでは決してない。いかなる意味でも、自殺の原因が一つ減ったのはよいことなのである。手紙の時代から、SNSに移って、おつきあいが軽くなってきたのも、人命尊重の意味からはよきことなのである。
今年、2019年の手塚治虫文化賞を取った、有間しのぶさんの「その女、ジルバ」は、ブラジル移民の女性が開いたバーを中心に繰り広げられるすばらしいマンガである。戦後70年を総括するこんな作品が、他でもないマンガのジャンルで出てくることを、本当にすごいことだと思う。ブラジルで10年暮らしたわたしはとりわけ冷静に読めなかった。バーの女主人だったジルバが残した遺品と手紙を、生きている人間が目にして、彼女の秘密を知る場面がある。そこに、「死者が遺した形あるものは暴かれる、生きているものは手を汚すのだ」というせりふがある。運命の恋が、残された手紙から暴かれていくのである。メールとSNSの時代になって、手紙があとに残らないことの悲哀も、また、以前の連載で書いた気がするけど、「その女、ジルバ」を読みながら、「暴かれる過去」がパソコンのパスワードとともになくなるのもよいことなのかもしれない、と思い始める。自分の隠したい恋愛関係はメールやLINEとともに消えるのなら、上等じゃないか。いかなる意味でも、軽い。あ、だから恋愛が心中するほどに、突き詰められないんだな・・・。妙に納得してしまった。