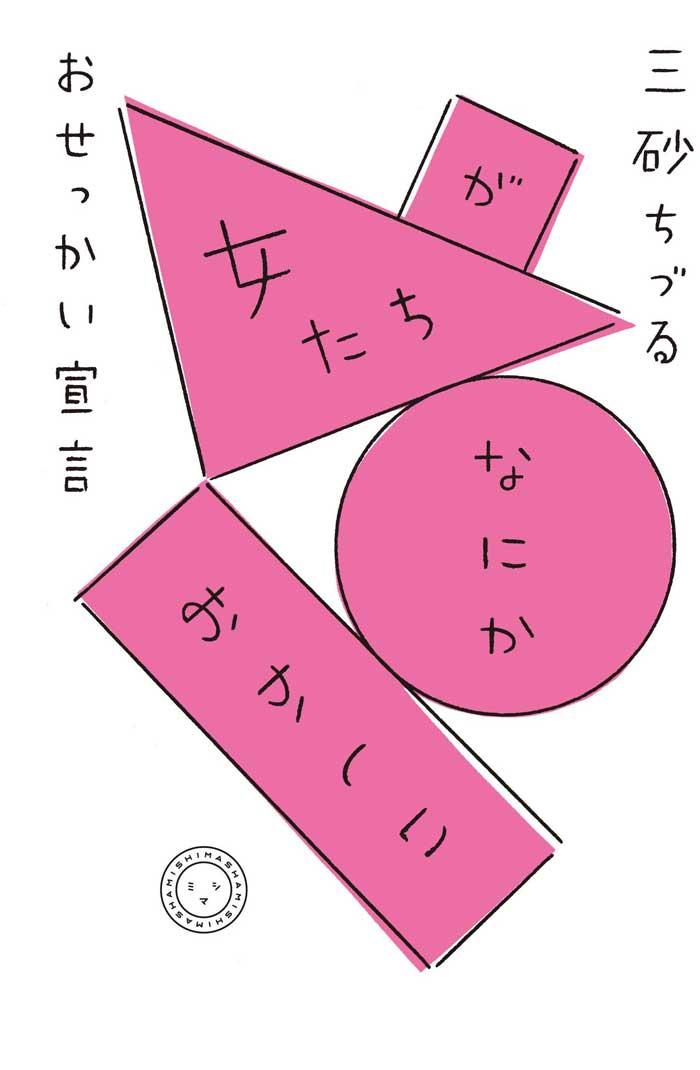第60回
"きれいにしていなくっちゃ"遺伝子
2019.07.10更新
パリに行ってきた。30年ぶりである。30年前のわたしは、ラテン世界を知らなかった。覚えかじった外国語は英語のみで、行ったことのある外国も「英国および英国の元植民地」であり、英語がちょっとできたら、なんとか"外国"では生き伸びていけるような気がしていた。そのあと、わたしはスペイン人を無二の親友とし、ブラジル人を子どもの父親とし、ラテンアメリカで10年生きてきて、おそまきながら、世界に「英語がちっとも通じなくて、英語なんか知らなくてもちっとも困らない」ところがたくさんあることを知ることになる。思えば当たり前である。日本だってそういうところなのだ。英語ができなくてもちっとも困らない。ましてや明治の先人たちの努力に始まる翻訳文化の豊かさのおかげで、英語のみでなく世界中の言葉の書物が、あっという間に日本語に訳されて、自分たちの言葉で読める。英語ができなくても困らないのだ。
でもここで言いたいのはそういうことではなくて、日本にとって「外国」とはやっぱり「英語圏」である、ということだ。英語ができなくて日本では別に生活上困らないけれど、でも、日本で「外国語」と言えば、やっぱり英語なのであり、「外国」と思うときは、「旧イギリス植民地」であることが多い。日本にとっての外国は、イギリスであり、アメリカであり、アフリカ、と言ってもそのイメージはキリンやゾウのいるサバンナ、つまりは東アフリカっぽいイメージであることが多いのだ。旧英領、のアフリカである。英語的な発想と英語的な考え方と英語によるシステム。長い時間がたって、それらのシステムへの親和性も高いし、また、アングロサクソン的な考え方や暮らしぶりはけっこう日本人と似ているところもあったりするから、結果として、日本にいると、外国語イコール英語であり、外国といえばやっぱりアメリカにイギリス。これが日本でイメージしていた外国だった、ということに、わたしはまことに、おそまきながら、気づくのである。
フランス語、スペイン語、ポルトガル語、(そしてイタリア語にルーマニア語)を話す「ラテン世界」というものがあって、そこには、アングロサクソン的、というか、英語的、というか、そういうものとは全く違う世界が広がっている。フランス、スペイン、ポルトガル、そしてラテンアメリカ全域。ブラジルはポルトガル語圏で、そのほかのラテンアメリカはスペイン語圏である。インターネットの普及は、英語の世界言語化でもあったようで、いまでこそこれらの国でも英語を習うことに余念がないようだが、ラテンアメリカでは、長く、第二外国語は英語ではなく、フランス語だった。人と人の間が近く、スキンシップが濃厚で、男と女の間に交わされるまなざしや会話は、いつも色っぽい。いまや職場で女性の服装や髪型を褒めたりするとセクシャルハラスメントと言われかねないが、これらラテン社会では、髪型を変えて職場に行ったのに、誰も何も言わないなんて、それこそが礼儀に反する。みんな、きょうもすてきだね、その髪型いいね、服がよく似合うよ、などと、臆面もなく褒めあうことに日々の生きがいを感じているので、誰も何も言ってくれない日本の職場に帰ると、なんだかおしゃれをする甲斐もないよう思えてしまう。これらラテン系の言葉には、親密な関係の異性を表す言葉が多彩にあって「制度的な配偶者」、「制度に関わらない配偶者」、「配偶者ではないがステディな関係」、「志を同じくする強い関係」、「からだだけの関係」などなど、それぞれ別の単語だったりして、その多彩さに極東島国出身の私はめまいがするようであった。
そう、30年前にパリを訪れたわたしは、これらラテン社会のことを少しも知らなかったのだ。ラテンの言葉も学んだことがなかったから、パリの看板の単語ひとつ、わかりはしなかった。彼らがしゃべっていることばも、ちんぷんかんぷん。素敵な街の、素敵な人たち、と思ったけれど、ただのおのぼりさんだった。その後、30年の時間は、まず、わたしをポルトガル語話者にした。ブラジル人男性が二人の子どもたちの父親となり、家族として15年くらい暮らして10年ブラジルに住んだから、いやおうなしにポルトガル語を話すようになった。ブラジルという国の英語の通じなさは日本どころではないので、ポルトガル語を話さないと生きていけないのである。さらに、日本人にとっては、スペイン語、ポルトガル語は発音が日本語に近いせいもあり、英語よりずっと上達しやすい。さらに、ラテンアメリカの皆様は、スペイン語、ポルトガル語初心者に対して、それはそれはやさしいし、おはよう、と言えるくらいで、お前は天才か、と言わんばかりにほめてくれるものだから、みんなすぐに語学が上達する。わたしもポルトガル語を繰るようになって、ブラジルに限らず、ラテン世界に開かれていった。ポルトガル語とスペイン語は、方言程度の違いでお互いそこそこ理解できるし、フランス語もだいたい書いてあることはわかるようになる。Google翻訳などのインターネットによる翻訳は日々、向上しているとはいえ、まだ日本語からの翻訳は心もとない。しかし、フランス語―スペイン語―ポルトガル語間(おそらくはイタリア語もルーマニア語も)については、Google翻訳(おそらくexciteとか他のサイトも)は、ほぼ完璧に翻訳してくれる。最近、スペイン語圏、フランス語圏で仕事をするときは、ポルトガル語で資料さえ作れば、Google 翻訳さんが完璧に翻訳してくれることに助けられている。
30年後に訪れたパリ、看板や標識や書いてあることがそこそこわかるようになっているし、会話もなんとなくわかり始めてきたし、フランス的文脈への理解も少しは進んで、本当に楽しかった。3年前に亡くなったフランス文学者、山田登世子さんが何度も書いておられるように、パリは、見て、見られる劇場都市である。カフェは道に張り出し、そこにいる人は飲み物を片手に会話を楽しみながら、道ゆく人を見ているし、また、道ゆく人に見られてもいる。年齢にかかわらず、男も女も実に魅力的であり、魅力的であろうとしている。いわゆる芸能人が年齢をかさねても綺麗な人が多いのは、人に見られる職業だからだ、というけれど、この街では、街を歩いているだけで、カフェで冷たい飲み物を飲んでいるだけで、常に人の視線を意識しているから、みんなが芸能人なみに、人に見られることを前提の自分、を作り上げているのである。
こういうところにいると、年齢にかかわらず「きれいにしていなくっちゃ遺伝子」がオンになってゆくのを感じる。自分を見られるに値する存在にしていたい、という欲望が出てくる。年齢がいっているとか、あまり美人でない、とか、太っているとか、やせているとか、そういうことと関係のない、見て、見られる、ことによって自分でつくりあげていく、自信、というものがあるんだな、と思わせられる。それは、魅力的であろうとする不断の努力であり、パリ在住の方に聞くと「それはそれで、疲れる」とおっしゃるのだが、そういう努力は、なにより、女性自身の自己肯定感を高めていくこと、つまりは、今の自分を認めて、その自分をより良い方向に、自分がより快適である方向に持っていこう、とすることにつながるのではないのか。そして、そういう自信こそを、ほんとうの強さ、というのではないのか。
2017年から2018年にかけて、ハリウッドを中心に巻き起こったセクハラ告発キャンペーン#MeTooに、フランスの大女優、カトリーヌ・ドヌーヴが意見文を出したのだが、彼女が言いたかったことは、要するに、女性は犠牲者で、男女差別に苦しむかわいそうな存在ではない、女性とは、嫌な人間に嫌なことをされたら、はっきりとノーをつきつけられる、単なるヘタな口説きと性的暴力くらいはみわけられる洞察力がある、嫌なことがあっても乗り越えられる、そういう強さと自己肯定感を持てる存在のはずだ、それこそがエンパワメントじゃないのか、ということだったと、私は思っているのである。