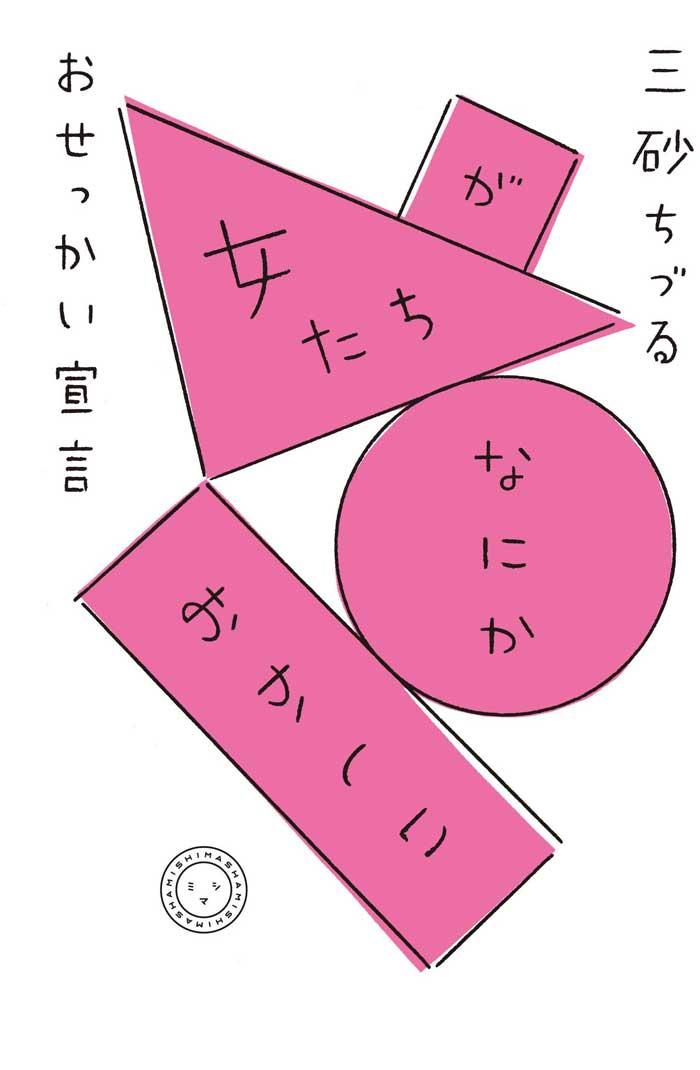第71回
失われる教育
2020.07.12更新
父は海軍兵学校入校予定者のままで終戦をむかえた。昭和2年生まれで、終戦時に18になる年だった。その年で戦争に行かないですんだのは、自分が海軍兵学校入校予定者だったから、と父は常々話していたのだ。それがなかったら、必ずや自分くらいの年齢の男は戦争に行かされ、そして死んでいたかもしれないんだ、と言っていた。
それが、どこまで本当のことだったのか、父の七回忌もすでに終えてしまった今となってはわからない。いや、それは父が死んでいるからわからない、というのではない。もともと、父に聞けばわかった、というレベルではないことだったのではないのか、と思っている。わたしが何度聞いても、父はきっと同じ話をくりかえしたことだろう。自分は海軍兵学校入校予定者だった、それで終戦を迎えた。78期として入校する予定だった、その予定だったからこそ、戦争に行かなくてすんだんだ、だからずっと家にいられた、だから、8月6日の西宮大空襲も経験することになった。聞けば同じことを言ったと思う。入校予定者、などというのは、おそらくは正式採用通知ではないのだから、確かめようもない。常に学ぶ意欲はあった人ではあったが、学校に行く余裕は、戦後にはなく、学歴コンプレックスを抱えることになった父は、その裏返しとして見栄をはりがちな人になっていたから、この話の真偽のほどはわからないのだ。
海軍兵学校は言わずと知れた当時のエリートコースで、男の子たちの憧れであり、女の子たちの憧れでもあった。兵学校の制服を着ていたら、とにかくモテたそうである、という話は、ずいぶんと聞いていた。スマートな海軍式教育に鍛え上げられ、もともと身体的にもすぐれ、頭も良い若い男の子たちは一層素敵な人になって卒業していったであろう。その優秀な若い人たちのどれほどの命が結果として失われたか、については、いまは語るまい。とにかく、海軍兵学校は多くの人の憧れだった。金もなく、家柄もないが、努力ができ、それなりの才があり、気骨もある、多くの若い男の子の人生は、軍に入ることによって変わっていく可能性がある、というのは世界中の歴史が示しているとおりだ。父の憧れは海軍兵学校だったのだ。
父は頑健な体を持ち、運動神経も良く、頭も決して悪い人ではなかったが、何しろ背が低かった。背丈は157か8センチくらいで160cmなく、靴も23センチをはいていた。男性としてはとても小柄、我が家では父も母も高校生くらいになった私も、全員身長も靴のサイズも全部同じ、運動靴は共用可能、という、いま思えば、変な家だった。すらっとして背も高くないと海軍兵学校には入れないんじゃないか、と思うから、こんな小柄な男性を兵学校がとったのだろうか、という原初的疑問には、父は、「回天要員だったんだろうな」とか、言っていた。「回天」というのは、日本海軍が戦況がいよいよ厳しくなる時に起死回生の戦略として使った人間魚雷である。一人だけ、背をかがめ、しゃがんだ姿勢で乗ることができ、ハッチを閉めたら開くことはない、と言われた人間魚雷で特攻をおこなう。大した成果はあげられず、事故や不発で亡くなったケースも多かったと聞く。ある意味、飛行機の特攻隊よりも悲惨といわれた、人間魚雷「回天」である。そこに入るには、あまり大柄な人は向かないことは誰が考えてもわかる。背の小さな父は「回天要員」として入校予定者になれたのではないか、という説明には、説得力もそれなりにあったのだ。
実際に海軍に行ったら行ったで、厳しい現実があり、憧れているだけでは終われない。しかし、行かなかったからこそ、海軍は、父の生涯の憧れであり続けた。海軍関係者の作った会社に入り、海に関わる仕事をし、実際、海軍関係者と多く働いたから、それなりに海軍について詳しくもなっていたものだ。結果として、山口県の「回天」教育施設近辺に作られていた海軍関係者の作った会社に入ったから、関西人の父は、山口県出身の母と出会うことになり、わたしもまた、その「回天」施設近辺で生まれたのである。
それほど憧れていたことを知っていたから、父の80歳の誕生日のお祝いに、父を広島県江田島に誘った。海軍兵学校があったところで、当時は海軍兵学校自体が「江田島」とよばれていた。現在は海上自衛隊の施設となっており、見学も可能である。死ぬまでに行きたかったんだ、と父はたいそう喜んで、二人で江田島行きの船の出るホテルに泊まり、翌日、見学をして構内をまわった。父は涙ぐんで感激し、たくさんの写真を撮り、イギリスから輸入したという赤煉瓦で作った校舎の前で撮った写真は、父の遺影となった。
そこには、1876年(明治9年)から1945年(昭和20年)まで存続した海軍兵学校の卒業生、つまりは大日本帝国海軍の将校となる士官候補生たちの名前と写真などが全て残っている。そこには、実は、父がずっと話していた「幻の78期」というのも、あったのである。実はもともと海軍兵学校の定員は300名くらいだったらしいが、戦況の悪化とともに、どんどん入学定員は増えてゆき、終戦の年、昭和20年4月に入港した兵学校最後の生徒、 78期は約4,000名と、海軍兵学校史上最大の人数となり、しかも江田島ではなく、針尾分校と呼ばれる長崎県の分校(現在は、そこがハウス・テンボスであるらしい)に入校したのだという。つまり、78期は存在しているわけである。しかも今調べてみると、この78期は昭和3年から昭和6年3月までに出生した人たちが応募できたようで、昭和2年生まれの父の年齢では入れないことになる。さて、そのへんはどうなっているのか、あえてきかなかった。思い出というのは語られ続けると、その人の真実になってゆく。本当のところがどうであろうが、父は、入校予定者のまま、人生を終えたのである。
そんな父によりそって訪れた江田島、すでにそのころ大学教師として働いていたわたしは、学校の美しさと、入念に手入れされ、磨きあげられた階段の手すりに胸を衝かれた。明治維新から10年も経たない明治9年に開学し、営々と80年近い丁寧な教育を積み上げてきた場所である。どれほどの教師と学生の、あるいは学生と学生の、豊かな交わりが築かれてきたことであろうか。営々と続けられてきた教育は、必然のように、終戦とともに、あっという間になくなってしまったのである。海軍がどう、戦争がどう、という前に、そこで教育を積み上げてきた教師の無念と、誇りと、複雑な思いは、教師のわたしに、ひとごとではなかった。どのような教育も、いかに丁寧に積み上げようと、終わりがある。一瞬にして形をなくすことがあるのだ。
コロナパンデミックの中、大学は閉校したわけではない。存在している。しかし、学生には会うこともできず、教室にも研究室にも立ち入れない。懸命に、オンラインで学生との関わりを保とうとしている。これらすべてをこえて、嘘のように、もどってくるのだろうか。あの学生との日々は。大学に行けなかったことがあったなんて、変だったね、と言える日がくるのだろうか。その可能性よりも、ただ積み重ねられていた学生との日常が突然なくなったことによる諦念を、江田島廃校時の教員の思いに重ねている自分を見つけて、やや、愕然としているのである。
編集部からのお知らせ
三砂ちづる先生の新刊『自分と他人の許し方、あるいは愛し方』熱いご感想を続々いただいています!
豊かな経験を持つ三砂先生は、まさに、「人生の先生」。決して他人を否定することなく、自分の考えを押しつけることもなく、柔らかな語り口で読者を包んでくれます。人生の岐路に立ったときに、きっと自分を助けてくれる、そんな1冊です。
こちらの記事でまえがきを公開中です。このまえがきで心をつかまれた、というご感想も多くいただいております。ぜひお読みください。