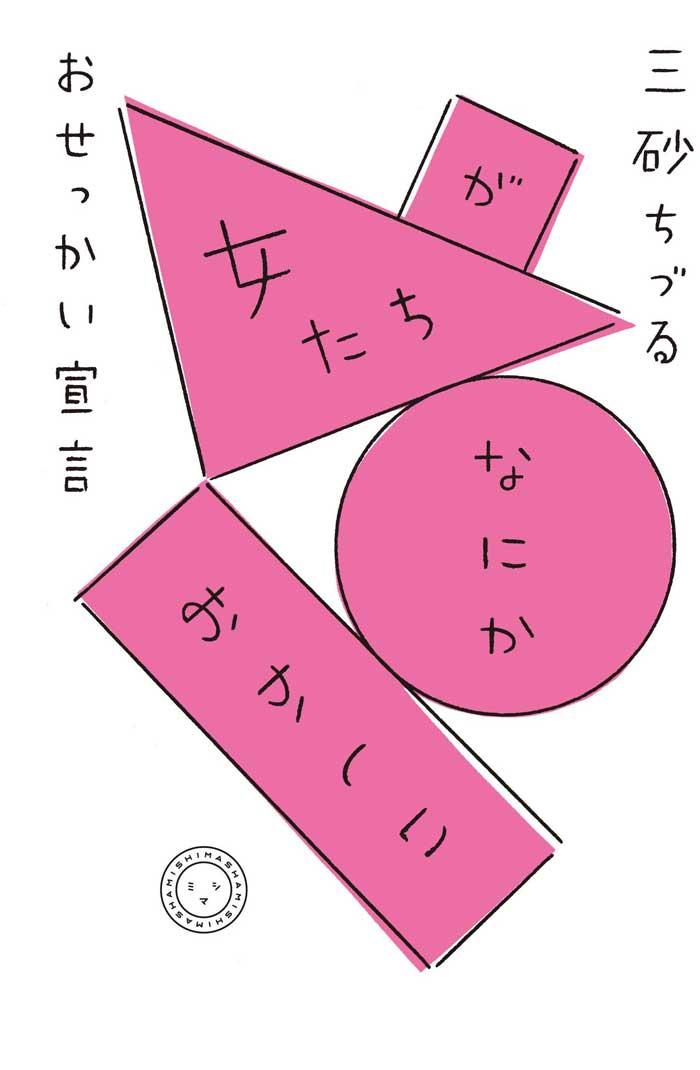第73回
知らなかった力
2020.09.21更新
参加型授業、という時に、思い出す話がある。教育学者の故 林竹二さんが、演出家であった竹内敏晴さんを相手に話をされていたのだったと思う[1]。林さんはある時、教員研修の一環として小学校で模擬授業をする。その時も、できるだけ生徒が参加するような「参加型授業」を、という教員研修だったらしいが、林さんはずっと小学生相手に話し続けた。別に生徒に議論をさせたわけでも、小グループに分けて話をさせたわけでもない。ただ、林さんが一方的に生徒に話していた(ように見えた)らしく、その授業が終わった後、他の教員から、一体。今のどこが参加型授業であったのか、という質問があったらしい。
その質問に林さんが答えておられた内容を忘れることができない。彼は、この国では、小学生といえど、ここまで生きてくる中で"鎧"を身につけている。"鎧"をつけないと、生きていくことが難しいのだ。生きていく上で、何らかの自分を守るための"鎧"を身につけている。その"鎧"をつけたままでお互いに議論をさせても、その人の言葉は出てくることがない。"鎧"に妨げられているからである。だから、自分は、子どもたちが"鎧"をおろすようなきっかけになる話をしたいと思った・・・。そんなふうに語っておられたのだ。
大学でも、参加型授業、ということがよく言われるのだけれど、ただ、学生に議論させたり、テーマを与えて、話し合いさせたりするだけで参加型授業と言えるのだろうか。林さんは"鎧"という言い方をしているけれど、なんというか、心が耕されていない状態、というか、ここで何を言ってもいい、という雰囲気がないと、また、ここでは何を言っても安全だ、という思いがないと、その人の本当の言葉は出てこないものだ。そして日本で生きていると簡単に心を閉ざしたり"鎧"をつけてしまったりしがちで、そのままで話し合いをしたとしても、というか、要するに参加型授業をしたりしても、文字通り、形だけのものになってしまって、自らの言葉、どうしても語りたい言葉同士の行き交う、豊かな学びの時間にはならないのではないだろうか。
「被抑圧者の教育学」[2]という、開発教育や、参加型教育のバイブルとも言えるような本を書いたブラジルの教育学者のパウロ・フレイレは、ブラジル北東部の出身である。彼の出身地にほど近いブラジル北東部に約10年住んで、フレイレという人はブラジル北東部の人々のお互いの関わり方やコミュニケーションの取り方をこそ、言葉にしたのだ、と思うことがよくあった。ブラジルの人たちは、ワークショップなどの場で、本当に率直で、すぐに"鎧"を下ろして、自らの言葉で話すことができるのだった。私は産科病院の出産ケアの改善に関わる日本の国際協力プロジェクトで働いていて、勤務先の病院で様々な職員が参加するワークショップを企画することもあった。そういったワークショップの冒頭で、アイスブレーキングを兼ねた自己紹介をしてもらうと、例えば、派遣されている側の日本人専門家は「私は日本から来ました、私は看護婦です、私はここから30分くらいのところに住んでいます」など、日本人なら誰でも自己紹介で言いそうなことを言うのだが、ブラジルの人たちはそうではない。単なる自己紹介でも、すっと"鎧"を下ろせるのだった。門番をしている病院職員の中年男性は自己紹介として自分の年齢を言った後、「私は恋をしています」と話し始めるのだ。自らの内面を語ることがこんなに気負わずにできるからこそ、参加型ワークショップが成り立ち、みのりある議論ができるのだ、と私はしみじみと思った。フレイレは、そのようなあり方をこそ、参加型教育、と呼んだのに違いない。
ブラジルでそういった"鎧"をおろした人たちのダイナミクスを見てきたから、日本に帰って大学で教えるようになっても、本来の参加型教育、と言うものは、その場にいる人たちが自分の"鎧"を下ろすことができる場でこそ行うことができるもの、と意識してきた。ある程度少人数の、例えばゼミナールのような場では、そう言う雰囲気を作ることができる。ここは"鎧"を下ろして、自らの言葉で語って良い場所である、と言うことがわかれば、本来の意味での活発な議論もできるし、学びを深めていくこともできる。
しかし、日本における、いわゆる"講義"では、具体的に言うと数十人以上が参加している授業では、そう簡単に参加型手法は使えないのではないか、と思っていたところに、冒頭の林竹二さんの言葉にふれたのだ。大学の講義では、私は、ほぼ一方的に私が話をする。しかし、それは学生たちの参加を拒んでいるのではなく、学生たちにまず"鎧"を下ろしてもらいたいから、そのきっかけになるような話をしたい、と努める。彼女たち(私が教えているのは女子大だから)がそれまでの人生で身につけてきた"鎧"は、先入観という形で張り付いているかもしれず、また、固定観念、といったふうに彼女たちを縛っているかもしれない。そういうものは、下ろしても良いのだ、下ろすことによってこそ、自らの心が耕され、生き生きとした学びに向かうことができる、と、私の話を聞いて、感じて欲しい。そういうきっかけになるような授業をしたい、と願っているのである。学生の参加は歓迎する、といってある。質問があればいつでもして欲しいし、私の話を止めてもいい、といっている。ほぼ、講義時間中は、私が話し続けている。林竹二さんの言葉を胸に。
そうやって、毎回、学生たちの"鎧"を下ろすきっかけになる授業をしたい、と思いながら講義を続けてきた。学生たちは、私の目の前にいたから、彼女たちが私の話を聞いていささかでも"鎧"を下ろせたかどうか、ほんの少しでも彼女たちの心を耕せたかどうか、それは、それこそ、彼女たちの表情と醸し出す空気で感じることができた。お互いに議論しなくても、そこには確実なインタラクションがあり、反応があり、共有する場があり、ありていに言えば、手応えがあったのである。
大学の講義をオンラインに移行して、当初はその手応えを感じることが難しかった。当たり前であろう。学生が見えていないのだから。パソコンの前で、パワーポイントの資料を画面共有しながら話しているので、学生たちの姿は見えないのである。学生たちと私は、場と同じ空気を共有できていない。物理的な距離が離れているのだから。新型コロナ・パンデミックで、場を共有して大人数の講義をすることはできなくなったのだから。
しかし、人間というのは不思議なものだ。何ヶ月かの講義をやった後では、私は、画面の向こうの学生たちの雰囲気が、なんとなく感じられるようになってきた。対面で見えていないが、自分の話が彼女たちの心に届いたかどうか、はなんとなくわかるようになってきた。学生のコメントシートを読むと、自分が感じていることが私だけの思い込みでないこともわかってうれしい。場は共有できなくても、同じ時間を共有していると、このようなインタラクションが出来上がっていくのだな、と、不思議だけれど、思うのだ。そんないい加減なことを言うな、と言われそうではあるが、何かが制限されたら、別の能力が開発されるのは、人間が今まで生き延びるためにずっとやってきたことであろう。いつまで続くのかわからないけれど、オンライン授業のクオリティーを上げていくこともできるのだ、と言う実感が伴い始めたことに密かな喜びも感じ始めている。
[1] 林竹二、竹内敏晴 「からだ=魂のドラマ―「生きる力」がめざめるために」藤原書店、2003年。
[2] パウロ・フレイレ著 三砂ちづる 訳「被抑圧者の教育学 50周年記念版」亜紀書房、2018年。