第76回
若い女性を愛する
2020.12.24更新
海外で暮らした人は、自分の国に戻って自らの文化に着地するまで、海外で暮らした期間の倍はかかる、というらしい。海外で暮らすことは、カルチャーショックの連続だが、海外で暮らして、自国に戻ってくることもまた、適応に時間がかかる、というのである。2000年までおおよそ10年をブラジルでブラジル人の夫(当時)と子どもふたりと家族として暮らしていたわたしはおそらく日本の暮らしにすっかり戻ってくるまで20年かかっていたのかもしれない、と、うらうらと思う2020年の暮である。
日本から12時間時差、まさに、地球の裏にあるブラジルの暮らしから学んだことは本当に数えきれないのだが、今考えても最も大きな影響を受けたのは、家族に関する考え方だったと思う。家族の関係性や家族の在り方や家族の印象。家族は助け合い、家族は受け止めあうもの、そういう、言葉にしてみれば当たり前のことを、文字通り一から教えられていたように思う。
他の本でも書いたことがあるのだが、あらためて、書いてみたい逸話がある。ブラジルに暮らしていたとき、大学に入学したばかりの姪のタチアーナが妊娠した、という知らせが入った。タチアーナの父親は、わたしの当時の夫の弟で、仕事の上では、いまひとつぱっとしなくて、お金に結構困っていた。タチアーナは大学に行きたいと言い、サンパウロでいい大学に行くにはそれなりの予備校に行かねばならない。医者である夫は、自分自身が育った家が裕福ではなくて、薬剤師になった叔父に予備校のお金をだしてもらって、予備校までの送り迎えもしてもらって医学部に進んだ、という。自分自身が生活に余裕ができたら、今度は自分が姪の予備校の費用を払うことは当たり前だと思っていたから、我が家はタチアーナの予備校の費用を出していた。そうやって名門サンパウロ大学に入学したばかりのタチアーナは、入学するなり妊娠してしまうのである。
大学の勉強も続けたいし、生活費を稼ぐだけの力もないタチアーナは、妊娠して困ってしまって、まず、父親に相談した。父親はすぐに親戚中に電話をして、タチアーナの妊娠はその日のうちに親戚中の知るところになり、親戚は次々とタチアーナに電話をして彼女をなぐさめ、彼女に応援を申し出る。夫と夫の兄、つまりは二人のタチアーナの叔父は、同時に、彼女に「心配することはない、うちで育てるから安心して子どもを産みなさい」と伝えたのである。ブラジルはカトリックの国で、妊娠中絶はご法度であり、だからと言って妊娠中絶のニーズが減るわけではないし、妊娠中絶を行うクリニックもお金を払えばいくらでも存在するのであるが、一般的な感情として中絶は愛でられない。中絶はファーストチョイスにならないことが多い。この日、タチアーナ妊娠、の知らせをきいて、タチアーナの叔父たち二人は、同じことをタチアーナに知らせた。
いいかい、あわてて結婚してはいけないよ。結婚相手はよく考えて選ぶものだ。妊娠したくらいで結婚しよう、と思ってはいけない。結婚はよく考えなければいけない。だけど、子どもは産みなさい。君が産む子どもはわたしたち家族みんなの子どもなんだ。君が育てないなら、私が育てるから、安心して産みなさい。サンパウロにいられないなら、うちにきて、子どもを産んだらいい。
そういうことが日本の文脈で言われたのだったら、妻であるわたしは、えー、忙しいし、大変なのに、姪が来るの? 赤ちゃんをうちの子として育てるの? そういうこと、相談してよ・・・とか、言うんじゃないかと思うのだが、その日、タチアーナに上記のことを言う夫に、私は心から賛同してしまって、そうだ、そうだ、タチアーナはうちに来たらいい、そして赤ちゃんはうちの男の子たちの弟だか妹だかとして育てたらいい、と、思って、むしろわくわくしてしまったのである。彼女は結局、結婚することになり、大学を少し休んで子どもを産むことになったので、我が家にタチアーナがくることもなく、赤ちゃんを我が家で育てることにもならなかったのだが、そのときのわくわくした気持ちを今も思い出す。
タチアーナはまず、自らの妊娠を父親に相談したから、こうやって親戚みんなで彼女のことを考えることになったのだ。10代の未婚の娘が妊娠した時、まず、父親に相談する、ということは日本で育ってきた私には考えにくかった。日本ではまず、両親には、知られまい、とするだろうに。すごいわね、と言ったわたしに、ブラジル人の夫は、それこそたいそう驚いて、「親戚の若い女性が困っていると言っているのに、助けてあげるのは当然だろう? 日本ではそういう親戚の若い女性が困っていると言うことをほおっておくのか」ときくのだった。ほおっておくどころか、相談すること自体があり得ない、というと、さらにたいそう、驚かれた。
未婚の若い女性が妊娠して、中絶する機会も逸し、赤ちゃんを産むことになり、そのまま赤ちゃんを殺してしまった、という痛ましい事件があいついで報道されている。性教育が足りない、とか、支援体制が足りない、と言われている。その通りだと思う。適切な性教育や自己肯定感を高める教育はいつだって必要だし、この少子化日本で、妊娠した人を支援する体制はどれほど強化されても強化されすぎることはない。
タチアーナの話を覚えている私は、このつらい状況に置かれてしまった若い女性のことを考える。彼女がそんなことをしてしまったのは、自分が妊娠したことを、自分の一番近しい家族に誰も相談できなかった、ということだ。母親にも、父親にも、祖父にも、祖母にも、きょうだいにも、おじにもおばにも、ましてや教師にも、誰一人として相談できなかった。なんと寂しいことだろう。どんなに悲しくて辛かっただろう。相談してもらえない、というだけで、もう、その関係性は定まっている。妊娠して困っている若い女性は、その時点で、誰も私を助けてくれない、と思ったのである。自分は、「気に入られるようなことをするときだけ」家族に受け入れてもらえる、としか認識されていない。家族のだれとも、自分が困っていることを相談できると思えない。
そして、その認識は、赤ちゃんを殺めてしまったつらい女性だけではなく、この国のほとんどの生殖年齢にある女性の認識と一致しているのではないか。家族は、困ったことを、人生で一番大変なことを、相談できる相手ではない、と思われている。わたしたちはなぜ、そういう若い女性が困ったときに、相談してもらえる親ではないのか。性と生殖の初めての経験、という、世界中の誰もがおそるおそるふみこむ経験で、困ったことがあるとき、なぜ、相談にのってやれる親や親戚や目上の大人ではないのか。自分は親ではない、という人も多いと思うけれど、わたしたちはみな、誰かの子どもだった。誰かの子どもだったわたしたちは、みんな、ただ、自分のあるがままを親に受け止めてもらいたかったのではないか。受け止めてもらえなかったから、さまざまな屈託を人生に抱え、性格に投影させ、行動を複雑化させていったのではないのか。そうならば、自分がしてほしかったことを、なぜ、若い世代に提供できないのか。
人はあるがままで受け止められているときに、つぎのステップにふみこめる。生殖年齢にある女性が子どもを産まない、子どもを産めない、産んでも育てられない、ということは彼女が誰にも受け止められていない、ということだ。少子化対策に不妊治療くらいしか思い浮かばない政策の貧困を目の当たりにしているのだが、若い女性をあるがままで受け止めるためにできることはまだまだあるのではないのか。若い女性の痛みを、なんとか受け止められる先の世代でありたい。





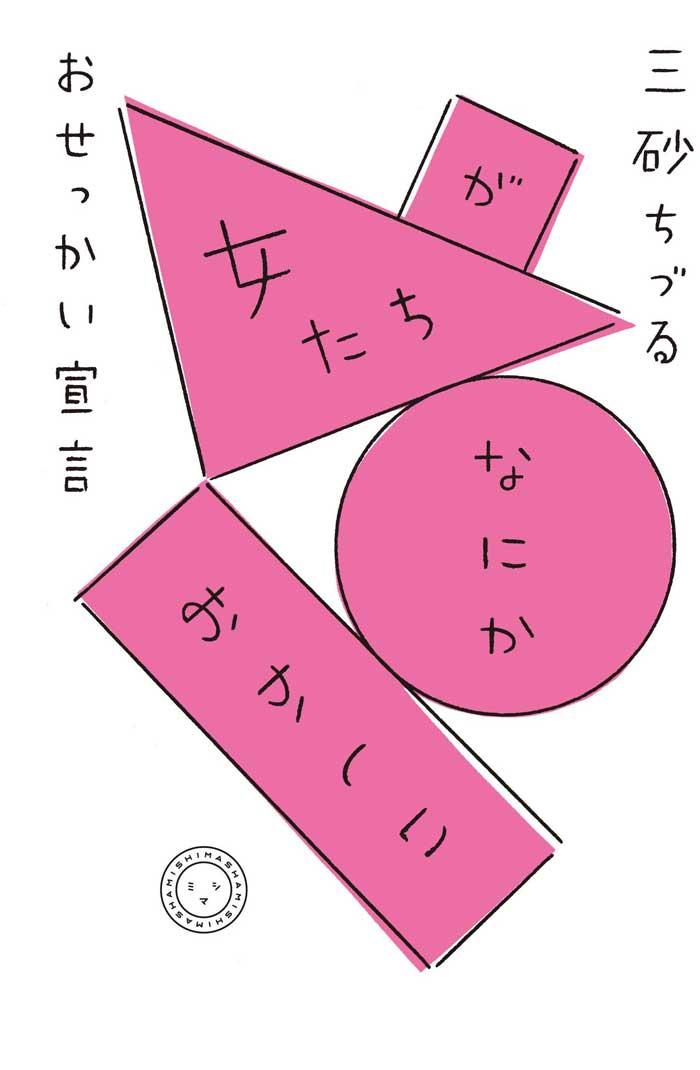


-thumb-800xauto-15055.png)



