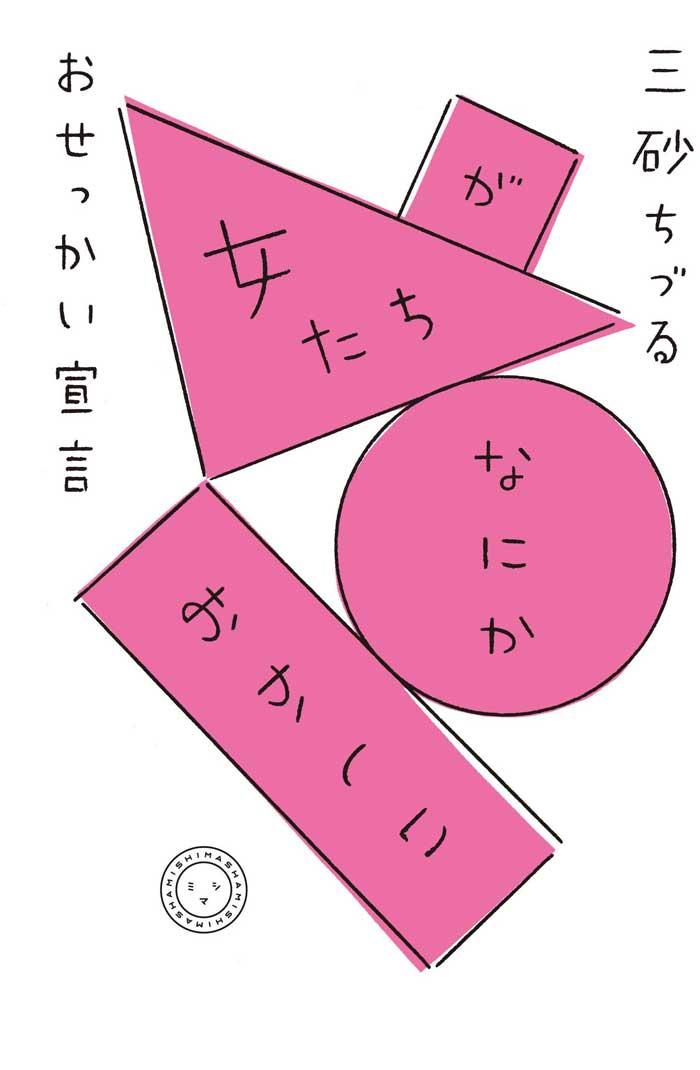第95回
ボーダ
2022.07.29更新
アオブダイという魚がいる。日本では、沖縄などに生息している。真っ青な色をしており、頭にコブができるものもあり、ナポレオンフィッシュのように大きくなったらしい。昔は、大きなものになると畳一枚ほどのものもいたようで、それを西表島ではボーダと呼んだ。今はもう、その大きさのものを見ることはないらしい。
昔は、獲れていた・・・、といって、どのくらい昔なのか、は、実は、よくわからない。だいたい大正生まれくらいの方に話を聞いた、という方の話の、また聞きだから、時代も事実確認も、「調査」という意味では、確証に欠けている。どなたか、漁労などを研究される方が、いつか、本格的に調査してくださることを待つばかりだ。が、お話、として聞くだけでも、実に興味深いものだった。今は、もう見つかること自体、ほとんどないらしいが、昔は、畳一畳くらいの大きなアオブダイが実際によくとれ、そして、その大きなアオブダイをとるために、とても特殊な漁をしていた、というのである。
西表は八重山諸島の島の中で最も大きく、山もあり、川もあり、豊かな自然に恵まれた島である。集落で祭祀を行う時には、村の男たちは何人かずつ、山に行くチームと海に行くチームにわかれ、祭祀のための食べ物をそろえたのだ、という。山に行くチームは、猪などを追う。海に行くチームは、もちろん魚を追う。畳一枚の大きさのアオブダイがとれれば、それはもう、集落全体の魚料理を賄うことができる量だから、意識してねらっていたようだ。
大きなアオブダイをねらうときは、サバニとよばれる南西諸島独特の船に、漁に参加している男のひとりをあおむきに、静かに寝かせる。みんなが漁をしている間、この男は動いてはいけない。じっと船の上でひとりで静かにしていること、が、役割なのである。男を寝かせた後、アオブダイとこの男をむすびつけるようなお祈りをする。そうすると、アオブダイは静かにしている、というのである。リーフに現れる、畳くらいの大きさのアオブダイを網でねらうのだが、この大きさの魚に暴れられると、捕まえることができない。アオブダイには、静かにしていてもらわなければならない。そのために、一人の男がサバニに横たわり、静かにしているべきなのだ。
ボーダに近づき、ゆっくりボーダを網で巻いて、網を縮めてゆく。そんな大きな魚なのだから、暴れられると取り逃してしまう。ところが、男をサバニに寝かせていると、ボーダもずっと静かにしている、というのだ。暴れることがない。そして、最後は、一貫して静かにしているボーダを、やさしく何人かでだきかかえるようにして、船に下ろす。畳ほどのボーダは、そのようにして捕獲され、祭りに供され、集落の料理の中心になるのである。
聞いた時、何のことを話しているのか、一度ではよくわからなかった。男を寝かせる? 船に寝かせる? 男と魚がむすびつけられる? 男が静かだと魚が静かにする? 一体何の話なのだろうか。これは、人間が、魚と交感できる、という話であり、現代の理性的な感覚では理解しづらく、科学的な検証は、おそらくもっと難しいものであるに違いない。しかし、体験談としてそのような漁が語られていたのである。現在の西表では、あまり知られていないようだ。
私は、妊娠、出産、の深奥に迫る、ということが長年、研究の目的の一つだった。人が人を産む、という、人間にとって、とても特別な瞬間には、人智を越えるような大きな力が働いている、としか言いようのないことも多くて、その場には、この「交感」と呼ぶにふさわしいようなエピソードも、多彩に立ち上がりがちなのである。
ある文化には、「擬娩」と呼ばれる習慣が存在する、ということは、文化人類学のテキストか何かに書いてあったように思い、知っては、いた。お産が始まり、妻が陣痛で苦しんでいる時に、その夫も同様にお産をするかのように陣痛で苦しむ。それを「擬娩」というらしい。これはある意味、苦しんでいる妻へのシンパシーというか、一人ではないよ、という励まし、というか、メタファーというか、そういうものなんじゃないのか、と何となく思っていた。実際に痛いはずは、あるまい。そう思っていたから、数年前にブータンに行った時、実際に男たちがこの話をするのをきいて、まことに驚いたものだった。50代の軍人男性は、首都ティンプーの軍人専用住宅で妻がお産する時、自分も、それはそれは痛かったんだよ・・・と、言った。そんなことについて、嘘が言えるような人ではなかった。実際にそうだったのだと思う。擬娩にまつわるジョークまで話してくれる男性もいた。あのね、あるところにね、キャプテン(将軍、であろう)がいたんだよ、偉いキャプテン。で、奥さんがお産になった。ところが自分はちっともお腹が痛くならない、おかしいなあ、なぜだろうかなあ、と思って、ふと、自分の車のほうをみると、ドライバーがお腹が痛い、と苦しんでいたんだよ・・・。というのがオチである。そういうことが冗談になるくらい、ブータン社会では、擬娩はよく知られている経験であるらしい。これは、子どもを産む、という瞬間に立ち上がる妻と夫の交感である。
それほどびっくりするような経験でなくても、日本でもお産につきそっている助産師さんが産婦さんが体感していることを同じように感じることがある、という話はしばしば聞いた。まるで自分がお産を経験しているように産婦さんの感覚がわかるのだという。それがわかれば、さぞや的確なケアができることであろう。現場の助産師教育でも、とにかく、助産師は、お産を怖がってはいけない、怖がると怖がっているようなことが実際に起こってしまったりするから、と、言われたりしているようだ。
普段の生活でも、自分が考えていることが相手に通じていたり、自分の頭の中で奏でられている歌を目の前にいる人がふと歌い始めたり、という話はよくあるわけだし、会いたいと思っている人がふと目の前に現れる、という経験も、誰でもしているのではあるまいか。時折そういうことが起こる、ということは、人間というのは、もともと、そういう能力は備わっていた、ということなのだろう。本来は常にそういう能力を使うこともできたのかもしれないが、特に必要無くなったから、使わなくなっただけなのかもしれない。
ボーダの話、繰り返すが、真偽のほどは、定かでない。しかし、こんな話を作り話にして伝えるだろうか。作り話だとすると、あまりにも突拍子もなく、安易でもあるからこそ、これはやはり経験していたことなのであろうと思われる。今となっては、詳細な話を聞ける人もおられないのかもしれない。サバニにのって、ただ、静かにしていた男は、どんな気持ちでいたのだろう。祈りによってボーダにつなげられるなんて、本人は一体どういう状態でいるのだろう。静かにしているだけでなく、ボーダのことがわかっただろうか。つかまえられたら、どう思ったのだろう。とらえられたボーダはそっと抱き抱えられて、サバニにのせられた、というが、ボーダとつながっている男はその時点ではどうなるのだろう。考えていると知りたいことばかりだが、もう、そんな話を実際にしてくれる人を見つけることは、おそらくできないのである。
編集部からのお知らせ
三砂先生の新刊『セルタンとリトラル ブラジルの10年』が発刊!
『セルタンとリトラル ブラジルの10年』三砂ちづる(弦書房)
世界地図を広げるとブラジルの面積は広大であることがわかる。日本からの移民も多く、ポルトガル語が公用語であることもよく知られている。北西部のアマゾンの森、南部のリオ・デ・ジャネイロ、サン・パウロなどとは風土がまったく異なる北東部ノルデステで、公衆衛生学者として10年間暮らして体感し思索した深みのあるノンフィクションである。
いわゆる「近代化」を拒む独特な風土を、著者独自の観察眼でユーモアを混じえて語り、命、美、死の受容、言葉以前の話など多くの示唆に富んだ出色の文化人類学的エッセイ。(弦書房書誌ページより)