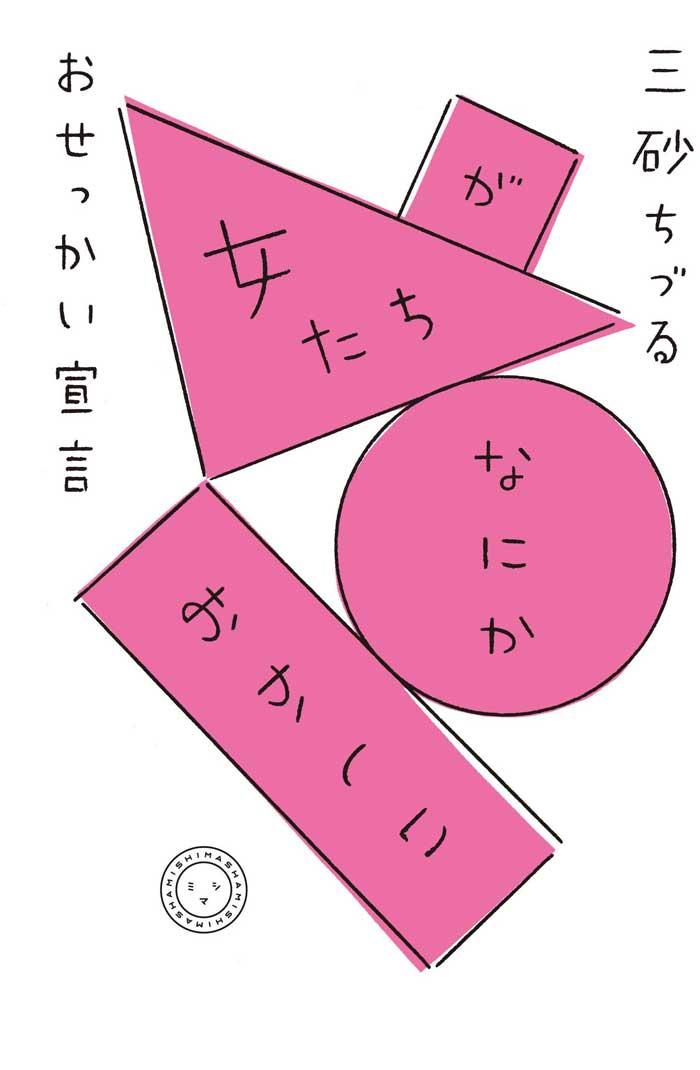第101回
嫁と姑
2023.01.28更新
日本では、確執の代表みたいに言われる、嫁と姑である。もう、話題には事欠かないし、文学のテーマにもなっていたし、現実に、自分の母親が、義理の母親(つまりは姑)のことを悪し様に語る様子も、娘たちはよく観察していたのではないだろうか。なんだかどろどろしたものの代表みたいで、緊張する関係、と理解されている。そのように聞いているし、経験しているし、読んでいるし・・・であるから、みんなそう思い込んで、緊張感を持って接することになる。それはもう、文化、というものである。嫁と姑をめぐる、日本の文化。
海外で長く暮らして、日本に戻ってくると、日本の文化に再適応するためには、海外で暮らした倍の時間がかかるのだそうである。この連載でも何度も書いているが、ブラジルで10年を暮らしたのちに日本に戻ってきた。それから20年は経っているので、もう、すっかり日本に再適応できたと信ずるが、なんと言っても暮らした10年間は40歳になるかならないか、までの、ほぼ30代の10年であったから、その影響は今も自分のうちにしっかりと刻印されている。ブラジル人の夫がいて、ブラジル人の親戚が山ほどいて、生まれた子どもたちは二人とも、のちには、日本の男の子として育っていくものの、当時は普通にブラジルで育つブラジルの子どもであった。30代だったから、夫と妻の暮らし、家族の暮らし、子どもたちの育ち方、などについて、それなりの若さとみずみずしさと驚きを持って、一つ一つ経験していき、今の私の根っこが形作られていったと言える。
記憶にある限り、ブラジルでは、嫁と姑は、確執のある関係だ、とは、思われていなかった。そういう認識を持たれていなかった。ブラジルで話されているポルトガル語で、姑、つまり、義理の母はソグラ(sogra)といい、嫁、つまり、義理の娘はノラ(nora)というのだが、家族の話を聞いても、周囲の友人たちの間でも、ソグラとノラの関係は、結構ほのぼのとしていて、緊張感を持って語られていなかった。人間同士だから、そりゃあ、相性はあるものの、別に、取り立てて、仲が悪いものだ、という言い方がされていなかったのである。カトリックの国、ブラジルでは、母親像、というのはもう、絶対なのであり、母と息子は総じて仲が良い。誰とでも挨拶としてハグしてキスする国だから(この COVID-19パンデミックの間はさぞや寂しかったことであろう)母と息子も、いつもハグしてキスしているのが普通である。ブラジルの男は総じてマザコンであり、ママが大好きであり、いつもママに甘えたいのだ。親しい日本人の友人が、いかつい柔道の使い手である日系ブラジル人の40絡みの男性が、実家の母に会った時に、ママーイ!(mamaeがお母さんのこと)と言って、ソファーに座っている母親の膝に頭を乗せてゴロン、となるのを見て、心底驚いていたことを思い出す。これはブラジルで珍しい光景では、まったく、ないのだ。息子たちは生涯、ママに甘えているし、母親も息子を抱きしめて、可愛がっている。
しかし息子は、自分の「男」ではないのだ。母にとって、息子は、息子であり、自分の「男」じゃない。自分は息子にとっての「女」、じゃないのである。だから、息子が「女」を見つけてくるとそれは母たちにとって、基本的にとても嬉しいことなのであった。だって、自分の可愛い可愛い息子を、男として受け入れてくれて、愛してくれる女性が現れることは、自分ができないことを全て息子にやってくれる女性ができた、ということで、母としては、ものすごく喜ばしいことなのである。自分は息子の「女」ではないし、息子と最後まで一緒に生きてやれるわけではない。息子を「男」として愛してくれて、一緒に生きてくれる女性が現れるなんて、あら、うれしや。なんと素晴らしいこと・・・・、と言った文脈で、いつもブラジルの家族のうちでは、語られていた。
むしろ、ブラジルの家族の中で、葛藤がある、と言われているのは、夫と、妻の母親との関係であった。母親というのは、息子が可愛くてたまらないのだが、娘だって可愛い。自分が手塩にかけて可愛がって育ててきた娘が結婚したら、娘の夫は、娘を蝶よ花よ、と可愛がってくれて当然である、と母親は思う。見ていると、どうも、娘の夫は、娘を十分に可愛がってくれていないように見える、と娘の母はいつも不満を持ってしまう・・・ということらしい。つまり、夫にとって義理の母、というのがコワい存在であるらしい。ともあれ、嫁と姑は、問題ではなかったのである。姑は、ひたすら嫁をかわいがるし、息子に「女」ができたことを、心の底から喜ぶ。
自分の生まれ育った文化はその人に色濃く影響を残すが、その後の人生のフェーズを過ごす場所の文化にもまた、人間は簡単に染められてしまうものである。そんなふうに染められてしまう、ということは、人間いつでも変わることができる、ということでもあり、幾つになっても違う人間になれる、ということでもある。その染められる幸せを求めて、ついふらふらとあちこちに住んでしまったような気もするのだが、それはともかく。嫁と姑が、確執と共に灰色の関係に塗り込められていた日本を出て、私の嫁姑に関する印象は、すっかりピンク色に塗り替えられてしまっていた。
新型コロナ・パンデミックの真っ只中の2020年9月に長男が結婚した。結婚したというのに、気の毒に、パンデミックのせいで、結婚式も新婚旅行も思うようにならない。ハワイが大好きなお嫁さん(お嫁さん、って、今はきっと、反発を呼ぶ言葉なのであろう。でも他にいいようがないし、本人も嫌じゃないらしいので、使わせてもらう)は、ハワイで着るウェディングドレスを選び、トローリーを借り、お料理を出してもらうお店も決めて、親戚はみんなムームーとアロハで結婚式に参加、引き続きハワイで新婚旅行、という計画を立てていたが、あの2020年にそんなことができるはずもなかった。籍だけ入れて一緒に住み始め、結婚式ができたのは、それから一年以上のこと、ハワイは諦めて、東京での式となった。ハワイへの新婚旅行ができたのは、さらにそれから一年後。すでに子どもも産まれていたので、嫁のお母さんと私は、ハネムーンを楽しんでもらうためのベビーシッターとして、前半、後半に別れて同行したのである。
お嫁さんというのはありがたいものである。なんと言っても、私よりも長男のことを気にかけて、手をかけて、愛を注いでくださるのである。結婚する前は、長男の出張予定も、聞けば、気になり、無事帰ってくるまで気が気ではなく、体調のことも気になった。しかし今や、長男には、私よりももっと、長男のことを気にかけてくれる人がいるのだ。いやあ、なんとありがたいことだ。私はすっかり長男のことを忘れてしま・・・ったりはしないが、気にならなくなってしまったのである。
お嫁さんは日本で良き教育を受けてきた、礼儀正しい方で、きっと頭に嫁姑の確執のこともおありで、姑というのは息子を取られた、と思いがちなのであろう、と忖度してくださって、息子と私を二人で出かけさせてくださったり、「母息子水いらずで」ゆっくりしてください、とか言ってくださったりするのだが、私は別に、今更、息子と二人で、とりわけやりたい事など、特にないのである。息子にお嫁さんができて、子どももできて、今は息子はその新しい家族の中の息子なのであって、みんなで会えればそれで最高。家族が増えて、可愛いお嫁さんが来てくれて、もう、本当に嬉しくてたまらない私は、やはりブラジル文化のおかげで嫁姑関係にピンクの色を重ねられたのである。幸せなことだ。ほんとに。
編集部からのお知らせ
三砂先生の新刊『ケアリング・ストーリー』(ミツイ・パブリッシング)が刊行しました!
ブラジルで子どもを育て、日本で父を介護し、夫を看取った疫学研究者が、人生の後半に綴るエッセイ。「父の元気なときは、これ食べすぎちゃ『からだにわるいよ』と言い、認知症になってなにもわからなくなってからは、食べないと『からだにわるいよ』と言ってしまう娘は、どうすればよかったんだろう、と、いまも、わからない」。介護や看取り、家族や夫婦の関係などを、国際母子保健の世界を渡り歩いた経験を交えて浮き彫りにする。誰かを気にかけたり、大切に思うこと=「ケアリング」という言葉から広がった25篇のストーリー。
(ミツイ・パブリッシングさん書誌ページより)