第104回
人間が生きているということ
2023.04.24更新
生きている、ということは、あたたかくてやわらかいからだがあることだ、とずっと思ってきた。死は、冷たい。死んだからだはあまりにも、冷たい、これ以上冷たいものがあると思えないくらい冷たい。死、とは、だから、なによりもまず、冷たくなることだ。切なさより悲しさより、冷たさに、これが死なのだ、と思う。あたたかくてやわらかいからだがあるときは、愛し合いたい、抱きしめ合いたい、ふれていたい。
人間はもとより、からだだけでできているわけではない。その精神的なはたらき、こころのありよう、というものが生きているということには付随するのであり、実はそれがどのようなものであるか、現在の科学をすべて動員しても、わからないことばかりだ。とはいえ、死ぬと体が冷たくなる、ということと同時に、死ぬと、その人の精神的なはたらき、というか、その人の考えや行動には、もう直接アクセスすることができなくなる。一人の人が死ぬということは、その人のうちに集積され、収束され、つなぎあげられていた実に複雑な体系は、なくなる、ということだ。
2022年12月25日、敬愛する渡辺京二さんが亡くなった。『逝きし世の面影』、『バテレンの世紀』、『黒船前夜』など多くの近代を問い直す著作を残した思想史家で、92歳だった。渡辺さんとは、2011年3月に熊本市真宗寺で二日間にわたって津田塾のゼミ生と珠玉の時間を過ごし、そのようすは『女子学生、渡辺京二に会いに行く』(亜紀書房、文春文庫)という本に残されている。それを機会に親しくお目にかかるようになり始めて、10年以上が過ぎていた。92歳なのだから、いつなにがあってもおかしくない、と、頭ではわかっていても、2ヶ月に一度お目にかかるたびにお元気に何時間もお話ししてくださって、からだはきついが、まだまだやりたい仕事があるとおっしゃっていたから、お別れするのは、まだ、先だ、先であってほしい、と願っていた。どう考えても92歳なのだから、そんなに先であるはずもなかったのに、渡辺さんの周りの人たちは、私だけでなく、みんな、もっと先のはず・・・と、それぞれに、今思えば、ただ希望を紡いでいたと思う。文字通りの現役で、熊本日日新聞に「小さきものの近代」を毎週連載しておられた。亡くなる前日、NHKの方との打ち合わせで、ご自身でコーヒーも淹れて接待され、ゆっくりお話されて、午後を終えられたという。ご家族とクリスマスイブのチキンを召し上がって、そのまま目覚められなかった。
亡くなる日や生まれる日は、家族に同じ人がいるとか、誰かと重なっている、とかして、記憶に残ることが多いのだが、渡辺さんはイエス・キリストの生まれた日に逝ってしまった。世界の人が記憶し、キリスト教国とは言えない日本でも、皆の心に灯火の灯る12月24日は、渡辺さんの逝った夜となり、25日は渡辺さんのご命日となった。渡辺さんの周囲にいた私たちは、もう、自らの命が終わる時までこの日を忘れることはありはしない。そんな日に突然逝ってしまった。亡くなる前の週にたくさんの方に連絡をしておられたことも後になってわかった。私のところにも、直筆のスマートレター(ゆうちょの扱っている小さなレターパックのようなもの)で、熊本起点の詩の雑誌『アンブロシア』が送られてきていた。「一生は終わりました」という渡辺さんの文章が寄稿されている。受け取って、お返事書かなくては・・・、と思っていたら、訃報が先に届いた。聞けば、少なからぬ方(特に女性)は、この『アンブロシア』を受け取っておられたようだ。書きかけの連載原稿は書き上げ、ファイルに入れ、ペンも置き、机は綺麗に片付けられていた、という。「もういつ死ぬかわからんから書いておかないとね」とおっしゃっていた熊本日日新聞の連載は、没後、毎週掲載して一年は続くほどに書き溜めてあるという。没後も連載原稿を読み続けている私たちである。
渡辺さんの読書量、知識量はたいへんなものだった。最近、本が読めなくなってねえ、と晩年におっしゃっていたが、それは「一日一冊しか読めなくなった」という意味であり、それまでは、一日に何冊も読み上げておられたのである。西洋の歴史と現在を理解するためには、どうしても必要なことである、と、全てそらで言えた、イギリスとフランス、そしてロシアの歴代王朝の名前が最近出てこなくて、困っている、と嘆いておられた。ものすごい記憶量でもあった。しかし、最も凄みがあったのは、それらの膨大な知識は、渡辺京二、という人のうちにあって、その人の思想の方向性と興味関心によって、見事に収束され、取り出され、使われ、思わぬ繋ぎ方をされていたことである。渡辺さん、という、「人間とはどういう存在なのか」を解明したい、という強い意志をもつ一人の人によって、歴史は掘り起こされ、読み返され、思索しなおされ、紡ぎなおされたのである。渡辺さんは多くの著作を残され、それらも多くの人に読まれることを待っているが、私が渡辺さんにいただいた最も大きな贈り物は、一人の人間が、ただ、そこにあって、一人で人間のやってきたことを問い直し、考え直し、統合していく力を持つこと、こそが、人が生きている、ということなのだ、ということを、誠に腑に落ちる形で見せていただいた、ということだ。
渡辺さんは本を読み知的な作業を積み重ねることを生涯追い続けられたわけだが、そういう仕事の人だからこそ、そのような作業が重要であるのではない。実は、生きている私たちは全て、何らかの形で自らの生まれた環境で、言語を学んだり、情報を受け取ったり、伝統を受け継いだり、周囲から学んだりしながら、多くの情報と知識を自らのうちに蓄積し、それらを自らの生きる方向に集積し、一人の人間のありようを形作っているのである。一人の人間には、それらを統合し、体現していく力があるのだ。
大学、という場所は、とりわけ人間のそのような知的作業をどのように腑分けし、どのように人間が積み上げてきたものを次世代に伝えるか、を細分化しながら系統立てて学べる方向を探求してきた場所なのだと思う。それらの系統立てて学んできた知識をどのように自らの中で統合し、その人のありようを作り上げていくか、を学んでもらうところだ。だから、やっぱり、一番大切なのは、「自らの問いを立て、テーマを追求する力」ということになってくる。そしてその問いは、自分がそこまで生きてきたことの集大成であるような心震える、生涯をかけて悔い無い、というような問いでなければならない。そのような問いを、学問、という枠組みで、限られた時間でどれだけ追えるか、ということを学んでもらうのが大学というところであり、そして、限られた時間と自らの限られた能力では限られたところまでしか行けない、ということを学んでもらうところでもある。限られたところまでしか行けないなら、生涯学び続けねばならないのだ、ということもわかるのだ。
Chat G P Tをはじめとする生成系A Iが、2023年が始まってから急速に世界に広がり、2023年4月の新学期を迎える頃には、大学生がこの生成系A Iを簡単にレポートや論文作成に使えてしまうことがわかって、各大学は、明確な方針を提示せざるを得なくなっている。Chat G P Tは、実に速く、自然な日本語で、見事な知ったかぶりを披露してくれて、同じ問いに同じ答えが返ってくることもないから、実際に書かれたものかどうかを判別することすら可能ではない。そんな中で、学生に伝えるべきは、あなたこそが知識と情報の集積のシステムであり、あなたの意志と思考の方向性の力によって紡ぎ上げられるものは、あなたにしかできないことである、ということ、つまりは、学びとは何なのか、をあらためて確認することでしかないのだ。渡辺京二さんのありようを思い出しながら、そのことを確信するのである。





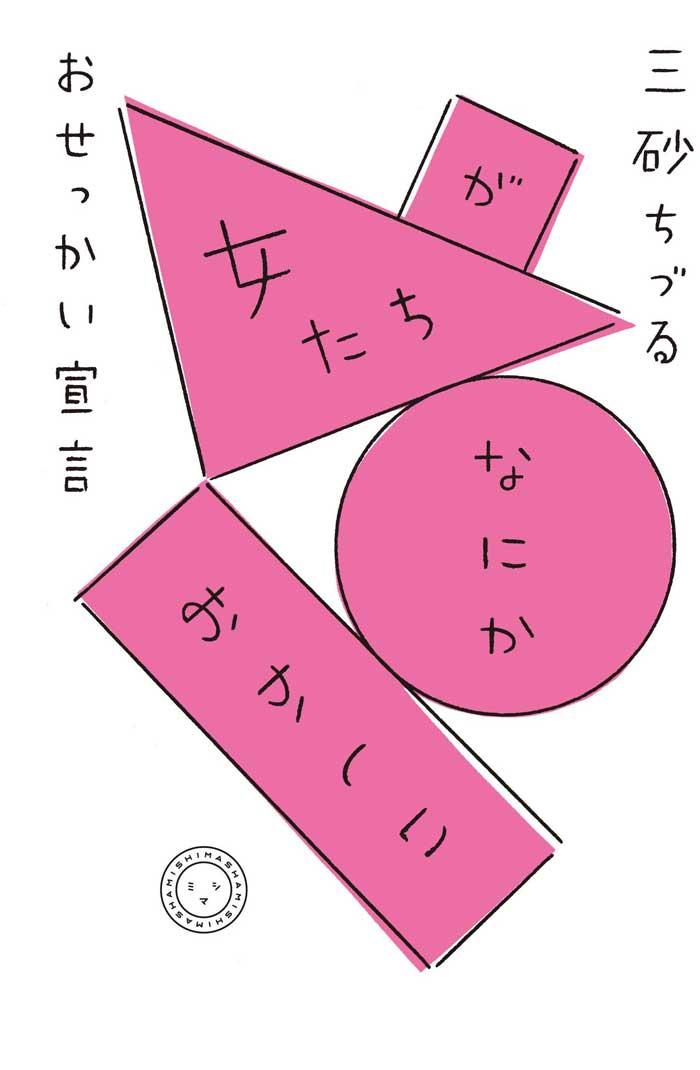


-thumb-800xauto-15055.png)



