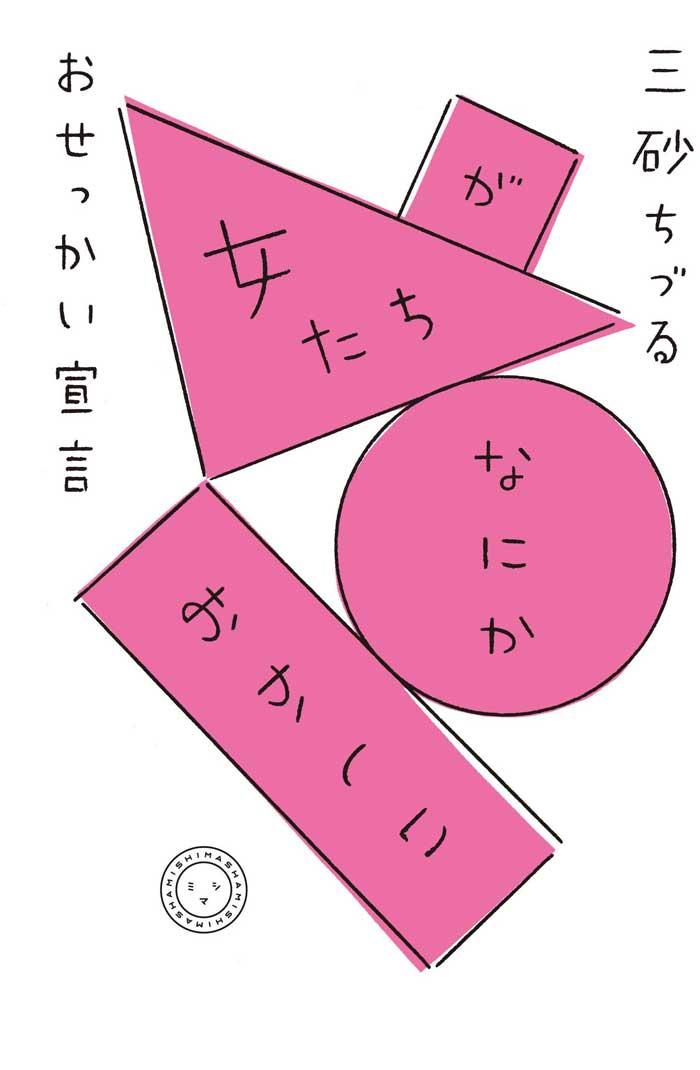第105回
タバコのある風景
2023.05.30更新
タバコがとにかく体に悪い、やめなければならない、吸わないようにしなければならない、受動喫煙だってよろしくないから、家にタバコを吸っている人がいたら家族は健康被害にあっているのだ、職場などでタバコを吸うとか、考えられない・・・というのが2023年現在なのであるが、こんなふうになってまだそんなに時間は経っていないのである。いまどきの方には信じられないと思うが、ついこの間まで、タバコは男らしさの象徴であり、かっこいい男はタバコを吸うものであり、渋い男のいる風景にはタバコがなければならなかった。ああ、このように書いていても、今や、「男らしさの象徴」などという言葉が、まるで冗談のように聞こえるのではあるまいか、と思う。男らしさ、女らしさ、などという性別によるステレオタイプな考え方は男女共同参画社会推進とは反するし、個人の自由な生き方を妨げ、女性も男性も抑圧する・・・、というまことにまっとうな考え方を"世間"というものが受容するようになって今に至る。要するに人間社会は、一人一人の生き方の多様性を認め、生きやすくするように進化している、ということになっているのだ。全くその通りであろう。
で、タバコだが。60代のわたしが子どもの頃は、大人の男はみんなタバコを吸っており、どの家庭にも灰皿、というものがあった。灰皿、は、プレゼントとか、引き出物とか、贈答品一般の中でもかなりポピュラーなもので、ちいさなものは当然のこと、どの家にも、居間に置かれるためのどっしりした持ち重りのする大きな灰皿もあったものである。お客さんが来ると、まずは灰皿を出し、さらに家によってはタバコ盆が出されたりした。おもてなしの一環としてタバコは全ての層にあまねく浸透していたのだ。引き出物の灰皿は21世紀になっても、まだ続けられており、我が家にはバカラのえらく高そうな重い灰皿があるが、これはどう考えても2000年すぎて我が家に届いたものだ。男のみでなく、1970年代には、タバコは"自立"していっぱしのものを考えている、と周囲に示したい女の象徴でもあり、ボブカットの桃井かおりがそれは素敵にタバコを吸っていたりしたものだから、世の中と親に反抗する1970年代末の女子大生はみんなタバコを吸っていた。1983年の末に、青年海外協力隊に参加してアフリカに働きに行ったのだけれど、その頃の青年海外協力隊の派遣前訓練には、東宮御所に赴いて皇太子(いまの今上陛下である)と接見、という行事が組み込まれていた。接見の間につくと「恩賜のタバコ」と呼ばれる、菊の御紋のついた有名なタバコが配られ、若い協力隊員たちは、自分がタバコを吸わないまでも親に見せたい、とか思って、一本いただいてきたりしたものである。そういう場で当然のように出されるものであったタバコであったのだ。宇多田ヒカルが1999年に出した3枚目のシングル、「First Love」は男性との別れを歌った切ない歌だけれど、若い女性はタバコのフレイバーを男の名残りとして思い出しているのであった。それがまだ、かっこいいことであったのだが、タバコのフレイバーのキスが記憶に留められているのも、今や50代以上であろうか。
このようにして、過去20年の間に、まるで文化人類学的記憶になろうとしているタバコの風景であるが、これは、もちろん「タバコと肺がんが関係がある」ということが、疫学調査で示されて「タバコは体に悪いんだ」ということが人口にあまねく膾炙したからに他ならない。1950年代頃からイギリスの疫学者が医者を集めて喫煙者と喫煙者でない人をわけて、5年も10年もさらにもっと追っていって、喫煙者の方に肺がんになる人が多かったことを「コホート研究」という、けっこう信頼のおける調査で示したから、「タバコという習慣と肺がんの発症には関係がある」ということになったのである。要するに、タバコと肺がんは関係がある、という「科学的根拠」が示された、ということになっている。「科学的根拠」は疫学調査が出すのだ。
そうか、疫学が科学的根拠を提供すれば、このように世の中の風景は変わっていくのか、かっこよさの源泉も変わってゆくのか、人間の行動も変わっていくのか、と思われるかもしれないが、疫学の科学的根拠というのは、そういう性質のものではないのだ。疫学というのは、あくまでも医療の枠組みの中にある学問体系であり、疫学はより良い医療のシステム、医療や公衆衛生のあり方を求めて、医療や公衆衛生の枠組みをより良くしていこうというデータを出しているにすぎない。それ以上でもそれ以下でもない。さらに、疫学調査で科学的根拠を出したからといって、医療の枠組みの中のことが変わっていく、とさえも言えない。疫学による科学的根拠は、研究者が、医療の枠組みで、このことはこのように変えていったほうがいいんじゃないか、という発想を持って、なるべく説得力のある調査を行なって、論文を書いて、それがそれなりの雑誌に載って、信頼できる科学的根拠である、と認められるものなのだが、そういう結果が出ても、現場の医療の枠組みが変わらないことなんて、いくらでもある。
仕事をしてきた母子保健分野でもそんなことは山ほどあった。例えば、この国では、病院で生まれた赤ちゃんというのは「新生児室」という赤ちゃんばかり集められた部屋にいる、と思っている人がたくさんいるであろう。多くの病院がそのようにして、健康で特に医療ケアを必要としない新生児を「新生児室」というところに入れているからである。生まれてきた健康な赤ちゃんは、特に母子に問題がなければ、産んだお母さんのそばにいる、ということが母乳哺育推進という意味でも、母子の絆を作る、という意味でも、赤ちゃんの感染症予防、という観点でも、最も良いのだ、という科学的根拠が出されて、半世紀くらいになるのではあるまいか。少なくとも「タバコと肺がん」と同じくらいの歴史がある「母子同室」、なのである。ワールドワイドなレベルで、大体の先進国も途上国と呼ばれる国も、この「母子同室」をやっていて、健康な赤ちゃんをみんな集める「新生児室」などは駆逐されているのだが、この国では、いつまで経っても、なくならない。天下のN H Kも、少子化問題など取り上げるたびに、病院の「赤ちゃんがずらーっと並んでいる新生児室」の風景を画面で流しているから、国民的に受容される風景は変わって行かない。以前は、ニュースでそういう画像が出ると、「あのような科学的根拠のない映像を流さないでください」と抗議していたこともあり、抗議するとしばらくは、「新生児室」の代わりに「赤ちゃんの顔の大映し」などに変わるが、喉元過ぎれば熱さを忘れるのであろう、すぐに、また新生児室の映像が流れるようになり、いまに至る。要するに、科学的根拠があっても、現場の医療関係者、公衆衛生関係者が、それを変えていこう、という気がなければ、全く変わらないのだ。日本の病院は、まだ、新生児室に赤ちゃんを入れている方が、管理上、問題もなくお母さんも楽だ、と信じている現場の方が多いということなのであろう。
では、なぜ、タバコをめぐる風景は、このように変わっていったのか。それは、タバコと肺がんが関連がある、ということが疫学調査によって示されたから、ではない。それは、その科学的根拠をもって公衆衛生上の健康活動をやりたい人たちがいて、さらに、そのことが産業構造の転換にも影響を与えても良い、と考える政策上の決定があって、世界のタバコの畑を減らして、タバコ産業は斜陽になっても良い、ことになったからにほかならない。それに伴って、何がかっこいいか、という判断が少しずつ変わっていったからだ。私たちの周囲にあまねく広がる「体や心によろしくないもの」についていくら科学的根拠を提示しようが、変わりそうにない無力感は、「新生児室」を例に挙げなくても、美味しそうなものは全て精製糖質でできていたり、原子力発電所がなくなることはなかったり、AIの働きを制御しようなどということができなかったりすることを見れば、直感的によくわかるか、と思われる。