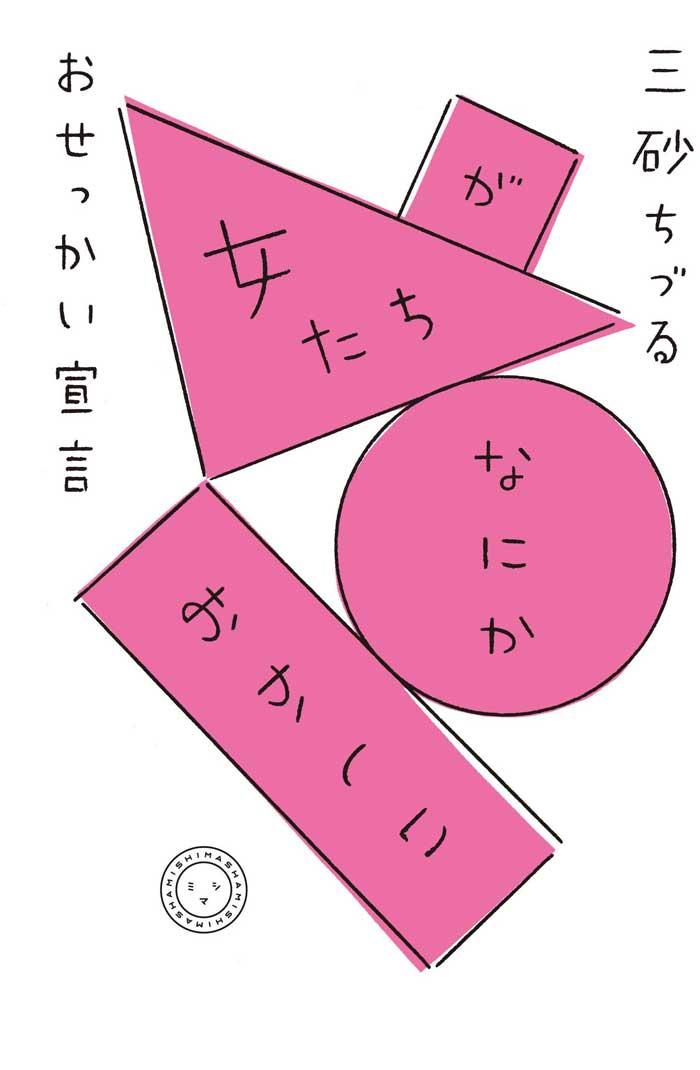第108回
one to one
2023.08.30更新
One to one midwifery、という言葉があった。今もあるのだろうか。助産の現場にいるわけではないので現状は良くわからないが、三〇年くらい前には母子保健分野でよく聞いた言葉だったし、助産師実習の根本においている学校も少なくないと聞いてきた。「一対一の助産」、つまりは、一人の妊婦さんに、妊娠した時から、ずーっと一人の助産師が担当し、その人がお産もみる。産後もその人がみる、ということだ。妊娠した女性にとっては「この人が私の助産婦さん(法律名では助産師だが、助産婦さん、という呼び方は、いのちのこもった呼びかけだと思う)」、というのがわかる。何かあったら、この人に頼ろう、何か不安なことはこの人に聞こう、と思える関係になる。
日本独特の助産施設である開業助産所でのお産は、おのずと、そういう形になっていく、というか、そういう関係性が欲しいから、助産所でお産する人は、助産所を選んでいるわけだけれども、one to one midwiferyはそういう一対一の関係をもっと大きな施設でもできないか、という提案だったのだと思う。この発想自体は本当に素晴らしくて、妊婦さんにとってはもちろん安心できるし、また、"助産魂"をゲットするには、やはりこの一対一の関わりが大切である、ということも助産教育の現場では体感されているようで、学生実習に取り入れているところも前述したように少なくないのだが、現実にそれをお産の現場でできている施設がどれほどあるのか、というと、まことにこころもとないと思う。現代の医療現場では、シフト制が基本だし、労働する側からすれば、労働の場に、ずーっととどまり続けるというのは、きついことであるから、システム化しにくいのである。それは理解できる。
でも、とにかく、「みてもらう側」からすれば、「私にはこの人がいる」というのはどれほどの安心感だろうか。とりわけ初めての妊娠の時には、わからないことだらけで、不安ばっかりである。これで大丈夫なのだろうか、こんなことがあったけど、病院に行かないといけないのだろうか、これ、たべてもいいのだろうか、夫と些細なことで喧嘩してしまったら、お腹が張ってしょうがない・・・とか、いろいろなことがあるし、夜中に滂沱と涙が止まらないことだってあるのだ。One to one midwiferyの基本には、「女性は、誰かいつも自分のことを見ていていてくれる人がいれば、それだけで、自分をよく観察するようになるし、安心できるし、成長していく」ということがあるのだ。誰かに見守られている、というだけで、人間は成長できるのである。
妊娠出産なのだから、医療知識もあり、いざという時に頼りになるプロの助産師が一対一でみてくれるのが一番いいに決まっている。しかし、「一対一で信頼できる先輩女性がそばにいる」ということについては、医療職でなくても、できることだ。近代医療の助けを簡単には得られなかった離島のような環境にあっては、女の子が生まれると生涯その女の子に寄り添い、お産にもつきそい産後も支える仮親のような存在が任命されていたという。
これは、親密な人間関係の問題である。親以外の人間で自分のことをあるがままで受け止め、寄り添って一緒に歩いてくれる人がいれば、人間は成長できるし、自分のことを愛することも覚えるのである。もちろん、結婚、というのもそのような人を見つけていく方法だったわけだが、同性の先輩、という存在があることの心強さは想像できると思う。
もう20年くらい前だったと思うが、埼玉県のある保健所のドクターが言っていた。「一人の子どもが生まれることに対していろいろな職種が関わっていますよね。妊娠したら助産婦さん、保健婦さん、産科のドクター、小児科のドクター、病院の看護婦さん、そして保育士さん、学校に行くようになると、先生もいる、でも、その子にとって、だれも、"私にはこの人がいる"と思えるようにはなっていない。どんどん次から次から異なる職種が現れて、その場かぎり。これだけたくさんの優秀なプロフェッショナルを揃えて、お金も使っていて、どの子にとっても、"この人は自分のためにいてくれる人だ"と思えない、というのはなにか、根本的に間違っているのではないですかね・・・」まことにその通りなのである。ファミリー・ドクター、家庭医、という制度は、「私にはこの人がいる」と感じらる公的システムによる医者作りであったのだが、開業医制度を基礎とするこの国の医療には、家庭医の入るスキはなさそうだ。
信じられないようなスピードで進む少子化日本、一人一人の子どもたちが大切にされてほしい、と思うけれど、結局私たちはどの子にも「私にはこの人がいる」というシステムを作れないでいるのである。私立小学校では担任が変わらないところがある、と聞く。ドイツのルドルフ・シュタイナーの思想をもとに作られたシュタイナースクールでは、人生を8年で一区切り、とわけているという。で、学齢期7歳から8年間担任が変わらないらしい。7歳から15歳までの間、ずっと自分のことを近くで見てくれる人がいる、というのはどんなに心強いことだろう。まあ、気が合わなかったらどうするのか、とか、担任を変えてほしいときはどうするのか、とか、いろいろあると思うが、ともあれそういうシステムで世界中でやっている教育なのである。
シュタイナースクールなどはいわゆるオールタナティブ・スクールと呼ばれるような学校であるが、都内でもっとも難しいとわれるエリート養成校とおぼしき私立小学校でも、6年間担任が変わらないらしい。つまり「ちょっと普通とは違うオールタナティブスクール」でも、「小学校お受験界のトップを走るような学校」でも、この6年とか8年とか担任を変えない、というシステムを長年やってきている、ということは、まことに注目に値することのように思われる。one to one midwifery ならぬ、one to one education、一対一の関係を大切にする教育である。その子の人生にとって、それはどれほど実り多い結果を産むことだろうか。
また、教師という職業を選ぶ人にとって、教師人生は思ったより短い。教師じゃなくても同じだけれど人生100年時代、職業として関われる仕事はせいぜい40年くらいであることが多い。その40年をいかにして子どもたちにゆったりと寄り添えた、という深い満足のあるものにしていくか、という働きがいの視点においても、この「担任を変えない制度」は重要であるように思う。たとえば、8年間同じクラスを持つとすれば、自分の教師人生で、多くて5サイクル、6年間ならば、6サイクル、くらいであろうか。教師という職業を選ぶ人にとってそのような子どもとの関わりは職業人生の終わりに深い豊穣をもたらすような気がする。教員の仕事があまりにたいへんで、教員のなり手がいなくなっている、と聞く。この少子化の時代に、教師が魅力的な職業ではなくなっているのである。担任を変えない、など、私立校だからできること、と言えるのかもしれないが、子どもの育ちに寄り添うこと、教師をゆとりをもって働きがいのある仕事にしていくために、このone to oneの発想も省みられる価値があるように見えてきた。