第117回
タレフェイラ
2024.05.27更新
ポルトガル語である。ブラジルで使われているポルトガル語、「タレフェイラ」。ポルトガルで使われているかどうかわからないが、1990年代十年間住んでいたブラジルではよく耳にした言葉であった。どの言語でもそうだと思うが、その言語でしかあらわせない独特の表現が元々あったり、生み出されたりしていくものだ。そしてそのような一言に文化の真髄があらわれたりする。この「タレフェイラ」は、今も忘れることのできない、一言である。
タレフェイラのもとになっている単語は「タレファ」であり、ポルトガル語で「tarefa」である。tarefaは、仕事、とか務め、とかいう意味だ。もっと軽く、作業、というような意味もあると思う。タレファは仕事、であり、タレフェイラは、直訳すると、「仕事をする人」という意味だ。
しかしタレフェイラ、というときには、もっと深い意味が含まれていた。「あの人は、タレフェイラだからね」というのは、決して本人の前では言ってはいけないことで、第三者のことを説明するときに使う。「あの人はタレフェイラ」というのは、あの人は仕事をする人だね、すごく仕事ができる人だね、という意味ではない。「タレフェイラ」というのは「あの人は言われた仕事しかしない人、言われたことしかやらない人、それ以上のことをやらない人、自分の頭で考えて仕事や作業をしていない人」のことを指す。タレフェイラは決して「仕事」ができないわけではない。むしろ、結構、できたり、する。はい、これが仕事ですよ、と言われたことくらいは、さささ、とこなせたりする。仕事早いね、とかいってもらえたりする。しかし、それしか、できない。自分の判断で、やれ、と言われた仕事をより洗練したものにしていく、とか、同じ仕事でも心を込めて仕上げて期待以上のものにしていく、とか、自分の判断でこれはまずいと思うことは改善したりする、とか要するに、AIじゃなくて、人間である、ということはそのようなことができることなのだから、言われたことしかやらないのは、非人間的なことである、というようなニュアンスが含まれるのである。
ブラジルにいた頃、二国間国際医療協力の仕事もしていた。だから、州の保健局とか、ブラジリアの保健省とかに仕事に行くことがある。親しい同僚に、「今度、保健省のxxさんに会いに行くんだよ」というと、「ああ、あの人はね、タレフェイラだからね、気をつけなさいよ」と言われたりする。こういうのは、悪口、というより、親しい人からの注意、っていう感じである。それは「あの人は仕事ができない人じゃないよ、でも、それ以上のことはやらないからね」ということで、ようするに「そんなに信頼できる人じゃないよ、だからそんなに深い話してもダメだよ、まあ、目の前のことだけ片付ける感じだね」と、そいういうことが含意されているのである。
これ、よくわかるのではないだろうか。よくわかるけれども、日本語にはそのようなことを一言でぴたり、と言い表す言葉がない。ない、ということは、そもそもそういうことは言わずもがなであった、とも考えられるし、だからこそ、そういうことを問題にするべきだという状況になったとき、表す言葉がない、とも言える。ポルトガル語には、この言葉があった、ということは、タレフェイラはあまり信用されない、ということだから、仕事の内容に関わらず、言われたことしかやらない、その場で自分の判断をしていかない、という人は、敬意を持って表されない、ということがよく表現されている、ということなのである。
近代をどういう時代、というか、いろいろな言い方があると思うけれど、ちょっと油断していると、タレフェイラの集合になってしまうのが近代、である。近代社会というのは専門性を持った職業が確立する世界、と言ったのはマックス・ウェーバーだった。専門性を持った職業が確立する、というのは、逆に言えばある職業に就くということは、誰がやっても同じことができるようになる、ということだから、近代社会というのは構造的にタレフェイラの量産を前提としているとも言える。だからこそ近代社会は学校というシステムを強固に確立し、タレフェイラ量産に励んだのである。そこで、いやいや、それは、人間的じゃないでしょ、人間ってもっとその場の、仕事の手ざわりとか判断とか心の通い合いみたいなものがないと、仕事の質を上げていけないでしょ・・・みたいな思いが結晶していくと「タレフェイラ」という言葉になりうるのであり、それはラテンアメリカ社会が近代社会のエトスのみに巻き込まれないような強靭さを持っていることの裏返しでもある、とか言っちゃうと、おそらく言い過ぎかもしれない。しかし何が言いたいいかというと、日本のようにもう、あわてて近代化しないと西洋列強の餌食になっちゃう、と、猛スピードで近代社会を作り上げ、それなりに、成功した、と、はたからみえるような社会を作っちゃった場合は、その弊害はおそらく、ラテンアメリカより出やすい。タレフェイラって言葉もないし。
2024年5月1日、熊本県水俣市で行われた水俣病慰霊式に続いて行われた環境省主催の伊藤信太郎環境大臣と患者及び被害者団体との懇談会、8つの患者や団体が3分間の発言を求められていたというが、二人の発言に対して、3分をこえたところでマイクが切られた。環境省の職員が、3分をこえたらマイクを切る、というマニュアルにそって、高齢男性が亡くなった妻の症状や被害のことを話している最中でも、マイクを切ってしまったというのだ。会場からは「最後まで言わせてやれよ」とか別の団体からは「私たちの時間を使って」という言葉もあったという。
誰が切った、切らない、という問題より、その場にいた、主催者側の誰もが「それぞれの発言は3分」という「タレファ」(作業)だけを遂行しようとするタレフェイラであり、タレファ以上のことをする気が、さっぱりなかった、ということである。そりゃあ、時間を守る必要はあるだろう。大臣は分刻みのスケジュールをこなしているのであろうし、新幹線の時間も飛行機の時間もあるだろう。だけど、そもそも、何をしに水俣に来ているのか。慰霊式であり、患者の声を環境相と環境省職員が直接聞く、ということ以上に大切なことはない。人間のことばは、その場の状況と、その人にその時、おりてくるものであって、それこそが大切にされるべきなのだから、あ、これは聞かなければならない、と感じることに心が動かされてこそ、「環境省の心ある仕事」が始まるはずなのだ。主催者側の大臣も環境省の役付きも、どの職員も、あるいは県や市の担当者もいたであろうに、誰一人として、マイクを切る行動に、「それ、今、やめとけよ」と、タレフェイラじゃない行動をする人がいなかった、ということである。省庁の人間は、大臣をおまもりする、とかいうことも重要な任務と受け取っているらしいが、結局、誰も、「マイク、今、切っちゃだめだ」という人がいなかったために、結果として「大臣をおまもり」なんかできなかったのである。タレフェイラばかりの大臣とか官僚とか、いらない。
その場ですぐ反応できる人間であること。反応する能力があること。response(反応)する能力(ability)がある、っていうことがresponsiblity、つまりは、責任(responsibility)ある人間になるということではないのか。目指すところはそういうところにしかないのだが、明らかに日本近代は官僚のタレフェイラ増産しかしてこなかったことが露呈して、それはもう、なんといっても近代教育のシステム化に人間的なありようが惨敗した、ということを示しているのでもあり、つい先日まで教師を職業としていたものとしては、うなだれるしかないのだ。今年の4月29日、朝日マリオンホールの水俣フォーラム主催、水俣病講演会の講演を担当したが、そういう話をすればよかった。くだんの事件の、二日前のことだった。





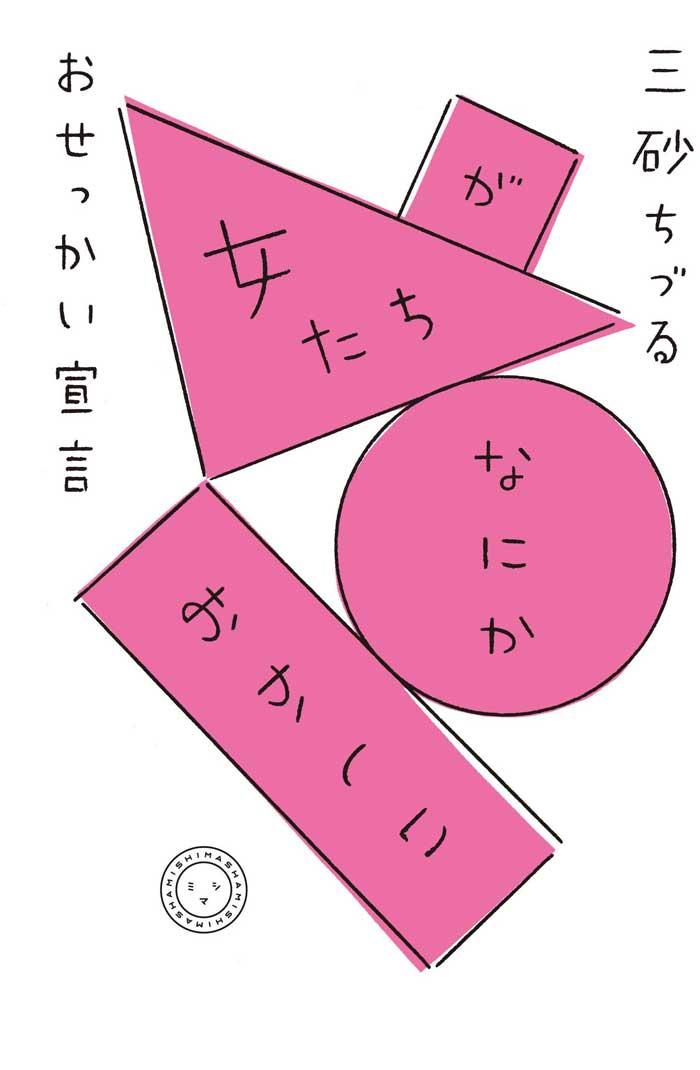


-thumb-800xauto-15055.png)



