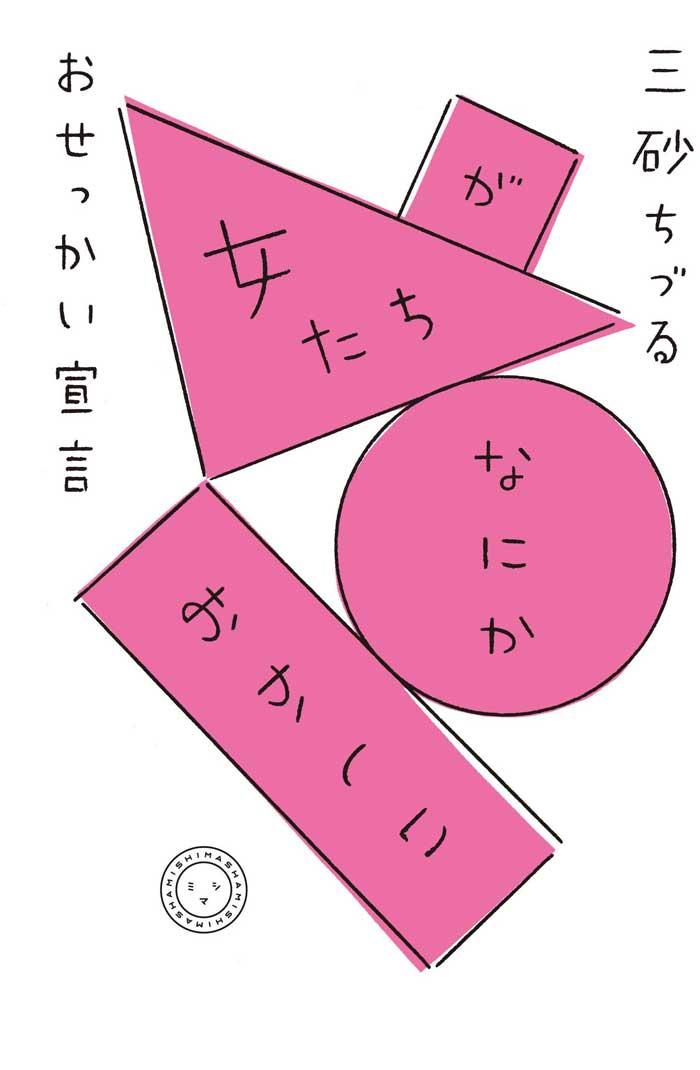第122回
再 ロングショットの喜劇
2024.10.28更新
座右の銘はなんですか、と、聞かれたので考えたが・・・。喜劇王チャールズ・チャップリンの残した言葉かもしれない。「人生は近くで見ると悲劇、でも遠くから見ると、全部喜劇」。要するにロングショットで見ると人生で起こっていることはすべて喜劇である。以前にもこのことについて書いたことがあるのでタイトルに「再」をつけた。ロングショットの喜劇。個人的なレベルでの自分の人生の苦労とか、まあ、たいしたことではないのだが、それでも当時は大変なことはあったよなあ。でも、今思うとたしかに、なんだか全部笑い事ではあるまいか。ここまで生き延びて、いま、笑って生きていこうと思うから、言えるのだと思うけれど。よくあんなことをやったものだ、よくあんなことをくぐりぬけたものだ、笑って済ませたくなる。
92歳で亡くなった歴史家、渡辺京二さんはよく、「苦労が身につかない」と、おっしゃっていた。多感なティーンエイジの時代に、戦後の満洲引き揚げとそれにまつわるさまざまな作業と個人的状況を経験され、熊本に帰還、ナンバースクールに進学したら結核で何年も入院、治療として右側の肋骨を除去、みずからの信念を貫くための資金的苦労、運動を主導する苦労、家族を支える苦労、いやもう、苦労には事欠かない人生ではないか、と、話をきいていると、思わずにはいられないのだが、そういった数々の苦労が「身につかなかった」とおっしゃるのは、実に爽快な感じだった。渡辺京二さんのことについては多くの方が書かれているし、追悼文も多く出た。私も親しくお目にかかる機会があるほうだったのでその姿は今もありありと目に浮かぶ。私の持っていた渡辺さんの印象は、笑顔のすてきな、チャーミングな方、少年のようにかわいらしいところがあり、センスの良いジェントルマン、というものだった。苦労人に、確かに、見えていなかった。
東洋のパリと呼ばれた大連で育つ。大連は本当に美しい街だった、という渡辺さんのことばに、私も行ったことのない大連に思いを馳せ、憧れた。大地に沈む真っ赤で大きな夕陽、からりと晴れ上がった高く青い空。整然とした美しいヨーロッパ風の街並みと、アカシアの花。京二少年はそこで、母や姉たち、素敵な女性たちに囲まれて、誠に幸せな日々を過ごす。幸せでおっとりと育てられた人は、とりわけ母や周囲の女性たちに本当の意味で愛されて愛でられて育った人は、そのゆったりとした雰囲気を生涯まとわせているものだ。京二さんはそういう人で、どんなその後の苦労も、その紳士ぶりに影響することはなかったのであろう。すてきなことだ。
離れた視点でみれば、人生は喜劇、を渡辺さんはよくわかっておられただろう。稀代の読書家であり、文筆家であったのだから。ものを書く、ということは、ロングショットの視点を携えることである。目の前のことだけ見ていては、書けない。視点をぐっとロングショットに引いて、自らのものがたりに作り直す。これはフィクションを書く時だけではなく、ノンフィクションを書くときでも、どんな短いものを書くときでも、変わらない。素材として見ているものは同じでもそこから視点をひいて、どのようなストーリーとして提示するか、提示できるか、ということが書き手の力量なのだ。それは書こうとしていることに対してロングショットの視点を持つ、ということにほかならないのだ。
某年某月某日、私がある人物を訪ねてしかじかの話をしたということが仮に叙述にあたいし、また仮にその談話の内容、その背景や場の雰囲気が忠実に再現されたとしても、その時の私の生の現実は会談自体よりずっと複雑多面的であり、そんなものからやすやすとはみ出してしまうのだ。
私はその会談が行われた一室の窓から、庭の木立の上にかかるひとひらの雲をみたかもしれない。そのことの方が会談自体より私の生のゆたかな実質だったかもしれない。だとすると、その会談を双方に日記の記載などから事実として確定し、そのような事実の取捨によって文脈を形成してゆこうとする歴史叙述は、人間の経験の総体に対して何を語っていることになるのだろうか。
人間の所有する現実、言い換えればわれわれの経験は多面的複合的かつ流動的で、それを「事実」として固定した時、すでにわれわれの生は抽象化され仮構化されている。だとすればありのままの歴史というものはなく、われわれが言葉の次元で現実を「事実」として限定し叙述した時、「歴史」は初めてわれわれの視野に出現したと言えるのだ。[1]
「だから、歴史は物語である」、と、渡辺さんは書く。「事実」というものは確かにあり、日記や記録をはじめとした資料は存在する。そこからなにを言葉の次元で限定するか、それは、歴史を叙述するものの力量に任される。そのときの、経験の総体に近づくことはできなくても、視点を引いて、生き生きと物語としての歴史をたちあげることはできる。
本を読む、物を書く、ということは、ロングショットの視点を持ち続ける、という作業なのだ。すぐれた、書かれた「歴史」でさえも、また。思えばそれは、演劇や舞踊や音楽や・・・全ての人間の創作に共通する視点なのかもしれない。アートとクラフトの違い、文学とそうではない記録記事文章のちがい、などについていろいろに議論することはできるけれども、それは、視点の持ち方なのかもしれぬ。目の前に必要とされているものを、目の前の視点で叙述し、また、つくりあげることは、芸術ではなく、生きていくための作業、それを視点を引いて、その人の視点であるロングショットで捉え直したビジョンを形にしていくことが芸術。そうなのかもしれない。
目の前のことは悲劇、ロングショットで見ると全て喜劇。さらに、このロングショットの視点は、「あの世」の視点、神の視点、のことなのかもしれぬ。あの世が存在するのかどうかだれにもわからないが、人類の多くが考え感じ、つたえてきたところによると、この世、とは違うあの世、というのがどうやらありそうだ。それは空の上にあり、海の向こうにあり、お天道さまのそばにあるか。私たちは、この肉体と魂を持って生まれてきており、魂を磨き、あの世にもどることがやるべきことのようだ。魂をよく磨いているか、魂がどういう経験をしたか、生きた人間としてなにをやっているのか、あの世の視点からすれば、興味あることであろう。神の視点からすれば、いかなることが起こっていたのか、いかなることを経験して成長したのか、ということだから、どのようなことが起こっても、興味を持って眺められる、ということであろうか。
つまり一人の人生は、神の視点、あの世の視点からすれば、全てエンターテインメントで喜劇なのであろう。そのあの世と神の視点のしくみを、小さなレベルで提示しようとしているものが、いわゆる私たちの作る芸術作品であるか。どんなことも、映画や戯曲や演劇や小説になりうる、それは芸術が神の視点の体現を示していること、とも言えるのだろう。だから、芸術に親しむことは、人生の苦難を乗り越えていくよすがとなり得るのである。神の視点に助けられることだから。