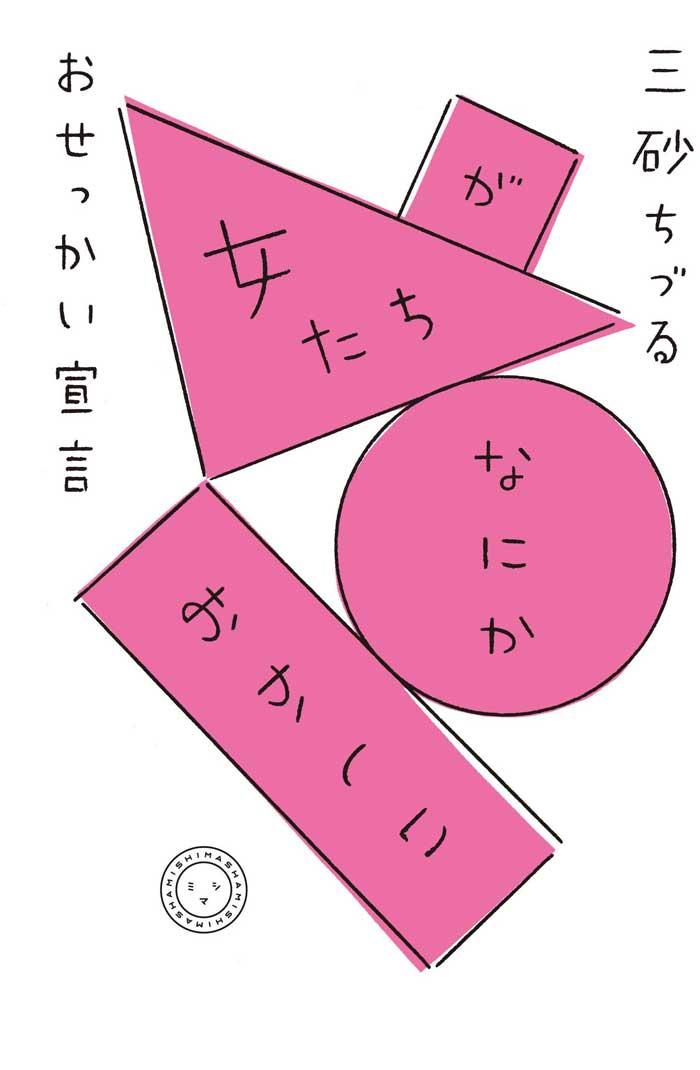第123回
グローバルとインターナショナル
2024.11.21更新
気にはなっていた。「国際保健」が「グローバルヘルス」と呼ばれるようになることである。国際保健、は、英語で言うともちろんインターナショナル・ヘルスなのであって、インターナショナル、であるからには、各国家間の思惑とその関係とその結果がヘルス、つまりは健康に大きく影響をしている、ということが一言で表されているのだ。
「国際保健」とか「グローバルヘルス」とか言っても何のことかわからないかもしれない。これは、世界の健康を考えていく、という分野であり、世界の健康を考える、ということについては、医療が発展していてどんな時でも病院に行けたり、行きたくない時は行かないで自分の健康な生活を選び取れたり、そういうところに住んでいる人にとっての健康を考える、ということではなくて、やはり、近代医療の恩恵を十二分に受けられない人がそれらを望めば受けられるようになる、ということを意味している。だから、いつも健康格差の問題であり、健康指標の問題なのであった。いうまでもなく、アジア、アフリカ、ラテンアメリカ、と長く発展途上国、と呼ばれている国の医療をどのようにするか、ということに他ならなかった。
もともと医療の十分でない地域は熱帯、亜熱帯に広がっていることが多かったから、第二次世界大戦後、1960年代くらいから「国際保健」という言葉が出てくるようになるまでは、この分野は「熱帯医学」と呼ばれていた。いうまでもなく植民地を持つ国々が、植民地である熱帯地方の医療を研究する、という分野であったわけだ。熱帯医学は、熱帯地方における医療のことではあるが、そもそも熱帯地域の多くは、構造的に植民地として支配されていった国が多かったわけだから、支配と被支配、搾取する側とされる側、という関係が影響しないはずがない。熱帯医学、とは言っても、医学研究だけやっているわけにはいかないのは、病院を建てるということ一つとっても、搾取する側の思惑と善意に頼っているなどという状況で、医学研究の成果が現実の住民の健康に反映されるはずもないからなのである。ここには、「公衆衛生:Public Health」とか「衛生:Hygiene」とかいう医学をもっと広く考える概念が必須であった。一対一の患者と医療者の関係だけで治癒を考えていくのではなく、集団としての健康を考える分野が公衆衛生であり、日常的な清潔や健康を守ることが衛生、である。
日本にいると、公衆衛生、衛生、といわれてもイメージは湧きにくい。新型コロナパンデミックを経た今では、どうやら保健所がやっていることらしい、ということは把握されてきたようだが、日本でこの集団の健康を扱う公衆衛生という分野が、「医学部:Medical School」の一部にしか存在せず、しかも、脳外科、心臓外科をトップとする医学部のハイアラキーの中で、見事に底辺に位置する講座であったため、公衆衛生の重要性についての認識が、歴史的にも現実としても生まれてこなかったのである。健康の問題を集団でとらえ、学際的に研究していく公衆衛生は、欧米では、Medica Schoolとは別に、Public Health Schoolすなわち公衆衛生校として独立している。多くのPublic Health Schoolは大学院であり、医療を医学的な問題だけではなく、社会科学、人文科学を総動員して社会的に医療と健康のありようを考える場となっており、ある意味、Medical Schoolつまりは医学部の良き牽制役になっていたりする。この公衆衛生校が歴史的に発展してこなかった日本なのだが、さすがに2000年を過ぎて学術会議あたりから提言がなされて、公衆衛生校構想というのができて、東大、京大をはじめとして幾つかの大学で公衆衛生の学位が取れるようになってはいるが、学生数も少なく、保健所に就職するわけでもない、ということで相変わらずマイナーな分野として終始してきて新型コロナパンデミックを迎えたのである。
世界の7つの海を制覇したといわれた大英帝国の名残を残すロンドンには、世界のトップ公衆衛生校の一つであるといわれるロンドン大学衛生熱帯医学校(London School of Hygiene and Tropical Medicine)があった。ここの名前は文字通り、熱帯医学と衛生、である。そしてここは、1960年代以降、ずっと「国際保健」の研究をリードしてきたところでもあった。1980年代おわり、公衆衛生校のない日本で、東京大学に国際保健の大学院を作る、ということになり、視察に人が派遣された先の一つもこの学校であり、現在もSchool of International Healthとして、医学系研究科の一つとして残っている。
1980年代始めには、「日本国際保健医療学会」ができて、日本における国際保健関係者の拠り所となっていく。学会の英語名は"Japanese Association for International Health "から"Japanese Association for Global Health"へ改められた。こちらの方が、海外から見た時、グローバルヘルスのアカデミア集団として認識されやすい、ということであるようだ。そもそも、冒頭で書いたように、世界の認識は「熱帯医学」から、「国際保健」へ、そしてそこから「グローバル・ヘルス」へ、と発展していき、さらには「プラネタリー・ヘルス」の時代である、ということで日本の熱帯医学研究拠点の一つだった長崎大学にはプラネタリー・ヘルスの拠点もできているくらいである。「国際保健」という言い方が植民地時代の発想、つまりは、先進国側が途上国側を支援する、という枠組みに抜き難い印象がある、という解釈もあったらしい。
というか、今となれば、そういうもっともらしい理由をくっつけて「国際保健」を葬り去ったような気がする。元々の熱帯医学から国際保健の誕生自体が、植民地主義を乗り越えることだったのだから、そこに植民地主義の枠組みを固定してみること自体が、国際保健の歴史(そう長くはないが、そう短くもない。そもそも専門分野の歴史というのは、それほど長くないものも多いのだ)と実践の否定にもつながりかねない。
グローバリゼーションというかけ声がかかり始めてもうすでに20年近く経つのではないかと思うが、グローバリゼーションとは、世界の近代化とは西洋文明の世界制覇であることと理解することに他ならず、グローバリゼーションの波というのは16世紀以降何度も世界を襲っているので珍しいことでもなく、今回が究極の形であることは明らかである。西洋の生活様式、言語、生産様式、思考の過程などが世界基準になっていくことがグローバリゼーションである。人権が保障され一人の人間が参政権、生存権、教育権を国家から付与される代わりに納税と防衛の義務を持つ、というありようは、一人一人の人間がどこかの国家の国民という存在形態をとらなければならない。この考え方自体も、その基礎となる国民国家自体も西洋で生まれたものであり、グローバリゼーションとはその広がりのことである。
世界の近代化は、疑問を呈する余地なく、良きことであった、と肯定されなければならない。いくら、その弊害が人間と地球にダメージを与えようと、間違いなく、この西洋的近代化により、人間の衣食住は画期的に向上したのであるから。そしてこの生活の向上と貧困の克服は自由な市場経済の活性化とそれこそグローバル化によって成し遂げられている。つまりは資本主義経済の恩恵なのであり、経済、というものに支えられている。私たちのこの豊かな生活、あるいは、豊かに向かおうとする生活は経済に支えられており、その経済は一国では成立せず、世界と連動しており、そしてその世界経済のユニットは、それぞれのネイション・ステイトである、ということになる。グローバリゼーションは世界が一つになることではなく、世界のネイションステートの競争、つまりはインターステイトシステムの強化につながることは不可避なのである。渡辺京二は、インターステイトシステムの強化を衣食住の豊かさをもたらした近代社会の"呪い"と言っているが、誠にその通りと思う。
そう思うと、健康、保健の分野も、ウィルスや細菌がそういったインターステイトシステムを無視して世界に広がっていくから、グローバルヘルスと呼ぼう、と牧歌的なことを言っている場合ではなかったのであり、インターステイトシステム間、つまりは国家間の競争が激烈になっていく中で、いったいどのようにすれば世界の人の健康を守れるのか、という、世界の経済主義に対峙しようもなく対峙する、というささやかな抵抗としての「国際保健」という言葉を死守するべきではなかったか、などと考えるのである。