第124回
思いつき
2024.12.16更新
ふと、思いつくことがある。クラシックのロシア五人組、ってだれだったっけ。ムソルグスキーとボロディンとコルサコフと・・・実はこれは私の思いつきではなく、村上春樹の小説の中に出てくるのだけれど。
ついこの間まで、こういう思いつきについて、わたしたちは結構必死で考えたものだ。だれだっけ、だれだっけ、えっと、あれ、なんだっけ。思い出せる時もあったし思い出せない時もあった。それでも思い出せない時は、資料を探しに図書館にでかけたりしたこともあった。人に聞いたこともあった。解決することもあった。しないこともあった。
いまはちがう。ご存知のように、何か、ふと思い立って、思いつくと、すぐにパソコンに向かう。えっとフランスでAbortion pill (中絶薬)って呼ばれていて、RU486って呼ばれていた薬は何年に使われ始めたんだっけ? 90年代になる前だと思うけど・・・、みたいな例えば講演に必要な知識は、googleがすぐに答えてくれる。近年は生成AIがどんどん賢くなっていくようで、何か検索すると、仮想空間上に存在する膨大な人類のデータの中から適切なものを見つけて文章にして、提供してくれる。
いわゆる、伝統の知恵、とか、職人技のようなものも、もちろん実際に見ないとわからないことの方が多いし、年季を重ねないとできないことも多いのだが、多くの技能についてはすでにネット上に文章や映像で上げられていることが多く、これはどんなものだったのだろうか、について、おおよそのことは知ることができるようになっている。一番知識が集積され、使われているのは、まずは、料理だろう。
料理は経験則だった。親や周囲がやっているのを見て、自分もやってみる。試行錯誤を重ねて、なるべく自分の好みになるように、自分の周囲の人が美味しいと言ってくれるように、作り上げていく。家庭の味、母親の味、などというのもそのようにして作られていったのだ。郷土料理もまた同じ文脈で、その土地の人が他とは違う独自のやり方で作っていったものを、そこの土地に行けば学ぶことができた。今は違う。あ、この料理を作りたい、と思えば、ネットで検索すると、山のようなレシピが上がってくる。人々の経験と知恵の蓄積から最も美味しい作り方を瞬時に探り当てることができる。
先日、竹富島にやってきた客人たちが釣りに行って、エーグヮー、すなわち、アイゴをとってきた。沖縄のエーグヮーは正式にはシモフリアイゴという魚らしい。ヒレに毒がある。客人たちはアフリカとかラテンアメリカとかでディープなフィールドワークを何十年続けてきたタフな人たちだったから、抜かりがない。竹富にも、ナイフや鋏や鱗取りを持ち込んで、釣った魚は海で捌いて持ち帰ってきた。エーグヮーもきれいにヒレを切り取り、お腹をきれいにした状態ですぐ料理できるようになって家に届いた。エーグヮーはマース煮が一番だよ、と島の人に聞いた。マース煮は、もともと、海の水でそのまま魚を煮ていたようだ。それでもきっとすごく美味しいだろう。塩だけで煮ても十分美味しい。でも、さっと「エーグヮーのマース煮」で検索すると、泡盛と昆布を入れよ、と書いてある。沖縄の昆布の使い方は、「食べる」ことである。出汁を取るだけではない。多くの汁や煮物、炒め物にして食べる。食べるから、本土で使うような硬くて立派な出し昆布ではなく、おそらく昆布としてはランクは落ちるのであろうが、柔らかくてすぐ戻り、すぐ食べられるような昆布がたくさん使われる。この柔らかい昆布をちょっと水につけて、結び昆布にしてエーグヮーのマース煮に入れた。レシピ通りのマース煮は夢のようにおいしくて、文字通り骨しか残らなかった。
これはスピードが上がった、ということだ。人類の集合的無意識からなにかとりだすことのスピードが。大きな図書館に出かけなくても、知の巨人のような人にたずねなくても、霊能力者に頼らなくても。コンピューターというのがもともと人間の脳を模して作られたものだ、というのはよく言われていた。コンピューターそのものが一人の人間の脳のようなものであって、デスクトップなどに上がっているものはいつも意識の表層にある。しかし、忘れている、と思っても、探していけば、自分が記録したもの、自分が書いたもの、自分が残しておいたもの、は、パソコンの中にある。探しにいけば見つかるのである。それは人間の脳の働きと同じなのだ、という説明がよくされていた。
1990年代に入ってインターネットの時代が始まり、仮想空間上に多くのものが存在するようになった。パーソナルコンピューターから、直接、人間の知識と知恵の集積にアクセスすることができる。これも、人間の脳と人間の精神的な働きを模したものなのだから、これは文字通り、人類の集合的無意識へのアクセスを形にしたもの、といえよう。ユングは集合的無意識を個人的な経験に由来するものではなく普遍的に同じ民族、種族、あるいは人類に共通して伝えられている無意識である、といった。つまりは人類が始まってからの知恵と知識の集積である。一体これがどこからくるものなのか、私たちはまだ、"科学的"には証明できていない。
私たちは生きている間にはいろいろなことを考える。いろいろなものを作り上げる。死んだら、それらはなくなる。私という存在とともに、なくなってしまう。しかし、この集合的無意識、は、そうではない、と言っているわけだ。生きていた人間が考えたこと、作り上げたこと、共に達成したことは、人類の集合的無意識として蓄積され、それが出会ったこともなかった個人の上に現れることがある、と言っているわけである。これはもう、アカシックレコードとか、スピリチュアルとか言わなくても、そういうものなのだ、ということだ。そして、このインターネット仮想空間、というのは、その人間のありようを模して作られている、ということだ。結果としてなのか、意識して、なのか、今の私にはわからないが(誰か説明可能なのだろうか?)。
集合的無意識から何かを取り出せる人は天才、と呼ばれた。音楽も、絵画も、文学も、才能と力量があり、集合的無意識の領域に行って、戻ってくる人ができる人が、その人類の懐かしい記憶を一人の個人の力量でまとめ上げて世に差し出す、それが芸術というものだったのだ。
マイケル・ジャクソンと村上春樹がよくわかるように説明している。マイケル・ジャクソンは言うまでもない天才で、現在のポップミュージックも、ダンスも、マイケル・ジャクソンなしにはありえない。あれほど世界を席巻したKポップの成功グループBTSのスタイルも、元々、マイケル・ジャクソンである。歌と踊りとパフォーマンスが凄すぎて、マイケル・ジャクソンが作詞作曲していたことは踊りほどには知られていないが(音楽好きや関係者には、もう、あまりによく知られていたことであったが)、ほとんどの彼の曲は彼が自分で作っていた。そのことについて彼は、谷に降りていって、美しい川があって、そこに行くと、"音楽"が、ある、そこにあるものを自分が拾ってきて、そして、それを曲にしている、ような感じ、だから、本当は、その音楽にマイケル・ジャクソン作、って書いていいのかな、と思ったりする、と語っている。
村上春樹は、自らが人間が文字を発明するより前からずっと行っていたストーリーテラーの末裔、とよく言っており、人々が焚き火の前に集まっていて、お話を語って聞かせる人がいる、自分が小説を書いているのも、そのようなもので、焚き火の前に集まっている人を想像することがある、と書いていた。人類の集合的無意識とでも言えるところまで降りていって、人類の物語にアクセスし、そして戻ってきて、それを小説、と言う形で書き上げる。それはとても体力のいることだから、彼はずっと体を鍛え続けていた。村上春樹との対談で作家の川上未映子が、このことを、二階建てで地下二階のある絵を描いて、見事に絵で説明している。私たちの現実の日々の暮らしは「お家の一階」で行われている。二階には自分の部屋があって、そこに自分の好きなものを並べたり、好きなことをしたりしている。地下一階は、近代的自我とでも言うべき部屋で、自分が生まれてきてからの自我の傷とか、周囲との軋轢でできた自分、とかの部屋で川上未映子は「クヨクヨ室」と命名している。日本近代文学の私小説などは、この「クヨクヨ室」の描写によって生まれてきたものだと言う。しかし、「お家」には、さらにもう一つ地下室がある。その地下室が「集合的無意識」の場所である。人類が始まって以来の様々な個人的な記憶の表層には立ち現れないような世界が、そこには広がる。村上春樹の小説は、そこに降りていって、二階に戻って、自分の部屋でそれを書く、という作業をしているようなものなのだ、と。確かに、体力がいる。
かように、優れた芸術家は、この集合的無意識の世界とのアクセスを、天性によって、あるいは不断の努力によって続けることができた人、ということであろう。意識している、していない、を別にして。そしてそれは容易なことではなかったから、命もかけなければならないようなものだったから、いわば「素人」が簡単にアクセスして同行するなどということは、能力的にまずできないし、やってしまったら危険なことでもあったのだ。
この集合的無意識が、仮想空間にかなりの範囲で形として存在するようになり、それを個人がすぐに探しに行けるようになった今、それは確かに、個人としてのスピードが上がり、個人としての力量が上がり、個人として、生きている間にできることが多くなった、ということだろう。スピリチュアルに人類の古層にアクセスしながら生きる、という特別な才能の持ち主しかできなかったことが全ての人間に開かれる。ある意味、現在はスピリチュアリティの俗化の時代だ。皆がスピリチュアルなことに興味を惹かれていくのも、当然のことといえよう。これはやはり加速しているとしか言いようがないが、その扱いについて、様々な危険もまた指摘されていることは今更いう必要もあるまい。
直感と、思いつきと、そこにつなげられるべき集合的無意識の領域がぐっと近づいていること、これを本来の意味での人間的成長につなげられるかどうか、と言うことは、やっぱり「お家の一階」で行われている、日々の暮らしや現実との格闘にしか、存在しないのであろう。



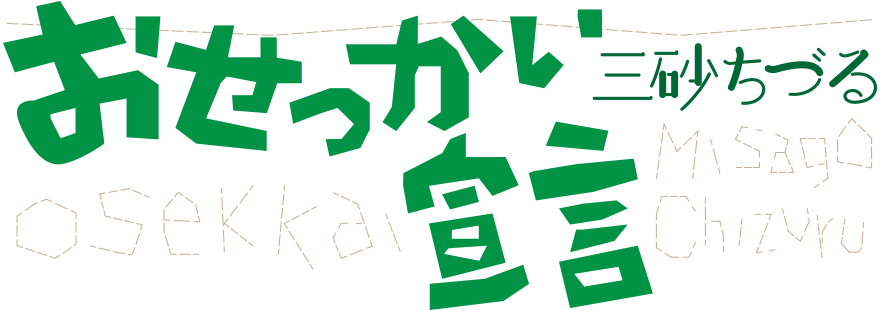

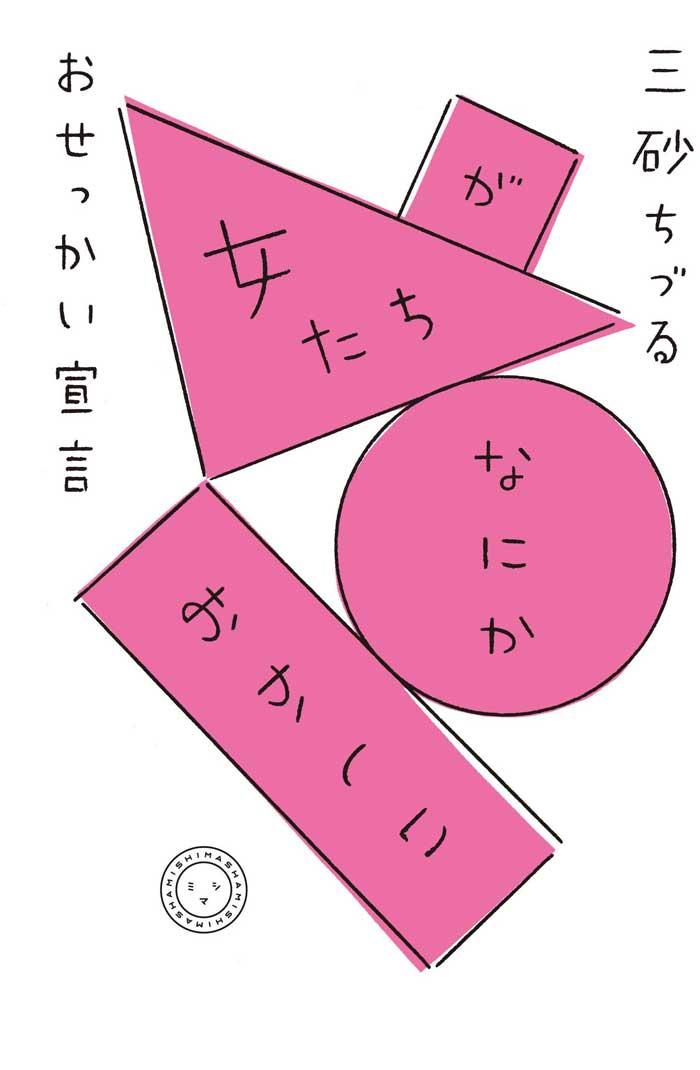
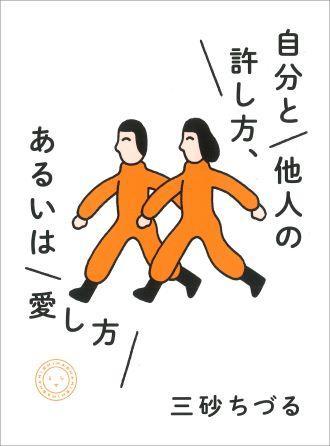

-thumb-800xauto-15055.png)



