第125回
Single story
2025.01.21更新
WHO(World Health Organization:世界保健機構)ジュネーブ本部が2003年に"A tale of two girls"(二人の女の子の物語)と言うスライドクリップを作っていた(現在はアクセス不能である)。世界の健康格差を理解するために作られた、ということで、日本の熊本に生まれたアイコという女の子と、シエラレオネのフリータウンに生まれたマリアムと言う女の子の二人の人生を年代ごとに対比させた物語になっていた。当時のシエラレオネの平均寿命は、世界でも最も低く、38歳だった。日本は、女性の平均寿命は85歳で世界最高レベルである。
九州在住のアイコは、産科医、看護婦などプロフェッショナルがずらりといる私立病院で生まれる、マリアムは低体重でビタミンも足りないが、出生時には生き延びた。6歳になったら、アイコは予防接種も終えて小学校に通っているが、マリアムは予防接種も受けられず、学校にもいけなかったが、お友達の十人のうち三人はマラリアとか麻疹とか栄養失調で死んだのだからラッキーな方だった。17歳の頃はアイコは高校3年生、医者になりたいという夢がある。マリアムは17歳で子供を産んだ。その一年前にも最初の赤ちゃんが生まれたが、その子は生まれてすぐに死んでしまった。アフリカでは毎時間五百人の母親が妊娠によって子供を亡くしている。30歳、アイコは最初の子どもをトップレベルの妊婦健診とサポートを受けたあとで生む。彼女自身もその病院で働く小児科医である。マリアムはHIV/エイズの症状が出て、具合が悪い。夫から感染した。薬も手に入らず、子どもの面倒を見ることもできず、働くこともできない・・・。36歳、アイコは子宮がんや甲状腺機能などの検査を受けている。この年齢の多くの日本女性がそうであるように、異常はない。マリアムは今日36歳になるはずだったが実は2年まえにエイズで亡くなってしまった。たとえエイズにならなかったとしても別の病気でなくなっていたかもしれない。80歳、アイコは老人ホームで80歳の誕生日を迎える。日本女性の平均寿命からするとあと5年くらい生きられるだろう。マリアムは貧困とネグレクトの犠牲になってしまったのだ・・・。
最初に見た時から、無性に気分が悪かった。女性の持つ力を活かし、生まれてくる赤ちゃんの力を最も生かすことができるための出産のありようを、世界でも日本でも追求してきた。精緻を極めた(不要なこともある)医療介入を推し進め、女性に医療がないと子どもは無事に産めない、と不安にさせるような方向ではなく、「出産のヒューマニゼーション」という、人間としての産む力、生まれる力を活かし、何かあったら助けてもらえる、そういうスタンスの産科医療のあり方を探ってきた。生物としての人間の、限界と可能性を追いたい、と思っていたのだ。日本の病院でも、見かけの立派さとか、入院中に出されるごちそうとか(多くの場合は母乳哺育にはあまりよろしくない)、女性の声をきく、という美しい言葉で、女性を好きなようにさせるが、産む女性としての本来のエンパワメントとは方向が違う・・・などという違和感を感じる病院は少なくなかったが、ビデオクリップで取り上げられている病院もそのひとつだったこともある。
平均寿命というのは、その国に住んでいる人が大体その年齢くらいには死んでしまう、という性格のものではない。平均寿命とはその時に生まれた0歳児が何歳まで生きることができるか、という指標であり、乳児死亡率、すなわち一歳までに何人の子どもが亡くなってしまうか、という指標に大きく影響される。乳児死亡率が高い国では、平均寿命はとても短くなってしまうのだ。今、生きている人がその年齢までしか生きられない、ということを示しているわけではない・・・ということを学生にも、いつも説明してきたから、その違和感もある。
しかし何より、気分が悪かったのは、その「ステレオタイプ」な見方であった。日本人として、日本の扱われ方も、ただ、気分が悪かった。揶揄されている、と感じた。極東の日本、経済的にも発展して、医療も発展している日本、女性の平均寿命は世界一っていうから、まあ、こういう生活なのよね、みたいに言われているような気がした。これはジュネーブで作られたビデオクリップだが、ヨーロッパ人は自分たちを同じようなモデルにして、ビデオクリップを作るだろうか。絶対に作らないと思う。"西洋側"にいる人たちは自らをそういう「ステレオタイプ」におくことを嫌がるからである。だって、文化と多様性を重要視する民主主義の国なんだもん。これが代表的な、この国の女性の人生、みたいな取り上げ方ができるのは、日本を躊躇いもなくそのステレオタイプに押し込めることができるからなのだ。
シエラレオネ側についてはいうまでもない。私がシエラレオネの政府関係者、保健省関係者であったら、即刻、WHOに抗議したことであろう。一体どういうことか、私の国の女性たちをどうすればここまで侮辱できるのか。マリアムの人生は厳しいものだったかもしれないが、彼女にも彼女の喜びがあり、人生があったはずだ。貧しくてミゼラブルで虫けらのように死ぬ人生だった、と、誰の人生をも総括できない。彼女の目に映った緑の美しさや、胸に浮かんだ人を愛する思いや、生きることへの敬意が、彼女の人生を生きるに値する時間にしたはずだ。
セネガルの作家、チママンダ・アディーチェの「シングルストーリーの危険性」[1]は素晴らしいスピーチだった。あるアメリカ人の学生が、セネガルの男性たちはあなたの小説に出てくるみたいに、すぐ女性を虐待するんでしょう、というのを聞いて、アディーチェはあら、私、最近、「アメリカン・サイコ」を読んだんだけど・・・、と返す。みんな一瞬にして彼女が何が言いたいのかがわかり、自らの言ったことに気付いたようだった。
アメリカン・サイコには猟奇的なアメリカの若者が出てくる。でも、私たちはアメリカの若者たちすべてが異常な性癖の持ち主で、精神にトラブルを抱え、異様な行動に走るサイコティックな人たちだ、と映画をみて、思うわけではない。それは私たちは、「アメリカ」について、実に多様なストーリーを知っているからだ。繰り返し流されるアメリカのニュース、多彩に展開されるハリウッド映画、フィッツジェラルドや、ヘミングウェイや、サリンジャーが多様なアメリカの若者たちを描いたものを読んでいる。ディズニー映画や、多彩な娯楽を通じて、「好きなもの」がアメリカにあることを知り、憧れている。そこには広大な自然と人々の織りなす多彩なストーリーがある。多様で色とりどりのストーリーが可能になる、ということがアメリカン・ドリームだ、と知っている。
だから「アメリカン・サイコ」を読んでもアメリカの若者すべてが、異常な人たちだと思わないのだ。あ、これはすごく特別なケースを取り上げて小説にしたんだな、と思える。それなのに、なぜアディーチェのえがくナイジェリア人の暴力的な男性の様子を読んで、全てのナイジェリア人がそういう人たちだ、と言ってしまうのか。それは私たちがナイジェリア、というアフリカトップの、世界で六番目の、2億を越える人口を抱えるアフリカの大国の多様さを知る機会がなく、大きく「アフリカ」とひとくくりにして、「貧困と内戦と女性抑圧の大陸」というストーリー、つまりはシングル・ストーリーしか持っていないからだ。
それに気づくと、なぜ"Tale of two girls"で、「指標の良い国」と、一見"ほめられている"ように見える日本の側から見ても、大変気分が悪かったのか、その理由が見えてくる。そこに描かれている日本は、西洋から見て「日本というシングル・ストーリー」つまりは、ちょっと前まではフジヤマ・ゲイシャの国、現在は、ハイテクノロジーと経済成長の国、男女ともに教育レベルは高く、平均寿命の長い国、しかし、女性はとっても差別されていて、男は死ぬまで働いているような、人生を楽しむことなど知らない国。もっと最近になると、アニメとゲームのエッジの効いたコンテンツを輩出する国・・・、であろうか。どちらにせよ、ある「ステレオタイプ」である。そこには、「あんたたち経済的にはうまくやってるだろうけれど、がむしゃらに働きすぎて余裕なんかないわねえ」とか、「医療のレベルは結構いいらしいけど、人間的に生きる、とかあんまり考えてないだろう」とかいう、西洋的な日本への偏見と、さらに自分達とあんたたちは違う、という優越的な姿勢がほの見えるからである。
人のせいにばかりできないのはもちろんで、それらの西洋的な他の地域をシングル・ストーリー化する眼差しは、深く私たちの間に染み込んでいる。アフリカを見る目、東南アジアを見る目、ラテンアメリカを見る目として表出する。バイオリニスト黒沼ユリ子が1980年にだした新書『メキシコからの手紙』[2]は心に残る名著である。メキシコ人の人類学者の夫と、息子と三人でメキシコの辺境で暮らす様子は個人的にも深くその像が刻まれ、10年ほど後には、全く同じようにブラジル人の公衆衛生学者の夫と息子と共にブラジルの辺境で暮らすことになっていた、という自分に気づくほど、大きな影響を与えられた本である。黒沼ユリ子さんの当時のメキシコ人の夫は、メキシコにすごくたくさんいる、いわゆる「白人」のメキシコ人である。ところが日本のメキシコ人のイメージは、やや褐色の肌、ソンブレロにポンチョ、みたいなメキシコ人である。日本で夫と一緒に歩いていても、アメリカ人ですか? ヨーロッパ人ですか? と聞かれ、メキシコです、というと、えっ・・・という顔をされるということを書いておられた。私も同様の経験がある。
ラテンアメリカのどこの国にも宗主国スペイン、ポルトガルの末裔のみならず、西洋諸国からの移民が多く、いわゆる「白人系」の人はたくさんいるのだが、私たちは、シングル・ストーリーから抜け出せない。黒沼ユリ子の本が書かれて45年の歳月が流れているのだが、まだまだ抜け出せない。
[1] チママンダ・アディーチェ: シングルストーリーの危険性(TED)https://www.youtube.com/watch?app=desktop&client=mv-google&hl=ja&gl=KE&v=D9Ihs241zeg&fulldescription=1 2025年1月9日
[2] 黒沼ユリ子「メキシコからの手紙 ―インディヘナのなかで考えたことー」岩波新書 1980年



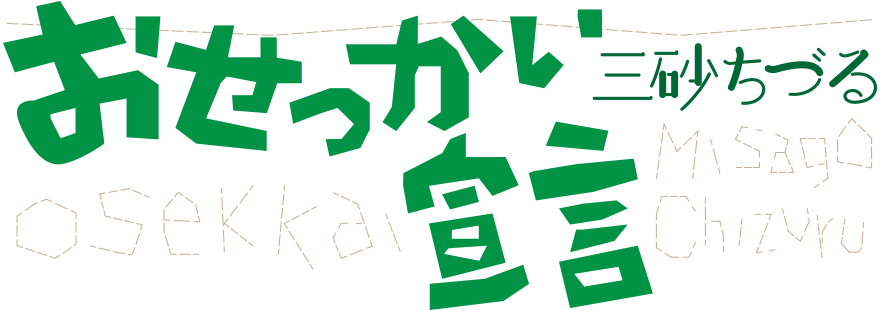

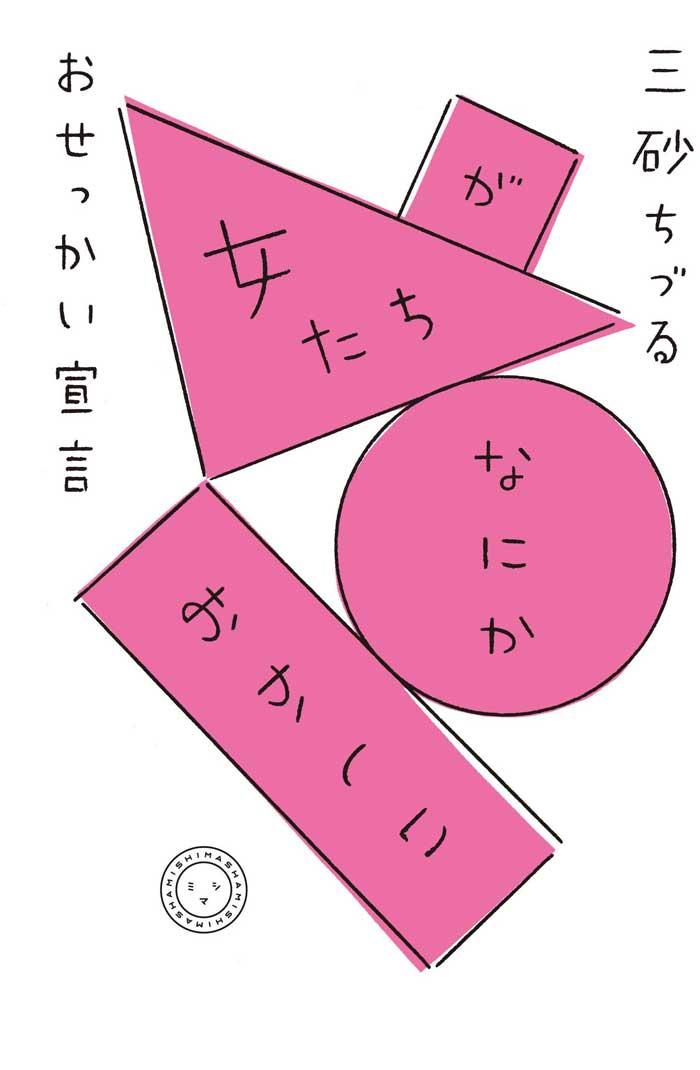
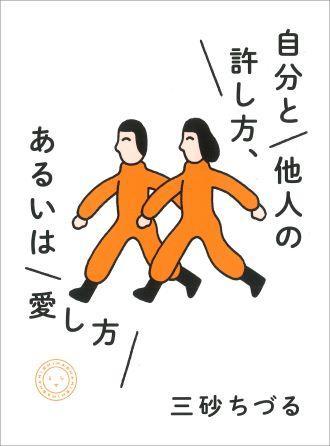

-thumb-800xauto-15055.png)



