第128回
アダン葉帽子
2025.04.16更新
帽子が出来上がった時の喜びは、ちょっと今までに感じたことのない、周囲の空気感が変わるような喜びだった。沖縄に自生するアダンの葉で帽子を作った。ものを作る、という経験は幼い頃から何度も重ねていたわけだが、これはちょっと特別な気がした。戦前には、2万人から3万人いた、というボーシクマーと呼ばれる「アダン葉のパナマ帽を作る人」の歴史をささやかながら自分も引き継ぐことができるかもしれない、ということ、そういう世代間伝承を目的と祈りとして作られた「おきなわ工芸の杜」、という場にいたこと、また、沖縄にいて、沖縄のアダンで、沖縄のやり方で編み上げたということ。そして、一人ではなく、同じ思いの仲間がいたこと、そして何より、いささかの権威的な態度もまとわず、見事な伴走ぶりで帽子作りを教えてくださった聡子師範とあやこ師範代のたたずまいに見守られていたということ。それら全てが特別な時間を作り上げていて、その中で、美しい帽子が作り上げられたからこそ、とてもとても特別な思いが感じられたのだ。
本来は、アダンを編み始めるまでの準備が大変なのである。帽子にできそうなアダンの葉を採りに行き、煮て、干して、適切な幅にカットして・・・多くの工程がある。しかし、参加したコースは、すでに編むべきアダンはカットされているものが用意されていて、「たこのちぶる」(標準語翻訳:タコの頭)と呼ばれる沖縄独特の帽子の編み始めのやり方を学び、そこから編んでいって自らのサイズの帽子としていく最後までやるのが目標の4日間だった。このあふれるような喜びの一つは、「すべての工程を自分でやった」というところにあるのだと思う。これがアダン葉を採りに行くところから始めていれば、時間はかかるだろうけれども、喜びもまた、さらにひとしお、であっただろう。この、すべての工程を、自分自身で一つ一つ経験しながら形にしていくことに、人間はなんとも言えない喜びを感じるのだと思う。
沖縄のアダンを使ったパナマ帽製造は明治時代、1900年代初頭から始まったようだ。その人気により、自生していたアダンは乱伐によって材料不足に陥ったこともあったらしい。アダン葉だけではなく、紙撚(こより)原料が開発されたことにより、沖縄の帽子作りは砂糖、泡盛に次ぐ生産量まで上り詰めたと言い、1900年初頭から沖縄戦の戦時体制に組み込まれる1940年代くらいまで続いたようで、すでに書いたように、いっときは県内に2万人から3万人のボーシクマーがいたと言われる。それだけの人数が編んでいたというのに、あっという間に衰退してほとんど記憶されることがなかったことの原因には、もちろん沖縄戦があり、戦後の復興過程があり・・・と言うことがもちろんある。しかし、もう一つ重要な要因として、聡子師範は「それぞれが分業していたからではないかしら」とおっしゃっていた。帽子作りが一大産業になっていく過程で、効率が求められるようになり、それぞれの工程を専門にやる人が出てきて、その部分だけを編んでいたようだ、というのだ。
「たこのちぶる」と呼ばれる編み始めを使って帽子のてっぺんの真ん中から編み始めるのが沖縄式の特徴の一つだが、この編み始めの部分を作るのがなかなか難しい。今回の講習でもあまりに難しくて、うわあ、ここを覚えなければどうにも先に進めない、と不安に思って、時間をかけようとしたり、復習をしたりしようとする私たちに、ここにこだわっていると先に進めないから、今回はとにかく最初から最後までの行程を一貫してやることを目標にしましょう、と先生に言われ、とにかく先に進んだのである。帽子作りが盛んだった頃も、この編み始めがとりわけ難しいと言われていたようで、先輩方に編んでもらっていた人もいたようだ。結果として、大規模に帽子を作るところでは、この難しい編み始めだけやる人、帽子の天だけ編む人、胴だけ編む人、縁だけ編む人、最後に点検して手を入れる人、などを分業化していたらしい。分業は効率を目指すと実に効果的であり、その部分だけを上手になれば良いから、誰でも参入できるようになり、製品は多く作り上げられる。
これはまさに手工業が機械製大工業に向かう過程であり、カール・マルクスはその過程で人間が疎外される、と言ったのだ。一人の人間の、かけがえのない労働によってできていた一つのものを作る工程が、分断され、効率化を求められ、代替可能なある部分のみを担う職工として、目の前のさほどの技術習得も必要のない部分を、毎日、毎日、繰り返し、それだけ担当させられるようになる。自分が休んでも、他の人が容易に交代できる。自分がその仕事を辞めても、自分の代わりはいくらでもいる。そのようにして「一つのものを作ってそれを喜びとする」人は、「ある過程のみを担当して、結果としてたくさんのものが製造できるが、自分自身のかけがえのなさと、完成の喜びは付与されることがない」人になり、つまりは、人間性を疎外された労働者の列が累々と続くような働きぶりが、近代社会で働く、ということになっていき、それがシステム化されていったのが、今、である。
私たちは皆、この巨大なシステムのどこかを担うことを求められ、そしてその大きなシステムの小さな役割を担うことを、就職活動と思い、それが仕事をすることだ、と信じ、身を粉にして働き、過労死するまでその役割を果たし続けようとすることが、ごく普通のこととして日々起こっていることを目にしている。働くことは厳しいことであり、大変なことであり、お金を稼ぐことだけが目標になっていく。そのこと自体が、生きていく上でどれほど大変なことか、私たちは自分でやろうがやるまいが、よくわかっているのである。
帽子を一から編み始めて最後の工程までやり終えることは、仕事というものは、手仕事、というものは、自然から頂いた何かに人間が手を加えて、何かを自分の手で作り上げる、という原初的な喜びを取り戻すことだったからに他ならない。私たちはこの近代システムの中での労働が、自らを損なうことを本能的に知っていた。仕事と呼ばれるものはもっと喜びと達成感と協働の歓喜に包まれていたはずだ。そうであったはずだ。そうであるはずだ。それを取り返せるはずだ。何か一つを最初から最後まで作ってみれば、それを取り戻せる。
忙しい日々の中で、手仕事の復興はまことに難しい。それでも私たちは、とりわけ女性たちは、そのDNAに、つらい日々をこのものづくりの喜びで相殺しようとしていた昔の女たちの思いをいまだに忘れてはおらず、何らかの手仕事にふれると、その喜びが立ち上がってくるのである。若い人が手仕事で仕事を立ち上げていくのは難しい。しかし、すでにこの連載でも取り上げたことがあるが、年金受給年齢になって、ある程度の生活の基礎ができる60代あたりから、可能であるような伝統的な手仕事を担っていく可能性はあるのではないか。それは伝統技能継承、という意味でも、一人の人がその疎外された人間性を取り戻していく過程、と言う意味でも、再考されるに値する、と信じる。



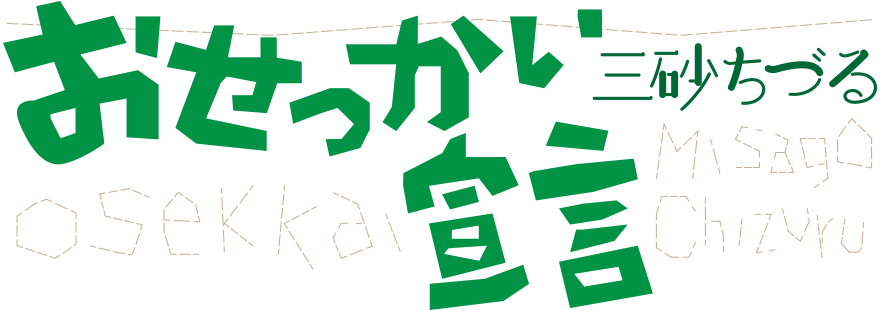

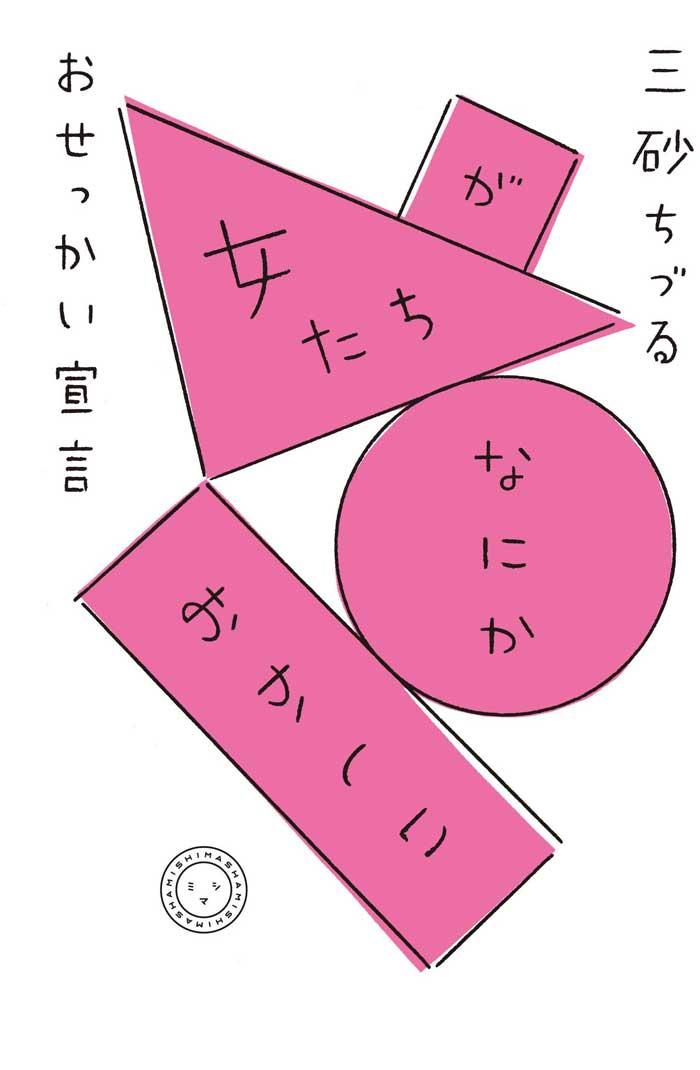
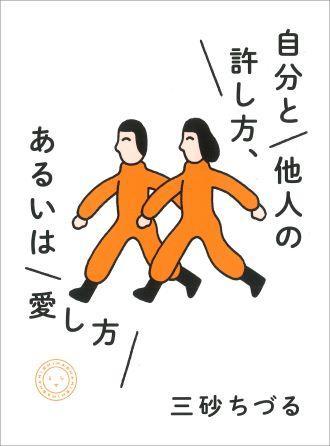

-thumb-800xauto-15055.png)



