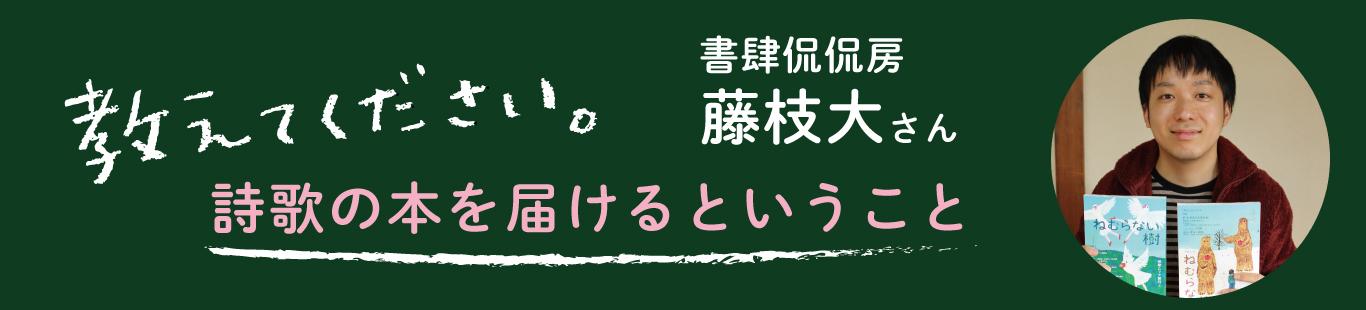第4回
書肆侃侃房・藤枝大さんに聞く 「詩歌の本を届けるということ」(後編)
2019.12.17更新
短歌の世界に新風を送り込んでいる福岡の出版社・書肆侃侃房の藤枝大さんへのインタビュー後編。本屋&カフェ〈本のあるところ ajiro〉のことから、そもそも書肆侃侃房さんが短歌の出版をはじめたきっかけ、そして多様な活動の根底にある思い・・・。ひとつひとつの営みに宿る強い思いを言葉にしていただきました。
(聞き手:池畑索季/写真:杉崎凛)
前回の記事はこちら
*** お話を聞いた人 ***
藤枝大(ふじえ・だい)さん
1989年東京都生まれ。東京の出版社を経て、2017年より福岡の出版社・書肆侃侃房で勤務。短歌ムック『ねむらない樹』などの編集、営業のほか、本屋&カフェ「本のあるところ ajiro」の運営などを担当している。
◆書肆侃侃房 http://www.kankanbou.com
常設フリマとしての〈ajiro〉――対面で熱量が伝えられる場所
―― 読者との接点をつくっていくときに、文学フリマやajiroがあると思うのですが、実際の運営はどのようにされているのですか?
 藤枝 ajiroが出来たのが2018年10月で、開店から1年ちょっと経ちました。会社としてはかなり早い段階から文学フリマに出店して直接販売するということをやっていたんです。やっぱり、熱量とともに読者に本を届けられるということがあって、「こんなにも短歌の本は届き得るんだ」「しかも若い方がこんなに買いに来られるんだ」という実体験がありました。なので、ajiroは書店ではありますが、「常設文学フリマ」と言い換えてもいいかもしれません。対面で、詩歌の魅力を相手に届けることができる。
藤枝 ajiroが出来たのが2018年10月で、開店から1年ちょっと経ちました。会社としてはかなり早い段階から文学フリマに出店して直接販売するということをやっていたんです。やっぱり、熱量とともに読者に本を届けられるということがあって、「こんなにも短歌の本は届き得るんだ」「しかも若い方がこんなに買いに来られるんだ」という実体験がありました。なので、ajiroは書店ではありますが、「常設文学フリマ」と言い換えてもいいかもしれません。対面で、詩歌の魅力を相手に届けることができる。
 自社の本を知ってもらい、他社の本も含めて分野の面白さを伝える場所。詩歌と海外文学というジャンルのアンテナショップである、というような位置づけでもやっています。ここに来れば、対面で詳しい話を聞いてもらえるし、普通の書店には並ばないようなISBNの付いていない本なども結構ある。この店で初めて海外文学や詩歌に触れたという方もたくさんいらっしゃるのは、うれしいことです。
自社の本を知ってもらい、他社の本も含めて分野の面白さを伝える場所。詩歌と海外文学というジャンルのアンテナショップである、というような位置づけでもやっています。ここに来れば、対面で詳しい話を聞いてもらえるし、普通の書店には並ばないようなISBNの付いていない本なども結構ある。この店で初めて海外文学や詩歌に触れたという方もたくさんいらっしゃるのは、うれしいことです。
―― イベントもかなりやられていますよね。
藤枝 そうですね。歌人の方が福岡に来られるタイミングに合わせて書籍の刊行記念イベントをやったりもしています。イベントや歌会にはたくさんの方が参加されますし、たとえ参加者が少人数だとしても、ものすごく豊かな場所になるんですよね。そこでお話をしてもらったり歌会をやったりする経験が、著者の方にとっても大きいのではないかと思います。
日常生活では一般の人はなかなか「歌人」に出会わないから、イベントをやることでさまざまな人が「歌人」に出会うことが出来る。ajiroっていう場所はたくさんの夢や希望や思いが詰まった場所として、かなり実験的にやっている部分がありますね。
東京や関西にいると著者の方など常日頃色んな方に会いやすい、交流もある。けれどやっぱり福岡だと、なかなかそういうわけにもいかないんですね。でも場所ができたことで、歌人の方や翻訳者の方が遠方から訪ねてきてくださったりします。多様な著者との出会いの場にもなっていて、九州でこの店をやることの意味を感じています。

一人の歌人への思いからはじまった書肆侃侃房の短歌出版
―― そもそも書肆侃侃房さんが短歌の出版をはじめたきっかけは?
藤枝 笹井宏之さんという26歳で亡くなられた佐賀の歌人がいて、その笹井さんの歌集を出したのが、書肆侃侃房が短歌の出版を始めたきっかけでした。これは私が入社する前の話です。笹井さんの短歌、読んだことありますか? 「ねむらないただ一本の樹となってあなたのワンピースに実を落とす」「えーえんとくちからえーえんとくちから永遠解く力を下さい」などの歌があります。
―― 短歌の新人賞「笹井宏之賞」を立ち上げられましたよね。
藤枝 笹井さんが亡くなったのが2009年で、笹井宏之賞の第一回が2019年。ちょうど没後10年のタイミングで、笹井さんを顕彰するために賞をつくりました。代表の思いがあって。第一回の大賞は、柴田葵さんの「母の愛、僕のラブ」に決まりました。もうすぐ歌集として刊行になります。
この賞の発表媒体が短歌ムック『ねむらない樹』です。半年に一度刊行しているのですが、まず、新しい人たちの作品を載せる場をつくりたかった。新鋭短歌シリーズから歌集を出されている著者の方たちもそうですし、学生短歌会にもすごく面白い人たちがいっぱい出てきている。結社に所属しない無所属の若い人にも寄稿していただいて。

―― 所属に関わらず、作品を世に問うことができるようにと。
藤枝 短歌に限らず昔の文芸誌などを読むと、20代の若い書き手でも自信をもって座談会で持論を展開していたりして、老成する前の、若いときだからこそ話せる内容もあると思うんです。若い歌人がいま何を考えているのか、そして短歌の現在の状況を、いかにして記録として残していけるか。『ねむらない樹』は積極的に、いまを詰め込んだ場所にしていきたいと思っています。だから町屋良平さんとか、滝口悠生さんのような作家と若手の歌人の対談を載せたり、短歌のジャンルの中でも若い歌人同士だから言えるという話を誌面に刻み込んでいっているつもりです。それは同時代の読者にとっても重要だし、あとから歴史的に見たときにも、結構大事なんじゃないかと思っていて。
来年2月に4号が出るんですが、これも面白いですよ。試行錯誤をしながら、つねに活気のある誌面をつくっていきたいです。

短歌の世界をひらく――同質性から多様性へ
―― ものすごいペースで新しい企画をやっていっていると思うのですが、どうしてそんなに次々と?
藤枝 会社としてまず、「何をやるべきか?」ということを考えているところがあると思います。やるべきことがまずあって、そこにいかに採算を合わせていくか。会社の規模によっても、やるべきことってきっと全然違っていて、10人以下の会社だからこそできることもあると思うんです。
―― 今後目指していくところは?
藤枝 「短歌の作者」の在り様のバラエティがちゃんと存在することが大事ですよね。今よりももっと色々な立場の人が色々な形で作品を世に問えるようにできたらとは思います。市場的にもある程度うまくいくことが、多様性にもつながったりする。短歌の世界のバラエティをより豊かにするためにも、ちゃんと売り、届ける努力をする。そう思ってやっています。
―― 営業努力をして、書店員さん、そして読者の裾野を広げることが、ひいては作り手の裾野を広げることにもつながると。
藤枝 小さな積み重ねが大事ですよね。こういった仕掛けを一つ一つやっていくことが、分野の活性化とか、多様な人の参入を結果的に呼び込むことになるのかな、なるといいなと思います。
―― 本を届ける者の一人として、めちゃくちゃ励みになりました。お話ありがとうございました。

編集部からのお知らせ
書肆侃侃房さんが満を持して創設された「笹井宏之賞」。記念すべき第一回の受賞作がついに昨日、書籍として刊行されました! ぜひ書店でお求めくださいませ!
---------------------------------------------------------
柴田葵 『母の愛、僕のラブ』
A5判変形、並製、128ページ
定価:本体1800円+税
ISBN978-4-86385-387-4 C0092
装画:宮崎夏次系
栞:大森静佳・染野太朗・永井祐・野口あや子・文月悠光

第一回笹井宏之賞大賞受賞!
プリキュアになるならわたしはキュアおでん 熱いハートのキュアおでんだよ
バーミヤンの桃ぱっかんと割れる夜あなたを殴れば店員がくる
エスカレーターばんばか回る 恐竜のよろこぶときに鳴る背びれたち
旧姓の印鑑は保管するべきか 土に埋めたらなにか生えそう
まひるまにほろほろと雪 生きている意味などすっ飛ばして生きたい
---------------------------------------------------------