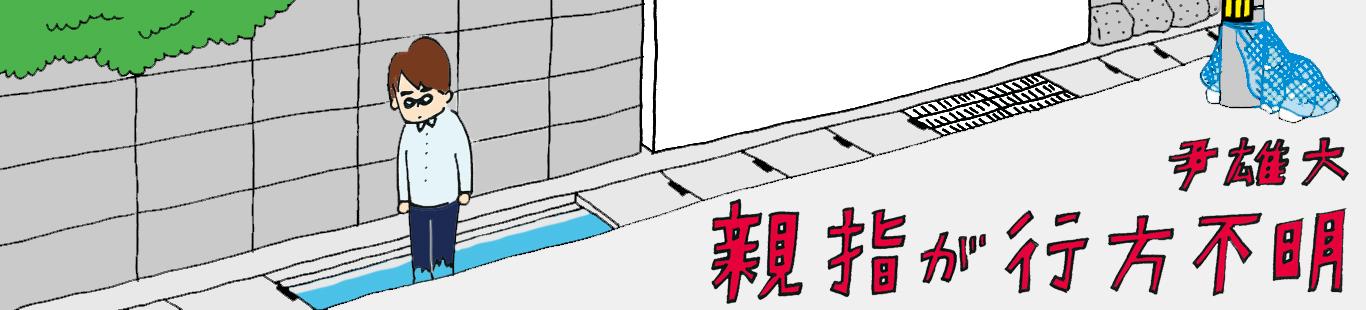第1回
非民主的でダイバーシティのない身体観に別れを告げる
2020.06.23更新
まとまらない身体
過日、『どもる体』や『記憶する体』を書かれた伊藤亜紗さんと対談した際、僕は自分の身体のままならなさについて話した。そうしたらポンコツぶりがバレてしまった。
たとえば、乗り慣れている自転車であれば、難なくまたがれるはずだし、自分でもそうだよなと思う。なのに何回かに一度、目測を誤りスネをフレームにぶつけてしまう。
飲み終えたコップを右から左へ移動させようとして、その間にあるものをなぎ倒す。もしくは手にしたコップをぶつけて割ってしまう。食事の際に、テーブルに置いたはずの箸を何度も落とす。これは力が強い人なら同意してくれるだろうけれど、手洗いした布巾やTシャツを絞ると破いてしまう。
さらには、ふたりくらいなら十分通れるはずの道で、行き違おうとしてぶつかってしまう。あるいはどう見ても通りにくいだろうというような間のほうにわざわざ入り込んでしまう。ここまで書いていて思い出したが、中学の柔道部で絞め技を知って、自分で首を絞めたら失神した。意識を取り戻した後で「普通、苦しくなったら手を離すだろう」と先輩に呆れられた。
こういった例からわかる通り、自分の行為の制御がうまくいかない。やり過ぎかやらなさ過ぎでギクシャクしてしまう。それにしても、どうしてこんなにもまとまらないままで動いてしまうかといえば、僕の身体の各々がはみ出ていたり、引っ込んだり、痛んだり、よそよそしかったり、空くような感覚があるためだ。それが足を引っ張っている。
指や足の言い分
ところで「身体の各々」と書いたのは、「部分」とか「パーツ」という名付け方では捉え切れないし、「そうしないほうがいいのではないですかね」という意見が示されるからだ。
誰からの提案? と聞かれたら、「指だとか足だとかですよ」と真顔で答えざるを得なくて、実は僕の指や足がそう要望してくるわけだ。
何を言っているのだ? と思うかもしれない。この辺りについては追々説明するとして、まずは「部分」「パーツ」の話に戻そう。
仮に「肩が凝る」として、肩という部位だけがひたすら純然と痛んでいる人なんているだろうか。そもそも肩というものを身体から切り出した純粋な部分として認識してなどいないはずだ。確認したらわかると思うが、肩と胸や腕はつながっていて、そこに切り取り線みたいな境はなくて、滑らかにつながっている。
だからと言って、肩は胸ではないし、それぞれを表す語があるということは、違いがそれらにはあるわけなので混同はできない。つながってはいるけれど、分かれてもいる。
この「分かれている」というところだけに寄り掛かった見方が、部分やパーツといった言葉を便利に使わせている。
だから痛んだら、そこをマッサージするだとか電気を流す、湿布するとか、つい局部だけに目がいってしまう。そんなふうに身体を切断されたものとして捉え始めたのは、解剖学によって得た知識で自分の身体を眺めるようになったことと関わりがありそうだ。
全体は部分から構成されているという確信は今や常識になっている。でもやっぱりそういう見方だと、自動車の部品を本体のボディにバコっとはめ込んだり、壊れたところを取り替えたりできるような、どくどくと流れる血とか抜きの「もの」みたいな扱いになってしまう。生きていながら自分をものとして見なす。これはまさに疎外というやつではなかろうか。
僕らはもの扱いされたらおもしろい気分にはならない。「おまえは誰とでも取り替え可能なんだぞ」なんて言われたら怒るか泣くかして、「ものじゃない。生きている人間だ」と抗議のひとつもするだろう。ものとしてあしらわれると、それだけ嫌な感じがするからなのだけど、でもなぜか自分の身体に対してはもの扱いして、肩だとか足の言い分を聞かない。
「いや、痛んでいるという言い分を聞いているから、専門家の治療を受けたりするんだ」と言う人もいるだろう。でも、それは現に痛んでいるという身体を誰かに預けてしまっていて、痛みというとても直接的な訴えを無視することになっているのではないか。確かに専門家に意見を聞くくらいのことはあってもいい。
だけど、例えば誰かがあなたに「最近の私、どうですかね?」と聞いてきたら「知らんがな」と思いませんか。「私はあなたじゃないからわからない」と言うかもしれない。自分の痛む身体を差し出して「痛むから診てください。どうですか?」と言うのは、これと同じことではないか。
身体の民主主義
マッサージを受けて、その時は気持ち良くなっても凝りや張りが解消されることはないのは、多くの人が経験しているはずだ。その原因は「ストレスがあるから」とか「デスクワークで前屈みになっちゃうから」と理由は並べた数だけ出てくるだろう。だけど、根本の理由は、痛むには痛むなりの必然性があるにもかかわらず、その訴えかけに耳を傾けていないからずっと痛みは去らないままなのだ。
痛んでいるのに無視する。ひいては「我慢が足りない」といって押さえ込みにかかる。それはすごく不当だし、意図的に無視するのは虐待だと思う。
不具合を感じたところを自分から切り離し、健康であるはずの自分とは関係のない、壊れた部分やパーツとして扱う。痛みはむしろ部分やパーツとして不当な扱いをしていることに対するデモンストレーションだ。
だけど意識というものがトップにあって、「思い描いた通りに身体はコントロールされるべきだ」と思っていると、抗議の声は煩わらしいし、弾圧してしかるべき対象になってしまう。なんという非民主的でダイバーシティのない世界観、と言うか身体観だろう。
「滑らかにコントロールされた身体」という決して実現されない像を僕らは、それがありえない理想だとも思うことなく、むしろ健康という名で呼んでいる。健全な状態であるとアピールするために、意識を頂点とするシステムは日夜、ちょっとした違和感や痛みを「なかったこと」にしようとする。その振る舞いに対して、「身体の各々」は手の先の凍えや刺さって取れない棘の疼きといった、ただちに問題ではないかもしれないけれど、暮らしの中で僕らの喜びを少しずつ削っていくような痛みがあるのだと小さな声で訴える。それを聞いた「意識としての自己」は不満分子であり「病んだもの」として小さな声の主を隔離する。滑らかな統治は日々のやりくりの中で交わされている言葉に耳を傾けない。
さて、僕は子供の頃から「滑らかにコントロールされた身体」とは無縁だった。ぎこちなく、まとまらない。バラバラになりそうな心と身体を抱えて、人と話すということもわからなくなった時期もある。滑らかな統治をしたがる意識はあからさまに滑らかではない身体と出会った。僕はどちらの側にもいて、板挟みの時期が長かった。でも、今はまとまりもせず、ぎこちない偏りを生きている。ひたすら偏在しているということが自分の中の様々な声を聞く素地を保証している。
統治をやめてみる
いつの頃からか僕の両手の親指には「行方不明」という感覚がつきまとうようになった。拳を握るのが非常に難しく親指が収まらない。今でもそうだ。感覚的にははみ出したまま、いつも熱をもっている。動くときはいちいち引っかかる。どうにもままならない。
そして、気づくと親指に限らず、身体のあちこちが自分からはみ出たり、思っているのとは違う方向に動こうとしたりする。そうした各々のメッセージは「違う、そうじゃない」「もっとこっちに注目しろ」と言っているらしいと近年になってわかるようになってきた。
それまでの僕はままならなさに対して、よくある為政者のような独善的な態度で統治を試みてきた。それをやめ始めたことから痛みの声が聞けるようになった。
これから始まる連載は、「ままならない身体」を統合もコントロールもすることなく、ただままならないものとして受け入れる。その身体への見方がもたらすのは一体何か? について書いていきたい。ままならないものを放置すれば無秩序になると恐れる人もいるかもしれない。けれど、生命はおそらく一度たりとも無秩序になったことはない。無秩序であれば、散逸してしまってもおかしくないが、私たちはこのような形を伴って生きていて、そしてまた無形の生命現象として刻々と運動している。だから何があっても僕らは死ぬまでこうして生きている。
編集部からのお知らせ
尹雄大さんの新刊が晶文社から刊行されます!

本連載の著者、尹雄大さんの新刊『異聞風土記 1975-2017』が2020年6月26日に晶文社より刊行されます。装丁は『モヤモヤの正体』と同じく矢萩多聞さんです。
高度成長期に生まれ、多感な時期にバブルとその崩壊を体験し、阪神大震災・東日本大震災という二つの巨大な天災をへて、いま未知のウイルスに浸食されている「私たち」。その姿をたった一人の視点と経験が浮かび上がらせる。神戸・京都・大阪、東京を経由して、福岡・鹿児島、そして宮古島へ。すでに行き去りし人々の息遣いと熱をまとった「私の物語」から明らかになるもう一つの日本史。(晶文社ホームページより)