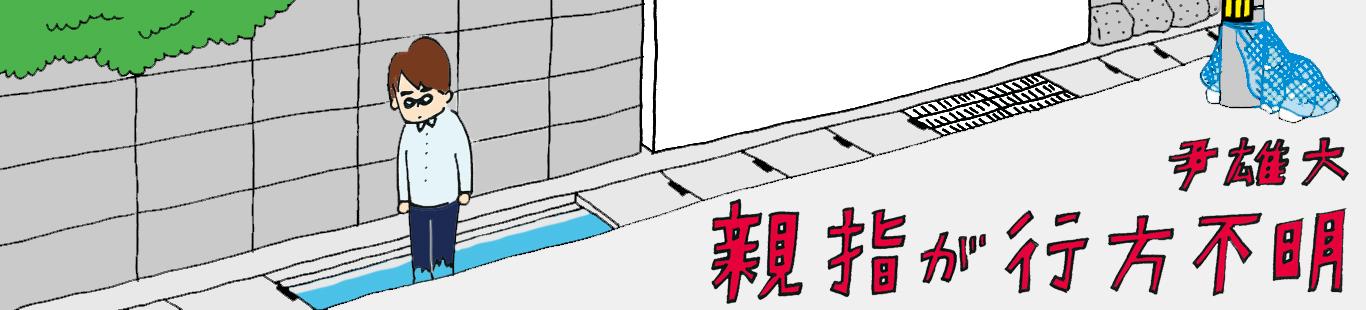第2回
ずっとズレている
2020.07.09更新
生きづらさの本当の理由
この連載では身体論について書くつもりはなく、身体観について描き出せたらいいなと思っている。この世を生きづらく感じている人も多いだろうけれど、誰にでも当てはまる一般的な「生きづらい」状態があるのではなく、人それぞれの生きづらさがあるはずだろう。そのとき、つらさを体現している身体観というものがその人の身体に生じているのではないかと思う。誰もが自分の身体観を見極めれば、生きづらさ一辺倒で自分をまとめ上げる作業の手を休められるのではないだろうか。
ひょっとしたら「生きる」と「つらい」を癒着させてしまっているのかもしれない。滑らかに現実が流れていかないときに人生が空転するような虚しさを感じるのだとしたら、生きること自体がつらいのではなくて、世の流れと自分の時間感覚の違いがもたらす、ズレがつらいのかもしれない。
差し当たり、極めて個人的な体験の中で起きたズレとそれがもたらした出来事について書いていこうと思う。それが読者に何をもたらすかはわからないけれど、自分なりの身体観を捉えるきっかけになるのではないかと思う。
不穏さと困りごとのマリアージュ
僕と身体との関わりは、気付いたらどこか知らない場所にいて迷子になっていた状態に近いものがある。迷い込んでいるのはわかっても、どこからやって来たのかもわからないし、目的地も帰り道もよくわからない。
この「よくわからない」という感覚が自分に対して初めて暴露されたのは、5歳の時だ。ようやく自転車の補助輪を外して乗れるようになり、母が近くの商店街まで買い物へ行く際、ついて行けるようになった。
自転車に乗れるようにはなったものの、それとの一体感にほど遠かった。普通は道具に慣れると自分の手足の延長のように扱えるものだが、この「こなれた」感覚がとても薄い。自家薬籠中のものにするといった体験がまるでない。だから、たとえ毎日料理はしていても包丁はずっと剣呑なままで、つい先日も包丁で親指の肉を削ぎ落とすような勢いで刃を滑らせ深い傷を負った。
自転車に乗れるようになって行動範囲は広がったが、次第に不穏な気持ちになり始めたのは、漕いでいる最中に「ここで手を離したらどうなるんだろう」という、よくわからない気持ちが起きるからだった。手を離したままで漕ぐという、5歳児からすれば曲芸に近いことに挑戦したいというわけではない。スリルを味わいたいわけでもない。手を離せばたちまち転けるとはわかっているのに、明らかな結果に向けて自分が自分を追いやろうとする。
時に追いやる側の勢いが強く、つい手が離れそうになると「危ない」と思わず叫んで制止する。手が自分の意思とは違う動きをしようとすることに必死で追いついて、そうさせまいとがんばる。だけど、困ったのは離そうとするのもまた自分だし、それに抵抗を示すのも自分だ。どちらの意思が本当なのか? と自転車に乗るたびに問われるわけで、これがとてもしんどい。
しかも、その問うてくる人物は誰なのかもわからない。自分が分裂しているというか層をなしているというのか。色々と混み合っている中、とりあえず自分として感じられるものに依拠して行動しないとまとまりがつかないのだが、それもまた輪郭が不確かな自分なものだから、とにかく僕は非常に困っていた。手が暴れるというか、言うことをあまり聞いてくれない。
「手を離さなくてはならない」という幻の声
破綻は唐突にやって来た。買い物に向かおうといつものように母が先頭を走り、僕が追いかける。住宅街を縫う、見慣れた道を走っていたら、酒屋を越えた横あいの道から、「手を離せ」という声が聞こえた。いや、声というよりは、突風が吹き抜ける際の全身に受ける圧みたいな感じというべきか。最初、僕は誰かが叫んだのかと思い、びっくりしてブレーキをかけた。あたりを見回すと酒屋の店主がジュースの補充をしていたが、そんな大声を出した気配はない。再び自転車を漕ぎ始める。幼いながら、いま自分が体験しつつあることは尋常ではないとわかっていたと思う。
真っ直ぐ伸びる道は、脇へと逸れる小道と交差しており、彼方にかけて十字路がいくつも目に入ってくる。そこを過ぎるたびにまるで漫画の吹き出しみたいな形で「離せ」という言葉が空中に現れたような、肉眼では見えないはずの景色を見る。しばらくは耐えられたが、やがてハンドルをギュッと掴んだ強張った手を、力が入った分だけ無理に自ら引き剥がすようにして、とうとう僕は手を離してしまった。
景色が斜めにずれていき、予告された通り、アスファルトに肩を打ち付けた。少し先を行く母が止まって振り返り、「大丈夫?」と声をかけた。
僕は必死に起き上がり、また漕ぎ出す。それからはもうダメで5メートルくらい進んでは転倒しを何度も繰り返した。自分でもおかしいと気付いている。涙が止まらない。痛くて泣いているわけではない。
自分で自分がまったく制御できないことに混乱していた。心というものが何かはわからなかったけれど、胸のあたりが広がり、それが自分を呑み込んでしまうような感覚があった。
「手を離さなくてはならない」という言葉を実行する以外に手立てがないような、オートマティックに転倒するという奇妙な状態に突入していた。あまりに転ぶので母が不審に思ったのだろう。一部始終を見ていた。我が子がわざわざ転けるために手を離している。何をしているんだと思ったろう。
僕のもとに駆け寄ると「どうして手を離せば転けるとわかっているのに、そんなことをするのだ」と声を荒げた。心底その言いようを不当に感じた。そんなことはとっくにわかっていることだったからだ。
だから地団駄踏むとはこういうことかというように足を踏み鳴らし、僕は「だって心がそうさせるんだもん」と激昂しつつ、泣きながら抗議した。それを聞いた母は爆笑した。「心がそうさせる」というフレーズがしばらく我が家で流行った。
気づいたらやってしまっている
数日後、両親に連れられて京都の宇治まで出かけ、地元では有名だという祈祷師のもとでお祓いを受けた。今なら精神科に直行だろうけれど、当時は精神病に対する偏見は強かったし、まして子供がカウンセリングを受けるとなれば、なおさらだった。スティグマを受けるよりはというので、その選択をしたようだ。ちなみに祈祷師が「この子はまだ右半身が成長していない」と言ったのを覚えている。
だいたいそのあたりからチック症が始まった。目をパチクリする。洟水が出てなくても頻繁に鼻をすする。これを異食症と呼ぶのが適当かわからないが、ともかく初めて人に言うのだけど、寝る前にカラーのサインペンで舌に3色を塗るという自分の中での儀式があって、これを済まさないとベッドに入れなかった。とんでもなく変ではあるとわかっていたので、決して親に見られてはならないという緊張感で毎夜臨んでいた。
チック症は流行があって、瞬きのシーズンが終わると別の症状が出てくる。あるとき何かに噛み付いていないと不穏になるというのがやって来た。ちょうどその頃、父が新しく車を買った。ドアの内側も革張りで、それを見ているとどうしても噛み付かざるをえない気持ちになってしまい、かぶりついてしまった。それを見た父は焦り、慌てて僕を引き剥がそうとしたものの、こちらは離されまいとがんばり、しっかり歯型がついてしまった。
傍目には奇行にしか見えないだろうけれど、チック症というのは自然とそうなってしまうので、本人にはそんなにつらいものではなかった。それよりも、いちばん迷子の感覚で混乱したのは、因果関係が逆転するような時間が訪れるときだった。
掃除機をかけていたときのことだ。最初は機嫌よくブラシを絨毯に滑らせていたものの、ふと脇を見ると水を張ったバケツが見えてしまった。父が窓を拭くために用意したものだった。掃除機のノズルとバケツが確認された途端、僕の視野には掃除機とバケツしか見えなくなり、その間に「水を吸わなくてはならない!」という横断幕が現れ、肉眼で見ている部屋とは関係のない舞台みたいな景色になってしまう。もちろん、水を吸えば掃除機が壊れるかもしれないというのはわかっている。
「AをすればBになる」という因果関係においてBが不利益を生じさせるならばAは行わない。至極当然の話だ。でも、僕には「Bがすでに確定してしまっているのでA以外の方法がない」というような関係に見えてしまう。これから何かが起きるのではなく、すでに起きてしまったということが、僕に開示される。
つまり見え方がふたつある。ひとつは肉眼で捉えたレベルの現実で、ここではバケツの水は吸われていない。もうひとつは「起きてしまった現実」でバケツの水は吸われてしまっている。後者のあり方が僕の視界というか心中いっぱいに広がってしまう。
あくまで掃除機は水を吸い込んではいないのだが、自分の中ではすでに吸い込まれているので、まだ吸い込んでいないとすれば、水を吸い込む以外になくなる。急いで現実に合わせないといけない。他人からは奇矯な振る舞いに見えても、僕からすると現実を修正することに近かったのではないかと思う。
心と身体、そして僕
この因果関係のねじれによって、様々なものを壊したりしたが、この流行が止んだのは、ホチキスで指を留めたときだった。ホチキスを使っていたら、ふと親指が目に入ってしまい、そうすると例の景色の一変が始まった。親指にホチキスを留めないといけない気持ちになってしまった。パチンとホチキスの針が食い込んだ。
激痛が走った。針の内側が折り畳まれて肉に食い込んでいるので、それを取ろうとするとさらに痛みは増した。痛いのだが、この痛みは誰の痛みなのか? 心なのか身体なのか。この強力な問いかけは、それまで漫然と離れていた心と身体を少し近づけた気がする。距離があるには変わらないが、ようやく互いの存在を目の端くらいには捉えるようになったという感じだ。
おそらく強迫性障害と言われるような行動なのだろう。しかし、障害と言っても生活全般に難儀したわけではなく、困る時間帯があった。僕は自転車の手離しを「心がそうさせる」と言ったが、時と場合によっては「心はやりたがっていないのに身体がそうさせてしまう」感覚もあった。
心と身体が分かれていて、互いにそれぞれの言い分があり、僕という存在はその「あいだ」にいる感じだった。あいだにいるからといって調停者にはなれなかったのは、そもそも心と身体が互いの存在を理解していなかったからだ。ホチキスの一件は両者が知り合う意味においては一歩前進だった。
編集部からのお知らせ
尹雄大さんの新刊が晶文社から刊行されました!

本連載の著者、尹雄大さんの新刊『異聞風土記 1975-2017』が2020年6月26日に晶文社より刊行されました。装丁は『モヤモヤの正体』と同じく矢萩多聞さんです。
高度成長期に生まれ、多感な時期にバブルとその崩壊を体験し、阪神大震災・東日本大震災という二つの巨大な天災をへて、いま未知のウイルスに浸食されている「私たち」。その姿をたった一人の視点と経験が浮かび上がらせる。神戸・京都・大阪、東京を経由して、福岡・鹿児島、そして宮古島へ。すでに行き去りし人々の息遣いと熱をまとった「私の物語」から明らかになるもう一つの日本史。(晶文社ホームページより)