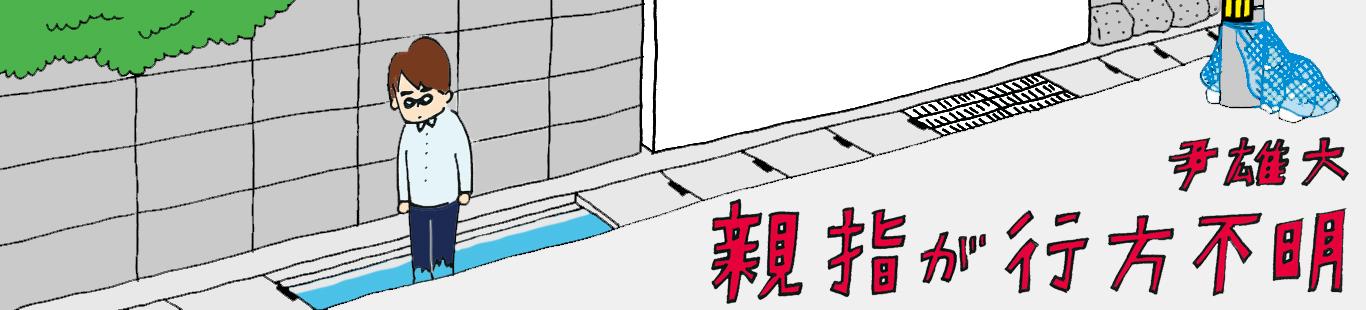第4回
言葉と時間からズレ続けてひとり
2020.08.18更新
取材の際、ノートを用意してもメモはほとんど取らない。記録はICレコーダーに任せている。取材の構えとして手ぶらでレコーダーだけでは、こちらに聞く意思がないように感じて怪しむ人もいると知っている。そのためノートを広げてはいる。けれども基本的に何も書かない。というより筆記の意味がない。相手の発言や印象に残ったエピソードの断片を書きつけたところで大きさも形も不揃いの字は、白いページをひたすら汚すだけの目的を達しているようにしか見えない。
話を聞きながら書きつけていた時期もあったが、その努力は同じ場所に字を重ねて書く取り組みに成り果て、いくつかの文字の塊が後に残されるばかりとなった。どのように試みたところで、読み返そうとしても自分で書いた文字でありながら判読できない。大袈裟に言っているのではない。「楔形文字か?」と言われることも珍しくないほどの悪筆だ。いや悪筆というのも違う。同じ字であっても同じようには二度と書けないくらい安定した字体を獲得しておらず、全般が不穏なのだ。したがってサインを求められても毎度違うことになり、サインの意味がまるでない。
書くことは乱調と苦役をもたらした
思い返すと筆記の記憶に乏しい。小学校時分から黒板に書かれた内容をノートに記したことがほとんどなかった。ひとつには教科書に書いてあることを教師が板書し、それをさらに書き写すという行為の意味がわからなかったせいだ。そのため授業は基本、ぼうっと白昼夢を見るようにして過ごした。
もうひとつは、興味のあることであっても、字が汚いあまり書く気が途中で失せてしまったからだ。「丁寧に書けばいい」と言われても、最後まで書き切ることが非常に難しい。崩し文字を通り越して独特の省略を経て解読不能に至るのが関の山だ。
例えば「あ」という文字の書き出しから終いまでの時間に耐えられない。しかも文章となると文字のひとつひとつを書き連ねていくわけで、気の遠くなる苦役に思えた。
言葉を綴ることで意味を形成していく速度と感じている速さがあまりにも違い過ぎて、イライラしてしまう。心中の苛立ちというよりも手が暴れてしまって抑えがきかない。これは「感じていることをうまく書きたい」といった意識が、そうはなれないことに葛藤を覚えての振る舞いではなかった。感じていることが感じているままに現れないことに全く納得できなかったのだ。
僕にとって文字は意味を表すために用いるものではなかった。意味に興味はなかった。感覚は刹那に過ぎていく。しかし、文字は変化しない。変化しては記録にならない。文字は再現性のある世界を保証する。いつ何がどのように起きたかを確定し、世界を記述していく。
だが世界は瞬く間に過ぎていく。時の流れの通り過ぎる様を感じはしても、それそのものを文字で表わせはしない。文字は時間の停滞の中でしか物事を表せない。試みたところで必然的にずれてしまう。文字を書くとは、ズレを示すための行為でしかなく、そこに我慢がならなかった。
だから自分の心境を正しく表そうとすれば、乱雑に書かざるをえない。のたうつような文字の綴り様は「言いたいことはそういうことではない」を示していた。
おそらく憤っていたのだと思う。それが筆圧の強さにも現れ、鉛筆やシャーペンの芯をよく折った。指でつまむ程度の力で書けばよいものを拳全体に力を込めて書くものだから、この過剰さが同じ字を異なった姿に見せる成り行きに拍車をかけた。
当世では文字を書くとは頭脳の働きと思われている節もあるが、身体の運動を必ず伴っているはずだ。頭を使う。息をする。胸が熱くなる。指が動く。すべて身体全体の運動あってのことだ。ところが僕の場合は手首で運動が切れ、指先まで届いていない感覚がずっと付きまとっていた。感じている速さとそれが文字にアウトプットされるまでの遅滞から来る軋轢が手首で生じている。自分の中で玉突き事故が起きているようなものだった。
空也上人になりたい人生だった
言葉を書くことが困難であれば、せめて話すことはと期待したいところだが、書く以上に難儀した。まず言葉を口にするには、いつも心の中で「せーの!」と踏ん切りをつける必要があり、そうでないと切り出せなかった。言葉はいつもくぐもっていた。何か口にしたところで、身の内に滞っていた澱のように古びた感覚と自分には思われて、話している中途で気持ちが萎れてしまう。
意を決して話し始めたことであっても「言いたいことはそれではない」の思いが追い越して、言い終えないうちに白けた気分に染まり、尻すぼみになる。話が空中分解の様相を呈し、実を結ぶことなく綻びてしまう。すると相手が怪訝な顔をする。そこで改めて自分の言いたいことは何だったかと思いあぐねていると、感じていることそのままを手で掴んでこの場に取り出したいのに、それができないことに気づく。
仕方なくなるべく目盛りの細かい言葉を使って、感じていることを正しく計測しようと思っても寸法が合わない。口が凍ったようになり立ちすくんでしまう。感覚的には、僕の中で何かが激しく起きているにもかかわらず、外からは「押し黙ったまま何も話さずに突っ立っている」状態でしかない。必然的によくわからない人になってしまう。
六波羅蜜寺にある「空也上人立像」を見た時、うらやましく感じた。近頃は、この上人像をコスプレにする人もいるから、教科書以外で目にした人もいるかと思うが、立像では口から仏が6体、中空に向けて吐き出されている。「南無阿弥陀仏」の6文字を表しているという。
空也上人が念仏をひとたび唱えれば、欣喜雀躍。市井の老いも若きも歓びに打たれ踊ったという。それは上人の言葉が真なるものだったからだろう。口にするべきことと口にするべき時と心とがピタリと一致し、それが口を吐いて出る言葉、というよりは音という運動に転換されるや辺りの空気を震わし始める。音の波が周囲に伝播すると、仏の功徳はかくあらんやと心ウキウキと三昧のグルーヴをなし、庶人は手の舞い足の踏む所を知らずに法悦の境地に至る。
僕が何か話すとすれば、舌はもつれ、口は籠り、6体の像は空中に地歩を固めることなく放たれた瞬間に落下していくだろう。
「あぐねる」だけで精一杯
書きたいことや言いたいことが明確にあって、それを書く、話すという順繰りの時間の展開の中で表していく。今日、僕らはそうやって論理的に考え、書き、話すことがコミュニケーション能力であると思っている。TEDやプレゼンテーションの場で巧みに話す人は、整序された書き言葉のような連なりを口にする。そうした滑らかな文法はノイズが少なく、繰り返し聞くにも耐えられる。
ノイズとは答えにすぐに行き着かない問いであり、矛盾であるだろう。答えに至らない問いは聞き手を混乱させる。それぞれに考えさせてしまい、時間の経過とともに言葉が耳に入って過ぎていくことを許さない。
矛盾とは、今用いている論理では扱いきれないことを示唆してしており、より包括的な視点が必要だと訴えかける。矛盾を前にすると話す側には言い淀むという滞空時間がもたらされ、聞く方には考えるという負荷が与えられる。
話す方も聞く方もともに矛盾を前にして考えあぐねる。「あぐねる」とは、思うように進めないという身体を僕らにもたらす。進みたくても進めないもどかしさに立ち会うと、僕らの身体は自然と捻れる。踏鞴を踏みもすれば地団駄も踏む。しかし、それもひとつのわからなさに対する回答、身体によるの応答のはずだ。
僕らがコミュニケーション能力の卓越さとしてあげるのは、意識によって入念に統括され、抜かりないリハーサルを経た言語活動だ。こうした行儀のよさに慣れてしまい、いつしかノイズも含む大きくて広い言論を口にすることを恐れてしまうようになった。少々間違えたことを言っても、熱量と濃度があれば説得力を生む。間違えたことが正しい結果をもたらすとすれば、それは各人が意味ではなく、熱量と濃度に感化され自律的に考えるという行為によって始まるはずだ。
思えば、僕はノイズだらけの身体をしていた。書くにあたっては、書くことの拒否のような筆遣いを、話すにあたっては口ごもることを常態とした。どちらにしても、くぐもり、宙ぶらりになることがあらかじめ決まっていたかのような身体だった。
文字は縦書きであれ横書きであれ、直線に配置されなければ意味を形成しない。自分でもうまく読めない文字をいくら頑張っても真っ直ぐに綴れない。だから屈折するままに書いた。
とつおいつの口ぶりは40半ばを超えるまで続き、今でも油断すると言葉が出なくなる。慣れ親しんだのは、吃音の「難発」に近い、言葉が出てこない身体であり、場面緘黙症に近い押し黙る身体だった。
ここでいう「身体」はレトリックではない。口ごもり沈黙するのは、「外部とつながれない」といった自閉した身体観をその時、僕が全力で表していたからに他ならない。
時代が要求する身体観というものがあるだろう。エレベーターが来ないとイライラしてボタンを連打する。スマートフォンをフリックすれば明日にはものが届く世界観の中では、一度押したにもかかわらず、すぐさまそれがかなわないことの方が異様に感じられる。時間は意識の速さに合わせて流れるべきだという想定が身に備わり始めている。その身体観が日常の当然の光景になれば、時間の滞りは「今すぐ」にかなう技術によって解決される問題として扱われる。「今すぐ」を手に入れたがる焦りは、未来をすぐさまここに持ち来たそうとする。
そうであれば、「感じていることが感じているままに現れない」ことへの苛立ちを抱えていた、かつての僕もまた「今すぐ」を欲していたのだろうか。
この社会に生きている。だが与さない
焦慮がもたらす「今すぐ」は確定した未来を今に実現しようとする。「そうでなければならない」からそうではない現実の方がおかしい。だから、現実を正そうとする。
それは記述した通りに現実を作っていくことを意味するだろう。だが、僕はそもそも言葉で表せない出来事がありありとあって、それを記述しなくてはいけないことに困難さを感じていた。僕の関心は記述ではなく、表現することに向かっていた。感覚という最大瞬間風速の速さを損なわずにどうやって身体で表現すればいいのかわからない。少なくとも筆記ではないとはわかっていた。わからないことへのある種の切実で真摯な応答が書きあぐね、口ごもる身体だった。
人間は自然環境ばかりではなく、社会の変化に適応しなくては生存はかなわない。書きあぐね、考えあぐね、言い淀み、口ごもり、引き攣って捩れた身体は現世への適応能力に甚だしく欠けていた。自分でもそう思い、また周囲もそう思っていただろう。
だが、今にして思うと能力に欠けるという体裁は、時代に合わない身体観をこの先に送り出すために僕が無自覚に準備した胚胎期間であったかもしれない。それは、この社会に属しながら、完全に与することなく個人的に生きるためのひとつのサバイバルの方法だったのかもしれない。