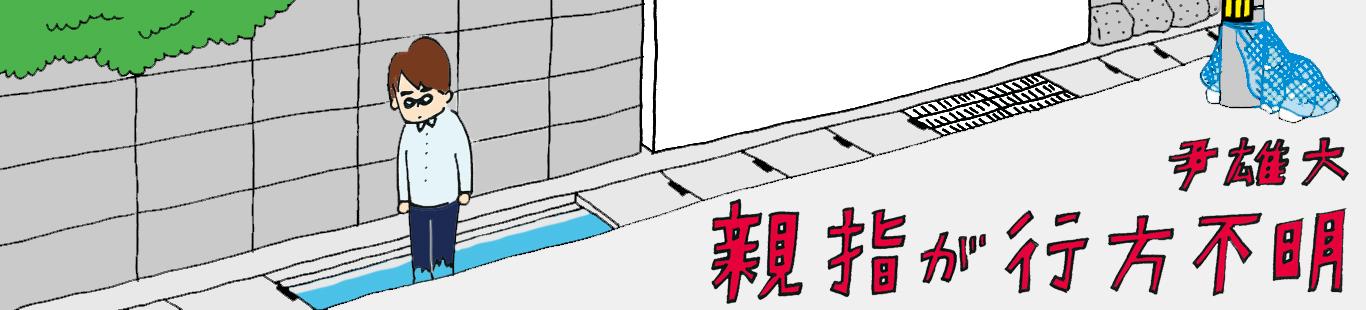第6回
光って見えるもの、あれは禿頭
2020.10.17更新
異語との出会い
中秋にはベランダに
普段は家族が集まったところで、ことさら話に花が咲くわけでもない。朴念仁を地で行く父が近くにいるだけで、緊張感は高まり、僕はソワソワしてしまう。前回で述べた階段から落ちた年の月見は、あまり酒を嗜まない父には珍しく杯を重ね、陽気にはしゃいでいた。
煌々と照らす月は、夜目にも父の首と言わず禿頭までが朱に染まっている様子を明らかにした。茹で卵の殻を剥いたような頭をピシャリと叩いて見せて、明るい月になぞらえるといった軽口のひとつも叩くのを見ると、なんだか見知らぬ人間が不意に現れたようで、どういう態度をしていいかわからない。
それにしてもさっきから父は調子はずれの声で流行歌を歌っているのだが、昭和世代は放歌高吟する際、手拍子の合間に必ずといっていいほど揉み手をしたり、箸で小皿を叩くのはなぜなのだろう。こんな浮かれた姿を会社の宴会でも披露しているのだろうか。そんなことを思いながら機嫌よく歌う父をぼんやり眺めていると、ひとくさり歌い終えたようで箸を置いた。緊張がほぐれ、ほっとしていると、父は傍らのスプーンを取り上げ、「スッカラ」と大きな声で叫んだ。その戯けた様子にもかかわらず、僕はギョッとして、父をまじまじと見た。後頭から照らされた頭頂は却って
僕はそれまで自分の喋っている言葉を取り立てて日本語だと思っていなかった。けれども「スッカラ」という異語は、自分の喋っている言葉が日本語だと気づかせた。
父は取り上げたスプーンをテーブルに置くとカツンと乾いた音を立てた。その後に「水、ちょうだい!」と言い、立ち上がってキッチンに向かう母の背中に向けて「ムル!」と声をかけた。どちらも普段、父は口にしない言葉だ。気まぐれで発したそれらの発音は日本語の抑揚と変わらない調子であったから、それだけに何かとってつけたような感じが漂った。そのことに気まずさを感じ、僕は慌ててスッカラとムルと唱えてみた。聞きなれない音の響きは、この先に自分が喋る言葉のすべてに「日本語で喋っている」という符牒を付けてしまうような感覚をもたらす。ただでさえ快活に話せない言葉の関節がさらに挫かれたような気分になる。
死なせないための取り引きの始まり
言葉との滑らかな関係が保てた時代は4歳頃で終わりを迎えた。そういう自覚を持っている。それ以降は、言葉はつかえ、くぐもるもので、とつおいつの口ぶりが当たり前となっていた。最初の口ごもりは今でも覚えている。1974年の夏だった。
膠原病を患う母が一時退院した折、薬の副作用で顔が腫れ、いわゆるムーンフェイスになっていた。久しく会えなかった寂しさに駆け寄ったものの、彼女の顔を見て絶句し、抱きつこうとして伸ばした手は行く先を失い、宙を彷徨った。彼女の懐に飛び込むはずの身体は失速し、そっと触れる程度の勢いに減じてしまった。
退院した日に撮影した写真がアルバムに残っている。母のそばにいる僕は彼女の面立ちのあまりの変わりようにショックを受けたことを気取られてはならないと思ってか、口をキュッと結んでおり、肩口に緊張が走っている。それ以降の写真に映る自分の表情は、以前にはなかった独特の暗さが宿るようになっている。死というものを朧げに知ったのだ。
その頃からだろう。言葉は自分の内側から溢れるものではなく、話そうとして話すものになっていた。彼女を死なせないためには、わがままを言ってはならない。本当に思っていることは注意深く避けて言葉を話さなくてはならない。そういう掟が僕の中に出来上がった。だからと言って、うまく演技ができるわけでもなかった。
いたずらにつっかえて話すことを平常とするようになった中で 「スッカラ」「ムル」という音の響きを耳にして気づいたのは、自分はしどろもどろに「日本語を話している」という自覚だった。
肌に合わないアイデンティティ
自分が韓国人だという自覚が芽生えたのはいつくらいだったろう。自覚と言いながら、果たして今に至ってもそのようなものがあるかと言えばとても心許ない。「自分は韓国人だ」と日本語で書くなり述べるしかできない。僕の頭の中は日本語で埋め尽くされている。情感を表す言葉も日本語だということは、日本的な感性を宿しているわけであり、それらの言葉に縁取られる中で「自分は韓国人だ」ということに、どれだけの確からしさ、真があるのだろうと思いはする。だから正確にいうと、自覚とは「日本人ではない」というぼんやりとした把握を指しているように思う。
親族が集まって執り行われる法事では、儒教に基づく三拝しての叩頭をした。テレビで放映されている世界の奇習を目の当たりにしたように思った。祭祀を終えた後に出される食事がこれまた赤みがかった色合いの料理で、他にも胡麻油や大蒜の効いた料理が並べられ、その色合いと香りにたじろいだ。普段、家で出されるおばんざいのような薄味のものとまるで異なる趣から、僕らは「日本人ではない」と感覚的に理解したのだろう。
しかし、「日本人ではない」と言葉にしたところで、すかさず「韓国人である」と自身を定めることは、早計だしアクロバティックなことだと感じていた。
自分は何者であるか?という問いを立て、それに国籍や民族という概念で答えるやり方がいまだに身に染みない。アイデンティティの確立とやらが肌に合わない。それ以前にもっと切実なのは、口ごもり、足はもつれ、右目が実はよく見えていない身体を抱えた、この行く宛のない自分だった。それを何者と名付けて良いのか?と問えば、それに対して「そもそも自分とは何か?」と問いで答えるほかないような、難儀な存在として自身がいつも自分の前にあった。
語られない母語と日本語
「スッカラ」「ムル」という言葉が発せられたその夜は、僕にとっては「我々は異邦人なのだ」ということが家族全員に周知された日として記憶に残っている。それからは感じていることや思いが言葉にならないという状態は、「日本語にならない」という認識に改められた。そのことで何が起きたかと言えば、改めて第一言語(母語)が日本語だと自覚された。
第一言語とは辞書の定義からすれば、「幼少期から自然と習得し、その使用に精通している言語」になるのだろう。僕にとって日本語は必ずしも滑らかに話せるとは言い難いもので、なおのこと自然ではなく、「操る」という感覚が芽生えた。
実際のところは操れていないのだが、「僕が話している言語は日本語だ」という自分を外から捉える視点が与えられ、それまで以上にうまく日本語を話さない限り、異邦人はこの社会の中で生きていくことはかなわないという暗黙の理解が導入された。
とはいえ、人と話さなければならない状況になると、決まって口は凍ったように動かなくなるのは相変わらずだった。そんな自分に恥じ入ると、相手の目を見られなくなる。それでも話そうとすると口ではなく、収まったはずのチック症のうちの瞬きだけが突出する。
目は間断なくパチクリとし、そうして表情の一部の運動は盛んになっても、顔全体は黙りを決め込み、引き攣って動かない状態を強調する。喉のあたりから胸にかけて詰まる感じや足に根が生えたような感覚になり、まるで動けなくなる。動かないのではなく、動けない。意思の力でどうにもならない。
自分と外界が切り離されたようになってしまい、外と全く関われなくなる。そうして身体が停止して、時間の流れから取り残された感覚が強まるのと比例して、内心の声は増えていった。どうして僕がこんな目に。嫌だ。やめたい。怖い。そんな言葉になりきらない感覚や感情がどんどん高まっていった。
やがて、外界に向けて示されない胸の内の声が言わば第一言語となり、日本語という意識的に操作する言語は第二言語にスライドした。おかげで第一言語を日本語に変換するという手間がさらに加わった。社会で流通している日本語に自身の内面の言葉を訳さないといけない。
決して語られない沈黙の言語は恐怖や不安、嫌悪、警戒に関する豊富な語彙と独自の文法を持っていた。正確にいうと語彙の豊富さとは、たとえば恐怖であれば、それを感じる目盛りが細かくなり、彩度が高まりを意味した。大きな音が苦手になり、陸橋や鉄橋の下を潜ることを異様に恐れた。
ちょっとした声音にその人の心情や思いがどちらに向かっているのかが感じられた。人によっては思い過ごしと言うのだろうけれど、僕には「そうに違いない」という確信として訪れる。妄想と呼ぶこともできる。けれども、あまりに強度があるので、やはり自分にとってはそれが現実としてしか思えない。わずかな声の震えやトーンの変化は、微風にほんの少し音を立てる葉擦れ程度のことであったが、僕はそれを目ざとく認める。独自の文法は、自分の身に良くないことが起きるかもしれないといった方向に、言葉の連なりを押し広げていった。
内面の声は恐怖や不安、嫌悪、警戒のポリフォニーで、その声が響き渡るほどに身体は引き攣れ、歯はぐっと食いしばられ、足や手に力が入り、硬直した。どれもこれもしようとしてするわけではなく、そうなってしまう。
第一言語の語彙と文法の発達は、生きる上での能動性を剥奪するように働いた。当時の僕は、周囲から引っ込み思案であるとか、おとなしいであると思われていたが、実際に起きていたのは、そのような見かけで判断されるような性格の問題ではなかった。言語と自分がつながれないということで、しかもそれ自体を言葉で伝えられないという事態であった。それは溺れる感覚にも似ていた。沈みきらないために必死だった。そのため人とうまく関わり、その中で知識を得たり、感情の交流をはかり、感性を豊かにするといった、大抵の人が体験する発達の過程を著しく損なった。長らく僕はそのことによってコミュニケーション能力が低くなり、「自閉症スペクトラム傾向が強い」と精神科医に言われるような顛末に至ったと思っていた。親しくなった人たちに「なぜあなたは人の心がわからないのだ」と何度言われたことだろう。それぞれ違う人が同じことを口にする。それを聞くたびに、悲しい思いをし、そうである自分を恥じ、嫌悪した。
自閉によって守られる感性と身体
だが、自閉的であることによって僕は第一言語で満たされた内面の世界を守ってきたのかもしれないと、近年になって思うようになった。これは開き直りではない。
コミュニケーション能力が大事だと言われ、まともにそれを受け止めた結果、滑らかに人と関われたとしても、自分が何を感じているのかわからないという、主体性を失った人が増えている。今どきの世の中では、「共感が大事だ」と言われる。けれどもそれはおかしいのではないか。共感はしてしまうものであって、するものではないはずだ。
自分がどう感じているかを脇に置いてまで共感を重んじた結果、人の意見に頷いてみせ、親しみに満ちた、それが故の波風立たない関係性は築かれはする。だけど、その代わりに何を手に入れているかと言えば、自分の感性を自分で殺すことだ。そうなると自閉的であることは案外悪くないのではないか。
自分の過去を振り返り思う。仮に僕が様々な困難を抱えた身体と心のままに、開かれたコミュニケーションという時代の潮流に合わせようとしたら、きっと空中分解を起こし、統合を失調していたのではないか。
僕は第一言語と日本語とが断線しがちなことで自閉的になった。僕の身体に宿る感性は社会から見れば、恐怖や不安、嫌悪、警戒と、およそポジティブな評価を得られないものかもしれない。何かを感じるたびに身体が捻れ、手は暴れ、口は閉じられた。社会との関係においては、確かに軋轢を生んだ。しかし、そのことで自身の感性は社会からの介入を防ぐことができたのではないかと思う。
自閉している状態は、社会と接点をうまく取り結べないことにおいては居心地が悪い。そう感じるのは、「社会性が欠けている」ことは「良くない」と判断するからだ。けれども、自分にとっては自閉は落ち着いていられる。
けれども一方でこう感じている。世の中のことは何事もそうだろうが、安住が可能だと思ってしまえば必ず腐敗する。感性とはいつも手放しで褒められるものではないし、心地がいいからといってそれが幸いだけをもたらすとは限らない。なぜなら恐怖や不安、嫌悪、警戒に長けた感性は、傷つきやすさを助長するからだ。気をつけていないと、自分はナイーブであるが、世間はがさつで無理解だと一方的に思うことをあっという間に正当化する。自分の身を守る感性が独りよがりの保身につながるかどうかの分岐点はどこにあるのだろう。その目印はわかりやすい形では示されない。
今のところわかるのは、「これが自分だ」と確定した途端、堕落するということだ。ある過去の状態を不変のものと錯覚し、固定した時から腐蝕は始まる。多くの場合、そうした固定を経験知と呼んで、過去の再帰に成功の法則を求める。それは生きながらに死んでいくことを本当は意味しているのではないか。
守ることと保身の違いは、今まさに体験しつつある出来事が、たった今の自分自身を教育し、エンパワメントするかどうかにかかっている。不確定で不安定な自分が必死に口にすることを汲み取る。自分が言っていることではなく、言わんとしていることは何か?その問いに応えること。それが自律的な教育を自身に施せるだけの力量になっていくのではないか。
「これが自分だ」と確固とした像を精神は求め、変わらないことを強さだと錯覚する。いくらそう思っても、思っている自身は常に変わっている。つまり身体は概念のような停止した時間の外に生きている。自閉的であること自身の感性との馴れ合い、退廃を生じさせないとしたら自分との対話、決して固まることのない身体が感じることを元手にしたコミュニケーションが不断に行われることによってだろう。
僕は無自覚ながら、それを行ってきたように思う。ただ、それが身体によるコミュニケーションとは誰も思わなかった。当人にとっても声に出されることのない第一言語は当て所のない独白としてしか感じられなかった。