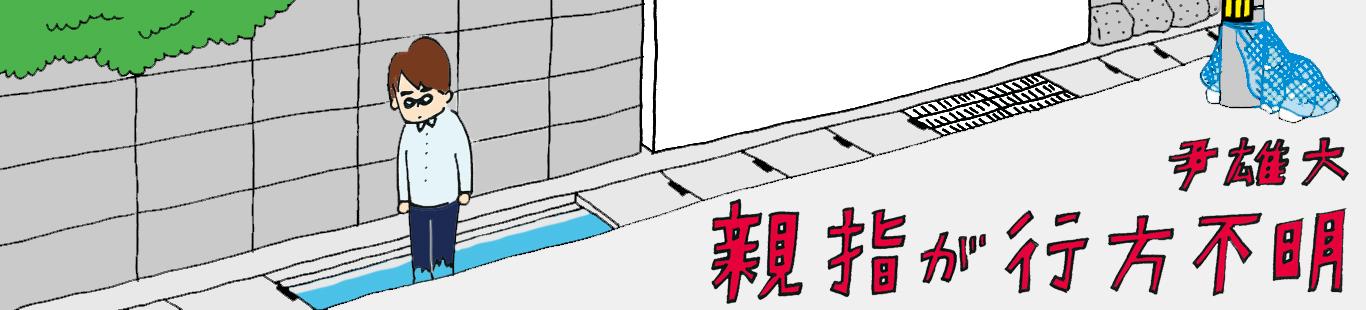第7回
デクノボーの全能感
2020.11.14更新
訪れた完璧な妄想
家のガレージの荷物置き場は格好の遊び場だった。そこで赤い錆を浮かべた鉄の釘を見つけては、火にくべて熱し、金槌で叩いて伸ばしてやすりで研いでいた。幼いなりに試みたのは日本刀の精錬の真似事だった。
他にはノートに城の石垣をひたすら描くことに勤んだ。あるページを余白なく石垣で埋め尽くしたかと思えば、石垣を仰ぎ見るアングルで捉え、はたまた苔むし崩れかけた石垣を描きと、全ページが石垣づくしだった。将来は刀鍛冶か穴生衆のような石工職人になりたいと思っていた。
その日も日課となっていた石垣のスケッチを終え、釘を求めて物置を漁っていたところ、乱雑に置かれたものの中に本があるのを見つけた。教科書だったか何かのアンソロジーだったか記憶は定かではない。手にとってパラパラとめくると「平家物語」の「敦盛の最期」が目に飛び込んできた。しばらく黙読した。その時に覚えた「熊谷涙をおさへて申けるは」から始まる件を今でも誦じることができる。
読んでいると、とても不思議な感覚に襲われた。それは「平家物語」とまるで関係ないことで、「自分はもう漢字の全てを読むことができる」という確信が訪れたのだった。実際、その日を境に字を一度見たら覚えられるし、わからない字に出会っても、字それ自体が読み方を教えてくれる。そういう感覚が芽生えた、と本人は思っている。
他人が聞けば完璧な妄想であり、根拠のない全能感だろう。だが、妄想だと一笑に付して退けることができないのは論より証拠で、漢字の書き取りテストは常に満点だった。試験に向けて暗記することの意味がわからなかった。振り仮名を書き入れる試験問題も僕にすれば、答えが書いてあるのと同じであり、加えて一瞥すれば字は覚えられるはずのものだった。
ある日、父が戦前に芥川賞候補になったことのある作家、「左近義親」の字をなぜか書いて寄越し、「読み方がわかるか」と聞いてきた。「さこんよしちか」と即答すると「読めたら小遣いやるぞと言おうと思ったけれど、言わんでよかった」と言った。
「字それ自体が読み方を教えてくれる」とは、僕の中で漢字はこう観えているからだ。親をなぜ「ちか」と読むのかと言うと、「さこん」の流れからすれば「義親」を「よしおや」と読むのはありえないし、「ぎしん」と読むのはそぐわないと「親」の字がしきりに言い、「ちか」だと訴えてくる。こういう感じで文字を読んでいた。推測とかイメージではない。この感覚は今は失われてしまったが、中学校を卒業するまでは確実にあった。
これを仮に直感的だとか想像力が豊かな感性と言ったとしても、その反面で何が起きていたかと言えば、7歳から16歳までの9年間、僕の身体を襲ったのはおびただしい怪我だった。どれもこれも右半身に生じた。右足の脛の打撲で骨が陥没。右足首のひどい亜脱臼で数ヶ月、松葉杖をついての生活を送った。それからの数えきれないほど負った右足首の捻挫、二度に渡る右肩脱臼。右膝の内側、外側の半月板損傷。以前、チック症が酷かった頃に宇治の祈祷師に「この子はまだ右半身が成長していない」と言われたのを思い出すと、何やら因縁めいて思える。
健全から遠く離れて
右側ばかりにダメージが蓄積して姿勢に偏りが出たのだろうか。あるいはチック症の一環なのか首を振ってコキコキと首関節を鳴らす癖がつき、それが余りに激しかったせいで首の関節も右に傾いている。おまけに背骨全体も横にS字を描くようにして歪んでいる。
生きていくということは、歪んだ身体として生きることに他ならなかったし、字を完全に覚えたという僕の思い込み同然の感性は、その傷んだ身体に宿った。
「健全な精神は健全な身体に宿る」と世間は言う。多くの人が健全を「けんぜん」と発音し、「健やかで異常がない」と日本語で理解している。「けんぜん」と僕も日本語の読みにならい発音する。
だけど、「けんぜん」の四文字のひらがなの発音の内に僕という存在が身を置ける場があるかどうか確信が持てない。なぜなら、僕は日本語の話者であっても日本人ではないのだから、健全をけんぜんと呼んで、その意味を共有する共同体に参加できるかどうかわからない。
同じ日本語を用いながら、その日本語を話せてしまうこと自体が不安を惹起させる。その不安は内面へと根をぐんぐん伸ばしていく。それは沈鬱な気持ちを募らせる一方で、不安と恐怖を基調とした第一言語で満たされた心の内側の空間を広げていくことでもあった。ただ、この寂寞とした世界には僕以外、誰も侵入することはできなかった。
僕の第一言語は日本語ではなく、恐怖や不安、嫌悪、警戒のポリフォニーから構成される、内面の言葉だと先述した。話せない、まともに字が書けない、人と交われないあり方をし、おまけに身体が歪んでいる自分は健全とは呼べない。世間の要求するまともさと違うところで自分のまとまりを作らないと、立ち行かないであろうことは、恐怖と不安を察知するに巧みな第一言語が漠然とした不安としてしきりと訴えた。
不安に満ちた内側から外界を見た時、ほとんど見通しが効かず、五里霧中という感じだった。その頃、親に中学受験をするよう迫られ、毎日塾に通っていたのだが、まったく頭に入ってこなかった。テキストに書いてある文字がうまく理解できないし、教師が何を言っているのかもわからない。おまけに自分が何を目指しているのかも不明だった。板書もできないのは当然のことだった。受験というものが行く行くは立身出世をもたらす上での重要なステップだと頭では理解していたが、「良い大学を出て社会的に成功する」という日本語の表現は、石垣を描いたり、釘で小さな刀を作っている自分の身体に全くそぐわなかったし、自分の身体に巻きついて離れない、拘束する言葉でしかなかった。
口をついて出るのはノイズばかり
受験が終わるまでの数年間、毎日文房具店へ行き、同じ消しゴムを買った。なぜかというと、カッターナイフで切り刻んで1日で使い物にならなくしていたからだ。当時はそれを取り立てておかしいとも思わなかった。ただそうせざるを得ない気持ちになるからそうしていた。合格発表が行われ、不合格が明らかになった途端、その衝動というか習慣がなくなった。
それを「ストレスを感じていた」と呼ぶのはたやすいし、実際そうだったと思うけれど、ストレスから開放されてよかったと言ったところで、根本的な社会のシステムが書き換えられたわけではない。自分が単に受験というふるいにかけられて、落ちただけのことで、抜本的にこの社会で生きることの安堵につながりはしない。
僕の第一言語はいわば感覚的言語というものだった。ただし、心中の思いが外に表現された際、意味に置き換えられるような言語ではない。ちょうど内面だけで奏でられる音楽みたいなもので、それを心の外に出そうとしても、たちまち音が変質してしまって、唸りとか呻きとかノイズにしか周りには聞こえなくなる。周波数が違うのか。外の世界で生きる人間の耳には届かない。自分の中で絶えず鳴り響いている音をかろうじて他の人に理解できる範囲に変換するとすれば、瞬きであったり、身体の引き攣りといった行為にする他なかったのだろう。人からすれば奇矯な振る舞いを通して、自分が今まさに体験している現実はこうも捻れているのだと、切実に訴えていたのだ。消しゴムを切り刻むという行為もまた音の言語化というルートを辿らないで現れた結果なのだと思う。
受験という他人の期待に応えることへの回答が切り刻む行為として現れたとすれば、大人になった今ではそれを言葉に置き直すことができる。その意味するところはNOだ。「やりたくない」と言葉で言えなかったのは、家庭内で交わされる言語は父親に対してYESということで成り立っていたこともある。逆らえないのだ。切り刻むという迂遠な形で受験への消極的拒否を示したのは、積極的に「嫌だ」と言えば、次に待ち構えているのは、「では、おまえはこの社会でどうやって生きていくというのだ?」と、小学生には荷の重い問いがやって来ることは目に見えていたからだ。否定するにも肯定するにも受験という仕組みの背景には膨大な日本語が控えていて、それは水平線の彼方まで広がっているように僕には感じられた。
見渡す限り習い覚えるべき言葉がたくさんあり、それとうまくつながらない限り、社会を生きていくことは難しい。受験を勝ち抜いたり、社会的に高い地位を占めることも、すべては世の中を作り上げている言葉の体系に習熟することでもたらされ、それができるかどうかが僕らの能力の優劣を決めた。
脱臼した言葉
どもり口ごもり、漢字は読めても算数や理科の理解にはつながらない。心身ともに跛行するありさまであるから社会というのは恐怖と不安の対象でしかなかった。到底まともに生きていける自信がなかった。まともという言葉に出会うとカチンと来ると同時に不安になったのは、社会から落伍していくことへの恐れがあったからだ。僕の中にある第一言語はひどく弱く脆い。まともという語がその後に従えている、まともな価値観だとか生き方に出会えば粉々に割れてしまうくらいの強度しかない。そう当時は思っていた。
だから自分の話す切れ切れの日本語は、たとえ何気ない調子の雑談であっても、怯えた感情に彩られてしまっていた。身体は萎縮し、それは内面の世界に及んでいく。怯えるほどに自閉し、内面は拡張していったのは、現実の暮らしに身の置き場が見当たらなかったからだ。いわば不安と恐怖の豊かな広がりではあるが、その豊潤さは安心をもたらさない。強さに転換されない。
仮に自分の内側の世界に完全に撤退すれば、不登校であるとか引きこもりといった行動として現れるのだろうが、良くも悪くも僕はわかりやすい因果関係に行きつかなかった。複雑なものは複雑なままに積極的に表すでもない表現をとっており、言わばずっとズレているし、脱臼した状態でい続けた。明確なプロテストにもならないため、傍目には木偶の坊、昼行灯として見えたことだろう。
このまともではない、ズレた状態でも生きていくことを可能にするのは何か。不安と恐怖を内に抱えながら、それでも生きていくとしたら、何をよすがにすればいいのか。これは幼いなりに真剣に考えるべきことであった。なけなしの手がかりは言葉だった。うまく話せないにもかかわらず、しかも内面の複雑さに応じてあちらこちらが脱臼しているような言葉。けれど決してそれを手離そうとはしなかった。誰の耳にも届く予定のない言葉だった。