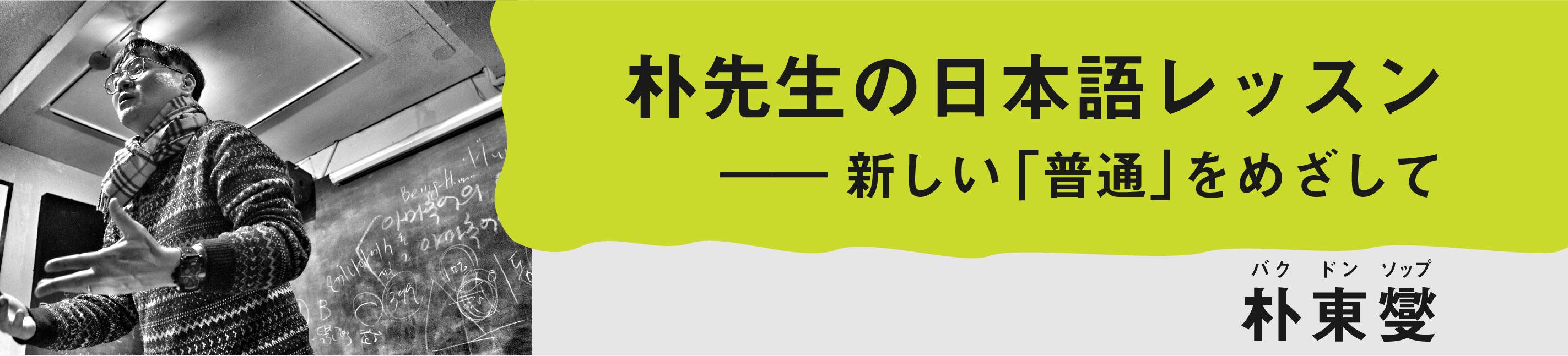第1回
新しい「普通」を一個増やす
2024.04.08更新
みなさま、はじめまして。朴東燮(バクドンソップ)と申します。
僕は韓国の釜山(ブサン)生まれ育ちで、いまも釜山の日光(イルグァン)という街に住んでいる、 生粋の釜山人です。いまの「イルグァン」は新しい街づくりで生まれた街でもありますが、白い砂浜の海水浴ビーチとしても有名なところです。
日本語は趣味で独学で勉強しはじめ、こうやってどうにかこうにか日本語で文章を書けるようになりました。僕の日本語運用能力は大きく分けて二つの柱で支えられていると思います。
一つの柱になるのが「玄界灘に立つ虹」という日本人向けの「KBSワールドラジオ日本語放送の番組」がありまして、この番組を大学生のころ二年ぐらいずっと休まずに聴いていたことです。
この番組は、 主に日本人のリスナーから寄せられたお便りの紹介をメインに、主に二人のパーソナリティがトークを進めていきます。扱っている内容も豊穣で韓国の政治から経済、文化、スポーツ、そして芸能ニュースまで実に様々なジャンルについて語ってくれる番組です。
今はアプリでも聴けますのでご関心のある方はぜひ聴いてみてくださいね(こちら)。
いまからおよそ30年前のことだと思いますが、この番組のパーソナリティの一人が番組中こう喋っていました。「外国語で人と向かい合って話すのも大変なんですけれども、電話はもっとそんな感じしますよね」という話だったと思いますが、僕はこれを聴いて一所懸命真似をするうちに思わず嘆声を発してしまいました。ということは、「外国語」を学ぶということは「こういうことなんだ」と改めて気づいたからです。
このフレーズをはじめて聴いたとき、まず生まれてはじめて接した言葉のリズム感とイントネーション、そしてグルーヴ感でちょっとしためまいが起きてしまいました。言葉ではなんとも言えないある種の「身体的な反応」だと言いましょうか、まだ輪郭の定かでない「星雲状のアイディア」だと言いましょうか 。まあ、とにかく気持ちがよかったです。そのあとふと我に返って「外国語」を学ぶことについてちょっと考え込んでしまいました。
外国語を発するには、つい内へと塞ぎがちな自分の身体を自分が生まれてから一度も発したことのない音韻を発声するとともに開いてみるという快さもありますが、もう一つ、別の考え方、世界との別のまみえ方、別の感じ方を自分のうちに一応無理やり住まわせることで、自分の凝り固まった想いを解し、編みなおし、あたかも別人であるかのように語ってみるという、ちょっと妖しい悦びもある。外国語を学ぶという行為は、この二つの快楽、つまり「快さ」と「悦び」を得るためのものであると気づきました。
そして、僕の日本語運用能力のもう一つの柱になるのが「五木ひろし」という日本の演歌歌手の歌をずっと聴いて吟味していることです。実は、「五木ひろし」は父が大ファンで、僕が中学生のころ、父は家にあったカセットテープデッキで「五木ひろし」の歌をずっと流していました。さすが中学生だった僕は日本語の歌詞の意味はまったく分からなかったのですが、サウンドだけで繰り返し聴くうちに、それがいつの間にか「好きな曲」になってしまったのです。
それで高校生になったとき、まず「五木ひろし」が大ブレイクした1971年の曲、『よこはま・たそがれ』の歌詞の意味を知ろうと日本語の文法の本を手にした時は、これからいよいよ日本語を習うのだと思って本当にワクワクしてきました。これまで自分にとってまったく理解不能だった言語がこれから理解可能になってゆくんですから。自分の母語とは異質な考え方、感じ方、世界とのまみえ方を、自分の理解可能な地平へとムリヤリ押し込むのではなく、それをそれ自体の方から学ぶということ、そのことで逆に自分の理解の地平を広げてゆくということ。これが外国語を身に通すことの意味であることにいちはやく気づいて、胸が膨らんでしまいました。
ですから「玄界灘に立つ虹」というラジオ番組と「五木ひろし」の歌は、僕にとって「日本語の原点」あるいは「日本語の原風景」だと言っても過言ではないでしょう。日本人の友人と面と向かって話をするときに、「五木ひろし」の歌を思わず歌い出す場合があり、相手を驚かせてしまいますが、それは僕なりの「日本語勉強の歴史」があるからだということで理解していただければと思います。
この長い日本語の勉強歴が育ててくれた日本語運用能力とものの弾みで、筑波大学で「心理学」で博士号を取りました。(心理学といえども、ちょっと、というか相当変な心理学なのですが、その話はあとでじっくりやりたいと思います)
ところで、いきなり変なことをいってしまい(じゃ、いままでの話は変じゃなかったのかと聞きたいでしょうけれど)、大変申し訳ないのですが、僕のファミリーネームの音韻って僕の感覚では「バク」だと思います。しかしそれが日本人の耳にはどうしても「パク」に聞こえてしまうようです(日本人になったことがないのでそのギャップは永遠に埋められないと思いますが)。それが僕にとってはいつも気になっていて、日本人の友人に会うたんびに「僕のファミリーネームの音韻って『パク』ではなく『バク』です」と、いつも訂正を心がけています。
先日も、実はミシマ社で長谷川実央さんにばったり会い、この「バクなのかそれともパクなのか」に関する議論をちょっとしていたのですが、彼女に「僕のファミリーネームの音韻」を口にするときはちょっと力を抜いたほうがいいですよと、アドバイスをしてあげました。ちなみに「起き抜けでぼんやりしてお腹も空いている状態で発音したほうがいいですよ 」と、冗談交じりのアドヴァイス(そのときは真剣な顔で)をしてしまいました(長谷川さんそのときはごめんなさいね)。
でも、内田樹先生もおっしゃっているように「本来、外国語というのは、自己表現のために学ぶものではないんです。自己を豊かにするために学ぶものなんです。自分を外部に押しつけるためではなく、外部を自分のうちに取り込むために学ぶものなんです」(内田樹著『街場の文体論』,p.244 ミシマ社)。
長谷川さん、これからは「内部」ではなく、ぜひ「外部」でお会いしましょうね。
まあ、この連載ではこの「どうでもいいような話」をベースにして言語の本質、日本語や韓国語の違いや共通点、母語が喋れるようになること、外国語を学ぶほんとうの理由、そして言葉を発することの意味合いなどなどを皆さんと一緒にじっくり考えていけたらと思います。実はこのような地味(『バクか』それとも『パクか』)な「ことがら」に「我々が知るべき大事なこと」が宿っているからだと思います。
僕は一応「独立研究者」(Independent Scholar) と名乗っています。 皆さんにとってこの「独立研究者」というのは、耳慣れない言葉だと思いますが、「独立研究者」は、全くどこにも所属していない完全な無所属状態(何かしらの大学の教授でもなければ、研究機関の研究員でもなく、大学の院生やODやTAやポスドクや非常勤講師ですらない)の研究者のことです。
僕はいまからちょうど八年前に大学を離れ、韓国のあちこちで講演・翻訳や執筆活動、そして最近は旅行ガイドもしながら生計を立て、僕の好きな研究を続けています。
2016年の3月に大学を辞めて「独立研究者」という身分になってから、周りからよく訊かれることは、「なんでせっかく大学教員になったのに大学をやめたんですか」ということです。訊いてくる本人は何気ない気持ちでしょうけれど、そう訊かれるたびに困ってしまいます。 いまもそうでありますが、僕にとって大学をやめて独立研究者になりたいと思ったはっきりとした「理由」があるわけではないからです。
「このまま大学にいると体調を崩すかもしれない予感がしたから」。「自分が選んだ研究テーマと方法と自分流の書き方で書く論文を評価してくれる審査委員が韓国内にはほとんどどころか一人もいないから」。「教員採用試験だけをめざした授業をやりなさいといつもまわりから圧力をかけられたから」「このまま大学に残って定型的なキャリアパスを進むことにうんざりしていたから」 「たまたま独立研究者という道を歩んでいる人が隣国にいたから」(ここでいう隣国の独立研究者は森田真生さんのことです)などなど。
こうやってそれらしき理由を並べることはできると思いますが、正直いって「なんとなく」としか言いようがないんです。だって、どうして「こんなこと」をしているのか、いまだに僕自身にもよくわからないからです。「どうしてこんなことをしているのか、本人にもよくわからないこと」なんか、人間はすぐ止めてしまいがちだとみんな思うかもしれないんですが、そうでもないんですよ。
逆です。 僕の経験知が教えてくれることですが、理由のよくわからないことを自分がしているときに、人間は「どうしてこんなことをしているのか」を必死になって知ろうとします。 意外だと思うかもしれませんが、その理由を知るためにいちばん簡単な方法はひたすら続けてみることです。だからこそ今も「独立研究者」として生き続けられていると思います。
普段、人から「朴さんってちょっと変わってますね」ってよく言われます。
しかし、僕的には「普通の感覚」で「普通の人」に見られるように頑張ってるわけでありますが、困ったことに周りの人はなかなか僕のことを「普通の人」に見てくれないのです。たとえば、僕にとって「学術というのは、ある種の『贈与』です」(これは内田樹先生からの受け売りですが)。 学術活動が「贈与的」であるというのは、今ではない時間、ここ(たとえば学会など)ではない場所、私とは度量衡を共有するわけではない読者にとってもリーダブルであるように行われてるということです。僕は学術活動は贈与的でなければならないと考えていますけども、これが僕にとっていつのまにか「普通」になったわけです。
あるいは、僕にとっての「普通の感覚」の変化をこう表現できるかもしれません。自分の中に貼られた「学術」にまつわる「普通」の札が「内田樹」という強風に出会い、はがれ、どこかに飛んでしまった。その代わり「学術=贈り物」という「新たな普通」が住み始めているわけですね。そこには、自分が変わる「危うさ」ももちろんあると思いますが、それとともに、変わる「快感」もきっとあると思います。
また僕にとっての「普通」は僕の専門にかかわることでもあります。
以前大学教員時代に「教育学部」に勤めていたこともありますが、自分のことを「教育学者か?」と訊かれると、「いえ、いまはとうてい教育学者とはいえないです。(実は大学に勤務していたころから自分のことをそう思わなかったです。)」という答えしかできません。
ならば、「『心理学は子どもの味方か?』(小沢牧子著)を韓国語訳し、ヴィゴツキー心理学を専門にして、本も何冊か書いたり、ヴィゴツキー心理学について講演もしたりしているから、きっと心理学者だろう?」「いや、そうとは思えない」。「じゃ、 ハロルド・ガーフィンケルと会話分析やエスノメソドロジーに関する本を書いたんだから社会学者か」「いや、そうとも言い切れない」。
「わかったよ。『数学する身体』と『数学の贈り物』そして『計算する生命』(森田真生著)などを翻訳したと聞いたのだが、数学者で間違いないね。」「いや、とんでもない。ぜんぜんちがう」。
「困ったな・・・それでは、『動詞として生きる』と『内田樹先生に学んで行きましょう』というエッセイを書いたんだから、『エッセイスト』でしょう?」「いやそれもちょっと違うな・・・」
「そういえば、安冨あゆみさんから聞いた話だけど、あなた『生きるための経済学』を翻訳したんだってね。それじゃやっぱり経済学者か」「いいえ、とんでもありません。」
「うむ、まいったな。それでは、きっとこれしかないな・・・去年『他者と死者――ラカンによるレヴィナス』と『レヴィナスの時間論』(内田樹著)の韓国語版も出しているし、『会話を哲学する』(三木那由他著)という本があなたの訳で韓国語版が出ると聞いているし、つい最近『成熟、レヴィナスとの時間』という著書も書き上げたんだから哲学者だろう、これで間違いないね」。
「ノーコメントです。」
「一体、あなたは何者だ?」
「いやあ、僕も正直よくわかりませんね」としか言いようがないんです。
僕のような人間は、「アイデンティティがない」と言えばないのですが、実は僕は、通常のジャンルではどこにもアイデンティティがない、ということを、僕自身のほんとうのアイデンティティだと考えています。ちなみに、僕なんかは典型的な「アイデンティティ喪失人間」です。これが僕的には「普通」です。
しかし、「学問」というのは、その根本から学際的(Interdisciplinary)にならざるをえないものだと思います。そして、研究者はすべからく「アイデンティティ喪失人間」になるべきです。学問(知)が作り上げられる土である我々の複雑な「生」がもう学際的なアプローチを求めているからです。我々の「生」に現代の学問がむりやり切り分けてしまった「分化」などないからです。
「道に転んでしまったことは、物理学的経験でしょうか」「愛していた人と別れて流す涙は生物学的現象でしょうか」「酸素と水素を分離することは化学的経験」であり、「カミュを読むのは単なる文学的体験に留まる」ことであり、「微積分の問題を解く行為はもっぱら数学にだけ使われる時間なのか」
僕は普段からこういったような疑問を抱え込んで研究を続けています。こういう研究の構えは多くの研究者にとっては「普通」ではないかもしれませんが、すくなくとも僕にとっては「普通」です。ちょっと変な言い方かもしれませんが、「いつ普通になるかわからないが、いずれ普通になってほしい普通」です。
そういえば、僕のような外国人に「連載」を持ってもらったり、しかもその連載のテーマはなんと「朴先生の日本語レッスン」という「普通ではありえない」企画を持ち込んだりする、ミシマ社の皆さんも多分新しい「普通」を一個増やそうとしているかもしれません。
僕も、皆さんのあたらしい「普通づくり」という実践に応えて、こういう連載のような「学術活動」を通じて新しい「普通」を一個増やしたいです。
みなさん、どうぞ楽しくお付き合いください。