第19回
「要するにどういうことですか?」
2025.04.11更新
僕は2012年から毎年、内田樹先生の韓国での講演会の企画や通訳を担当することになっています。コロナ禍や内田先生のご闘病などで中止が危ぶまれる年もあったものの、ZOOMのようなコミュニケーションテクノロジーの進化のおかげで13年も続けることができました。今年も、5月26日から29日まで、先生の韓国講演ツアーがソウルで予定されています。
講演の際、質疑応答の時間になると韓国のオーディエンスから例外なく飛んでくる質問に、こういうものがあります。「要するに内田先生のお話はどういうことなんですか」「一言で言ってください」「明日からわわわれは具体的に何をしろとおっしゃるんですか」。
作家の村上龍は、かつてあるインタビューで「この小説は何を言いたいんですか?」という質問をされたとき、その問いをしりぞけて、この小説が言いたいことはこの小説に書いてあります。ひとことで言えるなら小説なんぞ書きません、としごくまっとうな返答をしています。
「要するにどういうことなんですか」と訊かれるたびに、内田先生や通訳の僕は既視感でくらくらしてしまいます。内田先生はときには「そういう質問には僕はお答えしません」ときっぱり答えて、「日本のオーディエンスとあんまり変わらないですね」と独り言のようにおっしゃることもありました。僕もたまに講演をしますが、質疑応答の時間に「これこれを簡単に教えてください」と言ってくる人は必ずいます。
そういう人はおそらく、「学ぶ前の自分と、学びのプロセスが終わったあとの自分が、同一人物だと思っている」のだと僕は思うのです。
つまり、プロセスというものをすっとばし、時間をかけて自分が予想外の変化を遂げるかもしれないという可能性に気づかずに、いますぐに「答え」を得たいと思っているのではないか。学ぶ前と後で自分自身は少しも変化せず、知識やスキルが付加価値として「同じ自分」 に加算されると考えているのではないか。
それは 「学び」ではないと僕は思います。 商品を買っているのと同じ。消費者は商品を買う前と買った後で別人にはなりません。いや別人になったらむしろ困るわけですね。コンビニで買い物をする前とした後で別人になるはずがない。
でも、本当の意味での学びのプロセスでは、学ぶ前と後では別人になるのが当然なんです。
今回は、この「学ぶ」ということがテーマです。
泳ぎを知らない人に泳ぎを教えるというのは、何かを外付けの部品のように付加することではないですよね。 地上を歩くこと、あるいは地上で呼吸することとまったく違う体のシステムの使い方を習得しないと泳ぐことはできない。それは生きる仕方そのものを根本的に切り替えるということです。「学び」というのは本来そういうものだと思います。
でも、そういう了解は、 韓国の教育科学技術部にも、教育学の専門家にも、学校の先生にも、親たちにも、当の学生たちにも、少しも共有されてないと僕はつねづね感じています(たぶん、日本もあまり変わらないと思います)。
過日、若い親向けの講演会にお招きいただきました。講演会の主催者は、あらかじめ参加する親たちに「どんな質問がありますか?」とアンケートを取って、僕に送ってくれました。
その回答のなかで非常に目立つのが、「子どもの叱りかたを教えてほしい」というものでした。それも、兄弟喧嘩をしたときの、とか、おもちゃを片づけないでゴネたときの、というような具体的な場面が書いてあるわけではなく、どうも「叱りかた一般」についての質問であるようなのです。
もしやこれって、「子どもには厳しくすべきか、寛容にすべきか」というような質問? でも、子どもを叱るなんて、それぞれの価値観や関係、成り行きや具体的場面があってのことだから、一般的ノウハウなどあるわけがない。さあ困ったな・・・などと戸惑いながら、僕は講演の当日、オーディエンスに向かって次のように質問してみました。「みなさんはこういった講座に熱心に参加されているようですが、どうしてですか?」。
すると、多くの人が「幅広い知識を学んで実生活に活用したいからです」と答えてくれました。
僕はこの答えを耳にした瞬間、「広く学ぶ」という言葉にどこか違和感を覚えました。
「広く」というのは、ある種の「二次元」の概念ですね。何かを「広い」と感じるのは、ある固定的な視点に立って、「学び」の全貌を一望俯瞰する主体を想定しているからです。しかし、ここには「時間」というファクターも、「成熟」というファクターも、まったくはいりこむ隙間がありません。「広く」学ぶ主体というのは、いくら学んでも実質的には少しも変化しない主体として想定されているように僕は感じます。
韓国の大学で20年ぐらい教えた経験を持つ者として、この「広く学ぶ」とはどういうイメージから湧いてくる言葉なのか、身をもってわかります。18歳の学生が大学の入学時点で「これこれのことを学びたい」と思って、手元のカタログ(シラバス)から124単位分の授業を選んで、卒業単位を揃える。こういうイメージではないでしょうか。
でも、これってまさに買い物みたいですよね。スーパーで、入り口に置いてある買い物カゴを手に取って、店内を歩きながら、そこに「教育商品」をぽんぽんと放り込んでいく。いまの韓国の教育は、この「買い物」の比喩でしか構想されていないんです。
本来の「学び」というのはそういうものではないでしょう。ひとつ商品を 「買い物カゴ」に入れるたびに、買い物をしている人自身がそれを買う前とは別人になり、 「買い物カゴ」そのものも、ひとつ商品が入るたびに材質もサイズも容態も変わってしまう。そういうきわめてダイナミックなプロセスだと思うんです。
内田樹先生が、 学ぶというのは「コンテンツ(内容物)」が増加することではなく、「コンテナ(入れ物)」そのものの形状や性質が変わることだと言われた意味は、まさにこれだと思います。
「お店」に入った時とそこから出た時では人間そのものが別人になっている、というのが「学び」だと思いますが、いま韓国の大学は、18歳段階での価値観が4年間変わらないということが自明の前提になっている。
子どもの頃から、 お金とか権力とか情報とか文化資本とか、そういうものをたくさん手に入れた人間が「成功者」だというふうな価値観を吹き込まれた18歳が、その価値観のままに大学に入って、少しも変化しないで卒業して、 さらにはその価値観を死ぬまで維持していくような 「変化しない人間」が前提になっているのではないか。時間の流れの中で価値観そのものが変わったり廃棄されたりしていくような可能性はゼロ査定されているのではないか。
この教育観の根本にあるのは、教育資源というのは、互換性のある「情報単位」「技術単位」としてそこにある、という発想です。いわば「二次元的に」 そこにある。だから一望俯瞰的にカタログ化できるということになっているんですね。
でも、学術情報が個人にとって持つ意味って、 実際には一期一会の、まったく別のものです。
たとえば、同じ学問であっても、あることを経験した「前に」学ぶのと、経験した「後に」学ぶのとでは、その意味は大きく変わると思います。働いて生計を立てている時と、お小遣いをもらって遊んでいた時では、「経済学」でも「労働法」でも、重みが違ってくるでしょう。韓国人の友人ができた後とできる前では、韓国語学習のモチベーションは大きく変わると思います。
しかし、どういう条件でその学術情報と出会うのかを問わずに、ただ知識なり、情報なり、 技術なりをのっぺらぼうな球のようなものとして扱えるのが高等教育の理想的なかたちだと、多くの人が信じているようです。「『叱りかた一般』を教えてください」というように、多くの人が、いつでも、どこでも同じように使えるポータブルな知識を探し求めているのではなか。
でも、です。講演を数日後に控えた僕は、こういう質問も、とりあえずは考えてみるほかはないと思って、自分の子育ての場合はどうだったのかを思い起こしながら、「子どもを叱る」について考えてみました。
子どもと親は、毎日をいっしょに暮らす生身の間柄です。 子どもは親のつくった生活にあとから入ってきたのだから、基本的にはおとなの都合に合わせてもらわなくてはならない。何かをやるように急かしたり、押しつけたりすることは、そうしなければ生活が廻っていかないのだから、子どもに気の毒でも、やむをえない場面が少なくありません。言うならば、「しつけ」とは「押しつけ」。おとなの押しつけと子どもの反発は日常茶飯事で、そんな双方の押しつけあいの場面に「叱る」が登場せざるをえません。
問題は、何を子どもに押しつけたいのか、ということだと思います。
几帳面で散らかるのがきらいな人は、「片づけなさい!」を連発するでしょうし、散らかっていても気にならない人は、そこでは叱らない。その代わりに、子どもに親自身の夢を託した習い事をさせ、厳しいレッスンに通わせるかもしれない。他人の目が気になる性分の人は、人から非難されないようにという基準で子どもを叱るでしょう。
子どもを叱るとは、親が自分自身を見ること、知ることでもあります。「わたしは子どもをどうしたいのか、どうしてほしいのか。自分はどう生きたいのか、それが子どもとってはどうなのか」が問われます。だから、マニュアルが通用しないんです。厄介でも、親それぞれが、自分の生きかたとして考えざるをえないわけです。
子どもはいつだって、おとなをサボらせてくれません。日々、親に何かを考えさせずにはおかない。そのおかげで、おとなが少しは堕落しないで済んでいるのかもしれません。考えるのはたしかにめんどうですが、でもその機会を子どもから貰うのは、ありがたいことでもあると思います。
冒頭の講演会に話を戻します。「叱りかたを教えてほしい」という声の目立つアンケートをふまえて、僕は講演当日、親のみなさんに「どんな場面で叱りかたに悩むんですか」と尋ねました。
すると、ひとりの若いお母さんがこう言ったのです。「マンションの下の階の住人から、子どもの足音や物音がうるさいと、しばしば文句が来ます。 なんとか子どもを静かにさせようとするんですが、それが難しい。どう叱ったものかと、悩むんです」。
日本では、マンションの上階から聞こえる音は「床衝撃音」などと呼ばれますが、韓国では「層間騒音」、あるいは「上下階間騒音」と言われます。
韓国では最近、「층간소음(チュンガンソウム;層間騒音)」が社会問題になりつつあります。韓国では建物の階数を表す際に「층(チュン;層)」を使うのですが、「層間騒音」は、主に住宅の上下階間での騒音を意味する言葉です。
2021年には、全羅南道麗水市のマンションで層間騒音が深刻なトラブルに発展し、40代の夫婦が下の階に住む一人暮らしの男性に殺害される事件が起こりました。夫婦は子育て中で、しょっちゅう男性から苦情を受け、部屋の床にマットまで敷いていたということです。
そういう悩みだったのか、と僕は胸を突かれてしまいました。毎日のことだ。なんと気の重いことか。小さな子どもの世話をするだけでも若い母親はたいへんなのに、元気に遊ばせることもままならないとは。
そう言えば、以前に、別の講演で出会った幼稚園の先生から、こんな話を聞いたことがあります。寒い日に、幼稚園の教室内で園児たちと粘土遊びをしていたら、ある園児が粘土をやわらかくしようとその固まりを床にドシンドシンと叩きつけた。すると、ひとりの女の子が泣きべそをかきながら、先生の手を必死で引っ張る。何かを繰り返し訴えているので、手を休めて聴くと、「お電話かかる、お電話かかる」と言って泣いているのです。その子は家で大きな音を立てると、階下の人から「チュンガンソウム、うるさいからやめて!!」 と苦情の電話がかかってくるのでしょう。その恐怖から、床に粘土を叩きつける園児の行動を見て泣き出してしまったのですね。なんともかわいそうで、いつまでも忘れられない話です。
先の講演会では、若いお母さんに対して、会場のある男性からこんな励ましの声が出ました。 「子どもが音を立てるのは仕方がないですよ。 電車のなかの短時間ならともかく、一日じっとさせておくことはできないんだから。ビクビクしてもしょうがない。開き直って、下の人と顔を合わせたときに、「いつもすみませーん」って明るく言うしかないですよ」。
ほんとうにその通りだと思います。国は、少子化対策などと騒ぐ前に(韓国では日本を凌ぐ勢いで少子化が進行しています)、こんな親子の実態をきちんと見た上で施策をつくってほしい。たとえば、小さい子どものいる家族はマンションの庭付き一階部屋に、優先的に、しかも低家賃で住めるようにするなど、やるべきことは探せば山ほどあるのではないでしょうか。
こうして見えてきたのは、「子どもの叱りかた」ではなくて、じつは「政治家の叱りかた」 の問題なのでした。
「学び」とはこうやって、「子どもの叱り方」を問うていたはずの人が、「政治家の叱り方」を問う人に変わっていくような、実にダイナミックなプロセスなのです。
このエピソードは折に触れていろんな方に話しているのですが、にもかかわらず「学ぶとはどういうことですか?」と何度も質問されたことがあって、うんざりして「学ぶというのは、身銭を切らなくても人に訊きさえすればどんな問いの答えも得られると思っている人間には無縁なんです」と言ったことがあります。
この間は「ヴィゴツキー心理学を学ぶ意味はなんですか。一言で言ってください!」と訊かれたので、「そのような質問をしない人間になるために学ぶんです」と答えてしまいました。


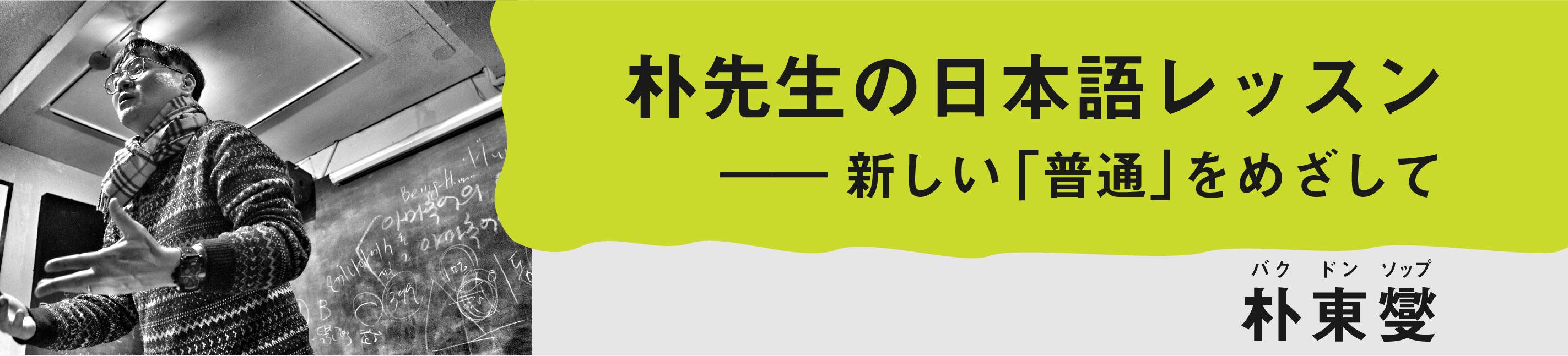


-thumb-800xauto-15055.png)



