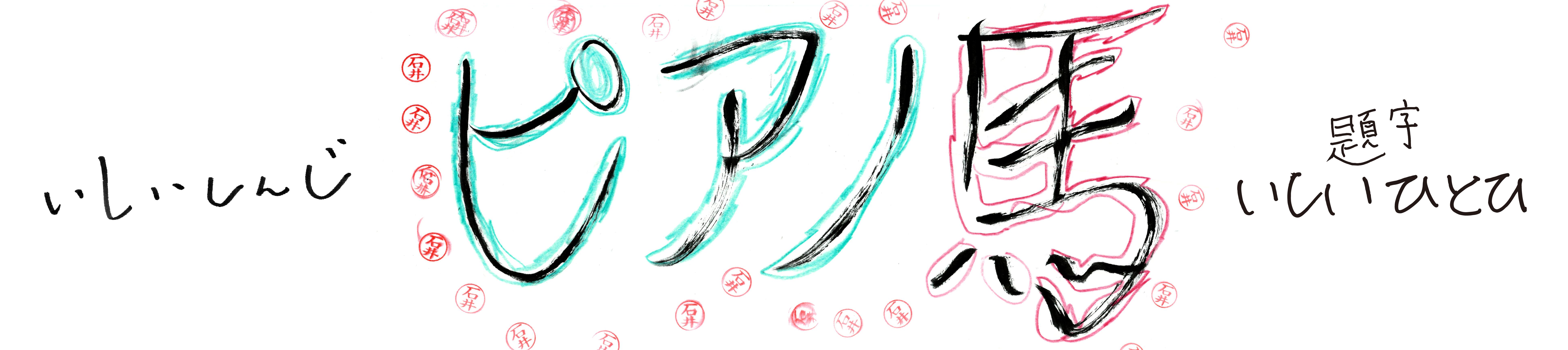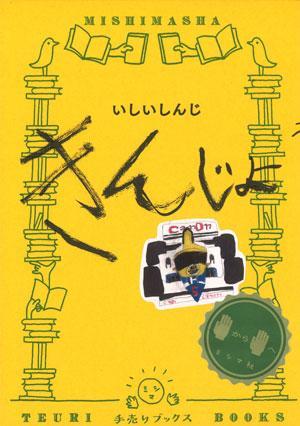第1回
ピアノがはじまる(上)
2022.06.22更新
去年の秋から、「自分はまあ、一生これにはまることはないだろうな」と、たかをくくっていたものにドはまりしている。
ベートーヴェン。
しかも、ピアノソナタだ。
きっかけはコロナだった。息子のひとひが通っているスイミングスクールの、ベンチつきの観覧席が「密」になるため使用禁止になった。
レッスンが終わるまでの1時間強、さて、どうしよう、とあたりを見まわす。頭のなかでうっすらと、なにかを告げる光が明滅している。目を凝らすとそれは、秋風にひるがえるのれんの閃きにかわった。
学生時代、二、三度はいったことがある。出町柳駅前、名曲喫茶「柳月堂」。のれんに招かれるように足をふみいれ、階段をのぼった。
制服の女性がうっすらほほえみ、その口から「リスニングルーム、ご利用ですか」と心地よい小声がもれた。あいまいに頷くぼくの前で音もなくドアがひらいた。
お客はぼくひとりだった。そのことには、ずいぶんあとで気づいたのだ。ドアがひらいた瞬間、ぼくは立ちつくし、音の壁に打ちつけられていた。なんだこの音、なんの鐘だ。柳月堂って、クラシック専門じゃなかったのか。こんなへんな、スペーシーな現代音楽、きいたことないぞ。
音が、空気が、波が飛んできて、ぼくの芯を叩く。そのくだけ散る音も含め、ぼくは立ちつくしたまま音楽を浴びた。うまれて初めてとも、うまれたときからなじんでいる曲とも感じた。現代音楽、というよりそれは、未来から響いてくる音楽にきこえた。
ドアの横に、レコードジャケットが一枚置いてある。手にとってみると、グラモフォンレーベルの日本版だ。裏返すと「マウリツィオ・ポリーニ演奏 ベートーヴェン・ピアノソナタ 第32番」と書かれてある。嘘やん、とぼくは思った。これ、おれ、持ってるレコードやん。
泳ぎ終わって気が抜けたひとひを引きずるようにしてダッシュで家に帰り、オーディオの電源を入れて大音量で、自分の持っていた「第32番」をかけてみた。
うちの機械では「柳月堂」ほどすさまじくは鳴らなかったものの、それでもたしかに未来の音が響いた。少なくとも近未来だ。十八世紀とか二十一世紀とか、ぜんぜん関係ない。たったいま、刻々更新されていく、まあたらしい「いま」。それこそつまり「近未来」ってことだ。
翌日の昼、市役所西の「100000tアローントコ」を訪ねた。主の加地猛くんは10分前に店をあけたところだった。この店のクラシックの棚に向かうなんてはじめてだ。200円のコーナーの端から、ひとさし指なか指をテクテクさせてレコードをめくってゆく。
10分後、ぼくは半ば以上呆れていた。両手のうちに、ピアノソナタ第32番のレコードを3枚、第29番のレコード2枚、第28番を1枚抱えながら。
「いしいさんがクラシックって、わりとめずらしいですねえ」
背後から加地くんの声がかかる。
「そこに積んである段ボール箱、ぜんぶ、まだ店に出してない新入荷のクラシックですけど、見ます?」
「見る」
段ボール箱5個ぶんのオランダ盤レコードのなかに、ベートーヴェンのピアノソナタは35枚はいっていた。ぼくはそのうち10枚を買い、うちに帰ってから思い直し、加地くんに電話をかけ、もう1枚、グレン・グールドの「第32番」を追加した。
すべてちがう演奏者によるベートーヴェンのピアノソナタを一枚いちまい聴いた。知っている曲も知らない曲も、すべて未来からぼくの部屋に響いた。ぼくはふと、「第1番から順々に、第32番まで聴いてみよう」と思った。
ひとひがまだ赤んぼうだった頃、昼寝の二時間のあいだ、隣でずっと、ドストエフスキーを処女作から順に、「カラマーゾフの兄弟」まで読みつづけたことがある(「カラマーゾフ」は異なる訳で三回読んだ)。はじめ地下の暗がりにこもっていた作家の目玉が、長編を書きつづけるうち地上にあがり、ひとの暮らす巷を見おろしながらゆっくりと浮上し、さいごには天体のすべてを見わたすような視野を得る。順に読んでいくとその高さ、広がりが、理屈でなく、経験として体感することができたのだ。
ここ20年で知りあった世界じゅうのレコード業者に連絡をとった。LPでもSPでもかまわない、お薦めの「ベートーヴェンのピアノソナタ」を教えてほしい、と。「おまえがベートーヴェンとは、なにがあった」「狂ったのか」などとメールの冒頭ではいいながら、みな熱っぽくそれぞれのベートーヴェンを語ってくれた。
クラシックは知らないことだらけだ。そもそもソナタってなんなのか。イスラエルのレコード店主はこう教えてくれた。「ソナタって記されたレコードに録音されてる曲が、ソナタだ。それ以外に正解はない」。
ベートーヴェンがうまれた頃はまだ、現代のピアノはなかった。少年から青年へ、作曲家としての成長と、楽器としてのピアノの発展史が、ほぼぴったり重なる。だからベートーヴェンはピアノ曲を、成長してゆく楽器の音をたしかめるように、楽しみながら数多く書いた、というのも、イギリスの犬好きレコードマニアの受け売りだ。
バックハウス、ブレンデル、グールド、ポリーニ、バレンボイム、ホロヴィッツ、グルダ、シュナーベル、フィッシャー。
モノラル、ステレオ、スタジオ盤、ライブ盤問わず、名ピアニストたちによる「ピアノ・ソナタ」のレコードが、昨年の秋からこの春まで、世界中の町から京都の左京区東竹屋町の一角へと、日々、黒いUFOのように飛来した。その間ぼくは、ベートーヴェンのピアノ曲以外、ほぼいっさい聴かなかった。バックハウスの演奏で、何度か「1番から32番」を聴きとおしたあとは、毎朝、その日の気分や体調に合わせて一枚をえらび、ターンテーブルにのせる習慣がついた。
スヌーピーやチャーリー・ブラウンでおなじみの「ピーナッツ」シリーズの作者チャールズ・シュルツが、インタビューで話していたことを思いだした。「家でたっぷり朝食をとったあと、自転車にのって仕事場にむかう。机の前にすわる前に、レコード棚からベートーヴェンのピアノ・ソナタをえらんで一枚かける。音楽が終わったら、まっさらな気持ちでペンをとるんだよ」
ルーシーのもたれかかる子ども用ピアノで、天才ピアニスト・シュローダーが弾いている曲は、だから、全部ベートーヴェンのピアノ・ソナタなのだ。そこまで思いだしてから、ぼくは不意に身をおこした。
なんで、おれ自身、ピアノ・ソナタ第32番、この手ぇで弾いたらあかん、なんてことがある?
(続きます *次回は7/6頃 公開予定です)