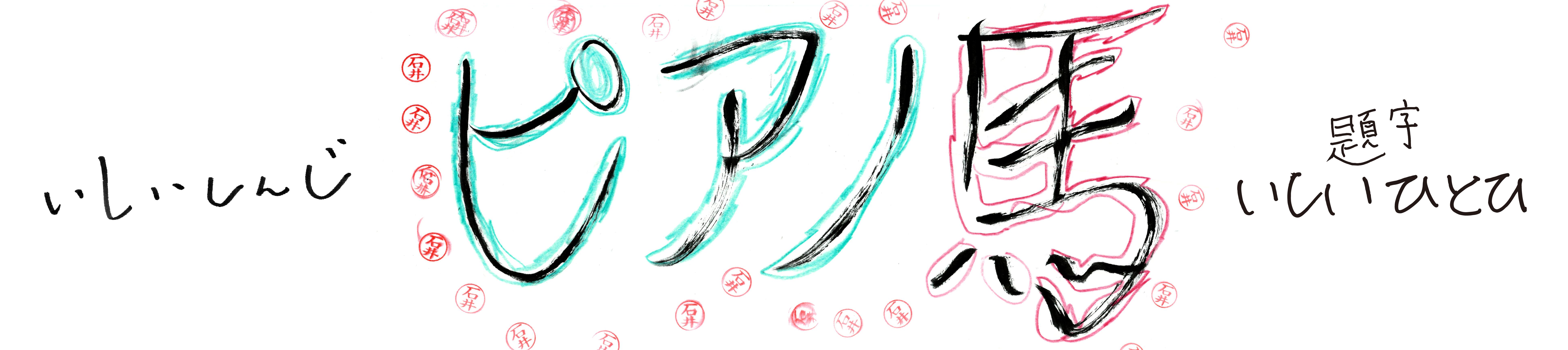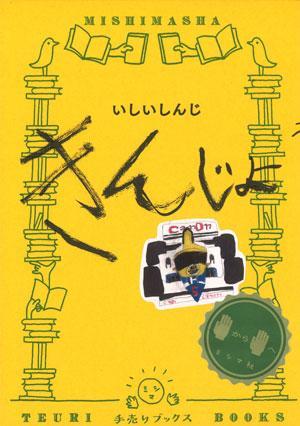第4回
馬がはじまる(下)
2022.08.17更新
午後の空気は奇妙な静けさにひたされていた。
入り口でもらったレーシングプログラムを胸に、ひとひはほぼ満員のスタンド中段に立ち、その緑をすべて吸いこまんばかりに目を見ひらいて、眼下にひろがる京都競馬場の、芝生のレースコースに向きあっていた。
この日、樟葉の乗馬クラブクレインから淀へ直行したら、偶然にも秋大詰めのG1レース、マイルチャンピオンシップが開かれていた。出走馬18頭中17頭が重賞ウィナー、うちG1馬が7頭と、近年まれに見る豪華メンバーがそろい、ここ数年来の短距離王を決める一戦と目されていることなど、すべてあとで知った。
ファンファーレ。手拍子。ゲートに吸いこまれる一頭一頭の姿。
「おとーさん、はじまんのん?」
「うん、は」
じまる、と言い終える前にゲートが開き駿馬たちが飛びだした。遠雷のような地鳴りが秋の空気を一瞬で沸きたたせた。ひとひは立ちあがり、全身をひらききって遠くで閃く黒い光を感じていた。
馬群が滑るようにバックストレッチを進み、最終コーナーを立ちあがってくるまで、長い旅のようだったが、一分さえ経っていなかった。最終の直線に馬たちが飛びこんでくると芝が巻きあがり緑色のレースの波となった。波はふくれあがり巨大化しながら突進し、そしてゴール板を通過した瞬間空へかき消え、レースが終わった。
スタンドには絶叫、ため息、拍手、地団駄がこだましつづけた。十八頭の馬たちは満足げに首をあげさげさせながら、第一コーナーあたりをゆったりと駆けぬけていった。宙に残るレースの波飛沫を、もくもくと食んでいるようにみえた。
ひとひは座りこんで、じっと馬群をみつめていた。競馬場のスタンドはいつも大潮の引き波くらい引けるのが速い。まわりにぼくたち親子しか残っていない状況になってようやく顔をあげ、
「おとーさん、かっこええ馬って、ほんま、かっこええんやなあ」
といった。
このとき握りしめていたレーシングプログラムは、むろんいまも、ファイルケースのなかに大切におさまっている。
この日からひとひは、馬を「読む」ことをおぼえた。クレインのクラブハウスに置かれた、乗馬専門誌「馬ライフ」。競馬馬の情報満載のフリーペーパー「うまレター」。まだ教わっていない漢字はどんどん飛ばす。写真、イラスト、カタカナは何度も何度もくりかえし見る。
そのうち、物販コーナーでみつけた『おがわじゅり的 21世紀名馬列伝』(おがわじゅり著 秋田書店)というマンガが、うまれてはじめての「愛読書」となった。文字どおり肌身離さず持ち歩き、クレインへの行き帰りはもちろん、家の玄関でも、台所でも寝床でも、クリスマスの前の日も、正月のおせちのあとも、えんえん、ずーっとページをひらいている。
この本でひとひは、オルフェーヴル、ウォッカ、ロードカナロア、エイシンフラッシュ、アグネスタキオン、ジャスタウェイ、ホエールキャプチャ、ホッコータルマエらの名馬に、初めて出会った。
「いぶし銀」「三冠馬」「圧勝劇」「流星」「クラシック」「重馬場」「ライバル」「配当」「ツンデレ」「セレクトセール」「ノド鳴り」「レコード」「号泣」「潜在能力」「スイッチが入る」などのことばに、初めて触れた。
名馬たちの名レースを思い描き、じっさい、おがわじゅりさんの絵をノートやスケッチブックに模写ばかりしていた。
クレインで自分の騎乗が終わっても、厩舎に残り、一頭いっとうの馬を眺めて過ごす時間が長くなった。自分が乗った馬だけでなく、ここにいる馬みんな、ひいては、この世の馬ぜんぶがおそらく、黒や茶やブチ色の、すばらしい光を帯びて目にうつるようになった。
「おとーさん、おとーさん」
ある日、稲妻をくらったような顔でクラブハウスへ駆けこんでき、
「あのな、びっくりしたらあかんで! おとーさん、こないだ、コロマンデルって乗ったやん」
「ああ、コロちゃんな」
フフ、とためを作り、思いっきりドヤ顔で、
「コロマンデルってな、あんな、すごいで、キングカメハメハのこどもやで!」
また別のとき、
「おとーさん、信じられへん!」
長鞭を持つ手をばたばたと動かしながら(危ないのでやめましょう)走ってくると、
「こないだ乗ったオールアズワンっておったやんか」
「あの、おっとりした感じの子な」
「あの馬な、G3の、札幌2歳ステークス勝ってんねんで! オルフェーヴルといっしょに、ダービー出てんねん。ほかにも、ぴっぴ、武さんとか、川田さんとか、ルメールさんが乗ってた馬に、乗れるかもしれへんねん!!」
憧れが、夢まぼろしなどでなく、みずからの現実に直結していると知ったとき、そのひとの暮らしは、可能性の光を帯びていきいきと輝く。自分の未来について、どんなケースであれ、おおむね前向きに信じられるようになる。だって次の週、ディープインパクトの子にさえ、乗れるかもしれないのだ。
学校の図画工作では、東京競馬場のジオラマを作り、コースを駆け巡る名馬たちの絵姿を貼りつけた。毎週日曜の午後3時からは関西テレビの「競馬ビート」。用事があって見られないときは、当日の夜、果物を頬張りながら録画映像にかぶりつく。
振りかえってみると、あのマイルチャンピオンシップ直後、三冠女王アーモンドアイの出走した第38回ジャパンカップを、リアルタイムでテレビ観戦したのが大きかったかもしれない。
それほどすばらしいレースだった。前半から菊花賞馬キセキが先頭をきって逃げ、アーモンドアイは淡々とその後方についていった。サトノダイヤモンド、シュヴァルグラン、スワーヴリチャードら、強豪たちが懸命に追いすがる。東京競馬場の坂をのぼりきり、最後の直線にはいったところでアーモンドアイのエンジンに火がはいった。真後ろの馬群を置いてけぼりにし、逃げつづけたキセキを秋風のようにかわして、ゆうゆう2馬身近くの差をつけてゴールに飛びこんだ。芝2400メートルを2分20秒6は、従来のコースレコードを1秒半も更新する、衝撃の世界記録だった。
競馬を見はじめたばかりのひとひは大興奮し、アーモンドアイはもちろん、超高速レースの立役者キセキの姿を、瞼に焼きつけるように、くりかえしくりかえし映像で見なおした。翌月発売の月刊誌「優駿」も、自分のおこづかいで買った。この号以来、足かけ4年間、ひと月たりとも買い逃したことはない。
ひとはこんなになにかに夢中になれるものか、と、そばで見ていて素直に思った。
YouTubeでは、「競馬・迷実況」「海外・すごいレース」「JRA・かっこいいCM」「大逃げ・馬」みたいな動画ばかり検索し、ゲラゲラ笑ったり、焼け焦げそうに見つめたり。
お風呂にはいる際は、ブルートゥーススピーカーにアップルミュージックをつなげ、東京・京都・阪神競馬場の、それぞれのG1ファンファーレを高らかにひびかせながらフリチンで登場。
本棚には「泣ける競馬」「馬はなぜ走るのか」「乗馬上達バイブル」「うまはともだち」などの単行本。「優駿たちの蹄跡」「優駿たちの門」「元競走馬のオレッチ」「馬まんが日記」「最強の名馬たち」ら、新旧のマンガ本(古本屋で探すとびっくりするくらいいろいろ見つかる)。
寝る前には「優駿」の名馬一覧のキャプション部分をぼくが隠し、ひとひが馬名をあてる「馬クイズ」(歴代G1馬なら小6現在ほぼすべて的中)か、「あぶみ」「ミスターシービー」「ビートブラック」「くりげ」「ゲート」「トウカイテイオー」とつないでいく「馬しりとり」で眠りにつく。
外食先には、マンガ、単行本と「優駿」か「ナンバー」の競馬特集号を必ずもっていき、料理が運ばれてくるまで、ひとりでえんえん見入っている(たまに「馬クイズ」に発展することも)。
カウンターの隣から、ちょっとビールのはいったおっちゃん、おにいさん、たまにおねえさんが、
「そんな年で馬か。ぼく、将来コワいな」
ひとひは嬉しげに顔をあげ、
「こないだの、タカラヅカ(宝塚記念レース)、すごかったですね」
「おう、そやな! 見とったか」
「タイトルホルダー、めっちゃすごくないですか」
「凱旋門状、いちばん人気らしいなあ」
と、世代をこえた熱い馬談義がはじまる。居酒屋でも、イタリアンでも、駅のうどん屋でも焼肉屋でも。世間のいたるところに、男女とわず、馬好きは隠れているものと、ひとひの馬好きのおかげで思い知った。
昆虫に夢中な子もいる。恐竜趣味、電車好きの少年もめずらしくない。ひとひの場合それが馬だった、という風に片づけてしまってよいのか、いまもわからない。うちには永らくゲーム機がなかったから(別にポリシーとかでなく、本人がほしいといわなかった)、その分、熱中度はより深まったかもしれない。とはいえ、最近、Nintendo Switchを買うことになって、やりたいゲームはなにかとひとひに訊ねてみると、やはりというか、当たり前の顔で、
「え、ダビスタ」
と言い放った。
「けど、まあ、ともだちとプロスピ(プロ野球スピリッツ)やってからかな」
熱狂ぶりに呆れながら、ふとふりかえってみたら、ベートーヴェンにはまったときの自分とひとひが大いに重なっているのに気づく。「トリツカレ男」の子はやはり「トリツカレ息子」というわけかもしれない。
重なっているのはそれだけではない。聴くだけでなく、みずからピアノを奏でることで、音楽のより深い楽しみに、ぼくがいま揺さぶられているのと同じこと。みずから馬に乗り、同時に競馬を楽しむことで、ひとひはきっと、いのちの流れるリズム、脈動、とでもいうべきものを、からだの芯で感知し、この世の生の時間を、高々と跳ねつづけているのだろう。
先週、ひさびさにクレインにいった。京都から枚方の奥に引っ越し、「クレイン学研枚方」と名前も変わっている。
「あ、ひとひくん、来てくれたん!」
と、フロアスタッフの女性。
「はい」
と照れくさそうにひとひ。
「最近、野球、いそがしかったんで」
いずれ書くことになるが、小4からはじめた少年野球チームの、ひとひは現在、先発投手、つまりエースの座についている。
フロアスタッフのリーダー格の男性が冗談めかし、
「毎月、予約いれてくれてるやん。でも、ああ、今週もキャンセルか、野球がんばってんねんなあ、て思っててん。きょう、ひさしぶりやな。びびってへんか?」
「ふふ、ちょっと」
とひとひ。いいながら、こんな風に迎えてもらえた喜びが、全身から湯気のようににじんでいる。馬好きは馬好き同士、まるで馬に対するように、たがいにこころを開きあう。たがいがたがいのことを、尊重し、敬愛し、会うたびごとに好きになる。
馬に乗ることは、未来を信じ、いのちを間近に感じることにもつながる。ひとひが馬好きに育ってくれてほんとうによかった。
「おとーさん、おとーさんて」
騎乗後、いつものようにクラブハウスへ駆けこんできて、
「あのな、すごいねん。きょう、新しい馬乗ってんけどな、ゴッドリヴァプールっていう」
「へえ、すごい名前やな」
「その馬な、おとうさんが、ハービンジャーやねんけど、さらにな、母の父が、ディープインパクトやで!」
そんなこんなで馬好きはつづく。ひとひの部屋の床柱にはいま、とある居酒屋の店主がおくってくれた、日本最強牝馬アーモンドアイの尾毛が(ほんもの)、ジップロックにたいせつに封入され、ちょうど小6の目の高さに、押しピンで留めてある。
(了)

編集部からのお知らせ
8/17(水)イベント:いしいしんじ 書こうとしない「かく」教室 松本編@栞日 開催します!
この夏、いしいしんじさんが松本に戻ってくる!
「この本は、書く時に言葉をどう動かしていけばいいのかということを正面から扱っていて、頼りになる」(渡邊十絲子「毎日新聞」本紙 2022.6.25)
いしいさんの新刊『書こうとしない「かく」教室』は、子どもから大人まで、「書こう」とする人たちを自由へと導く、類のない一冊です。その本書の欠かせぬ一章を担っているのが「松本」編。この地で小説『みずうみ』が生まれた経緯がつづられています。
そして今回、その舞台である松本で、いしいさんが「かく」教室を開講!
講座内ではご参加の皆さんに実際に文章を書いていただき、ご希望の方にはいしいさんがコメントしてくださいます!
今回の教室は「こども編」と「おとな編」の二本立て。夏休みの作文に困っているこどもも、仕事や趣味で文章を書いているおとなも、そしてもちろん「かく」ことが好きな全ての皆様、ぜひご参加ください。オンライン参加も可能です!