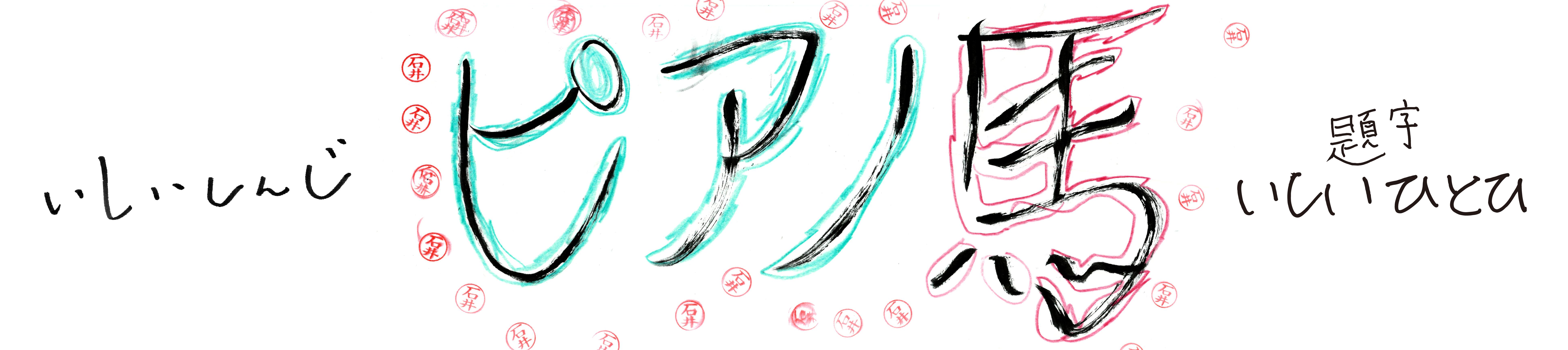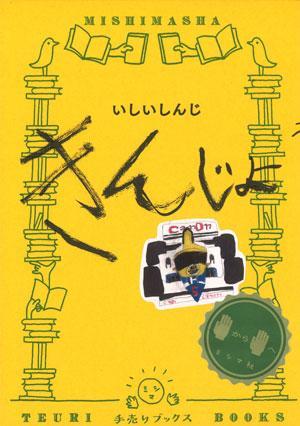第5回
松本そだち
2022.10.25更新
松本への帰郷は、数えてみたら五年ぶりだ。
生まれた町は大阪だけれど、ぼくにとっては、いったん住んだ場所は、生きていくためのホームテリトリーとしてずっと残るので(犬のマーキングみたいに)、三崎でも、東京でも、博多でも、京都でも、出かけてゆくときは「そこに帰る」感じになる。
小学校の夏休みも終わりかけた、八月のお盆過ぎ。京都駅からのぞみ号で東へ。名古屋駅で中央本線「しなの」に乗り換え、木曽川に沿って北東へすすむ。はじめのうちは市街地、畑地と見なれた風景がつづくが、旅程の半ば過ぎから、断崖絶壁の底をエメラルド色の奔流がくだり流れる、木曽路独特の景観が窓外にひらける。
「だんだん、山っていう感じしてきたなあ」
と小6のひとひ。
ここ何年も、石塚真一作のマンガ『岳』にはまっている。主人公は、山岳救助ボランティア、山を愛し、山に愛された山男、島崎三歩。舞台は信州の北アルプス。山登りに来たひとびと、山で働くひとびとと、三歩との、いのちの限りを尽くしたさまざまなエピソードが、一話ずつ、抑制された筆致で語られる。十八巻あるうちの後半は、これまで読んだあらゆる読みもののなかで、もっともこころを揺さぶられた(ひとひは最後の巻だけは「まだ」「もうちょっと」といって、あえて読んでいない)。
「まつもとー、まつもとー、まつもと、です」
と、なつかしい、寒い場所でめざめたような女声がプラットフォームに響く。コンコースのあちこちに「セイジ・オザワ 松本フェスティバル」のポスターが貼ってある。
「あ、知ってる知ってる。ここ降りたらバスとかタクシーとかとまってんねんな」
とひとひ。『岳』にもときどき松本駅前の様子が描写されている。
泊まりは、松本城近くの「ホテル花月」。住んでいたころ、泊まりで会いに来る編集者や取材の方には、決まってこの宿をお薦めしていた。民芸調のインテリア、深夜まで入れる大浴場。喫茶室「八十六度館」では、一杯いっぱい86度の適温で淹れたネルドリップコーヒーが楽しめる。
五年ぶり、と書いたけれど、住んでいたのも、五年間。住もう、と、この町を選んで引っ越してきたわけではなかった。
選ぶ余地はなかった。いやおうもなく決まっていた。園子さんが、松本在住、染織職人の本郷孝文先生に弟子入りし、その後、園子さんと三浦市役所で入籍したぼくは、2004年の秋、2年遅れてやってきて、この町で住み暮らすことにしたのだった。
まずは本郷先生のところへあいさつにいく。市内を流れる女鳥羽川のそば、「本郷織物」には、遠来のお弟子さんが、雑誌の取材班が、犬が、猫が、本郷先生の技と人柄を慕ってやってくる。
「こんにちはー」
と臆せず、木戸をくぐりぬけたひとひに、
「ようこそようこそ、元気だったかやあ」
と先生は、丸みのある信州弁で声をかけてくれる。やわらかな板の香り。染料につかう草木の匂い。園子さんはこの工房に自転車で七年かよった。朝は、ぶどう畑にかこまれた家から市街地まで坂をくだり、陽が暮れたら買い物をすませ、ぎっころぎっころペダルを踏んで、腹をすかせた物書きがひとり待つ家まで坂をのぼる。
五年ぶりなのにきのうもやってきたような顔の園子さんと、それが当たり前のように受けいれて話す本郷先生をはたでみていて、師匠と弟子の、あり得べき姿って、こういう感じなんだろうな、としみじみ思った。
渡すものや伝える技術だけでなく、ふたりは互いに深い「信頼」でつながれている。それは相手を通し、この世ぜんたいへの肯定へつながっていくような、揺るぎのない感覚だ。
「このひとがこのようにいるなら、自分たちをとりまくこの世界はだいじょうぶ」と迷いなく受けいれられる。他人なのに、ではなく、深い肯定に支えられた他人同士だから、曇りのないまなざしで、相手の心根がすなおにくみ取れ、相手にもひろびろと、自然に自らを開くことができる。
園子さんばかりでない。本郷先生のまわりにはそんな信頼の糸が、織物のように張り巡らされ、その柔らかさ、ぬくもりが工房には充ちている。だからひとが、犬や猫が、へびが、たまにたぬきまでが暖まりにやってくるのだろう。
ひとひもすっかり居着いてしまった。木皿のお菓子を頬張り、先住の猫二匹を腹ばいになって見つめ、床板の上をごろごろと転がっていく。まるで猫のなかの、いちばん下の後輩のように。
変わっているようで変わっていない市街地の風景。
カタクラモールが巨大なイオンモールになった。高速バス乗り場のむかいに丸善がはいった。大きな変化はそれくらい。あと、むかしレコードプレイヤーを修理にもちこんだ電気屋さんが、しゃれたブックカフェにうまれかわっていた。
そのブックカフェ「栞日」。ついた翌日、ここで新刊発売記念のイベントをひらくことになっている。ミシマ社刊「書こうとしない『かく』教室」は、これまでぼくがどんな場所で、どんななりゆきのもとに小説を書いてきたかを語りおろした一冊だ。当然ながら、松本で書いた「みずうみ」や「四とそれ以上の国」といった作品にまつわる顛末も隠すところなく披露している。
松本はつまり、ぼくにとって、そこで本を書いた町、であるだけでなく、本に書いた町、でもある。ふしぎなようでふしぎでない。東京、三崎、松本、京都。それぞれの町に住みながらぼくはずっとその町を小説に書いてきた。そして、その町を小説に書く、というの、その町を舞台にした小説を書く、というのとは、似ているようで、ずいぶんちがっている。「『かく』教室」では、そのちがいについてぼくが感じていることを、別のことばで、これでもか、というくらい語っている。
その内容もふまえて、「栞日」に集まったみなで、じっさいに「かく」ことをやってみることにした。日中に「こどもの部」、夜に「おとなの部」。こどもとおとなの区別は自己申告制。七十の坂をこしても「自分はこどもだ」と感じるひとは、堂々と「こどもの部」に参加してかまわない。
栞日の菊池さん、ミシマ社の三島さんと、このことだけは決めた。
「明日の「こどもの部」は、こどもたちがどんなことを書くか、それでなにを学ぶか、そんなのはまったく問題じゃない。明日のイベントの目的は、たったひとつ。参加したこどもたち同士が、なかよくなること。やって楽しかった、と感じてくれること」
当日、「こどもの部」に集まってくれたのは、名実ともにこどもどまんなか、小学生6人。地元松本のゆうくん、みはるちゃん、はるきくん、みひろちゃん。京都のせいすけくんと西宮のはなちゃんは、壁に映ったスクリーン上で、オンライン参加だ。
関西と松本、遠く離れた相手の住んでいる場所について、思いついたたことを、みんなで画用紙に書いてもらう。京都は、「おてら」「あまざけ」「きもの」があがった。松本について、関西のふたりは「おしろ」「しか」「川」「森」「大きい病院」「おみそしるおいしい」と、イメージ豊かに書いてくれた。
「川、ちょーある!」と、松本のみんなは喜んでいる。「おしろって、ほら、松本城」「おっきい病院もあるよな」
西宮は、松本に生まれ育った四人にはちょっとイメージしづらい地名だ。うんうん頭をしぼった末、ゆうくんが「これ」と差しあげたのは「酒」のひと文字。
ぼくは驚き、
「おー、よう知ってるやん。灘のお酒って日本一有名やで」
「知ってる、っていうか」
とゆうくんは照れくさげに、
「西宮の『西』にいろいろ付けてたら、『酒』になった」
それからみなで相談し、関西のふたりを、松本まで連れてくる「おはなし」をつくることになった。
「乗りものは、電車? クルマ? しかに乗ってくる?」
「クルマ」
と書いた画用紙を、西宮のはなちゃんがさしだし、シートにおさまってハンドルをにぎる。せいすけくんはパジャマを着て、途中からクルマの後部席に乗りこんでくる。ふたりは京都から東へ向かい、名古屋で曲がり、木曽川に沿って北東へすすむ。川のそばに住むいろんな動物を、松本の4人のアドバイスをもとに、つぎつぎと見つけながら。
しか、やまねこ、たぬき、きつね、ねこ、こぶた、カエル、イモリ、いぬ、とり、いのしし、おおかみ。
とちゅう、サービスエリアの駐車場で休む。クルマの窓をこつこつ叩く音がし、みるとそこに、頭にツノがあり、耳がとんがっていて、髪がバクハツして、お酒のびんをもっている、そんなのが立っている。「しかと人間が合体した、しか人間だ!」と、せいすけくんは見破る。
しか人間を追っぱらうためには、どうすればいい?
「ライターで火をもやす」「ピストルを、うちまくる」「大きな声でこわがらせる」「川の水をひっかけて、そのあいだににげる」
「しかせんべいをぶっつけたら?」と、せいすけくんは思いつく。60びょう、動きがとまるし、こうかがなくなったら食べるし、その間ににげればいい!
しかせんべいを食べたしか人間は、少しやさしい顔になる。あいかわらずツノがあって耳はとんがり、髪はバクハツしているけれど。
はなちゃんははっとして、
「ひょっとして、おかあさん?」
ときいてみた。
しか人間はうなずき、
「ちょっと怒った、おかあさんだったのよ」
はなちゃんとせいすけくんのふたりは安心し、クルマを出発させる。松本はもう、すぐそこだ。
ふたりが松本にきたら、松本のゆうくんは「さんぞくやき、いっしょに作りたい」、みはるちゃんは「いどみず、のもうよ」、みひろちゃんは「旧開智学校、あんないしてあげる」。
はるきくんが、
「きてくれてありがとう!」
と元気な声を投げると、はなちゃんは、
「みんなと、なかよくなりたいな!」
せいすけくんは、
「さんぞく焼き、つくろう!」
たった一時間たらず。6人はまるで、ずっと同じクラスで過ごしてきた仲間のように笑みと声をかけあっている。知らない土地に住んでいても、初対面でも、こどもの使うことばの自由さは、こんな風に、互いのこころとからだをひと息で重ね合わせる。
松本でも京都でも三崎でも、いったん住んだ場所は、生きていくためのホームテリトリーとしてずっと残る、とぼくは書いた。
こどもたちにとって、住んだことあろうがなかろうが、実在する土地であろうがなかろうが、まわりにひろがる世界のすべてが、自分のうまれ、なじんだ場所、勝手知ったるホームなのだ。楽しみと冒険に満ちた森であり、そこで出会う誰もが、いっさい疑いなく信じられる、長年の親友となる。
京都、西宮、松本、名古屋、6人はその遙か上空で、笑い、はしゃぎ、雲のボウルで作ったさんぞく焼きをほおばっている。
了

編集部からのお知らせ
松本で子どもたちとつくったお話をもとに、いしいさんに小説を書いていただきました。12月上旬発刊予定の次号『ちゃぶ台10』に掲載いたします。ぜひこの連載と合わせて、お読みください。