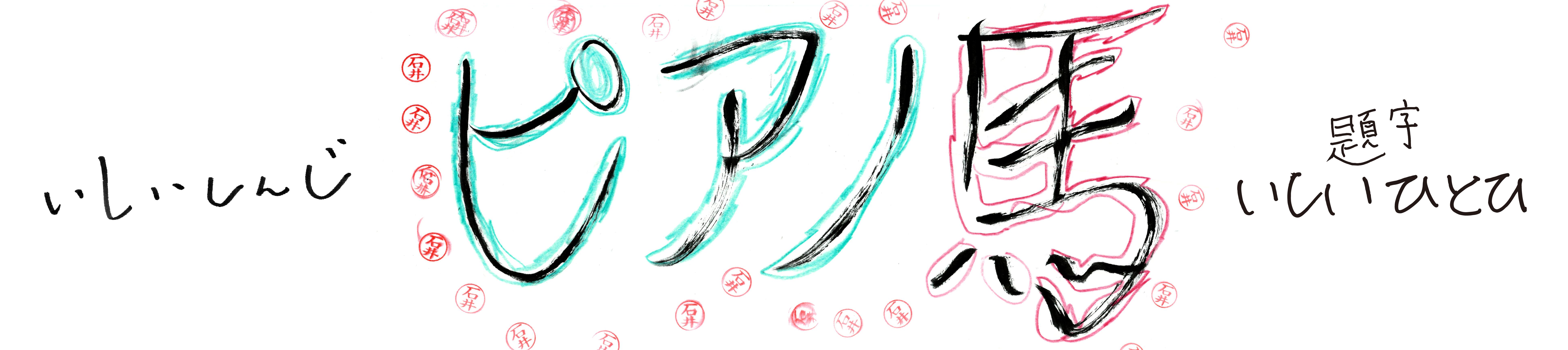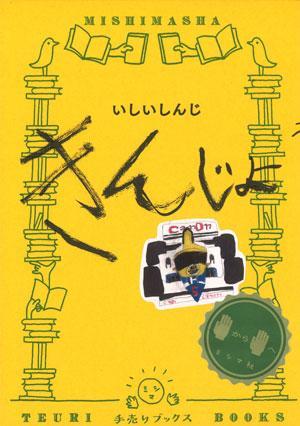第6回
ひとひの21球(上)
2022.12.28更新
ひとひが野球チームを引退する日がやってきた。
日本全国どこでも少年野球の選手たちは、6年生の12月、次代の中心となる5年生にチームをひきつぐ。卒団の日、監督から「最後のノック」をうけ、それぞれの番号をハサミで切りとられる。そのような儀式が決まっている。
もともとはまっていたのは、モータースポーツと競馬だ。
隔週雑誌「オートスポーツ」で小1の春からぼくとともに連載をもち、F1マシンやWRCのラリーカーの絵を、二週間に一度、毎回およそ3時間かけて描いた。尊敬する人物はカルロス・サインツとアイルトン・セナだった。
小2から乗馬をはじめ、その流れで競馬が好きになった。毎月「優駿」の発売日を楽しみに待ち、クリスマス前にはサンタクロースに、悲劇の名馬サイレンススズカのぬいぐるみをくださいと手紙をしたためた。学校から帰ってくるや、「おとーさん、担任の先生しんじられへん! オルフェーブルも、ステイゴールドも、ゴールドシップも知らんねんで。さらにな、ディープインパクトも、知らんかってんで!」
その分、クラスの誰とも話が通じない。それがある日、「阪神タイガース」の話題ならまわりに通用することがわかった。一気に野球にのめりこんだ。鳥谷や藤浪のことを話せば友だちといっしょに過ごせる。ひとひは外面めちゃくちゃに明るいようで、刃物の上を歩くようなギリギリの繊細さを秘めている。バカっぽい態度で、自分でもわからない不定型な不安を、外からも内からもかくしている子だ。
小3の秋、自分なりに考えぬき、地元の野球チーム「錦林ジュニア」に入団を決めた。土日は朝から日暮れまで練習がつづく。夏休みや冬休みをのぞいて、雨天でグラウンドが使えないとか、保護者にコロナ感染が出て練習中止とか、そういったときにしか乗馬クラブにはいけない。
それでもひとひは友だちをとった。だからはじめのうちは、キャッチボール、バッティング、守備練習の時間、みんなとともに過ごせるだけでよかった。僕は「いしいコーチ」として、グラウンドの練習にも試合にも、行けるかぎり参加した。選手の父親はみな「コーチ」と呼ばれるのだ。
友だち、といっても、1年生で入団した同級生たちは、上級生にまじっても見劣りがしないくらいレベルが高い。兄弟や家族に、野球経験者がいたりして、もともと気持ちが野球に向かっているし、三年間、毎週土日うちこんできた練習の差はかんたんには埋まらない。
ほとんど試合に出られない日々がつづいた。ベンチから声を出し、そのかけ声がとんちんかんなことを周囲に注意される。たまに出してもらっても、外野フライを落球、ど真ん中を見逃し三振。同級生はひとひを練習相手として数段下とみなした。当然キャッチボールの相手としては選ぼうとしない。「ひとひ、ちゃんとボールみろ」「ボールから逃げんなって」と、下級生にさえ叱咤される。
それでもひとひは野球から逃げなかった。週日の毎日、ガラリと開き戸をあけて学校から帰りつくや、
「おとーさーん、やきゅーっ!」
と、近所じゅうまる聞こえの声で叫ぶ。ふたりグローブとボールを手に、鴨川右岸、丸太町橋北側の広い草地へ自転車で向かう。まずは、ぼくがゴロを転がし、フライを投げ、ひとひがキャッチする守備練習。真正面のごく簡単なボールを「初級」として、一級、二級、と難易度をあげてゆく。三級のゴロをすべて拾えば、出町柳の「ふたば」で豆餅を買う約束。
守備が終われば、ピッチング練習。ひとひが川を背にし、ぼくは茂みと金網の前にすわる。というのも、まだこの頃、ひとひの球は、どこにいくか、マジ、ボールにきいてくれ、というレベルだった。10球投げて、5球ストライクが入れば大成功。残りは横っ飛びに飛びついても捕球できない(ぼくがへたっぴなこともありますが)。
コーチのはしくれとして、ボールを受けていて決めていたことはふたつだけ。
ひとつは「まっすぐ投げる」。ひとひとぼくの間に架空の直線を引き、その上にボールを乗せるよう、右足を踏みこみ(ひとひはサウスポーです)、肘をあげ、腕を振りおろす。くりかえす。何度も、何度も。
もうひとつは、どんな暴投をしても、どんな遠くへボールを拾いにいく羽目になっても、けして怒らない。文句いわない。あせらせない。
3年生から4年生にかけて、鴨川でふたり、野球をしない日はほぼなかった。プラスティック製のカラーボールに砂の入ったサンドボール(両方、打ってもあまり飛ばなくて安全)、バッティング練習用のネットとティーなどなど、誕生日や子どもの日がくるたびに道具が増えていった。使うバットも、初心者用の金属バットから、チームのみんなが持っている低反発素材バット「ビヨンド」へと進化した。
少年野球にかぎらず、サウスポー、左利きの選手は、ポジションが限られる傾向にある。二塁、三塁、ショートだと、ゴロを一塁へ送球する際、右利きで投げるよりどうしてもワンステップ多くかかり、その分、タイミングが遅くなる。キャッチャーの一塁けん制のときも、左投げだと右バッターが邪魔になる。センター、レフトがなぜ避けられるのかよくわからないが、なにはともあれサウスポーの守備位置は、ファースト、ライト、そしてピッチャーと、どのチームでも相場が決まっているらしかった。
ひとひもご多分にもれず、試合に出るときにはライトからはじまった。高々と打ちあがったボールを、3年のうちはうまく捕れず、たまにフライがグローブに収まったら、コーチや同級生から「奇跡や!」と拍手で迎えられた。
4年でファーストを守ることが増えた。もう卒業した左利きの大先輩から、ファーストミットを貸してもらった日は顔を輝かせていた(いまも借りたままです)。ただ、一塁は試合中、バッテリーをのぞけば、もっともボールに触る回数の多いポジションだ。そのぶん落球の機会も格段に増える。
「ひとひ、とったれや!」
「ファースト、しっかりせえって!」
捕って当たり前。必死に腕をのばし球にくらいついても、ファインプレイとはみなされない。
が、ボールまわしやノックで、自分の場所ができた喜びが勝った。内野陣のなかでいちばん声を張りあげ、5年のエースを絶えず鼓舞しつづけたのはひとひだった(この年代には6年生がいなかった)。
7月のある日、練習試合の前、監督に呼ばれた。 「ひとひ、ピッチャーやってみるか」
4年生のとき、背番号は13番だった。マウンドにその数字があがるのを見て親バカ以上に胸が熱くなった。相手は大宮小学校。なんだかむこうの子らの体格がやたら大きくみえる。緊張してるやろなあ、と見まもっていると、プレイボールの声。第一球、いきなりストライク。二球目、ツーストライク。そして三球目、三振、え。次のバッターも、ストライク、ツーストライク、三振、え、二者連続。
ここで、三者連続、とはいかなかった。シングルヒット、四球、デッドボールをあたえ、2点とられてさらにツーアウト満塁。この場面でピッチャー交代。
夕方、家に帰ってきたひとひはコピー用紙に、跳ねあがるような筆ペンの字で「石井一日 7月18日 ピッチャー初登板」と書き、画鋲で鴨居に貼った。園子さんは晩ごはんにローストビーフを作った。
のちに監督にいわれたことだけれども「ひとひのフォームは、ピッチャーとして、最初からできあがってたからね。教えることなかった」と。コーチのひとりには「左腕の使いかたがすばらしいです。やろうと思ってできることじゃない。天性ですよ」と。半信半疑だった。野球経験者の目にはそんな風にうつるものなのか。
9月22日、淀川河川敷グラウンドにて、2年から4年で組まれるJチームによる、乙訓LIV杯一回戦、相手は壬生ライガー。ひとひは6番ファーストで出場。初打席はフライを打ち上げるも、相手のエラーで出塁、その後ホームに戻ってきて1得点。2打席目はみごとにレフト前ヒット、これで初ヒット、初打点、初得点。
錦林ジュニアが合計13点をあげ、試合の趨勢が決まりかけた3回、監督が球審にむけてひとひの名をコールした。公式戦の、これが初登板。
僕はバックネット裏から祈る気持ちで見ていた。一球目は、右打者の外角低めにのびやかに滑ってゆくストレートで、初ストライク。その後ヒットを2本打たれたが、どちらも打ちとった当たりだった。内野から、外野から、ベンチからも、「ひとひ、ええボールいってる! ナイスピッチや!」と声がとんだ。この瞬間ほど、ひとひのからだが喜びに燃えあがってみえたことはない。すっと表情をととのえ、右足をふみこんで、最後のバッターをストライク、空振り三振に切ってとった。
ゲーム後、
「もっともっと投げてもらうで」
と円陣のなかで監督は笑った。
翌週の29日、京大そばの整形外科にいった。たいしたことではなかった。鴨川で練習はつづけていたし、練習の休みには乗馬にでかけたりミニカー屋さんをのぞいたり、ひとひらしい一週間を過ごしていた。なんとなく右手首に違和感があるので、いちおうレントゲンを撮ってもらって、監督を安心させて明日からの試合にのぞもう、という話だった。
豪放な感じの医師だった。ひとひの手首まわりを触診し、
「いたいか」
「いたない」
「平気か」
「うん」
「ふーん」
といって右手をはなし
「これ、折れてるかもしれまへんな」
なんと! そしてレントゲン写真撮影。結果、右橈骨遠位端骨折、転んで手をついたひとがわりとようやってまうんやね、医師はいった。LIV杯一回戦の第一打席が頭によみがえった。内野フライを打ち上げ、それでも猛然と一塁にダッシュし、駆けぬけたところですっ転び地面に手をついた。あれか。
了(つづく)